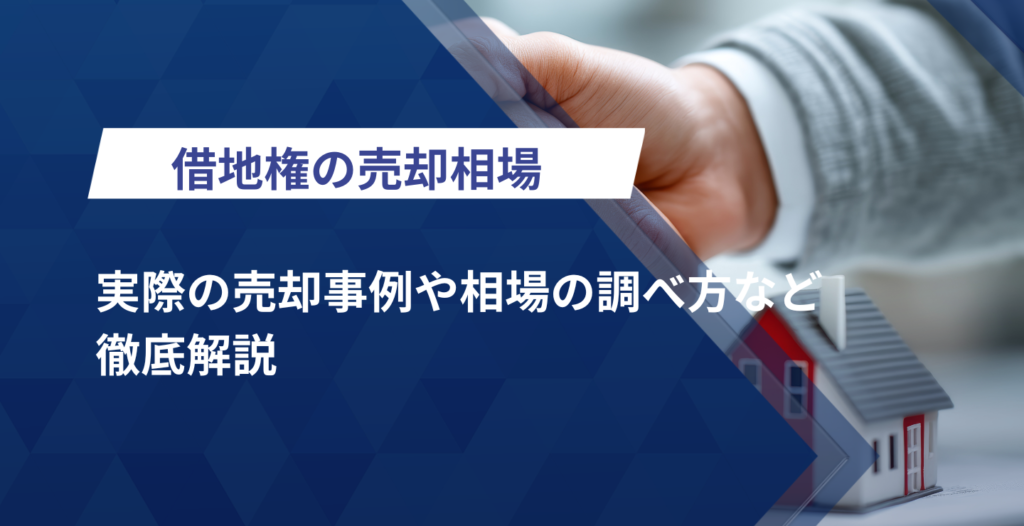借地権トラブルにはどんなものがある?実際のトラブル事例を専門家が紹介

訳あり不動産の買取を専門とする弊社では「借地のことで地主とトラブルになった」「借地権を手放したいが、地主に承諾してもらえない」などのご相談をいただくことがあります。
借地権は、他人が所有している土地を借りる権利のことであり、所有権はあくまでも地主にあります。借地人は自由に借地を利用できるわけではなく、建て替えや譲渡の際には、原則として地主の承諾が必要となります。
借地権をめぐって起こりやすいトラブルの事例は以下のとおりです。
- 契約更新時に、高額な更新料を請求される
- 地主から地代の値上げ請求を受ける
- 借地権を売却する際に地主から承諾を得られない
- 借地の建て替えや増改築で地主の承諾が得られない
- 地主側の都合により、長年住んでいた借地からの立ち退きを求められる
- 地主の代替わりによって地代や契約条件の見直しを求められる
- 共有名義の借地で地代の支払いや管理をめぐって争いが起こる
- 契約内容が口約束のままで、更新料や承諾料の妥当性がわからない
上記のようなトラブルが発生した場合、まず契約書を確認し、地主との交渉で解決を図るのが基本です。交渉が難しい場合や、話し合いが決裂した場合、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、対応方針を整理しましょう。
なお、借地権を手放したい場合は、借地・底地の取引実績が豊富な不動産会社に相談するのがおすすめです。とくに専門の買取業者に依頼すれば、地主との交渉や契約内容の整理を代行してもらいながら、適正な価格で借地権を売却できます。
借地権でトラブルが起こりやすい原因
借地権でトラブルが起こりやすい主な原因は以下のとおりです。
- 借地人が自由にその土地を自由に使えるわけではないため
- 契約期間が長期にわたることで地主との関係性や地価が変わりやすいため
- 相続などで地主や借地人が変わることで口約束だった契約内容が不明瞭になりやすいため
- 借地権の種類や契約形態が複雑であり誤解が生じやすいため
借地人が自由にその土地を自由に使えるわけではないため
そもそも借地権とは、他人が所有する土地を借りる権利のことです。借地人は土地の使用権を持っていますが、所有権はあくまでも地主にあるため、土地を自由に使えるわけではありません。
たとえば、借地に建てた建物を建て替えたり売却したりする場合には、原則として地主の承諾が必要です。勝手に建物を増改築したり、第三者に譲渡したりすると契約違反とみなされます。
土地を自由に使えないことが原因で起こりやすいトラブルとして、以下のようなものがあります。
- 地主の許可を得ずに建物を建て替え、トラブルになった
- 借地権を売却しようとしたが、地主の承諾が得られなかった
- 建物の利用方法をめぐって地主と意見が対立した
このように、借地権は所有権とは異なり、土地の使い方に制限がある権利です。建て替えや譲渡をするためには地主の承諾が必要となるため、拒否された場合は地主との間でトラブルが生じる可能性があります。
契約期間が長期にわたることで地主との関係性や地価が変わりやすいため
借地には契約期間が設けられており、期間が満了すれば契約を更新するか、更地にして返還することになります。契約期間は短くても20年〜30年、借地権の種類によっては50年以上に設定されることもあります。
そのため、契約当初とは社会情勢や経済状況、地価や税制が大きく変わるケースも珍しくありません。また、長い年月の間に地主や借地人が世代交代を迎えることで、双方の関係性や考え方が変化することもあります。
このような変化によって、契約当初に交わした内容に対して不平不満が生じ、トラブルに発展するケースが多くみられます。トラブルの一例は以下のとおりです。
- 地価の上昇を理由に地主が地代の値上げを求めてきた
- 地主の代替わり後、新しい地主から更新料や地代の値上げを要求された
- 契約書の内容が不明確になり、当時の条件が確認できなくなった
とくに、社会情勢や地主の代替わりなどにより、更新料や地代が突然値上げされるというケースが多いです。借地人は必ずしも値上げに応じる義務はありませんが、拒否することでトラブルに発展する可能性があります。
相続などで地主や借地人が変わることで口約束だった契約内容が不明瞭になりやすいため
借地契約は、当事者同士の合意があれば書面を交わさなくても成立します。そのため、過去には「地代はこれくらいでいいだろう」「建て替えるときは連絡してください」のように、口約束のまま契約が続いているケースも少なくありません。
しかし、地代や更新料、建て替えの承諾料などの取り扱いを明文化していないと、地主や借地人が代替わりした際にトラブルが起こりやすくなります。新しい当事者にとっては、前の世代が口頭で合意した内容を証明する手段がなく、「そんな約束は聞いていない」と認識のズレが生じてしまうからです。
このような曖昧さが原因で起こりやすいトラブルには、以下のようなものがあります。
- 今まで更新料を請求されなかったが、新しい地主が高額な更新料を請求してきた
- 契約内容に関する証拠がなく、双方の主張が食い違って関係が悪化した
- 契約期間がいつまでなのかが不明瞭になっており、更新のタイミングがわからない
口約束で借地契約を交わしていた場合、地主と借地人の間で「言った」「言わない」の水掛け論になるケースが多くみられます。結果的に双方の関係性が悪化し、トラブルに発展する可能性があります。
借地権の種類や契約形態が複雑であり誤解が生じやすいため
借地権にはいくつかの種類があり、それぞれ契約内容や権利の強さが異なります。
かつては旧借地法のもとで契約された「旧法借地権」が主流でしたが、1992年8月に施行された借地借家法により「普通借地権」や「定期借地権」など新しい形態が設けられました。借地権の種類ごとの概要は以下のとおりです。
| 種類 | 概要 | 契約期間 |
|---|---|---|
| 旧法借地権 | 1992年8月以前の旧法による契約であり、借地人が希望すれば更新が可能 | 木造などは30年、鉄骨造などは60年 (更新後は木造20年、鉄骨造30年) |
| 普通借地権 | 一定の契約期間が設けられているが、借地人が希望すれば更新が可能 | 当初30年、1回目の更新20年、以降10年ずつ |
| 定期借地権 | 契約期間が満了すると更新されず、更地で返還する契約 | 50年以上 |
旧法借地権や普通借地権は借地人の権利が強く、契約更新が半永久的に認められるのに対し、定期借地権は契約期間が終了すると更新されず、土地を返還しなければなりません。
このような制度の違いを把握せずに契約を結んだり相続したりすると、以下のようなトラブルが生じやすくなります。
- 定期借地権なのに更新できると誤解し、契約終了後も使用を続けてしまった
- 旧法借地権と認識していたが、実際は新法契約であり条件が異なっていた
- 相続で契約形態を把握できておらず、更新に関して地主と揉めた
借地権の種類や契約内容を把握できていなければ、地主と借地人の間に齟齬が生じてしまいます。とくに、相続で借地権を引き継ぐ場合には契約形態が不明瞭になりがちなので、トラブルが生じるケースが多いです。
借地権のトラブルが起こりやすいタイミング
借地権は地主と借地人の間でトラブルが生じやすいのですが、とくにトラブルが起こりやすいタイミングは以下のとおりです。
- 借地権の契約更新のタイミング
- 借地権を売買するタイミング
- 借地権を相続するタイミング
- 借地に建つ建物を建て替え・増改築・解体するタイミング
- 地主から地代の値上げを請求されたタイミング
借地権の契約更新のタイミング
借地権の契約更新のタイミングは、借地権に設定されている契約期間が満了したときです。このとき、更新料や更新の可否、地代の値上げなどをめぐってトラブルに発展するケースがあります。
弊社でもよく相談がある事例として「更新料の支払いを求められた」「更新するなら地代を値上げすると言われた」などがあります。契約更新時には地主や借地人が代替わりしているケースも多く、「支払う必要があるのか」「値上げの金額は妥当なのか」などの点で揉めやすくなります。
また、地主側に土地活用の計画や相続などの事情があると、契約更新そのものを拒否され、土地の明け渡しを求められることもあります。
旧法借地権や普通借地権であれば、借地人が希望する限り半永久的に契約更新が可能となっています。そのため、地主側は正当な理由もなく一方的に契約更新を拒否したり、立ち退き請求を求めたりすることはできません。
一方、定期借地権の場合はそもそも更新ができないため、契約終了後には土地を更地にして返還する必要があります。なお、地主が承諾すれば「再契約」という形で土地を借り続けること自体は可能です。
このように、借地権の契約更新時はトラブルが発生しやすいタイミングとなっています。トラブルを避けるためにも、あらかじめ契約内容について確認のうえ、更新の可否や更新料に関して地主と話し合っておきましょう。
借地権を売買するタイミング
借地権を売買するタイミングは、借地人が土地の利用をやめて第三者に権利を譲渡したいときです。
借地権を譲渡するためには地主の承諾が必要となり、その際に譲渡承諾料を求められることがあります。譲渡承諾料の支払いは法的に義務付けられているわけではありませんが、慣習として支払うケースが多いです。
借地権の売買で地主の承諾を得る際には、「地主が承諾してくれない」「譲渡承諾料が相場より高い」などのトラブルが生じるケースがあります。
このような場合、基本的には地主と根気よく話し合って売買の許可を得るしかありません。譲渡承諾料についても、相場程度の金額に値下げしてもらうよう交渉する必要があります。
なお、地主が正当な理由もなく借地権の売買を認めてくれない場合、裁判所に申し立てをすることで許可を得ることが可能です。これは借地人に認められた権利であり、借地借家法第19条で以下のように定められています。
(土地の賃借権の譲渡又は転貸の許可)
第十九条 借地権者が賃借権の目的である土地の上の建物を第三者に譲渡しようとする場合において、その第三者が賃借権を取得し、又は転借をしても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。
引用元: 借地借家法|e-Gov 法令検索
裁判所から譲渡の許可を得られれば、地主が拒否していても第三者に借地権を売却することが可能です。
上記のほかに借地権の売買でトラブルになりやすいケースは、借地権付き建物を共有名義で所有している場合です。共有名義の不動産を売却する場合、共有者全員の同意が必要です。たとえ地主が売買を承諾してくれていても、共有者が拒否すれば売却はできません。
このように、借地権を売買する際には地主の承諾が前提となり、さらに建物が共有名義の場合は共有者全員の同意が必要になります。まずは共有者同士の意思統一を図り、そのうえで地主との交渉に臨みましょう。
借地権を相続するタイミング
借地権を相続するタイミングは、借地人(被相続人)が亡くなり、その権利を相続人が引き継ぐときです。相続時に起こりやすいトラブルの例は以下のとおりです。
- 「誰が借地権を引き継ぐか」で相続人同士で揉める
- 共有名義で相続したことにより、活用方法や維持管理費の負担で揉める
- 高額な相続税が発生する場合がある
- 地主から名義変更料を請求される
- 地主の土地の返還を求められる
まず、相続時には「誰が借地権を引き継ぐのか」を相続人同士で話し合って決めなければなりません。もしも話し合いがまとまらずに共有名義で引き継ぐと、「誰が地代を支払うか」「売却するか」などで揉めやすくなります。
さらに、借地権には相続税が課せられる点にも注意が必要です。借地権の評価額によっては高額な相続税が発生する可能性もあるため、税理士などに相談しながら相続を進める必要があります。
借地権を相続するタイミングでは、相続人同士の話し合いだけでなく、地主との間でもトラブルが生じるケースがあります。
代表的なトラブルとして多いのは、地主から名義変更料を請求されるケースです。本来、相続による借地権の承継は「譲渡」にはあたらないため、地主の承諾や名義変更料の支払いは必要ありません。ただし、地主との関係を悪化させたくない場合など、支払ったほうが良いケースもあります。
また、地主から「相続したなら土地を返してほしい」と求められることもありますが、相続に地主の承諾は必要ありません。契約内容もそのまま引き継がれるため、返却に応じる義務はないものの、拒否したことで地主と感情的な争いに発展する可能性があります。
このように、借地権の相続は法律上の手続きや人間関係の問題が絡みやすくなっています。事前に契約内容を確認し、地主や相続人全員が納得できるまで根気よく話し合いましょう。
借地に建つ建物を建て替え・増改築・解体するタイミング
借地に建つ建物を建て替え・増改築・解体する主なタイミングは、建物が老朽化したときや、バリアフリー化、耐震化など大規模な改修をしたいときです。
建物の改修時には、地主の承諾をめぐってトラブルが発生することがあります。
というのも、多くの借地契約では「増改築禁止特約」が定められているためです。これは、借地人が勝手に建て替えや増改築をおこなうことで、土地の利用に不利益が生じるのを防ぐ目的があります。
そのため、増改築禁止特約が定められている場合、地主の承諾を得ない限り建て替えやリフォームができません。災害などで建物を失った場合でも、原則として地主の許可がなければ再建築はできないため、注意が必要です。
また、建て替えの承諾を得る際には「建替承諾料」や「増改築承諾料」などの費用を求められることがあります。法的に支払い義務はありませんが、支払いを拒否すると承諾を得られない可能性があります。
金額に納得がいかない場合や地主がなかなか承諾しない場合は、交渉が長期化することもあります。建物が老朽化していたり耐震性能に不安があったりなど、どうしても工事を進めたい場合は裁判所に申し立てをおこない、地主の代わりに許可を得ることも可能です。
なお、契約書に増改築禁止特約が記載されていない場合でも、建物に手を加える際には地主へ連絡しておきましょう。無断で工事を進めると、信頼関係が損なわれたり、後に更新や譲渡の際に影響が出たりする恐れがあります。
地主から地代の値上げを請求されたタイミング
地主から地代の値上げを請求されるタイミングは、主に固定資産税や都市計画税の増加、地価の上昇など、経済事情の変化があったときです。
しかし、借地人側としては安く借りられたほうが良いため、拒否や減額交渉をすることで、トラブルに発展する可能性があります。
地代に値上げに関しては、借地契約で「地代を増減しない」と定められていない限り、地主に正当な理由があれば増額請求が可能です。これは、借地借家法第11条により、以下のように定められています。
(地代等増減請求権)
第十一条 地代又は土地の借賃(以下この条及び次条において「地代等」という。)が、土地に対する租税その他の公課の増減により、土地の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍類似の土地の地代等に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって地代等の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間地代等を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。
引用元: 借地借家法|e-Gov 法令検索
地代の値上げを正当に請求できるのは、土地にかかる固定資産税・都市計画税が上昇した場合や、地価の上昇によって土地の価値が高まった場合、周辺の土地と比べて地代が著しく低くなっている場合などです。
ただし、借地人は地主の請求に必ず従う必要はありません。値上げ幅が不当に大きいケースもあるため、金額や値上げの根拠に納得できない場合は、まず地主と交渉してみましょう。交渉が決裂したときは、調停や裁判などで最終的な地代が決定されます。
地代の値上げ請求は法的にも認められた手続きですが、理由や金額が正当なものであるかをしっかりと確認する必要があります。トラブルを防ぐためにも、値上げ請求を受けたときは司法書士や弁護士などの専門家に相談しましょう。
借地権のトラブルで実際に起きた事例
訳あり物件の買取を専門とする弊社では、借地権に関する相談をいただくことが多くあります。ここでは、実際に弊社へ寄せられたご相談の中から、借地権のトラブルで起きた事例をピックアップして紹介します。
- 借地権の売却で地主から承諾を得られずに揉めてしまったトラブル事例
- 更新料をめぐり地主と揉めてしまったトラブル事例
- 借地に建つ建物について地主から建て替えの承諾が得られなかったトラブル事例
- 共有していた借地権の地代を誰が払うのかで揉めたトラブル事例
- 地主から地代の値上げ交渉があったことで起きたトラブル事例
- 地主から契約更新を拒否されたトラブル事例
- 地主が代替わりしたことで起きたトラブル事例
- 契約内容が口約束だったために起きたトラブル事例
借地権の売却で地主から承諾を得られずに揉めてしまったトラブル事例
借地権の売却で地主から承諾を得られず、交渉が難航した事例です。
そこで弊社が仲介に入り、売却の背景や買主の人物像を丁寧に説明しました。信頼関係を重視した交渉を重ねた結果、承諾料を支払うことで地主の理解を得ることができました。
最終的には、当初の想定よりも高い価格での売却が実現しました。
借地権の譲渡には地主の承諾が必要ですが、今回の事例のように、感情的な理由で拒まれるケースも少なくありません。
承諾が得られない場合は、第三者を交えて冷静に話し合い、信頼関係を築きながら交渉を進めることが円満な解決につながります。
更新料をめぐり地主と揉めてしまったトラブル事例
更新料の金額をめぐって地主と揉めてしまった事例です。
最終的には弊社が借地権を買い取り、地主側とは弊社が直接交渉をおこないました。結果として、相当額の承諾料を支払う形で和解が成立しました。
ご相談者様は訴訟に発展するリスクを避け、無事に借地権を現金化することができました。
更新料は明確な法的基準がないため、金額の妥当性をめぐってトラブルに発展するケースが多くみられます。
相場と大きく乖離した請求を受けた場合は、早めに司法書士や不動産会社などに相談し、適正な条件での解決を目指すことが大切です。
借地に建つ建物について地主から建て替えの承諾が得られなかったトラブル事例
借地に建つ建物の建て替えにあたり、地主から承諾を得られずに長期間揉めてしまった事例です。
地主は「契約満了時には更地で返す約束だった」と主張し、さらに「建て替えるなら土地評価額の10%を承諾料として支払うように」と高額な条件を提示されている状況でした。交渉は数年にわたって進展せず、建物の劣化だけが進む状況でした。
そこで弊社が介入し、現地の状況を踏まえたうえで借地権を買い取り、地主と直接交渉を実施しました。法的な根拠と地域の承諾料相場を示しながら粘り強く交渉を重ねた結果、承諾料を適正水準に抑える形で建て替えが実現しました。
借地契約には「増改築禁止特約」が記載されている場合が多く、その場合、建物を建て替えるためには地主の承諾が必要になります。しかし、今回の事例のように、建て替えを拒否されたり高額な承諾料を求められたりするケースは少なくありません。
建て替えをスムーズに進めるためには、契約内容や地域相場を正確に把握し、地主と冷静に話し合う必要があります。感情的な対立に発展しそうなときは、不動産会社などの専門家に相談しましょう。
共有していた借地権の地代を誰が払うのかで揉めたトラブル事例
共有していた借地権の地代負担をめぐって相続人同士が対立した事例です。
弊社では、3名それぞれと個別に面談をおこない、話し合いのうえでそれぞれの共有持分の買取を実施しました。
地主にも契約関係を整理して引き渡しをしたことで、滞納問題は解消しました。結果として、地主・相続人の双方が納得できる形で問題を終結させることができました。
共有名義の借地権は「誰が地代を支払うのか」「建物をどう使うのか」といった点で意見が分かれることが多く、トラブルに発展しやすい傾向にあります。
今回の事例では、各相続人の共有持分を買い取る形で問題を解決しました。共有持分とは、複数人で不動産を共有している場合に、各共有者が持つ所有権の割合のことです。共有持分は他の共有者の同意を得ることなく、個人の意思で自由に売却できます。
相続で借地権が共有状態になっており、かつ共有者同士で揉めている場合、持分の売却も検討してみてください。
地主から地代の値上げ交渉があったことで起きたトラブル事例
地主からの地代値上げ交渉をきっかけに、関係が悪化してしまった事例です。
長年築いてきた信頼関係が崩れ、ご相談者様も精神的に疲弊していました。 弊社では現状を調査したうえで借地権を査定し、そのまま買取を実施しました。
地主側には弊社が直接交渉をおこない、過去の契約履歴や周辺の地代相場をもとに調整を重ねました。結果として、地主にも納得いただける条件で借地権の譲渡が成立しました。
地代の値上げをめぐる交渉は、感情的な対立に発展しやすい問題のひとつです。地主と良好な関係を築いていても、お金の問題が絡むと信頼関係が崩れやすくなります。
地代に関して、冷静に話し合いを進めることが難しい場合は、相場や契約関係に詳しい司法書士や不動産会社に相談することをおすすめします。
地主から契約更新を拒否されたトラブル事例
地主から契約更新を拒否され、立退きを求められた事例です。
長年地代を滞りなく支払い続け、生活の拠点としてきた借地であったため、突然の更新拒否に戸惑いと不安を抱えておられました。 弊社でも借地権の買取をご提案しましたが、地主が譲渡を強く拒否したため、まずは弊社と連携する弁護士を紹介しました。
弁護士が代理人として立退料の交渉をおこない、最終的には適正な金額の立退料が支払われる形で和解が成立しました。ご相談者様からは「不動産だけでなく、法的な部分も支援してもらえて安心できた」との声をいただきました。
借地契約の更新拒否は、借地人にとって生活基盤となる家を失う重大な問題です。ただし、旧法借地権や普通借地権であれば、正当な理由がない限り更新拒否は認められないため、応じる必要はありません。
今回の事例のように、地主に立退料を支払ってもらう形で和解することも可能なので、不動産会社や弁護士などの専門家に相談のうえ、法的な解決を目指しましょう。
地主が代替わりしたことで起きたトラブル事例
地主の代替わりをきっかけに、地代をめぐって関係が悪化した事例です。
代替わり後の地主と話し合いを重ねましたが、折り合いがつかず、関係が悪化してしまいました。精神的にも疲弊してしまい、弊社までご相談いただきました。
そこで弊社では現地の状況を確認したうえで借地権を査定し、買取を実施しました。地主側とは弊社が直接交渉を行い、地代や承諾料の整理を経て譲渡契約を締結しました。
今回の事例のように、地主の代替わりによって、契約条件や関係性が変化するケースは少なくありません。元々の地主との口約束や慣例が引き継がれないことも多いため、代替わりで揉めてしまったときは弁護士や不動産会社などの専門家に相談しましょう。
契約内容が口約束だったために起きたトラブル事例
契約内容が口約束だったために、地主とトラブルに発展した事例です。
新しい地主が「正式な契約書もなく更新料も払っていないのはおかしい」と主張し、契約更新を拒否しました。そのまま話し合いがこじれてしまい、ご相談者様は精神的にも大きな負担を感じておられました。
そこで弊社は借地権の査定をおこなったうえで買取を実施しました。その後、地主と直接交渉して法的な根拠や過去の経緯を整理して丁寧に説明しました。
結果として、承諾料を相場の範囲に収めて合意が成立し、ご相談者様はスムーズに借地権を手放すことができました。
借地契約を口約束のまま続けていると、代替わりなどのタイミングで条件をめぐる誤解や対立が起こりやすくなります。後のトラブルを防ぐためにも、契約内容は書面で残し、更新料や地代などの条件を明確にしておくことが大切です。
借地権のトラブルを起こさないための対策
借地権は契約期間が長期にわたるため、世代交代や地価変動など、さまざまな要因によってトラブルが発生しやすい性質を持っています。
そのため、借地権のトラブルを防ぐためには、「今後も借地を所有し続けるのか」「売却して手放すのか」という方向性を明確にし、早い段階で専門家へ相談することが大切です。
借地権を今後も所有したい場合には、弁護士などの専門家に相談して契約内容の確認や地主との交渉を進めましょう。手放したい場合は、借地や底地に特化した不動産会社に相談し、買取や譲渡の選択肢を検討するのが現実的な解決策となります。
地主から承諾を得られず、すでにトラブルになっている場合は「借地非訟」の利用も検討しましょう。借地非訟とは、地主が正当な理由なく承諾を拒んだ場合に、裁判所へ「借地権譲渡の許可申立て」をおこない、地主の代わりに許可を得るための手続きです。
裁判所が譲渡の必要性や地主の事情を考慮したうえで判断するため、話し合いが行き詰まった際には有効な解決手段となります。
借地権を今後も所有したい場合:弁護士などの専門家に相談する
借地権を今後も所有し続けたい場合は、弁護士などの専門家へ相談しましょう。
借地契約は法律的にも複雑で、更新料や承諾料、増改築の可否などをめぐり、地主との認識にズレが生じやすい契約形態です。とくに長期間にわたって契約を続けている場合や、契約内容が曖昧なまま相続しているケースでは、トラブルが生じやすくなります。
弁護士に相談すれば、契約の法的有効性を確認し、借地人にとってどのような権利があるのかを整理したうえで、最適な対応方針を提案してもらえます。また、地主との交渉を弁護士が代理することで、感情的な対立を避けながら、法的根拠に基づいた冷静な話し合いが可能になります。
交渉が難航した場合でも、弁護士は調停や借地非訟、訴訟などの法的手続きにも対応できます。専門的なサポートを受けることで、不要なトラブルを防ぎつつ、自身の権利を守る行動がとれます。
借地権の更新や建て替え、譲渡などで少しでも不安がある場合は、早い段階で弁護士などの専門家に相談し、法的な観点から現状を整理しておきましょう。
借地権を手放したい場合:借地・底地専門の不動産会社に相談する
借地権を手放したい場合は、借地や底地の取引実績が豊富な不動産会社へ相談するのがおすすめです。
借地権は土地の所有権を持たない特殊な権利形態であるため、一般の不動産よりも売却手続きが複雑です。また、売却には地主の承諾が必要であり、承諾料の金額や交渉の進め方を誤ると、取引が進まなくなるリスクも抱えています。
借地権を売却する方法には、仲介業者に依頼して買主を探す方法と、不動産買取業者に直接売却する方法があります。時間をかけてできるだけ高く売りたい場合は仲介、早期に現金化したい場合は買取が適しています。
ただし、借地権は買主にとって扱いが難しい資産であるため、仲介では成約までに長い時間を要する傾向があります。早めに借地権を手放してトラブルの種から解放されたい場合は、専門の買取業者に依頼しましょう。
経験豊富な業者であれば、地代や承諾料の相場を踏まえて適正な価格で取引できるよう調整してもらえるため、無用なトラブルを避けられます。
まとめ
借地権はあくまでも土地を借りる権利であり、自由に土地を使えるわけではありません。売買や建て替えなどの際には地主の承諾が必要となり、その際に「承諾してもらえない」「高額な承諾料を求められた」などのトラブルが生じるケースがあります。
また、借地権の契約は数十年単位に及ぶため、その間に地価の変動や法律の改正、契約当事者の代替わりなどが起こり得ます。このような変化により、地代の値上げや更新料の請求などをめぐって対立が生じることもあります。
借地権のトラブルを防ぐためには、まず現在の契約内容を正確に把握し、法的な観点から整理することが大切です。借地権を今後も所有したい場合は、弁護士などの専門家に相談し、契約の有効性や更新・建て替えに関する権利を確認しておくとよいでしょう。
一方、トラブルが長引いている場合や、借地を所有し続けるのが難しい場合は、借地・底地専門の不動産会社に相談して手放すという選択肢もあります。専門の買取業者であれば地主との交渉にも慣れており、承諾料や譲渡手続きまでスムーズに進めることが可能です。
借地契約の途中解約はできますか?
契約期間に定めがない場合、または途中解約に関する特約を設けている場合は、借地人側から借地契約を途中解約することは可能です。なお、借地契約は長期契約を前提としているため、正当な理由がない限り地主から一方的に解約することはできません。
借地権付き建物を第三者に貸すことはできますか?
借地上の建物を第三者に貸す場合は、地主の承諾が必要です。地主の承諾を得ずに転貸すると契約違反となり、借地契約の解除や損害賠償を求められる可能性があります。