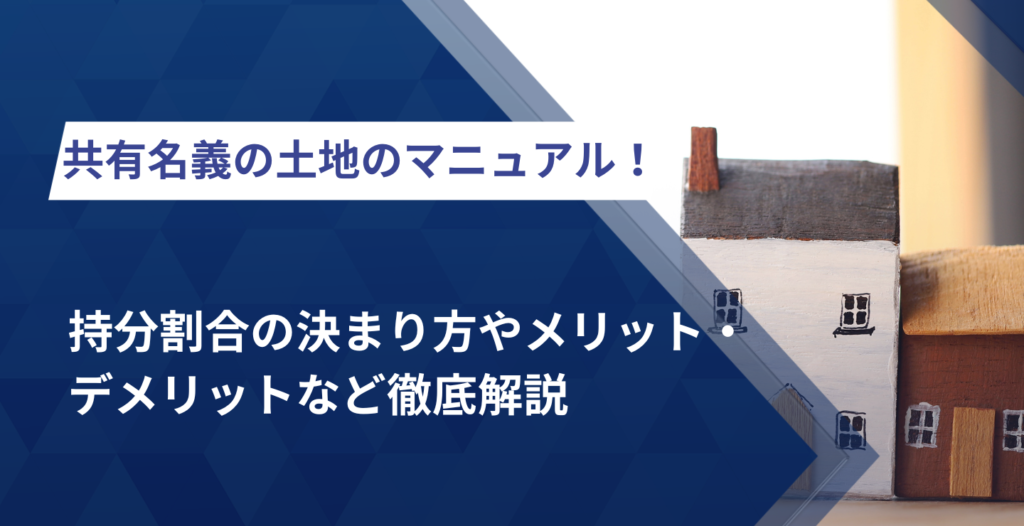共有持分の一部移転登記は注意が必要!方法や注意点、代わりの方法を解説

共有持分の一部移転登記は、不動産を複数人で共有している場合に、その持分のさらに一部を他の共有者や第三者に移すために行う登記手続きです。
「共有持分の一部移転登記は相続税対策になる」「共有持分の一部移転登記で、共有者どうしの持分割合を調整できる」と聞いたことのある方の中には、一部移転登記の実施を検討している方もいるでしょう。
しかし、一部移転登記により共有者が増えることで権利関係が複雑化し、共有不動産の利用方法で揉めるなどのトラブルが発生しやすくなる可能性があります。さらに相続税対策目的で一部移転登記を考えているとしても、登記費用がかかったり、場合によっては贈与税が発生し、むしろ損をしてしまう場合があるため、あまりおすすめはできません。
もし共有不動産の扱いに困っているのであれば、自己持分の売却をおすすめします。自己持分だけの売却は他の共有者に合意を得る必要がなく、自身の判断だけでできるメリットがあります。特に、共有持分専門の買取業者への売却は比較的短期間でできるため、早く共有状態から抜け出すための方法として有効と言えるでしょう。
本記事では、共有持分の一部移転登記の詳しい内容や他の登記手続きとの違い、手続きの具体的な方法などについて解説します。
その上で、共有持分の一部移転登記よりも最適な手段として「自己持分の売却」についても解説しますので、共有持分の取り扱いに困っている方はぜひ本記事を参考にしてみてください。
目次
共有持分の一部移転登記とは?
共有持分の一部移転登記とは、不動産を複数人で共有している場合に、その持分の一部を他の共有者や第三者に移すために行う登記手続きです。
不動産の「持分」とは、共有者それぞれが持つ所有権の割合を指し、持分を移転することで、所有権の割合が変更されることになります。
例えば、持分の1/3を持っている親がその持分の半分(つまり共有不動産全体の1/6)を子に渡す場合などに行われます。
この登記は、主に売買や贈与が発生した場合に行われる手続きです。たとえば、共有者が自分の持分の一部を他の人に売却したり、共有者が自分の持分の一部を無償で他人に贈与したりする場合に行います。
共有持分の一部移転登記とその他の登記との違い
共有持分の一部移転登記とその他の登記との違いを以下の表にまとめました。
| 登記の種類 | 不動産の所有者 | 移転する所有権の割合 |
|---|---|---|
| 共有持分一部移転登記 | 複数 | 持分の一部 |
| 持分全部移転登記 | 複数 | 持分全部 |
| 所有権一部移転登記 | 1人 | 不動産の一部 |
| 所有権全部移転登記 | 1人 | 不動産全体 |
| 共有者全員持分全部移転 | 複数 | 持分全部 |
共有持分の一部移転登記とその他の登記との違いの詳細は、以下で見ていきましょう。
持分全部移転登記との相違点は一部の持分を譲渡するかすべての持分を譲渡するか
共有持分の一部移転登記と持分全部移転登記の主な違いは、移転する持分の範囲です。共有持分の一部移転登記では、共有者が所有している持分のうち一部を他者に譲渡する場合に行われます。たとえば、1/2の持分を持っている共有者が、そのうちの1/4だけを譲渡したい場合にこの登記を行います。
一方、持分全部移転登記は、共有者が所有する全ての持分を譲渡する場合に行われます。つまり、共有者がその不動産に対するすべての権利を手放すときに行う登記です。このように、どの程度の持分が移転されるかが両者の相違点です。
所有権一部移転登記との相違点は不動産が共有名義が単独名義か
所有権一部移転登記との違いは、不動産が共有名義であるか単独名義であるかにあります。共有持分の一部移転登記は、不動産が複数の共有者によって所有されている場合に行われ、移転されるのは共有者の持分の一部です。
これに対し、所有権一部移転登記は、不動産が単独名義で所有されている場合に、その不動産の一部の権利を他者に譲渡する際に行われます。たとえば、単独名義の土地の一部の割合を売却する場合、この所有権一部移転登記が必要になります。
このように、両者の相違点は、不動産が共有名義が単独名義かという点にあることがわかるでしょう。
所有権全部移転登記は単独名義の不動産全体を譲渡する
所有権全部移転登記は、単独名義の不動産全体を他者に譲渡する際に行われる登記手続きです。この場合、所有者はその不動産に対する全ての所有権を他者に移転します。たとえば、ある人物が単独で所有している土地や建物を丸ごと他者に売却する場合、所有権全部移転登記が必要となります。
これに対し、共有持分の一部移転登記は、不動産が共有名義で所有されている場合に、その一部の持分を移転するために行われます。所有権全部移転登記は、不動産全体を単独で所有していること、そして全ての所有権が移転されることがポイントです。
共有者全員持分全部移転は共有者全員がすべての持分を譲渡する
共有者全員持分全部移転登記は、共有者全員がその不動産に対する全ての持分を譲渡する場合に行われます。これは、共有名義の不動産を全員で他者に譲渡する際に必要な登記です。たとえば、複数の共有者が共同で所有している土地や建物を丸ごと第三者に売却する場合に、共有者全員持分全部移転登記が行われます。この場合、すべての共有者が自分の持分を手放すことになります。
共有持分の一部移転登記と共有者全員持分全部移転との違いは、共有持分の一部移転登記が一部の持分のみを移転するのに対し、共有者全員持分全部移転は全ての持分が移転される点にあります。
共有持分の一部移転登記を行う具体的な方法
ここでは、共有持分の一部移転登記を行う具体的な方法について解説します。
共有持分の一部移転登記は、次の流れで行います。
- 必要書類を用意する
- 必要な費用を用意する
- 登記申請書を作成し法務局に提出する
- 登記完了後、法務局から書類を受け取る
それぞれのステップについて、以下で詳しく見ていきましょう。
必要書類を用意する
まず、共有持分の一部移転登記に必要な書類を用意します。
- 登記済証(登記識別情報)
- 住民票(持分を取得する人)
- 登記原因証明情報(売買契約書など)
- 印鑑登録証明書(持分を譲渡する人)
- 固定資産評価証明書
司法書士に手続きを依頼する場合は、書類の取得も手伝ってくれますが、委任状への押印など、一部の手続きには関与が必要です。そのため、司法書士に一任するのではなく、司法書士と協力して必要書類を揃えるようにしましょう。
必要な費用を用意する
書類と同時に、必要な費用も用意します。
共有持分の一部移転登記に必要な費用は以下のとおりです。
| 項目 | 費用の目安 | 負担する人 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 固定資産税評価額の2% | 原則として、買主・売主(当事者間の合意で決めることも可能) |
| 必要書類を取得する費用 | 2,000円程度 | 書類を取得する人 |
| 不動産取得税 | 宅地と住宅用の建物は固定資産税評価額の3% 住宅用以外の土地建物は4% |
買主 |
| 司法書士への報酬 | 1件3〜5万円程度 | 通例では買主 |
詳細は以下の記事で解説していますので、併せて参考にしてみてください。
登記申請書を作成し法務局に提出する
続いて行う手続きは、登記申請書の作成と法務局への提出です。この登記申請書の作成は、法的に正確な内容を記載する必要があるため、司法書士に依頼することが一般的です。司法書士は、専門的な知識を持ち、必要な書類や情報を正確に記載することで、登記手続きがスムーズに進むようサポートします。
登記申請書の作成にあたっては、移転する持分の詳細や取引の内容を明記することが求められます。たとえば、売買や贈与に基づく共有持分の一部移転であれば、その契約内容に基づいた情報が記載されます。もし自分で書類を作成する場合は、法務局が提供する記載例を参考にしながら進めることが重要です。書類には、不動産の所在地、移転する持分の割合、新しい共有者の情報などが記載されるため、これらの情報を正確に把握し、記載する必要があります。
登記完了後、法務局から書類を受け取る
登記申請書を提出し、法務局での審査が完了すると、登記手続きが正式に完了します。ここで、法務局から新たに発行される登記識別情報(いわゆる権利証)を受け取ります。登記識別情報は、共有持分を取得した人がその権利を証明するための重要な書類です。
登記完了後は、法務局から新しい登記簿の写しを取得し、その他の関連書類とともに、一式を持分を取得する人に返却します。新たな共有者が自らの権利を確認し、今後の不動産取引や管理に必要な情報を持てます。受け取った書類は、将来的に再び登記を行う際にも必要となるため、大切に保管しておくことが重要です。
共有持分の一部移転登記が行われるケースとメリット
共有持分の一部移転登記が行われるケースとして、以下の2つが挙げられます。
- 共有持分の一部の売買を行う
- 共有持分の一部の贈与を行う
各ケースについて以下で見ていきましょう。
共有持分の一部の売買を行う
共有持分の一部の売買を行うケースについて、具体例を用いてみていきましょう。たとえば、AとBがそれぞれ1/2ずつの持分を持つ土地があるとします。そして、Aが自己持分のうち1/2(共有不動産全体の1/4)をCに売却することに決め、共有持分の一部移転登記を行うとします。この登記手続きによって、Cが1/4の持分を取得し、土地はA(1/4)、B(1/2)、C(1/4)の3人で共有することになります。
このようなケースは、Aが土地の一部を現金化したいと考える場合に生じます。たとえば、急な資金が必要になった場合、土地全体を売却せずに持分の一部だけを売却することで、土地の所有権を一部保持しながら必要な資金を得られます。共有持分の一部売買は、共有者が資産の一部を有効活用する手段として利用されることが多くあるのです。
共有持分の一部の贈与を行う
共有持分の一部の贈与を行うケースでは、共有者が自分の持分の一部を無償で他者に譲渡します。たとえば、AとBが1/2ずつ所有しているA持分の1/5を息子Cに贈与する場合、共有持分の一部移転登記を行います。この登記手続きにより、Aが4/10、Bが5/10、Cが1/10の割合で共有することになります。
このような贈与は、相続税対策として用いられることが多くあります。Aが自身の持分を少しずつ贈与することで、生前に財産を移転させ、相続時の財産を減らせるため、相続税の負担を軽減することができるのです。
しかし、贈与を行う際には、贈与税にも注意が必要です。受贈者が年間合計で110万円を超える贈与には贈与税が課せられるため、贈与額が大きくなると相応の税負担が生じます。AがBに贈与する持分の評価額が200万円であれば、その差額に対して贈与税が課されることになります。さらに、贈与を行うことで登記費用もかかるため、その点も加味した上で贈与するべきか判断することが重要です。
共有持分の一部移転登記に関する注意点
共有持分の一部移転登記に関する注意点として、以下の2つが挙げられます。
- 共有者が増えるとトラブルに発展する可能性がある
- 共有持分を放棄する際は共有持分の一部移転登記はできない
各注意点について、以下で解説します。
共有者が増えるとトラブルに発展する可能性がある
共有持分の一部を他者に移転することで、共有者の数が増える場合があります。例えば、AとBが1/2ずつ持分を所有する土地があるとします。Aがその持分の半分、つまり1/4をCに売却することに決め、共有持分の一部移転登記を行います。この登記によって、Cが新たに共有者として加わり、その土地はA(1/4)、B(1/2)、C(1/4)の3人で共有することになります。このように、一部の持分が移転されることで、もともと2人だった共有者が3人に増えることになります。
共有者が増えると、意思決定が複雑化し、トラブルに発展する可能性が高まります。共有不動産の管理や使用に関して、共有者の同意が必要であるため、意見の不一致が生じやすくなります。なお、共有不動産に対する行為に必要な同意は行為の種類によって異なります。共有不動産に対する行為には、「変更行為」「管理行為」「保存行為」の3種類があり、それぞれについて、以下のように他の共有者の同意の必要性が異なります。
| 行為 | 具体例 | 必要となる同意 |
|---|---|---|
| 変更行為 | 不動産の売却・登記申請・不動産の改築 | 共有者全員の同意が必要 |
| 管理行為 | 一定期間を超えない賃貸借契約・軽微なリフォーム | 共有者の過半数の同意が必要 |
| 保存行為 | 不動産の修繕・無権利者に対する明け渡し請求 | 単独で可(共有者の同意不要) |
また、共有者の中に特定の人が自分の権利を強く主張したり、共有物の売却や賃貸に反対するケースも考えられるでしょう。
これにより、スムーズな管理が困難になり、最悪の場合、訴訟に発展することもあるのです。そのため、共有持分の一部を移転する際には、将来的なトラブルのリスクを十分に考慮し、慎重に判断することが重要です。
共有名義の土地を持つことで起きるトラブルの詳細については、以下の記事を参照してください。
共有持分を放棄する際は共有持分の一部移転登記はできない
共有持分を放棄したいと考える場合、その放棄を一部移転登記で処理できるのではないかと考えることがあります。しかし、実際には、共有持分の放棄では一部移転登記を行うことはできません。共有持分を放棄する場合、その持分は他の共有者に共有者の持分割合に応じて帰属するため、放棄者がその帰属先を決めることはできないのです。
このため、共有持分の放棄は、あくまで「全部移転」として処理されるべきものであり、放棄された持分は他の共有者に平等に分配されるか、共有者全体で再分配されることになります。
共有名義不動産の扱いについて困っているなら自己持分の売却がおすすめ
共有名義の不動産は、複数の共有者が所有権を持っているため、その管理や利用に関して合意を得ることが難しく、トラブルに発展しやすいという問題があります。特に、共有者間で意見が合わず、物件の売却や利用方法を巡って対立が生じることが少なくありません。
このような状況で悩んでいる場合、自己持分の売却が有効な解決策となります。持分の売却によって、共有名義不動産の煩雑な管理から解放され、現金化して別の資産運用に切り替えることができるのです。以下では、自己持分の売却方法として「他の共有者に売却する」方法と「共有持分買取専門業者に売却する」方法の2つをご紹介します。
他の共有者に売却する
自己持分の売却先としてまず考えられるのが、他の共有者に売却する方法です。
これは、共有者間で話し合いが可能であれば、比較的スムーズに取引が進む利点があります。他の共有者があなたの持分を購入することで、共有名義から単独名義に移行できる可能性もあり、不動産の管理や利用が簡単になるでしょう。また、共有者同士の信頼関係が保たれている場合、売却交渉が進めやすく、トラブルを避けることができます。さらに、他の共有者に売却することで、売却先が明確であり、取引の不確実性が低いというメリットもあります。
ただし、他の共有者があなたの持分を購入する意思がない場合や、購入資金を準備できない場合は、この方法が難しくなることもあります。そのため、事前に他の共有者と十分に話し合い、売却の可能性について確認しておくことが重要です。
共有持分買取専門業者に売却する
他の共有者に持分を売却することが難しい場合や、早急に現金化したい場合には、共有持分買取専門業者に売却する方法が有効です。
共有持分買取専門業者は、共有不動産の持分を積極的に購入し、その後の管理や利用に関するリスクを引き受けてくれるプロフェッショナルです。これにより、共有者間の交渉が難航する場合でも、迅速に持分を売却し現金化することが可能となります。
共有持分買取専門業者に売却するメリットは、手続きがスムーズで、専門的なサポートを受けられる点にあります。また、一般の市場で共有持分を売却するよりも、買い手が見つかりやすいという特徴もあります。
ただし、買取業者はリスクを引き受ける分、買取価格が市場価格よりも低くなる可能性があるため、その点を考慮に入れる必要があるでしょう。それでも、共有不動産の扱いに困っている場合、確実に売却できる方法として有力な選択肢となります。
弊社クランピーリアルエステートも、共有持分の買取を専門に取り扱っています。年間3,000件以上の相談実績があり、共有名義不動産を高値で買い取らせていただいていることが大きな強みです。また、司法書士や弁護士などの士業と密に連携することで、法律が絡む不動産問題にもしっかり対応できます。弊社では簡易無料査定もご提供しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
まとめ
共有持分の一部移転登記は、不動産の共有者が持分の一部を他者に譲渡する際に必要な手続きです。売買や贈与に伴う法的手続きや税務面での注意が求められるため、司法書士のサポートを受け、必要書類を準備して進めることが重要です。
また、共有名義不動産の扱いに困っている場合、自己持分の売却も有効な解決策です。他の共有者に売却するか、専門業者に依頼することで、迅速に現金化が可能です。正確な情報と専門家の助言を活用し、適切な対応を心がけましょう。
共有持分の一部移転登記に関するよくある質問
相続において共有持分の一部移転はできる?
相続において、共有持分の一部移転は基本的にできません。
相続が発生すると、被相続人の所有していた共有持分は、そのまま相続人に移転されます。相続時には、共有持分全体が各相続人に法定相続分に従って分割されますが、個別に共有持分の一部だけを特定の相続人に移転することはできません。
ただし、遺産分割協議において、相続人全員が合意すれば、特定の相続人が共有持分全体を取得し、他の相続人が他の遺産を取得するなどの調整は可能です。このようなケースでは、共有持分が一部移転されたかのように見える結果になることもあるでしょう。