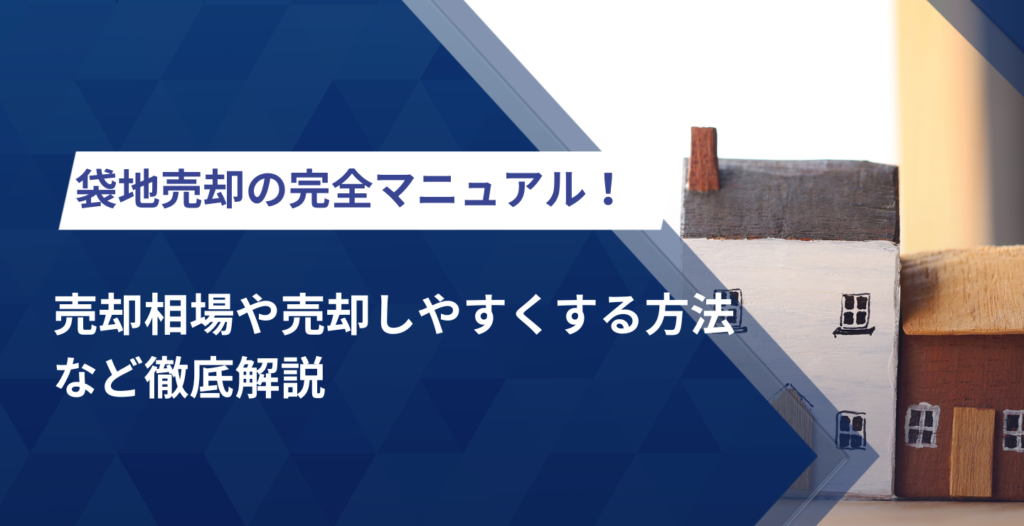未接道物件の売却マニュアル!売却が難しい理由から売却成功の対策も解説

未接道物件とは、建築基準法で定められた接道義務(幅4m以上の道路に敷地が2m以上接していなければならない)を満たしていない物件を指します。具体的には、周囲を他人の敷地に囲まれた袋地や、道路に接する部分(間口)が2m未満の旗竿地などが典型例です。
未接道物件は、建物が老朽化したり災害で損壊したりしても建て替えができず、増改築や大規模リフォームも制限されます。弊社にも「建て替えができないから住めない」「売却したいのに買主が見つからない」「処分方法が分からず固定資産税や維持費だけが負担になっている」といった相談が多く寄せられています。
また、未接道物件を所有することにはさまざまなリスクがあるため、基本的には敬遠されやすく買主がつきづらいのが実情です。その主な理由には以下が挙げられます。
- 再建築不可物件にあたるため建て替えや増改築などができない
- 住宅ローンを組んで購入するのが難しい
- 災害などの緊急時に車両の進入がしづらい
- 公道に出るには隣接する他の敷地を通らなければならない
- 解体・リフォーム工事が高額になりやすい
ただし、「駅近にある」「近くに商業施設がある」など条件が良ければ、売却できるケースもあります。一般的な売却相場は、近隣の建築可能な通常物件と比べて50〜70%程度が実務上の相場です。
そのままでは売却が難しい場合でも、以下のような対策を取ることで売却の可能性を高められます。
- 接道義務を満たせるように隣地の一部を買い取ってから売却する
- 隣地全体を購入して接道義務を満たした通常物件として売却する
- セットバックをして再建築可能にしてから売却する
- 未接道物件のまま隣地所有者に売却する
- 43条但し書き申請をして再建築可能な通常物件として売り出す
こうした対策が難しい、あるいは費用や時間をかけたくない場合は、買取業者への売却も1つの手です。買取業者であれば未接道物件を現状のまま直接買い取ってくれるため、短期間で現金化できます。
本記事では、未接道物件の売却が難しい理由や相場、売却できるケースと難しいケース、成功につなげるための対策などを解説します。
目次
未接道物件の売却は難しいと言われる理由
未接道物件とは、建築基準法第42条で定められた接道義務を満たしていない物件を指します。
接道義務とは「幅4m以上の道路に対して、敷地が2m以上接していなければならない」というルールです。
接道義務を満たさない物件は、新しく建物を建てる「建て替え」ができず、増改築や大規模リフォームも制限されます。そのため、生活上の不便やリスクが多く、売却を試みても買主が見つかりにくいのが実情です。
未接道物件の売却が難しい理由は以下のとおりです。
- 再建築不可物件にあたるため建て替えや増改築などができない
- 住宅ローンを組んで購入するのが難しい
- 災害などの緊急時に車両の進入がしづらい
- 公道に出るには隣接する他の敷地を通らなければならない
- 解体・リフォーム工事が高額になりやすい
弊社に寄せられる相談でも「不動産会社に仲介を依頼したが、1年以上買い手がつかない」といったケースは珍しくありません。
再建築不可物件にあたるため建て替えや増改築などができない
未接道物件とは、建築基準法42条で定められた「接道義務」を満たしていない物件です。接道義務(幅4m以上の道路に対して、敷地が2m以上接していなければならない)を満たさない物件は、建物の建て替えができない「再建築不可物件」となります。
具体的には、次のような土地が未接道物件(再建築不可物件)に該当します。
| 道路にまったく面していない土地 | 他人の土地や崖、川などに囲まれて道路に出られない袋地。民法上、隣地を通行できる権利「囲繞地通行権(民法第210条)」が認められているため、居住・生活には問題ない。ただし、通行範囲は必要最小限であり、通行料の支払いが必要なケースもある。 |
|---|---|
| 間口が2m未満の土地 | 建築基準法上の道路に接しているものの、接している部分(間口)が2mに満たない土地。旗竿地や細長い土地に多いケース。 |
| 間口と敷地を繋ぐ通路幅が狭い土地 | 間口は2m以上あるものの、敷地に続く通路の一部が2m未満の土地。旗竿地や敷地延長などに多いケース。 |
| 幅4m未満の道路に接した土地 | 間口は2m以上あるものの、接している道路の幅が4m未満の土地。都市計画区域のなかには、防火や避難の観点から6m以上を求められる地域もある。道道路幅を広げる方法として、セットバック(敷地を道路に提供して幅を広げる措置)を行うといった選択肢もある。 |
接道義務を満たさない未接道物件に該当する場合は、建物の建て替えができないことに加え、増改築や大規模リフォームについても制限されます。(建築基準法第42・43条)
買主からすると「老朽化しても建て替えができない」「災害で建物が倒壊しても再建できない」といったリスクを抱えることになるため、購入をためらわれ、売りに出しても買主が見つかりにくいケースが多いです。
建築基準法の改正によって大規模リフォームも事実上できなくなった
2025年4月の建築基準法改正により、「4号特例」と呼ばれる制度が縮小されました。4号特例とは、本来必要な建築確認申請(建物が法律の基準に合っているかを審査する手続き)の一部を、小さな住宅に限って省略できる仕組みです。
これまでは、未接道物件のように建て替えができない家でも、この特例を利用して大規模なリフォームや増改築を行うことができました。
しかし改正後は、耐震補強や間取りの大きな変更といった工事も必ず申請が必要になり、接道義務を守っていない未接道物件では許可が下りることはまずありません。
その結果、以前は可能だった「骨組みを残して内部を全面的に作り替えるスケルトンリフォーム」などが行えなくなり、現在は外装や内装の一部を直す程度の小さな修繕しかできなくなっています。
この改正によって、未接道物件は以前よりもさらに扱いづらくなり、売却を希望しても買主が見つかりにくい状況になっています。
住宅ローンを組んで購入するのが難しい
不動産を購入する際、多くの人は住宅ローンを利用します。ローンは購入する家や土地を担保にして融資を受ける仕組みですが、未接道物件は「建て替えができない」「将来の資産価値が低い」と判断されやすいため、担保として認められにくいのが実情です。
そのため、金融機関の大半は未接道物件を対象に住宅ローンを組むことを認めていません。結果として、買主は現金一括で購入するか、手持ち資金とあわせて金利の高いフリーローンなどを利用するしか方法がなくなります。
購入方法が限られることで、未接道物件は買主が見つかりにくく、売却も難しくなってしまいます。
災害などの緊急時に車両の進入がしづらい
未接道物件には、道路にまったく面していない土地の他、接している部分が2m未満と狭い土地、接している道路自体が狭い土地などがあります。
こうした条件のため、災害や事故が起きても緊急車両が敷地の近くまで入れない、または入りにくいケースが多く、救助や消火活動が遅れるリスクがあります。
具体的には次のような状況が考えられます。
- 火災が発生しても消防車が近くまで進入できず、消火や救助に時間がかかる
- 通路が狭い旗竿地や、他人の土地に囲まれた袋地では、大地震で建物が倒れて通路がふさがれ、救助が遅れたり避難が困難になったりする
- 急病人が出ても救急車が家の前まで来られず、処置が遅れる可能性がある
未接道物件は安全面で大きなリスクを抱えているため、買主にとっては不安が大きく、結果として需要が低くなり売却も難しくなります。
公道に出るには隣接する他の敷地を通らなければならない
未接道物件のなかには、道路にまったく接していない「袋地」と呼ばれる土地があります。袋地の場合、公道に出るためには必ず隣の敷地を通る必要があります。
民法では「囲繞地通行権(民法第210条)」が定められており、袋地の所有者は周囲の土地を通って、公道に出る権利があります。
ただし、通れる範囲は必要最小限に限られており、原則として通行料の支払いも必要です。ただし、土地を分ける分筆の結果として袋地になった場合は、通行料は無償とされています。(民法第212条・213条)
通行のたびに隣地を利用することへの心理的な負担は大きく、隣地との関係が悪化するとトラブルに発展するリスクもあります。こうした制約や不安は買主にとって大きなマイナスとなり、結果として未接道物件は売却が難しくなるのです。
解体・リフォーム工事が高額になりやすい
未接道物件は、建物の解体やリフォームを行う際に通常の土地より費用がかかるケースが多いです。
道路に面していない、あるいは接している幅が狭いと、工事用の重機やトラックを敷地の近くまで入れることができません。そのため、資材や廃材の搬出入を人力で運んだり、小さな車両を何度も往復させたりする必要があり、作業効率が大きく下がります。
結果として、工期が長くなり人件費や運搬費が増えるため、解体費用やリフォーム費用が通常よりも高額になりやすいのです。
例えば、一般的な木造住宅の解体費用は坪3~5万円、30坪なら90万~150万円程度が目安です。未接道物件の場合は人力作業や運搬コストが上乗せされ、さらに費用がかかることが考えられます。
リフォームについても、キッチン・浴室・トイレ・洗面所といった水回りすべてを改修する場合は100万~300万円前後が相場ですが、未接道物件では資材搬入や作業効率の悪さから追加コストが発生し、より割高になる可能性があります。
こうしたコスト増も買主にとっては大きな負担となり、売却をさらに難しくする要因となります。
どんな未接道物件なら売却できる?売却に期待できる・難しいケースを紹介
未接道物件は、建て替えができないなどの制限があるため、買主から敬遠されやすく、売却がなかなか進まないケースもあります。実際、弊社への相談でも「仲介を依頼したが買主が見つからなかった」「建築可能にするためにセットバックを勧められた」といった声が寄せられています。
とはいえ、条件次第では買主が見つかることもあり、必ずしも「売れない物件」というわけではありません。売却に向いているケースとそうでないケースを理解しておくことで、可能性を見極めやすくなります。
売却しやすい・しづらいケースの具体例は以下のとおりです。
| 売却が期待できるケース | 売却が難しいケース |
|---|---|
|
・立地条件が良い場合 ・建物が使える状態の場合 ・セットバックで建築可能になる土地の場合 ・投資家の需要がある土地の場合 ・他用途で利用可能な土地の場合 ・隣地所有者が買い増しを検討している場合 |
・立地条件が悪い場合 ・建築可能にするのが難しい土地の場合 ・解体費用が高い場合 ・通行トラブルのある土地の場合 ・工事コストが高い土地の場合 |
売却に期待できる未接道物件の例
未接道物件であっても、条件によっては購入希望者が現れることがあり、売却が期待できるケースがあります。以下は、比較的需要が見込まれる代表的なケースです。
| 立地条件が良い場合 | 駅や商業施設が近く、生活の利便性が高い土地であれば、接道に難があっても一定の需要が見込めます。 |
|---|---|
| 建物が使える状態の場合 | 築年数が浅い、またはリフォーム済みで、そのまま居住や賃貸利用が可能な場合は、購入希望者がつきやすいです。 |
| セットバックで建築可能になる土地の場合 | 接している道路が4m未満の場合でも、敷地の一部を道路として提供する「セットバック」を行えば、建築可能になる見込みがあります。将来的に建て替えができる可能性がある土地は、購入者にとって安心材料となり、売却につながりやすいケースがあります。 |
| 投資家の需要がある土地の場合 | 「低価格物件」を狙う投資家にとっては、リスクよりも安さが魅力となり、需要が見込めます。 |
| 他用途で利用可能な土地の場合 | 敷地が広く、駐車場や資材置き場など建物以外の用途として活用できる土地の場合は、未接道物件であっても売却できる可能性があります。 |
| 隣地所有者が買い増しを検討している場合 | 隣接する土地の所有者が土地を広げたい場合は、交渉の余地があり売却につながりやすくなります。例えば、隣地も袋地で通路を確保したい場、建築可能な状態にしたいと考えている場合は、成約につながりやすいでしょう。 |
未接道物件であっても「活用方法がある」「将来的な安心材料がある」といった条件がそろえば、買主の目に留まりやすく、売却に結びつく場合があります。
売却が難航しやすい未接道物件の例
未接道物件はもともと売却が難しい不動産ですが、条件が悪ければさらに買主がつきにくく、売却がほとんど望めないケースもあります。特に以下のような土地は、建築や利用に大きな制約があるため、敬遠されやすい傾向があります。
| 立地条件が悪い場合 | 周辺環境が悪く、交通や買い物の利便性が低いエリアでは購入希望者が集まりにくい。 |
|---|---|
| 建築可能にするのが難しい土地の場合 | 袋地など、建築可能な状態にするのが難しい土地は需要が低い。特に、隣地所有者との交渉が必要になるケースでは、話し合いがまとまらず接道義務を満たせない可能性もあり、売却は一層難航しやすい。 |
| 解体費用が高い場合 | 老朽化した建物が残っており、解体費用が高額になる見込みがあると、買主の負担が大きい分、購入を敬遠されやすい。 |
| 通行トラブルのある土地の場合 | 袋地の場合、公道に出るために他人の敷地を通らなければなりません。民法で「囲繞地通行権」が認められているものの、実際には通行の範囲や通行料をめぐって隣地所有者と揉めるケースが少なくありません。すでにトラブルが起きている土地は、購入希望者から特に敬遠されやすくなります。 |
| 工事コストが高い土地の場合 | 車両が近くまで入れない袋地や、敷地までの細い通路を資材運搬のたびに往復しなければならない旗竿地では、工事効率が大幅に落ちます。その結果、解体やリフォームなどの工事コストが割高になりやすく、購入希望者からも敬遠されやすい傾向にあります。 |
立地条件や権利関係、工事費用の高さなどがネックとなる未接道物件は、売却に時間がかかったり、大幅な値下げを求められたりするリスクがあります。
未接道物件の売却相場は通常物件の50%~70%程度が目安
不動産の売却価格は、立地や建物の状態、需要と供給のバランスなど、さまざまな条件によって決まります。そのため、「未接道物件はいくらで売れる」と明確に断言はできません。
とはいえ、まったく目安がないわけではありません。弊社に寄せられる相談事例をもとにすると、未接道物件の売却相場は、接道義務を満たした近隣物件と比べて50〜70%程度まで下がるケースが多いのが実情です。
例えば、近隣の同条件の物件が3,000万円で取引されている場合、未接道物件は1,500万〜2,100万円程度が目安となります。
条件によっては価格に差が出ます。駅に近い、商業施設が充実しているといった利便性の高いエリアであれば、通常物件の70%前後で売れるケースもあります。
一方で、袋地で再建築が難しく、さらに解体費用が高額になるような場合は、50%を下回る価格にしかならないこともあります。
このように、50〜70%という数字はあくまで目安であり、実際には個々の物件の条件を詳細に調査して判断する必要があります。
未接道物件の売却を成功させるための対策
未接道物件はそのままでは売却が難しいケースが多いですが、決して「売れない不動産」というわけではありません。売却を進めるためには、条件を改善したり、買主にとってのリスクを減らす工夫が必要です。
具体的には、次のような対策を講じることで売却の可能性を高められます。
| 対策 | 概要 | 向いているケース |
|---|---|---|
| 接道義務を満たせるように隣地の一部を買い取ってから売却する | 道路に接している部分(間口)が2m未満の場合、隣地の一部を購入することで接道義務を満たせる可能性があります。接道義務を満たせば、再建築可能となり通常物件として売却できます。 |
・間口が足りない旗竿地、形状の悪い不整形地である場合 ・隣地所有者が一部売却に応じてくれる場合 ・隣地の一部を購入するための資金がある場合 |
| 隣地全体を購入して接道義務を満たした通常物件として売却する | 隣地全体を買い取り、土地をまとめて接道義務を満たすことで、通常物件として売却する方法です。土地の規模が大きくなるため利用価値も高まります。 |
・隣地所有者が土地全体の売却を希望している場合 ・広い土地を求める買主が見込める場合 ・隣地全体を購入するための資金がある場合 |
| セットバックをして再建築可能にしてから売却する | 接している道路幅が4m未満の場合、敷地の一部を道路として提供(セットバック)することで再建築可能にできます。セットバック後は、通常物件として売却可能です。 | ・敷地に余裕があり、セットバック可能な場合 |
| 未接道物件のまま隣地所有者に売却する | 未接道物件の状態のまま、隣地所有者に売却する方法です。隣地所有者が土地を広げる、通路を確保する目的で購入するケースがあります。 |
・隣地も袋地などで、所有者が通路を確保したい場合 ・隣地所有者が買い増しを検討している場合 ・隣地所有者に買い取るだけの資金がある場合 |
| 43条但し書き申請をして再建築可能な通常物件として売り出す | 建築基準法43条の「但し書き申請」により、特例的に建築を認めてもらう方法です。許可が下りれば再建築可能物件として売却できます。 |
・行政との協議で許可が下りる可能性がある場合 ・用途や建築計画に柔軟な買主が見込める場合 |
未接道物件を再建築できる状態にするには、どうしても手間や費用がかかります。隣地所有者との交渉が必要になるケースもあり、必ずしもスムーズに進むとは限りません。
「できるだけ手間や費用をかけずに売却したい」という場合は、不動産買取業者に相談するのも1つの手です。買取業者であれば、不動産を直接買い取ってくれるため買主探しの必要がなく、未接道物件でもスピーディーに現金化できます。
接道義務を満たせるように隣地の一部を買い取ってから売却する
未接道物件を売却しやすくする対策として、隣地の一部を買い取って接道義務を満たすという手段があります。
接道義務をクリアすれば再建築が可能になり、土地の利用価値や資産価値が大きく向上します。その結果、通常物件として売却できるようになり、買主も見つかりやすくなります。
例えば、敷地と道路が接している間口が2mに満たない旗竿地などの場合、隣地の一部を購入して間口を2m以上に広げれば、接道義務を満たせます。このようにして土地の価値が高まれば、隣地購入にかかった費用を売却益で回収できる可能性もあります。
ただし、隣地所有者が売却に応じてくれることが前提であり、関係性が悪かったり、売却の意思がなかったりする場合には実現が難しいのが実情です。
隣地の一部を買い取る方法は、成功すれば未接道物件を通常物件として売却できる有効な手段です。しかしハードルが高いため、状況によってはセットバックや不動産買取業者への相談など、他の選択肢も検討することが重要です。
隣地全体を購入して接道義務を満たした通常物件として売却する
隣地全体を購入して接道義務を満たし、通常物件として売却する方法もあります。
未接道物件のなかには、間口が2m未満しかないため再建築ができないケースがありますが、隣地をすべて取り込むことで間口不足を解消できます。さらに、敷地全体が広くなることで土地の資産価値も上がり、売却の可能性が高まります。
例えば、間口が1.5mしかない旗竿地の未接道物件であっても、隣地全体を購入して道路に接する部分を広げれば、接道義務をクリアできます。その結果、再建築が可能になるだけでなく、敷地面積も大きくなるため、ファミリー層や事業用としての需要も見込める物件に変わります。
ただし、隣地の所有者が土地全体の売却に同意しなければ実現できず、購入費用も大きくなるため、資金的な負担は避けられません。
隣地全体を購入する方法は、一部を買い取る方法に比べて費用や交渉のハードルが高いものの、成功すれば土地の規模と資産価値が大きく高まり、未接道物件を魅力的な通常物件として売却できます。資金に余裕があり、隣地所有者との合意が見込める場合には有効な選択肢といえるでしょう。
セットバックをして再建築可能にしてから売却する
未接道物件の原因が「前面道路の幅が4m未満」である場合、セットバックを行うことで接道義務を満たすことができ、売却しやすくなります。
接道義務は「幅4m以上の道路に敷地が2m以上接していなければならない」というルールです。道路が狭いままでは再建築が認められませんが、境界線を後退させて道路幅を広げる「セットバック」を行えば接道義務を満たせるため、通常の物件として売却できるようになります。
例えば、敷地が幅3mの道路に接している場合、その境界を1m後退させることで幅4mを確保できます。これにより接道義務を満たし、再建築可能な土地として評価されるのです。費用は土地の形状や面積などによって異なりますが、30万〜80万円程度が目安で、自治体によっては補助金を利用できる場合もあります。
ただし、後退した部分の土地は道路として扱われるため、門や塀、建物を建てたり、駐車場として使ったりすることはできません。セットバックを行えば、敷地が狭くなることも覚えておきましょう。
費用や敷地減少といった負担はあるものの、セットバックは未接道物件を再建築可能に変える有効な手段です。再建築が可能になれば買主にとって大きな安心材料となり、売却のチャンスを広げることにつながります。
未接道物件のまま隣地所有者に売却する
買主が隣地の所有者であれば、未接道物件をそのままの状態で売却できる可能性があります。一般的な買主は「再建築できない」「住宅ローンが使えない」といった理由で購入をためらいがちですが、隣地の所有者にとってはむしろプラスの条件になることもあります。
例えば、隣地の所有者が買い増しをすれば、敷地が広がり資産価値が向上するだけでなく、駐車場の増設やより大きな建物の建築など、土地の活用の幅が広がります。
さらに、隣地も未接道物件の場合は、土地を買い取ることで接道義務を満たし、再建築可能な通常物件となるケースもあります。そのため、隣地所有者にとって未接道物件は意外と魅力的に映ることがあります。
ただし、隣地の購入には多額の資金が必要であるため、相手の経済的な余裕が前提になります。また、日頃から関係性が良好でない場合や、相手に購入の意思がない場合には交渉が難航することもあります。
一方で、隣地所有者に購入の意思があり条件が整っている場合には、売却が比較的スムーズに進む可能性もあります。特に「買い手が見つからない」と悩んでいる場合には、まず隣地所有者への打診を検討する価値があります。
43条但し書き申請をして再建築可能な通常物件として売り出す
未接道物件の原因が、前面道路が「建築基準法上の道路」として認められていないことである場合は、「建築基準法43条但し書き申請」によって例外的に再建築が可能になるケースがあります。これが認められれば、通常の物件として売却できるため、買主が見つかりやすくなります。
この申請は本来、建築を行う買主が行う手続きですが、売主が実際に認定を取得してから売却に出すことも可能です。あるいは、売主が事前に行政へ相談し、「この土地は43条但し書きで再建築可能になる見込みがある」と確認しておけば、その情報を買主に伝えられるため、安心材料として売却活動を有利に進められるでしょう。
| 制度 | 概要 | 条件 |
|---|---|---|
| 43条2項1号(認定制度) | 一定の要件を満たす場合、建築審査会の審査を受けずに、特定行政庁の認定で再建築が可能になる |
・敷地が幅4m以上の道と2m以上接していること ・その道が「公共の用に供される道」(例:農道や河川管理用通路など)、または道路位置指定の基準を満たす通路であること ・建てる建物が延べ面積500㎡以内の住宅や長屋などであること ・交通・安全・防火・衛生面で支障がないと判断されること |
| 43条2項2号(許可制度) | 一定の要件を満たし、建築審査会の許可を得ることで再建築が可能になる | ・包括同意基準や個別同意基準を満たすこと |
例えば、前面道路が「幅4m以上あるが公道として認められていない農道や管理用通路」の場合、43条2項1号に基づく認定を受けることで建築が可能になるケースがあります。
43条2項1号に基づく認定を受けられない場合は、43条2項2号の許可制度を利用し、建築審査会の許可を得ることになります。許可をを得るには、各自治体が定めている「包括同意基準」や「個別同意基準」を満たさなければなりません。
| 包括同意基準 | 自治体があらかじめ「この条件を満たせば許可します」と定めている基準。例として、幅は狭いが安全上問題がない通路に接しているケースなど。該当すれば審査がスムーズに進みやすい。 |
|---|---|
| 個別同意基準 | 包括同意基準に当てはまらない場合、建築審査会で一件ごとに審査される。交通や防災上の安全が確保できるかを判断し、同意が得られれば建築可能になる。 |
43条但し書き申請は「例外的に再建築を認める制度」であり、恒久的なものではありません。将来建て替えを行う際にも、その都度申請や許可が必要です。売主にとっては義務ではありませんが、可能性を調べておくことは買主の安心につながり、売却を有利に進める一手となります。
未接道物件の売却が難しい時は訳あり物件専門の買取業者に相談する
未接道物件は、「買主が見つからない」「費用や土地の形状の問題でセットバックができない」「隣地交渉がまとまらない」など、思うように売却が進まないケースが少なくありません。実際に弊社への相談でも「仲介で売れなかった」「隣地に断られた」といった声が多く寄せられています。
こうした場合は、訳あり物件を専門に扱う不動産買取業者に相談するのがおすすめです。仲介では敬遠されやすい未接道物件でも、買取業者ならそのままの状態で買い取ってもらえます。
買取業者に相談するメリットは以下のとおりです。
- 売れない未接道物件も売却に期待できる
- 数日〜1週間程度で売却できる
- 再建築不可のままで買い取ってもらえる
- 契約不適合責任を問われずに売却できる
手間や費用をかけずに確実に売却できるのが、買取業者を利用する大きな魅力です。
売れない未接道物件も売却に期待できる
未接道物件は仲介での売却が難しいケースが多いですが、訳あり物件専門の買取業者であれば売却できる可能性があります。仲介では「買主を探す」必要がありますが、買取業者は業者自身が直接不動産を買い取るため、購入者が見つからずに売却が進まないといった心配がありません。
また、訳あり物件を専門とする業者は、購入後に活用するためのノウハウを持っているため、接道義務を満たさない土地であっても柔軟に対応できます。
数日〜1週間程度で売却できる
仲介で不動産を売却しようとすると、買主を探して契約を結ぶまでに数週間から数ヵ月かかるのが一般的です。未接道物件の場合、買主が現れないケースも多いため、それ以上の期間が必要となるでしょう。実際、「1年以上売れなかった」という相談も少なくありません。
一方で、買取業者に依頼すれば、業者が直接不動産を買い取るため、買主探しの手間が不要です。最短で数日〜1週間程度で売却が成立し、スピーディーに現金化できます。仲介手数料もかからず、査定と売買契約のみで取引が進むため、手間や費用をかけずに済みます。
「できるだけ早く現金化したい」「仲介ではなかなか売れない」と悩んでいる方には、買取業者の利用がおすすめです。
再建築不可のままで買い取ってもらえる
買取業者に依頼する場合は、再建築ができない状態のままでも買い取ってもらうことが可能です。売主が事前にセットバックをしたり、隣地所有者と交渉して接道義務を満たしたりする必要はありません。資産価値を高めるための工事や手続きは、買取後に業者が行うため、売主は手間や費用をかけることなく、スムーズに物件を現金化できます。
買取業者は、物件の状態や買取後にかかるコストを踏まえて査定額を提示します。訳あり物件の取り扱いに慣れている業者であれば、買取後の活用方法をあらかじめ見据えているため、適切な価格での買取が可能です。
契約不適合責任を問われずに売却できる
不動産を個人の買主に売却する場合、売主には「契約不適合責任」が発生します。これは、売却後に物件に欠陥や不具合が見つかった際に、売主が修繕や損害賠償などで対応しなければならない責任のことです。
一方で、不動産買取業者に売却する場合は、取引時点で物件の状態を理解したうえで購入するため、契約不適合責任を免責とする契約が一般的です。
つまり、売却後にトラブルが発生しても売主が責任を問われることはほとんどありません。特に、隣地との通行権トラブルや再建築不可といった複雑な条件を抱える未接道物件では、この点は大きな安心材料となります。
未接道物件を売却せずに所有し続けることのリスク
未接道物件の多くは、1950年に建築基準法が施行される以前に建てられたもので、築年数が古い建物が多いのが実情です。そのため、相続などで所有しているケースも少なくありません。実際に居住していない物件であれば、使い道がないまま放置されてしまうこともよくあります。
しかし、活用していない未接道物件をそのまま所有し続けると、以下のようなリスクが生じます。
- 所有をするだけでも固定資産税や維持管理費を負担しなければならない
- 犯罪に悪用されてしまう可能性がある
- 子どもや孫に負の遺産として残してしまう
居住していない、活用していない未接道物件であれば、放置せずに売却を検討することをおすすめします。
所有をするだけでも固定資産税や維持管理費を負担しなければならない
未接道物件は利用していなくても、所有している限り毎年固定資産税を支払う必要があります。さらに、草木の伐採や建物の補修といった維持管理にも費用がかかります。
放置して管理が行き届かなくなると、建物の倒壊や近隣への被害といったトラブルにつながり、結果的に余計な出費を招く可能性があります。
加えて、老朽化した未接道物件を空き家のまま放置していると、自治体から「特定空き家」に指定されるリスクもあります。
特定空き家とは、空家等対策特別措置法第2条で次のように定められています。
- 放置すれば倒壊など著しく危険になるおそれがある状態
- 著しく衛生上有害となるおそれがある状態
- 管理不足で景観を大きく損なっている状態
- 周辺の生活環境を守るうえで放置が不適切とされる状態
特定空き家に指定されると、固定資産税の軽減措置(住宅用地特例)が外され、最大で税額が6倍になる可能性があります。
未接道物件を活用せずに空き家のまま所有し続けることは、経済的にも大きなリスクです。利用予定がないのであれば、放置せず売却を検討することが賢明な選択といえるでしょう。
犯罪に悪用されてしまう可能性がある
未接道物件を空き家のまま放置すると、人の出入りが少なく人目がつきにくいため、犯罪に悪用されるリスクが高まります。
実際に、不法侵入や放火、ゴミの不法投棄といった被害が報告されています。さらに、空き家が違法薬物の受け渡し場所や盗品の保管場所として利用されるケースもあり、社会問題となっています。
こうした事態が発生すれば、所有者として責任を問われる可能性も否定できません。防犯や地域の安全の観点からも、未接道物件を放置するのは危険です。利用予定のない未接道物件であれば、放置せず売却を検討しましょう。
子どもや孫に負の遺産として残してしまう
未接道物件は建て替えができず、居住や活用がしづらい物件です。そのうえ売却も難航するため、資産としての魅力が低いといえます。
所有者が未接道物件を処分せずに亡くなった場合、配偶者や子ども、孫に相続されることになります。しかし、相続した家族にとっては、毎年の固定資産税や草木の伐採・建物補修といった維持管理の負担ばかりが残り、事実上「負の遺産」となってしまうケースも少なくありません。
実際、弊社への相談でも「相続した未接道物件の処分に困っている」という声は多く寄せられています。
こうしたリスクを避けるためには、活用できない未接道物件を売却し、自分の代で現金化して処分しておくことが大切です。早めに売却に踏み切ることで、将来の家族に余計な負担を背負わせずに済みます。
まとめ
未接道物件は建て替えができないうえに、住宅ローンが利用できないケースも多く、買主から敬遠されやすい物件です。そのため、「売却したいのに買主が見つからない」「処分したいのに進まない」と悩む方が少なくありません。
売却を成功させるためには、セットバックや隣地の一部を購入して接道義務を満たすなど、再建築可能な状態にする工夫が必要になる場合もあります。ただし、これらの方法には費用や手間がかかるため、相続で取得した未接道物件などでは放置されてしまうケースも多いのが実情です。
しかし、未接道物件を空き家のまま所有し続ければ、固定資産税や維持管理費といった負担が増え続けるだけでなく、特定空き家に指定されて税金が跳ね上がったり、犯罪に悪用されたりするリスクもあります。
手間や費用をかけずに未接道物件を売却したい場合は、不動産買取業者に相談することをおすすめします。弊社のように訳あり物件を専門とする買取業者であれば、需要が低く処分に困る未接道物件でも直接買い取ることが可能です。まずは無料相談や査定を活用し、売却への一歩を踏み出してみてください。
よくある質問
未接道物件の買取業者はどう選べばいい?
未接道物件を安心して売却するには、業者選びが重要です。まずはホームページや口コミを確認し、実際に未接道物件をどの程度扱っているか、買取実績があるかをチェックしましょう。
そのうえで、最低でも3社程度に査定を依頼し、価格や対応を比較することが大切です。複数の業者に依頼していると伝えることで競争が働き、買取価格が上がる可能性もあります。実績のある業者を選び、複数査定で比較検討することが、未接道物件の売却を成功させる近道です。
未接道物件でもリフォームすれば売却できる?
未接道物件は再建築ができず、大規模リフォームにも制限がありますが、外壁の塗り替えや壁紙の張り替え、水回りの設備交換などの小規模なリフォームであれば可能です。修繕によって住環境を整えれば、自宅利用や賃貸需要を見込めるため、売却につながる可能性も高まります。
ただし、リフォームすれば必ず売れるわけではありません。どの程度価値を高められるか、費用対効果を見極め、隣地交渉や業者買取といった他の選択肢と比較検討したうえで判断することが大切です。