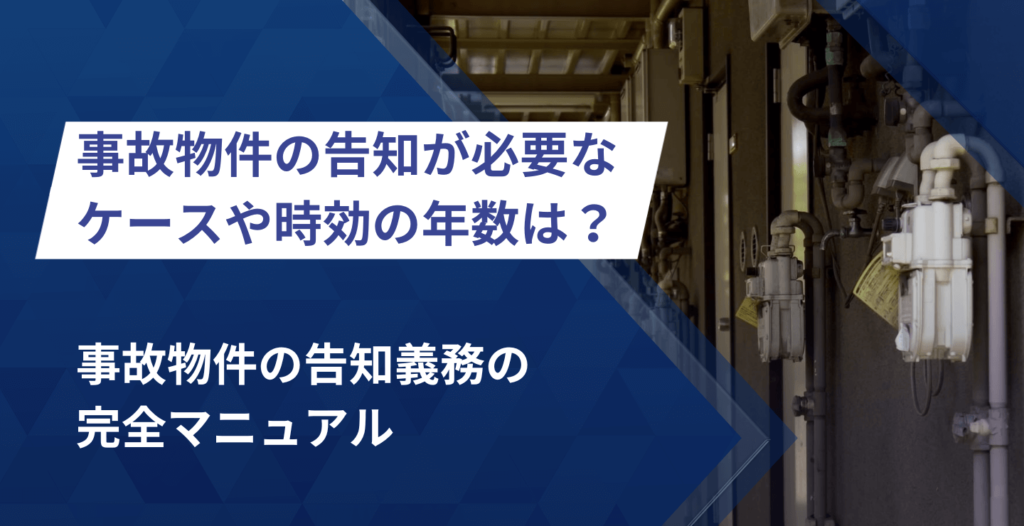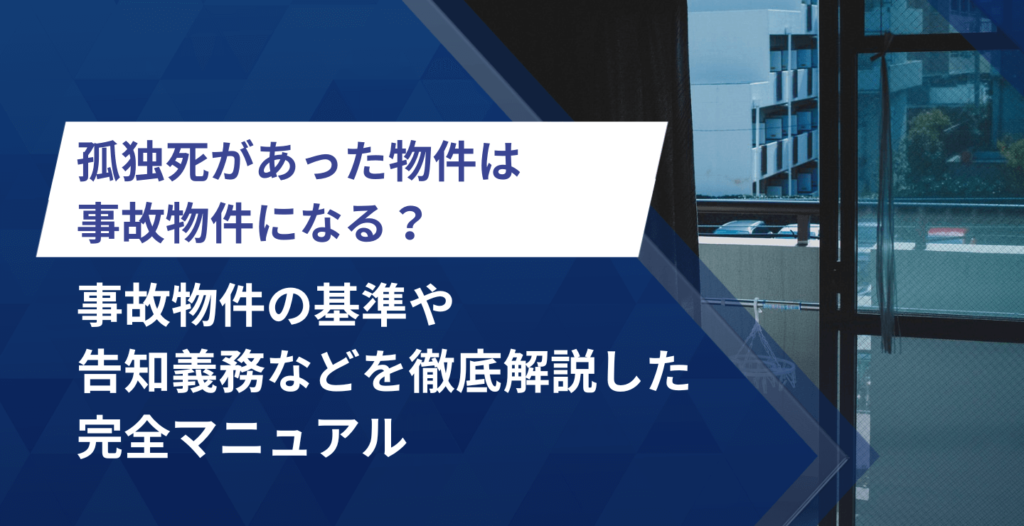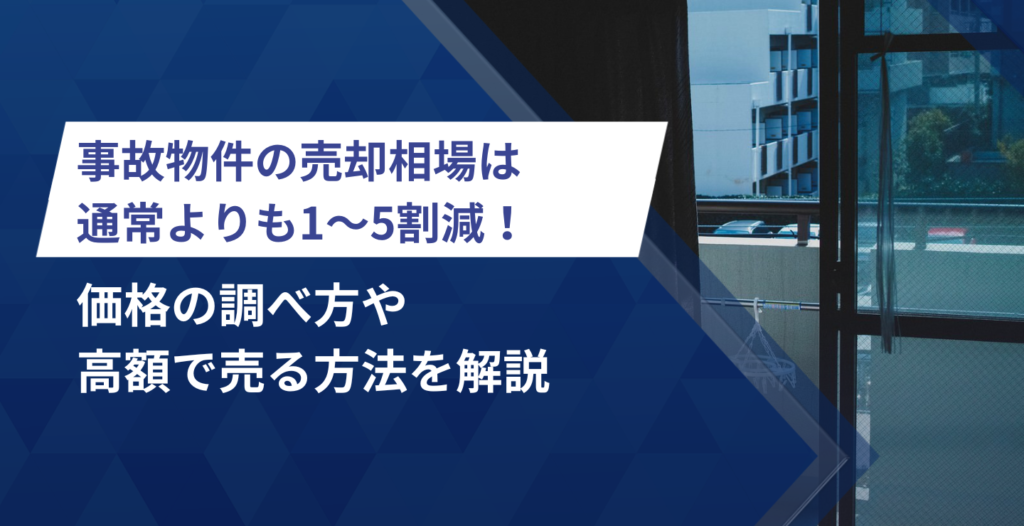事故物件は更地にしても告知義務はある?売却相場や高く早く売るための方法も解説

事故物件とは、過去に自殺・他殺・火災など人の死に関連する出来事があり、購入者や入居者に心理的な抵抗感を与える不動産のことを指します。事故物件には「告知義務」があり、売買や賃貸の際には人の死があったことを取引相手に知らせなければなりません。
人の死があったことを告知すると、取引相手には心理的な抵抗感が生まれ、売買相手や入居者が見つかりにくくなります。そのため、「更地にすれば告知義務がなくなり、売れやすくなるのではないか」と考える人もいるでしょう。
結論から述べると、建物を解体して更地にしても告知義務が消えることはありません。人の死があった建物が取り壊されたとしても、その土地で人の死があったという事実に変わりはないためです。
事故物件を更地にしても心理的瑕疵が消えるわけではないので、売却価格は市場相場より10%〜50%ほど下落する傾向にあります。具体的な売却相場は以下のとおりです。
- 特殊清掃が行われた事故物件:1割〜2割程度下がる
- 自殺があった物件:1割〜3割程度下がる
- 他殺があった物件:3割〜5割程度下がる
建物の大きさなどにもよりますが、解体費用は100万円以上になるケースが多いため、売却価格が下落すると利益がほぼ手元に残らないという状態になりかねません。
「事故物件の活用を考えていない」「少しでも高く買い取ってほしい」と考えているのであれば、訳あり物件専門の買取業者に依頼する方法がおすすめです。専門業者に依頼すれば、更地にせずそのままの状態で買い取ってもらえるだけでなく、お互いが条件に合意すればスピーディーに現金化できます。
本記事では、事故物件を更地にした際の告知義務や、事故物件に該当する事例、更地にするデメリットなどを解説します。更地にした場合の売却相場や更地にしたほうが良いケースなどもあわせて紹介するので、ぜひ参考にしてください。
目次
事故物件を更地にしても告知義務はなくならない
事故物件に該当する場合、不動産を売却・賃貸する際には、その事実を相手方に知らせなければなりません。これは「告知義務」と呼ばれ、不動産取引においては、取引相手に対して人の死など物件の重要な事実を知らせる義務があります。
「人の死があった建物を取り壊せば告知義務はなくなるのでは?」と考える方もいるかもしれませんが、事故物件を更地にしたとしても告知義務はなくなりません。
建物が取り壊されていたとしても、その土地で心理的瑕疵に該当する出来事が起きた事実は変わらないためです。たとえ人が亡くなった建物を取り壊して土地だけになったとしても、告知義務は残り続けます。
告知義務は法律上で明文化されているわけではありませんが、国土交通省が公表している「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」により、一定の基準が設けられています。
上記のガイドラインは、不動産会社や個人事業主など宅地建物取引業者が物件を売買や賃貸に出す際に、参照すべきルールとして位置づけられています。ガイドラインの内容に反した取引をおこなった場合、トラブルや訴訟に発展するリスクがあります。
ガイドラインには、事故物件の告知に関して以下のように記載されています。
宅地建物取引業者は、人の死に関する事案が、取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合には、これを告げなければならない。
宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン
「人の死に関する事案が、取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合」というのは、主に他殺や自殺、事故死(火災など)などが該当します。
「自然死・日常生活の中での不慮の死(転倒事故、誤嚥など)」については、買主・借主に対して告知する必要はないとガイドラインで定められているため、基本的に告知義務は発生しません。
たとえば「家族に看取られて自宅で亡くなった」というケースなどが該当します。自然死や病死は誰にでも起こり得る出来事であり、特別に心理的な嫌悪感を抱かせるものではないことから、原則として告知義務の対象外とされています。
建物を取り壊しても、上記と同様の基準で告知義務が生じることに変わりはないため、更地にするかどうかは慎重に検討する必要があります。
告知義務がある事故物件の例
前述したように、日常生活を送るうえで起こるであろう死因については告知は不要ですが、まず起こらない死因については告知義務が生じます。具体的にいえば、告知義務がある事故物件の例は以下のとおりです。
- 部屋の中で他殺・自殺・事故死があった物件
- 部屋の中で孤独死や病死などがあり特殊清掃を行った物件
- 共用部分で人の死があったマンションやアパート
それぞれの事例について、詳しく解説します。
部屋の中で他殺・自殺・事故死があった物件
部屋の中で発生した人の死が買主・借主の判断に影響を及ぼすと考えられる場合には、原則として告知義務が生じます。
たとえば、自殺や他殺など事件性のある事案や、原因不明の火災などで事故死があった事案は心理的な抵抗感が大きいため、契約前にその事実を説明しなければなりません。
とくに、事件性や報道などにより周知性が高まっている場合は、必ず告知することが求められます。
部屋の中で孤独死や病死などがあり特殊清掃を行った物件
自然死や病死であっても、発見までに時間がかかり、特殊清掃をおこなう必要があった場合には、原則として告知義務が発生します。
特殊清掃とは、体液や臭気、害虫の発生などがあり、通常の清掃では原状回復が困難な状態になった際におこなう専門的な作業のことです。
このようなケースでは、心理的瑕疵だけでなく、建物自体にダメージが残っていることが多く、物理的瑕疵としても扱われるのが基本です。
物理的瑕疵は買主・借主の判断に直接影響を与える要素となるため、人の死があったこととあわせて、特殊清掃をおこなったことも契約前に必ず伝えなければなりません。
共用部分で人の死があったマンションやアパート
マンションやアパートのような集合住宅では、専有部分だけでなく、共用部分で人が亡くなった場合にも告知義務が生じる可能性があります。
「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によると、「告げなくてもよい場合」として以下の例が記載されています。
【告げなくてもよい場合】
(中略)
②【賃貸借取引】取引の対象不動産・日常生活において通常使用する必要がある集合住宅の共用部分で発生した①以外の死・特殊清掃等が行われた①の死が発生し、事案発生(特殊清掃等が行われた場合は発覚)から概ね3年間が経過した後
③【賃貸借・売買取引】取引の対象不動産の隣接住戸・日常生活において通常使用しない集合住宅の共用部分で発生した①以外の死・特殊清掃等が行われた①の死
宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン
上記②③の記載を踏まえると、買主や借主が日常的に使用する共有部分で起きた死については、告知義務が生じることになります。たとえば、エントランスや玄関、エレベーター、廊下、階段などが該当します。
このように、物件の所有空間とは直接関係のない場所であっても、心理的な抵抗感を与える要素がある場合は、告知が求められることがあるため注意が必要です。
事故物件の告知義務が生じる期間は賃貸と売却で異なる
告知義務が生じる期間は、売却と賃貸で以下のような違いがあります。
- 売却契約|告知義務に時効はない
- 賃貸契約|事故が起きてからおおむね3年が時効
なお、賃貸契約で3年が経過している場合でも、入居希望者から問い合わせがあった場合は、隠さず事件・事故の発生について伝える必要があります。
人の死の発覚から経過した期間や死因に関わらず、買主・借主から事案の有無について問われた場合や、社会的影響の大きさから買主・借主において把握しておくべき特段の事情があると認識した場合等は告げる必要がある。
宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン
ここからは、国道交通省が定めた「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を参考に、それぞれの告知義務が課される期間について確認しましょう。
売却契約|告知義務に時効はない
事故物件を売却する際には、告知義務に明確な時効はありません。
「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」でも「何年経過すれば告知不要になる」という定めはなく、過去に人の死があった事実が買主の判断に影響を与えると考えられる場合、時間の経過にかかわらず告知が必要です。
そのため、人の死が起きたのが何年前であっても、売却の際にはどのような事件・事故が発生したのかを必ず伝えなければなりません。
売却では契約金額も大きくなりやすいため、トラブルを避けるためにも、正確な情報を事前に伝えることが大切です。
賃貸契約|事故が起きてからおおむね3年が時効
賃貸に出す場合の告知義務の期間は、事案発生からおおむね3年、特殊清掃が入った場合は事案が発覚してからおおむね3年が目安です。
国土交通省のガイドラインでは、以下のように記載されています。
【告げなくてもよい場合】
(中略)
②【賃貸借取引】取引の対象不動産・日常生活において通常使用する必要がある集合住宅の共用部分で発生した①以外の死・特殊清掃等が行われた①の死が発生し、事案発生(特殊清掃等が行われた場合は発覚)から概ね3年間が経過した後
宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン
原則として、事案の発生・発覚から3年が経過すれば、貸主側から事件・事故があったことを伝える義務はなくなります。
ただし、「おおむね」とされているように、必ずしも3年経てば告知義務がなくなるとは言い切れません。国土交通省のガイドラインでは、以下のようにも記載されています。
告げなくてもよいとした②・③の場合でも、事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案は告げる必要がある。
宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン
つまり、事件がメディアで大きく報道されたり、事件内容が猟奇的であったりする場合には、3年が経過していても告知が必要になります。
告知すべきかどうかの判断がつかない場合は、あとから契約不適合責任に問われないためにも、念のため事件・事故の内容を伝えておいた方が良いでしょう。
告知義務違反をすると損害賠償請求・契約解除などのリスクがある
心理的瑕疵があるにもかかわらず、買主・借主に伝えないことは告知義務違反に該当し、契約不適合責任に問われるリスクがあります。
契約不適合責任とは、引き渡された物件が契約内容と異なる場合に、売主や貸主が負う責任のことです。具体的には、以下のような形で責任を追及されることになります。
- 損害賠償請求
- 退去費用・裁判費用等の請求
- 契約解除請求
- 物件代金の減額請求
買主・借主から上記の請求を受けた場合、話し合いで解決するか、裁判で争うかのいずれかを選択することになります。裁判で争う場合、実際に告知義務を怠っているのであれば、買主・借主の訴えが認められる可能性が高いでしょう。
実際、過去には告知義務を怠った貸主に対し、損害賠償請求が認められた判例が存在します。
裁判の結果、貸主には本件事実を告知する義務があったとして、約64万円の退去費用、30万円の慰謝料、10万円の弁護士費用の合計104万円の支払いが命じられた。
参照:心理的瑕疵の有無・告知義務に関する裁判例について|国土交通省
さらに、心理的瑕疵の存在を知りながら故意に隠した場合は悪質と判断され、詐欺罪に問われる恐れもあります。
前述したとおり、事故物件を更地にしても告知義務が消えることはないため、告知を怠ると損害賠償請求・契約解除などのリスクを負うことになります。トラブルを防ぐためにも、心理的瑕疵の事実は正確に伝えることを心掛けましょう。
事故物件を更地にすることのデメリット
事故物件を更地にしても告知義務は残り続けるほか、以下のようなデメリットがあります。
- 建物を解体するための費用がかかる
- 住宅用地の特例が適用されなくなり固定資産税が高くなる
- 再建築不可物件の場合は新たに建物を建てられなくなる
それぞれのデメリットについて詳しく解説します。
建物を解体するための費用がかかる
事故物件を更地にしようとする場合、まず建物の解体費用が必要になります。
建物の大きさや構造によってかかる費用は異なりますが、解体費用・廃材の処分費用は少なくとも100万円はかかると考えたほうがよいでしょう。
解体費用の目安は以下のとおりです。
| 建物の構造 | 解体費用の相場 |
|---|---|
| 木造 | 3~4万円/坪 |
| 鉄骨造 | 3.5~4.5万円/坪 |
| 鉄筋コンクリート造(RC) | 5~7万円/坪 |
たとえば30坪の木造住宅でも、解体費用は100万円前後かかる計算になります。加えて、廃材の運搬や処分費用、場合によってはアスベストの除去費などが上乗せされるケースもあるため、さらに高額になることも珍しくありません。
更地にすることによって大幅に資産価値が上がるのであれば、解体を検討する余地はあるでしょう。しかし、解体にかかったコストを売却価格の上昇で回収できるとは限らず、結果として手元に残る金額が減ってしまうこともあります。
上記のような理由から、更地にする場合は「解体費用よりも売却価格の上昇が上回るかどうか」を見極める必要があります。
住宅用地の特例が適用されなくなり固定資産税が高くなる
建物を解体して更地にしてしまうと、固定資産税が高くなるというデメリットがあります。
土地に住宅用の建物が立っている場合に限り、「住宅用地の課税標準の特例」という税の軽減措置が適用され、税率が最大6分の1に下がるためです。詳細は以下のとおりです。
| 区分 | 固定資産税 | 都市計画税 |
|---|---|---|
| 小規模住宅用地(200㎡以下) | 標準税率×1/6 | 標準税率×1/3 |
| 一般住宅用地(200㎡超) | 標準税率×1/3 | 標準税率×1/3 |
よって、建物が解体されて更地になると、固定資産税の軽減措置が適用されず、支払わなければならない税金が最大6倍にまで上がります。
固定資産税は、毎年1月1日に不動産を所有している人に課税されます。固定資産税が大幅に上がることを考えると、長期間買い手が見つからなければ税金の負担が大きくなるため、購入者の当てもなく更地にしてしまうのは避けたほうが無難です。
再建築不可物件の場合は新たに建物を建てられなくなる
所有する建物が再建築不可物件の場合、建物を解体してしまうと新たな建築ができなくなり、結果として土地の利用価値や売却可能性が大きく下がる恐れがあります。
再建築不可物件とは、土地の形状・立地が現在の建築基準法を満たしていない不動産を指す。現行の建築基準法は1950年制定で、それ以前に建築された建物は現行の建築基準法に不適合であっても違法とはならない。
再建築不可物件の代表的な例として、接道義務を満たしていないケースが挙げられます。法律上、建物を建築するためには、敷地が幅4m以上の道路に2m以上接していなければならないというルールがあります。再建築不可物件のある土地に、新築物件を建てようとすると、接道義務を満たすために隣地を買い上げたり私道を作ったりと、土地の条件に手を加えなければなりません。
そのため、再建物を解体してしまうと、将来的に住居や店舗などを新たに建築することができず、活用の選択肢が極端に限られてしまいます。たとえば、駐車場や資材置き場としての利用は可能ですが、採算が取りづらいケースが多く、投資対象としても敬遠されがちです。
なお、再建築不可物件を建て替えすることはできませんが、条件を満たせばリフォームやリノベーションは行うことができます。つまり、再建築不可物件の場合、建物が残っているほうが活用の幅が広がるということになります。
所有している不動産が再建築不可物件かどうかを確かめるには、市町村役場の建築・道路関連の部署で確認してもらうのが確実です。登記簿謄本(登記事項証明書)や公図を持参したほうがスムーズに調べてもらえるため、事前に問い合わせて必要書類を確認しておくとよいでしょう。
事故物件は更地にしても売却価格が相場より10%〜50%ほど下落しやすい
事故物件は、事件や事故が発生したという事実から買い手がつきにくくなります。物件自体の条件によって売却価格は決まるため一概には断言できませんが、事故物件の場合は市場価格よりも10〜50%程度下落した価格が相場となります。
「事故物件を更地にすれば、心理的な抵抗感が薄れて相場が高くなるのでは?」と考えがちですが、その土地で心理的瑕疵の原因となった事案が起きたことに変わりはないため、建物がなくても価値の減少の影響は避けられません。
当サイトを運営する株式会社クランピーリアルエステートの買取事例を参考にした、事故物件の買取相場は以下のとおりです。
- 特殊清掃が行われた事故物件:1割〜2割程度下がる
- 自殺があった物件:1割〜3割程度下がる
- 他殺があった物件:3割〜5割程度下がる
立地によっては価格下落が抑えられるケースもある
駅前や繁華街など立地条件が非常に良い場合、大きな集客力が期待できることから、店舗や駐車場として需要が見込めます。
たとえば、前のコンビニを利用する際、そのお店ができる前に事件・事故があったかを気にする利用者は少ないものです。
また、心理的瑕疵は人によって感じ方が異なるため、「安く買えるなら問題ない」と考える買い手が現れる可能性もあります。そのため、立地条件が良い物件であれば、相場価格の10〜20%程度の下落で済むケースもあります。
特殊清掃が行われた事故物件:1割〜2割程度下がる
特殊清掃とは、遺体の痕跡や体液、においなどを除去し、室内を再利用できる状態に戻すための専門的な清掃作業です。建物内で孤独死や病死などが発生し、発見までに時間がかかった場合に特殊清掃が入ることがあります。
特殊清掃が入った事故物件は、心理的瑕疵の程度としては比較的軽度に分類されるため、市場価格の1〜2割程度の下落にとどまるケースが多いです。
ただし、購入希望者によっては「特殊清掃をおこなった」という事実に強い抵抗を感じる人もいるため、築年数や立地など他の要素も含めて総合的に判断されます。
また、更地にしたとしても、特殊清掃が必要なほどの事案が起きた土地として告知義務は継続するため、価格への影響が完全になくなるわけではありません。
自殺があった物件:1割〜3割程度下がる
室内で自殺があった物件は、心理的瑕疵による抵抗感を感じやすいことから、事故物件のなかでも避けられやすい傾向にあります。物件の立地条件などにもよりますが、売却価格は市場相場より1〜3割ほど下がることが多いです。
売却価格については、自殺の方法や発見までの時間、周囲に与えた影響などによっても印象が異なります。たとえば、火災や飛び降りによる自殺で建物が損傷していたり、ニュースで事件が報道されていたりした場合は、さらに買い手が付きにくくなる傾向にあります。
また、更地にしたからといって心理的瑕疵が消えるわけではなく、自殺があった土地としての事実は残り続けます。
なお、当サイトを運営する株式会社クランピーリアルエステートのこれまでの買取傾向からは、飛び降り自殺が発生した物件においては、相場価格からの下落幅が比較的抑えられる傾向が見られます。
目安としては、通常の物件価格と比べて1割程度の下落にとどまるケースもあり、人気の高い立地や知名度のあるマンションであれば、大きく価格が落ち込まずに売却できる可能性もあります。
他殺があった物件:3割〜5割程度下がる
事故物件の中でも、他殺があった物件は特に心理的抵抗が強く働く傾向にあります。そのため、売却価格は一般的に市場相場より3割〜5割ほど下落するケースが多いです。
さらに、事件の内容や報道のされ方によっては、下落幅がより大きくなることもあります。
たとえば、殺人事件の報道がテレビや新聞など全国的なメディアで大きく取り上げられた場合や、連続殺人の現場となった場合などは周知性が高まり、購入希望者から敬遠される度合いが強まります。
上記のようなケースでは買い手がまったく見つからず、最終的な売却価格が7割~8割程度まで下落することも珍しくありません。
更地にしても、事件のあった土地である事実は変わらないため、建物の有無にかかわらず価格の下落は避けられないと認識しておきましょう。
事故物件を更地にするのが適しているケース
心理的瑕疵に該当する事案が発生した場合、更地にしたからといってその事実が消えることはありません。
しかし、それでも更地にするのが適しているケースは以下のとおりです。
- 事件の印象が強くマイナスのイメージを払拭したい場合
- 建物の活用は難しいが土地なら活用できる場合
それぞれのケースついて、次の項目から詳しくみていきましょう。
事件の印象が強くマイナスのイメージを払拭したい場合
事件の印象が強く残っており、マイナスのイメージを払拭したい場合は、更地にするのも一つの手段です。
事件や事故が起きた建物がそのまま残っていると、周囲の人々にとっては「過去に人が亡くなった場所」という印象が強く残りやすくなります。視覚的な情報があることで、その記憶が呼び起こされやすくなるためです。
一方、建物を解体して更地にすれば、事件や事故を想起させる象徴的なものがなくなるため、地域住民の記憶も徐々に薄れていく傾向にあります。心理的な抵抗感も少なくなり、購入希望者にとっても前向きに検討しやすくなる可能性があるでしょう。
建物の活用は難しいが土地なら活用できる場合
建物がないことで土地を活用できる幅が広がるため、買い手が見つかりやすくなる効果も期待できます。
建物が残ったままだと、そのまま賃貸に出しても家賃は相場より安くなり、他の方法で活用するとしても解体から始めなければなりません。
更地であれば、大きな費用をかけずに整備できるコインパーキング・駐車場の経営や店舗の建設など、さまざまな活用が検討できます。
建物の状態が悪く活用できない場合は、更地にしたほうが売却しやすくなるでしょう。
更地にせずに事故物件を売るなら専門の買取業者に依頼する
更地にせず事故物件を売却するのなら、専門の買取業者に依頼する方法がおすすめです。買取業者に依頼するメリットは以下のとおりです。
- 仲介では売れなかった事故物件も買取に期待できる
- 数日〜1週間程度で事故物件を現金化できる
- 物件の状態にかかわらずそのままの状態で売却できる
- 契約不適合責任が免除される
事故物件を買取業者に依頼するメリットについて、詳しく解説します。
仲介では売れなかった事故物件も買取に期待できる
心理的瑕疵がある事故物件は、一般の買主を見つける仲介では売却が難航しやすいのが現実です。
内見の段階で過去の事件・事故が気になるという理由で購入を躊躇する人も多く、売却までに長い時間がかかるケースも少なくありません。
そこで事故物件の取り扱いに慣れている買取業者に依頼すれば、市場に出しても売れなかった物件や、問い合わせが全く入らないような物件でもスピーディーな買取が期待できます。
「更地にしても売れないかもしれない」と悩んでいる方にとって、現状のまま売却できる方法があるのは大きな安心材料といえるでしょう。
数日〜1週間程度で事故物件を現金化できる
仲介による売却は、買主探し・内見・条件交渉などの多くの過程を経るため、売却完了までに数ヶ月以上かかることも珍しくありません。とくに事故物件の場合は、内見の段階で断られることも多く、想定以上に時間がかかる傾向にあります。
一方、事故物件に対応している専門の買取業者であれば、査定から契約、引き渡しまでが非常にスムーズです。状況が整えば、最短数日〜1週間程度で現金化が可能です。
物件の状態にかかわらずそのままの状態で売却できる
事故物件を仲介で売却する場合、内見対応やイメージ改善のために、リフォームや清掃、不要品の処分などが求められることもあります。しかし、心理的瑕疵がある物件はどれだけ手入れをしても、買主の抵抗感からなかなか売れにくいのが現実です。
その点、事故物件に特化した買取業者であれば、原則としてそのままの状態で買い取ってもらえます。リフォームや清掃が必要なケースでも業者側に対応してもらえるため、売主の負担を最小限に抑えられます。
契約不適合責任が免除される
一般的な不動産売買では、売却後に物件の欠陥や説明不足が判明した場合に、契約不適合責任に問われる恐れがあります。事故物件の場合、心理的瑕疵に関する告知が不十分でトラブルに発展すれば、損害賠償請求などを受けるリスクがあります。
一方、不動産買取業者への売却では、契約不適合責任が免除されます。物件の状態や事情を理解したうえで買取が行われるため、売却後に責任を問われるリスクを避けられることが特徴です。
まとめ
心理的瑕疵にあたる事件や事故が起きた場合、買主・借主にその内容を伝える「告知義務」が発生します。たとえ建物を取り壊して更地にしても、告知義務が消えることはありません。
告知義務が生じる期間については、売却時は無期限、賃貸の場合はおおむね3年間が目安とされています。ただし、事件性や周知性が高い場合、3年が経過しても告知義務が生じるため注意が必要です。
なお、事故物件は心理的に抵抗感や嫌悪感、不安感を覚えやすく、買い手を見つけるのが難しいのが現実です。ただし、立地条件が良ければ相場に近い価格で売れる可能性もあるため、まずは不動産仲介業者に相談してみるのも一つの方法です。
一方で、自殺や他殺など心理的瑕疵が大きく、さらに立地条件なども悪い場合、住宅地としての需要が下がり、買い手が見つかりにくくなります。素早く事故物件を手放したい場合には、訳あり物件専門の買取業者に依頼してみましょう。
更地の事故物件に関するよくある質問
事故物件を更地にした場合、どんな活用方法がおすすめ?
心理的瑕疵のある物件は、駐車場やコインパーキング、トランクルーム、コインランドリー、店舗、民泊などの活用方法が考えられます。いずれにしても、心理的瑕疵が問題になりにくい活用方法がおすすめです。
駐車場やコインパーキング、トランクルーム、コンビニ、コインランドリーであれば、過去に事件・事故があったか気にする人は少ないでしょう。また、地震が少なく古くからの建物を何世代にもわたって使う国の人は、事故物件という概念自体がないことも多く、安価な民泊にすれば安定した収益を得られる可能性があります。
事故物件は解体して更地にしたほうがメリットがある?
「事故物件なら解体して更地にしてしまったほうが売れやすいのでは?」と考える人もいるでしょうが、更地にすると少なくとも100万円以上の解体費用がかかる上、固定資産税が上がることになるため、安易に解体するのはおすすめできません。ただし、更地にすることで土地の活用の幅が広がるというメリットはあります。
事故物件の建物を解体すべきか否かは、ケースバイケースで判断されるので、自己判断せずに不動産仲介業者または、不動産買取業者に相談するのがおすすめです。場合によっては、更地にしないほうが手元に多くお金が残ることもあります。
事故物件は更地にしても買主にバレる?
事故物件を売却する際は、建物が残っていても更地にしても買主に告知する義務があります。もし隠したまま売却できたとしても、近所の人SNS、過去の事件を取り上げたメディアなどからバレる可能性は十分にあります。
さらに、告知義務を怠り、心理的瑕疵を買主に伝えなかった場合、損害賠償を請求されるリスクがあります。心理的瑕疵の告知は売主の義務として、必ず取引相手に伝えるようにしましょう。