共有持分を買取業者に売るメリットは?業者を選ぶポイントも解説
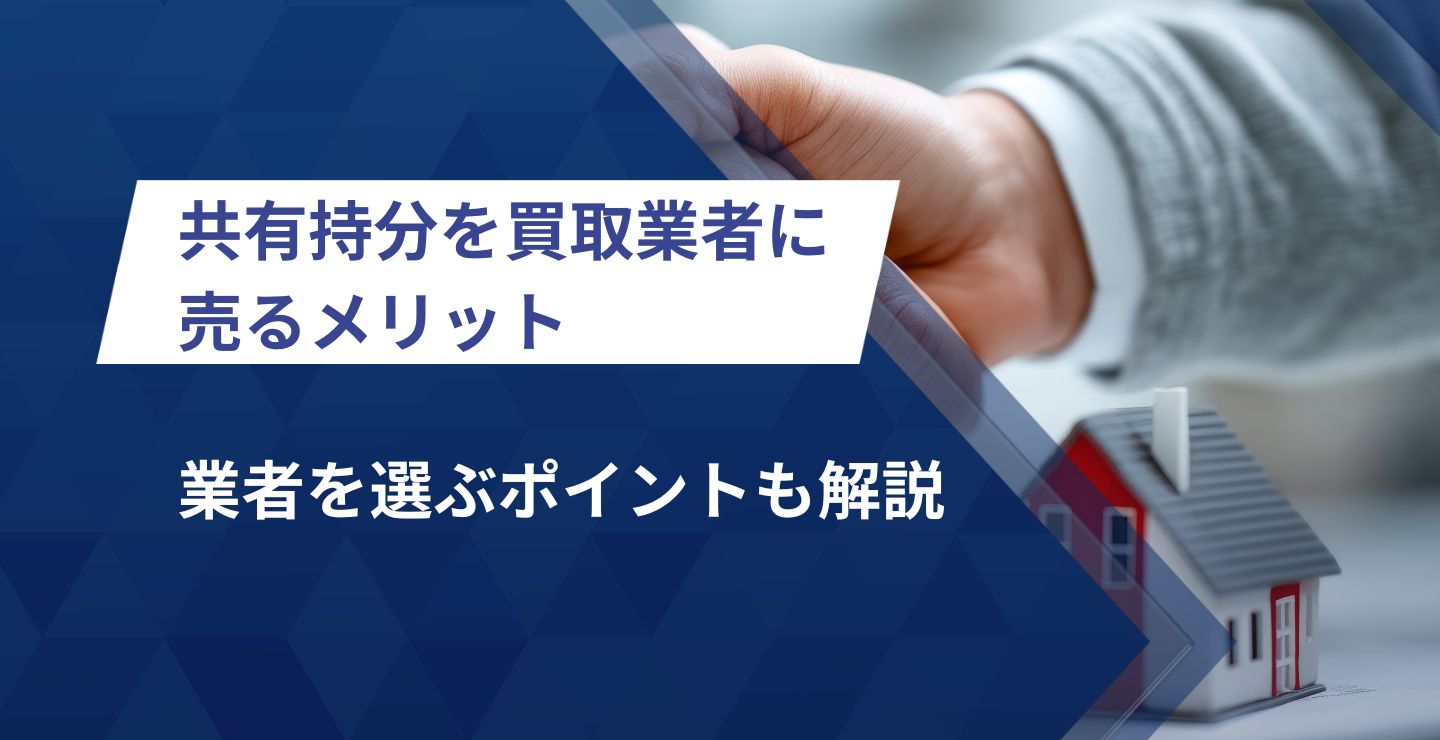
共有持分は、他の共有者の同意を得ずにご自身の判断だけで売却することが可能です。もっとも、一般の不動産市場においては「持分のみ」の取引需要は非常に限られており、仲介によって買主を探すのは現実的ではありません。そのため、実務上は弊社のように共有持分を専門に扱う買取業者へ売却されるケースがほとんどです。
共有持分を扱う買取業者は、他の共有者からも持分を取得して単独所有にまとめ、その後はリフォームや解体を経て、転売や賃貸といった活用方法につなげています。このような仕組みがあることで、権利関係に制限がある「持分のみ」でも売却が可能となります。
共有持分を業者に売却する代表的なメリットとしては、以下の点が挙げられます。
- 仲介に比べ短期間で現金化できる(即日~数週間)
- 仲介手数料が不要
- 契約不適合責任を免責できる(売買契約後に物件の瑕疵が見つかっても売主は損害賠償を免れる)
- 業者が直接の買い手となるため広告を出す必要がなく、他者に知られることなく売却できる
一方で、買取価格については注意が必要です。買取業者は将来的なリフォーム費用や解体費用を見越して査定を行うため、他の共有者へ売却する際の相場(不動産全体の価格×持分割合)と比べると1/2〜1/3程度に低くなる傾向があります。
そのため、共有持分の売却を検討される際には、こうしたメリットとデメリットを正しく理解したうえで、信頼できる業者を選定することが欠かせません。特に、豊富な実績と専門性を持ち、必要に応じて弁護士とも連携できる体制を備えた業者であれば、安心してお任せいただけるでしょう。
本記事では、共有持分を買取業者に売却するメリットと注意点、さらに信頼できる業者を選ぶためのポイントについて解説します。共有持分の処分で悩んでいる方にとって、現実的な解決手段を見極める参考になれば幸いです。
目次
共有持分売却で買取業者を利用するメリット
買取業者は、取得した持分をもとに他の共有者と交渉し、単独名義にしてからリフォームや解体などを行い、不動産の価値を高めて再販売や賃貸に活用することを目的としています。そのため、一般的な仲介市場では買い手がつきにくい共有持分でも、現金化できる出口を提供できるのです。
当社でも「早く現金化できた」「他の共有者に知られずに手放せた」といった声を多くいただいております。
共有持分を買取業者に売却することで、以下のようなメリットがあります。
- 仲介手数料がかからない
- 比較的短期間で共有持分を売却できる
- 契約不適合責任が免除される
- 他共有者に知られることなく自分の共有持分を売却できる
- 業者によっては売却が難しい特殊物件・訳あり物件でも対応可能
以下では、それぞれのメリットについて解説します。
仲介手数料がかからない
買取業者へ共有持分を売却するメリットの一つが、仲介手数料が不要になる点です。通常の不動産仲介では、売却価格の3%+ 6万円(別途消費税)が手数料として発生します。たとえば持分を1,000万円で売却した場合、約36万円の仲介手数料を支払う必要があります。
この手数料が、買い取り業者に売却した場合にはかからない、というのは大きな利点です。
ただし、知っておかなければならないのは、買取業者はリフォームや解体などのコストを見込んでいるため、仲介による売却価格よりも2〜3割程度低くなる傾向があることです。そのため「手数料がかからない=必ず得になる」とは限りません。
一方で、買取では仲介活動に要する時間や広告費用も不要で、早期に現金化できるため、固定資産税や管理費などの負担が軽減されるメリットもあります。結果として、ケースによっては仲介で売却する場合よりも手残りが多くなることもあります。
比較的短期間で共有持分を売却できる
当社へご相談いただくお客様の多くから、「できるだけ早く現金にしたい」といった切実な声をいただいております。買取業者を利用すれば、査定から売却完了までスピーディーに進められるのが最大のメリットです。不動産会社が直接買主となるため、最短で問い合わせから即日で現金化できるケースもあり、一般的には数日から数週間で手続きが完了します。
一方で仲介の場合、買主探しに時間がかかりやすく、通常の不動産でも売却完了まで数か月から1年以上かかることが珍しくありません。特に共有持分は一般の市場で需要が乏しく、仲介ではほとんど売れないケースも多いため、迅速な現金化を望む方には買取の方が現実的な選択肢となります。
契約不適合責任が免除される
仲介による不動産の個人間売買では、売主が「契約不適合責任」を負うことになります。契約不適合責任とは、売買契約で引き渡した物件が契約内容と違う状態だった場合に、売主が買主に対して負う責任のことです。2020年の民法改正で導入された制度で、従来の「瑕疵担保責任」に代わるものです。
たとえば雨漏りやシロアリ被害、境界の問題などが代表例で、修繕費や損害賠償を請求されることもあります。実際に、「売却後に予想外の出費が発生しないか心配」という声をいただくことも少なくありません。
ところが買取業者に売却する場合は、将来的なリフォームや修繕、解体を前提として買い取るため、この責任は基本的に免除されます。売主は売却後にトラブルへ巻き込まれるリスクを避けられ、安心して取引を進められる点が大きなメリットといえるでしょう。
他共有者に知られることなく自分の共有持分を売却できる
仲介を通じて共有持分を売却する場合、買主を見つけるために広告やインターネット掲載を行うのが一般的です。その結果、他の共有者や近隣住民に売却の意向が伝わってしまい、人間関係の悪化や不要なトラブルにつながる可能性があります。
一方、買取業者への直接売却であれば広告は不要であり、売却の事実が外部に知られるリスクはほとんどありません。
当社でも「不仲な共有者に知られずに処分できて安心した」といった声をいただくことが多く、共有状態にある不動産を静かに手放したい方にとって、大きな安心材料となります。
業者によっては売却が難しい特殊物件・訳あり物件でも対応可能
狭小地や袋地、接道条件を満たさない再建築不可物件、さらには事故物件などは、一般市場では買い手がほとんどつかず、仲介での売却は極めて困難です。そのため「売りたいのに全く問い合わせが来ない」「固定資産税だけが重荷になっている」と悩む所有者も少なくありません。こうしたケースでも、共有持分の買取業者なら将来的な活用方法を前提に買い取るため対応が可能です。
当社にも「他社では断られたが現金化できて助かった」というお声をいただいており、売却先が見つからない物件でも、早期に資産を手放せる出口がある点は大きなメリットといえるでしょう。
共有持分の買取を相談されたい方は、お気軽にお問い合わせください。
共有持分を買取業者に売る際の注意点
共有持分を買取業者に売却することは、スムーズに現金化できる反面、いくつか注意すべきリスクもあります。特に価格面と共有者との関係性については事前に理解しておくことが重要です。
代表的な注意点は次のとおりです。
- 買取価格が「不動産全体の価格×持分割合」より安くなりやすい
- 他共有者との関係が悪化する可能性がある
これらのリスクを踏まえ、実績豊富な共有持分専門の業者を選び、必要に応じて弁護士と連携して進めることが、安全で納得感のある売却につながります。
買取価格が「不動産全体の価格×持分割合」より安くなりやすい
共有持分を買取業者に売却する際の注意点として、多くのお客様からご質問をいただくのが「価格」についてです。一般的に、買取による売却金額は仲介での売却価格と比べて2〜3割ほど低くなる傾向があります。これは業者が買い取った後に他の共有者と交渉を行い、リフォームや解体をして価値を高め、再販売や賃貸運用を前提にリスクを引き受けているためです。そのため、仲介より低くなるのはやむを得ない側面があります。
ただし、共有者間の関係性や物件の立地・状態によっては、必ずしも大幅に安くなるとは限りません。少しでも高く売却するには、共有持分に特化した実績豊富な業者に相談することが重要です。適切な相場感を持ちつつ、複数社に査定を依頼して比較することで納得感のある取引が実現できます。
他共有者との関係悪化やトラブルに発展するおそれがある
共有持分を買取業者に売却する際には、他の共有者との関係性に影響が及ぶ可能性がある点に注意が必要です。特に親族や知人が共有者である場合、突然の売却によって驚きや不安を与えてしまい、今後の人間関係にしこりを残すことも考えられます。
こうしたトラブルを避けるためには、できる限り事前に売却の意思を伝えておくことが望ましいでしょう。たとえ反対意見が出たとしても、誠意をもって説明することで理解を得やすくなり、売却後の関係悪化を防ぐ助けになります。
さらに、弁護士と提携している共有持分専門の買取業者であれば、売却に伴う法的な懸念や共有者間の調整についても適切にアドバイスを受けられるため安心です。専門的なサポートを受けながら進めることで、共有者との関係に配慮しつつ、安全でスムーズな取引が実現できます。
共有持分の売却に買取が向いている人・向いていない人
共有持分の売却方法は「買取」と「仲介」で大きく異なります。どちらを選ぶべきかは、ご自身の状況や目的によって判断することが大切です。以下に、買取が向いている人・向いていない人の特徴を表にまとめました。
| 買取が向いている人 | 仲介(買取が向いていない人)に向いている人 |
|---|---|
| できるだけ早く現金化したい(相続税・生活費・債務返済など資金需要がある) | 売却価格を最優先し、時間をかけても高値で売りたい |
| 他の共有者と関係が悪化しており、話し合いが難しい | 共有者と協力して不動産全体を売却できる状況にある |
| 広告などを通じて周囲に知られたくない | 売却活動をオープンに行っても問題がない |
| 狭小地・袋地・再建築不可物件・事故物件など、仲介市場では売れにくい物件を所有している | 人気エリアや好条件の物件を所有し、市場に出せば需要が見込める |
| 契約不適合責任などのリスクを避けたい | 売却後のトラブルリスクをある程度負担してでも高額売却を目指す |
このように、スピードや安全性を重視するなら「買取」、価格の最大化を重視するなら「仲介」が適しています。
早期に共有持分を売却したい方は、一度ご相談ください。
信頼できる共有持分買取業者を選ぶポイント
共有持分の売却は、専門的な知識と経験が求められるため「どの業者に依頼するか」が大きな鍵となります。特に、共有持分専門の買取業者を選ぶこと、そして豊富な実績や口コミ・評判が良い業者を選ぶことが重要です。
実績のある業者であれば、過去のノウハウを活かして適切な査定を行い、売却後のトラブルも最小限に抑えることができます。
「クランピーリアルエステート」では、共有持分専門として多数の相談実績があり、専門性の高さから安心して依頼できる体制を整えています。共有持分の売却をお考えの方は、こちらのページからお気軽にご相談ください。
査定価格の根拠を明確に説明してくれる業者を選ぶ
共有持分の売却に際し、どの業者に依頼すべきか悩む方も多いかと思います。その中で特に重要なのが、「査定価格の根拠を納得できるように説明してくれる業者を選ぶ」ことです。業者によっては査定額だけを伝えるケースもあり、お客様からは「なぜこの価格なのか、根拠がわからない」といった不安の声もあります。
このような不安を払拭するためにも、「何を基準に評価したのか」「どのような市場データや物件条件に基づいているのか」といった説明がきちんとある業者を選ぶことが重要です。また、複数の業者に査定を依頼することで、相場の確認だけでなく、各社の対応や専門性も比較できます。一社ごとに異なる査定基準や対応スタイルを見て判断することで、より信頼できる業者に絞り込むことができます。
価格に納得感があることは、売却への安心感にもつながります。共有持分という特殊な資産を扱う以上、専門知識や専門性のある業者を複数比較する姿勢を持ちましょう。
弁護士と連携している業者を選ぶ
共有持分を売却すれば、その後の共有者との交渉や対応は基本的に買い取った業者が引き継ぐことになります。そのため売却した本人が直接トラブルに巻き込まれることは少なくなりますが、売却前にすでに共有者との関係が悪化している場合や、売却後に思わぬ問題が生じた場合には、法的な知識や対応力を持つ業者のサポートが安心につながります。
特に弁護士と提携している共有持分専門の業者であれば、トラブルの予防や解決に必要なアドバイスを受けられるほか、紛争性が高い物件でも対応可能なケースがあります。一方で、弁護士と連携していない業者では、複雑な案件は「対応不可」とされることも少なくありません。
売却後の安心や、難しい案件への対応力を重視するなら、弁護士と連携している業者を選ぶことが大切です。
共有持分を買取業者に売却する際の流れは?
共有持分の売却は、一般的な不動産売却と比べてスピーディーに進められることが多いです。全体の流れはシンプルで、以下の3つのステップを踏むことで完了します。
- 共有持分の買取業者を選定し、査定を依頼する
- 条件を確認し、売買契約を締結する
- 決済を行い、持分の移転登記を完了する
共有持分の買取業者を選定し、査定を依頼
売却の第一歩として重要なのが、複数の買取業者に査定依頼を行うことです。理由はシンプルで、査定先を一社だけに絞ると相場の妥当性が判断しにくく、最適な価格で売却できないリスクがあるからです。一般的には最低でも3社から査定を受けることが推奨されており、そうすることで提示価格の違いから相場感を把握しやすくなります。
また、査定額の高低だけで業者を評価するのではなく、問い合わせ対応の速さや説明の丁寧さなど、対応品質にも注目するべきです。レスポンスが迅速で親身な対応をしてくれる業者は、信頼感と安心して進められる取引につながります。
こうして選定した複数社を比較することにより、価格面・対応面ともに納得できる業者を見極めることができ、売却成功への第一歩となります。
売買契約を締結
複数の査定結果や対応を比較し、依頼する買取業者を1社に決めたら、次のステップは売買契約の締結です。契約時には、売却条件や支払方法、引き渡し時期などを明記した契約書を作成し、署名捺印を行います。この段階で合意した内容が法的に効力を持つため、条件面をしっかり確認してから契約することが大切です。
また、不動産売買契約では宅地建物取引士による重要事項説明も行われ、売主として安心して進められる体制が整えられています。
決済・持分移転登記
売買契約が締結されると、次は代金の受け取りと共有持分の移転登記を行います。決済当日は、通常司法書士が立ち会い、代金の入金確認と同時に登記申請を進めるため、安全性の高い取引が可能です。代金を受領した後、法務局に所有権移転登記を行うことで正式に買主へ名義が移り、売却は完了となります。
クランピーリアルエステートの買取事例
共有持分の売却といっても、その内容や状況は物件ごとに大きく異なります。当社では、土地や建物、空き家から商業物件まで、さまざまなケースに対応してきました。
ここでは、実際に当社が手掛けた買取事例を紹介します。具体的な金額や期間、物件の特徴を確認することで、共有持分売却のイメージをより具体的に持っていただけるはずです。売却を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。
1. 土地・建物の共有持分を2億1,000万円で買い取った事例
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ①概要 | 相続をきっかけに兄弟間で争いが発生。売主は不動産を使用しておらず、資金化を希望。共有者が売却に消極的で交渉が難航していた。弊社が調整を行い、共有持分を買い取ることで問題を解決。 |
| ②物件の詳細 | 渋谷区初台と国分寺市光町の土地・建物。2名で共有。渋谷区は共有者夫婦が居住、国分寺市は共有者の息子家族が居住。法定相続登記済み。 |
| ③買取までの期間 | ご相談から約1か月 |
| ④買取金額 | 2億1,000万円 |
兄弟で相続した不動産をめぐり、生前贈与や金銭問題から関係が悪化していました。売主は使用していない共有持分を早期に資金化したい一方、居住している共有者が売却に消極的で交渉が進まない状況でした。弊社が間に入り調整を行い、最終的に2億1,000万円で共有持分を買取ることで、売主様の希望を実現しました。
2. 土地の共有持分を2,000万円で買い取った事例
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ①概要 | 長年姪と土地を共有していたが、地代が入らず固定資産税だけを負担していた。共有者との関係も良好ではなく、将来の相続リスクを回避するため売却を決断。弊社が持分を買取り、共有状態を解消。 |
| ②物件の詳細 | 東京都北区の土地。土地のみ共有で、建物は共有者が単独所有・居住。元は両親から兄弟へ相続、その後姪と共有に。 |
| ③買取までの期間 | ご相談から約2週間 |
| ④買取金額 | 2,000万円 |
本件は、地代収入がないまま固定資産税を払い続ける負担を抱えた売主様が、将来の相続リスクに備えて共有状態を整理したいと希望されたケースです。共有者は姪で関係が良好ではなく交渉も難しかったため、弊社が間に入り持分を2,000万円で買取。短期間で売主様の不安を解消する結果となりました。
3. 土地の共有持分を970万円で買い取った事例
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ①概要 | 売主と実姉が共有する土地上に、それぞれが単独所有する建物が存在。売主は転居のため自身の持分を処分したいが、姉による買取や土地の分筆が困難な状況。弊社が持分を買取り、共有状態の解消を支援。 |
| ②物件の詳細 | 神奈川県中郡大磯町の土地。両親から相続し、売主と姉が持分2分の1ずつ共有。土地は共有だが建物は各自が単独所有。固定資産税は折半。 |
| ③買取までの期間 | ご相談から約1か月 |
| ④買取金額 | 970万円 |
本件は、相続により姉と共有する土地を売却したい売主様が、分筆や姉による持分取得が難しく行き詰まっていたケースです。弊社が適正な査定を行い、売主様の持分を970万円で買取。共有状態を解消し、安心して転居できるようサポートしました。
4. 古家付き土地の共有持分を1,600万円で買い取った事例
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ①概要 | 相続により兄弟3名で共有していた不動産。売主様は利用できず、他の共有者2名が居住していたため活用できない状態。売却を打診したが不仲により話が進まず、弊社が持分を買取ることで問題を解決。 |
| ②物件の詳細 | 東京都足立区の古家付き土地。土地は約3分の1、建物は約4分の1を所有。現況は古家あり・入居者あり。境界未確定の状態で、一括決済にて対応。 |
| ③買取までの期間 | ご相談から約2か月 |
| ④買取金額 | 1,600万円 |
本件は、兄弟3名で相続した古家付き土地の持分を所有する売主様が、活用できない状態を解消するため相談された事例です。共有者同士の不仲により話し合いが進まず不安を抱えていましたが、弊社が現況のまま調査・査定を行い、持分を1,600万円で買取。共有状態を整理し、売主様に安心を提供しました。
5. 空き店舗の共有持分を1,460万円で買い取った事例
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ①概要 | 被相続人の死去により、売主と義弟が不動産を共有することに。過去の親族間裁判により関係が悪化しており協議が不可能。老朽化した空き店舗の処分に困り、弊社が持分を買取り問題を解決。 |
| ②物件の詳細 | 東京都目黒区の空き店舗。売主は土地・建物の持分4分の1を所有。建物は長年空き家で老朽化。共有者との協議は困難で、売主は遠方居住。 |
| ③買取までの期間 | ご相談から約1か月 |
| ④買取金額 | 1,460万円 |
本件は、相続をきっかけに義弟と共有することになった空き店舗の持分売却事例です。建物は老朽化が進み、共有者とは過去の裁判で関係が悪化しており、協議による処分が不可能でした。遠方に住む売主様は精神的負担も大きく、弊社が1,460万円で持分を買取ることで早期に問題解決を実現しました。
まとめ
本記事では、共有持分を買取業者に売却する際のメリット・注意点・業者の選び方を具体的に解説しました。仲介では買い手が見つかりにくい共有持分でも、買取であれば仲介手数料が不要で、数日〜数週間で現金化できるうえに、契約不適合責任を免除できる安心感があります。その一方で、仲介と比べて2〜3割程度安くなる傾向があることや、共有者との関係悪化リスクといった点には注意する必要があります。
これらのポイントを念頭に置いて共有持分専門で実績のある買取業者を選び、査定根拠を丁寧に説明してもらえるか、弁護士と連携できる体制があるかを確認することが大切です。売却を成功させるには、短期的な現金化だけでなく、将来の資産設計や家族への負担軽減も見据え、複数業者に相談して比較検討する姿勢が欠かせません。
「クランピーリアルエステート」では、共有持分専門として多数の相談実績があり、専門性の高さから安心して依頼できる体制を整えています。共有持分の売却をお考えの方は、お気軽にご相談ください。
共有持分についてのよくある質問
買取業者へ共有持分を売却する以外に共有状態を解消する方法は?
共有状態を解消する方法は、必ずしも「買取業者への売却」だけではありません。共有者同士の話し合いや法的手続きを通じて解消する道もいくつか存在します。以下の表では、代表的な方法とその概要を簡潔にまとめています。
| 解消方法 | 方法の概要 |
|---|---|
| 共有者全員の合意のもと不動産全体を売却 | 共有者全員が合意し、一括で物件を売却して代金を持分割合で分ける方法。最も公平かつシンプルだが、全員の同意が必須。 |
| 自分の共有持分を他共有者へ売却 | 他の共有者に自身の持分を売却し、単独所有にまとめる方法。共有者同士で合意が取れればスムーズに解消可能。 |
| 自分の共有持分を放棄 | 自らの持分を放棄し、他の共有者に無償で帰属させる方法。代金は得られないが、税金や管理負担から解放される。 |
| 共有物分割請求訴訟を提起 | 裁判所に訴訟を提起し、競売や分割を通じて強制的に共有関係を解消する方法。合意が困難な場合の最終手段。 |
| 分筆する(土地の場合) | 土地を物理的に分割して登記をやり直し、それぞれが単独所有できるようにする方法。土地の形状や規制により制約あり。 |
共有持分を買取業者へ依頼する場合に必要な書類は?
共有持分を売却する際には、契約や登記に必要な書類をあらかじめ揃えておくことが重要です。書類が不足していると手続きが遅れたり、取引が成立しない場合もあるため、早めの準備をおすすめします。以下に主な必要書類をまとめました。
| 書類の種類 | 書類の説明 | 取得先 |
|---|---|---|
| 登記簿謄本(登記事項証明書) | 不動産の権利関係や持分割合を証明する書類 | 法務局 |
| 公図・地積測量図 | 土地の位置や面積を確認するための図面 | 法務局 |
| 固定資産税評価証明書 | 不動産の評価額を示す書類で、登録免許税の算出にも使用 | 市区町村役場 |
| 身分証明書(運転免許証・マイナンバーカードなど) | 売主本人確認のために必要 | 各本人が所持 |
| 印鑑証明書 | 実印と併せて売買契約や登記申請に必要 | 市区町村役場 |
| 住民票 | 住所確認や登記申請で必要になる場合がある | 市区町村役場 |
詳しくは関連記事でも解説していますのでご参照ください。
共有持分を買取業者に売却する際にかかる費用・税金は?
共有持分の売却では、仲介手数料が不要な一方で、必要となる費用や税金があります。以下に主な項目をまとめました。
費用
- 印紙税:売買契約書に貼付する収入印紙代。契約金額に応じて数千円〜数万円
- 登記費用(司法書士報酬など):所有権移転登記を行う際に必要。数万円程度
税金
- 譲渡所得税(所得税・住民税):売却益が出た場合に課税。所有期間によって税率が異なる
- 復興特別所得税:譲渡所得税に上乗せされる税金
詳しくは関連記事で解説しています。




