借地権の売却相場は?実際の売却事例や相場の調べ方など徹底解説
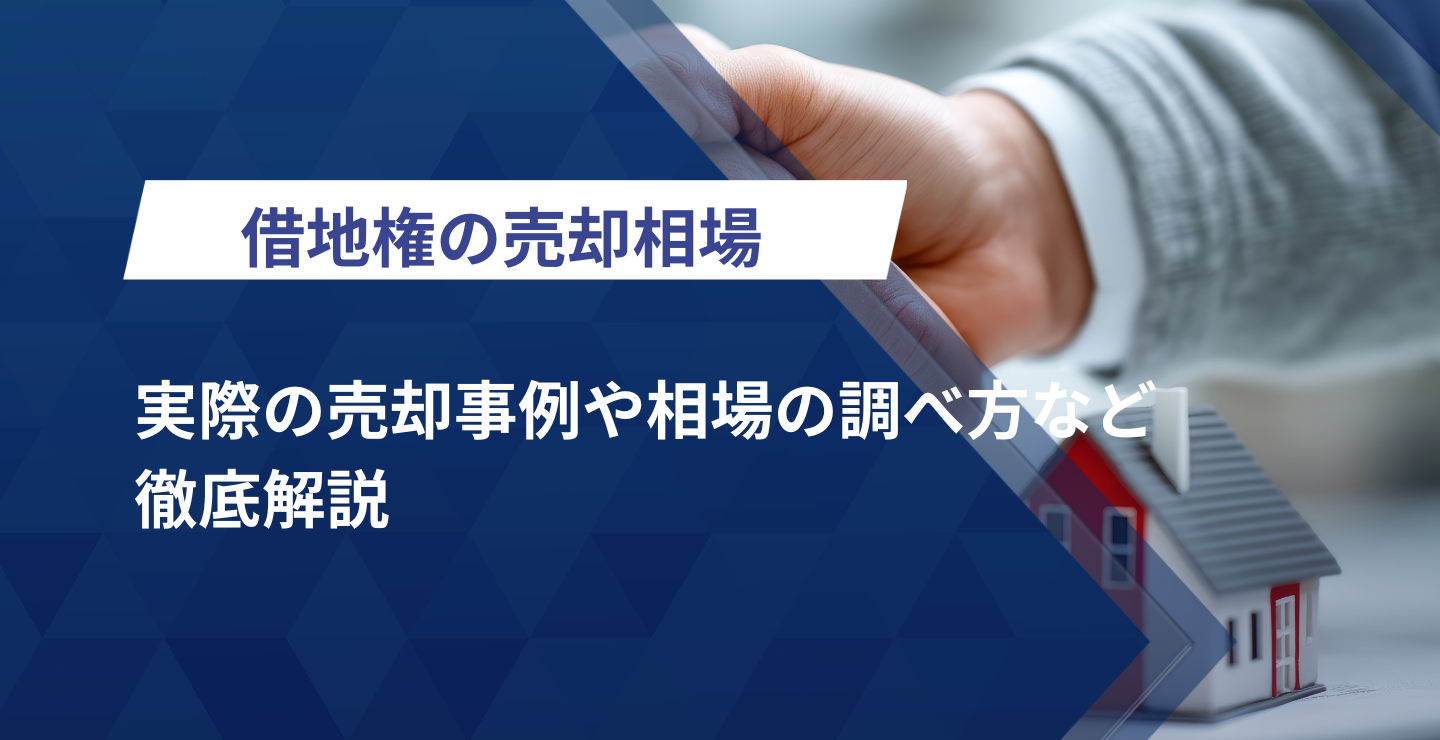
弊社では、借地権の売却に関して「借地権を手放したいが、相場がわからない」「実際の売却事例を知りたい」といったご相談をいただくことがあります。
結論から述べると、借地権の売却相場は「誰に買い取ってもらうか」で以下のように異なります。
| 売却先 | 相場の目安 |
|---|---|
| 地主 | 更地価格の50〜70%程度 |
| 買取業者 | 更地価格の50%程度 |
| 不動産投資家など(仲介) | 更地価格の70%程度 |
借地権の売却相場は売却先によって変動し、地主なら更地価格の50〜70%前後、買取業者なら更地価格の50%程度、投資家など仲介での売却なら70%程度が目安となります。
ただし、実際の売却金額は立地条件や地主との関係性、借地権の種類などさまざまな要因によって変動します。そのため、上記はあくまでも目安の一つであると認識しておきましょう。
また、借地権を譲渡する際には地主の承諾を得る必要があり、その際に「譲渡承諾料」の支払いを求められる場合があります。さらに、建物の解体費用や仲介手数料、登記費用、譲渡所得税などの費用・税金がいくら発生するのかも、事前に確認することをおすすめします。
本記事では、借地権の売却相場について、売却先ごとに詳しく解説します。実際の売却事例や売却相場の計算方法、さらには売却にかかる諸費用についてもあわせて紹介するので、ぜひ参考にしてください。
目次
借地権の売却先と売却相場の一覧
借地権は土地そのものではなく、あくまで「土地を利用する権利」であり、通常の土地に比べて市場価値は低く評価されます。借地権を買ったとしてもその土地を自由に使えるわけではないため、通常の更地価格よりも安い水準で売却されるのが基本になるのです。
そのため、前提として借地権を通常の土地と同じ相場で売却をするのは難しいと認識しておきましょう。
そのうえで、借地権の売却相場は、誰に売却するのかによっても変動しやすいです。あくまで実務経験をもとにした数値ですが、借地権の売却相場は下記が目安になります。
- 借地権を地主に売却する場合:更地価格の50%〜70%程度が相場
- 借地権を専門の買取業者に売却する場合:更地価格の50%程度が相場
- 借地権を投資家などに仲介で売却する場合:更地価格の70%程度が相場
仲介での売却がもっとも高値になりやすく、次いで地主への売却、買取業者の順で相場が下がる傾向にあります。
借地権を地主に売却する場合:更地価格の50%〜70%程度が相場
借地権を地主に売却する場合の相場は、更地価格の50%〜70%程度になることが多いです。この割合は、国税庁が定める「借地権割合」を基準としています。
ただし、地主は「安く買いたい」と考える一方、借地人は「高く売りたい」と考えるため、どちらが交渉を持ちかけたのかによって相場が異なります。
| 提案者 | 売却相場 |
|---|---|
| 地主から借地人に提案 | 更地価格の60~70%程度 |
| 借地人から地主に提案 | 更地価格の50%程度 |
地主側から買い取りを希望する場合は、借地権割合に基づいた売却価格での取引が基本となります。また、地主が借地人に退去を求める形になるため、引越し費用や新居の取得費用を補償する目的で価格が上乗せされることもあります。
そのため、地主側から買取交渉を持ちかけた場合の売却相場は、更地価格の60%〜70%になることが多いです。
地主が買取を希望する理由として「別の目的で土地を使いたい」「新たに賃貸経営を始めたい」などがあります。借地権を取り戻すことで土地を自由に活用できるため、地主にとっては相応の金額を提示してでも買い取るメリットがあります。
一方、借地人から地主に買い取りを依頼する場合、借地権割合そのままの価格で売却できるケースは少なく、更地価格の50%程度にとどまるケースが多いです。
借地人にとって第三者への売却は地主の承諾や譲渡承諾料が必要となり手間がかかるうえ、買い手が見つかりにくいという事情があります。そのため「地主に買い取ってもらいたい」という依頼自体が弱い立場を生み、結果として更地価格の50%前後に落ち着きます。
このように、地主への売却は借地権割合を基準としつつも、どちらが交渉を持ちかけたのかによって売却相場に差が生じるのが基本です。
借地権を専門の買取業者に売却する場合:更地価格の50%程度が相場
借地権を専門の買取業者に売却する場合、更地価格の50%程度が相場となります。
買取業者は、買い取った不動産を転売したり賃貸にしたりすることで利益を得るというビジネスモデルを採用しています。不動産を安く仕入れなければ利益が少なくなってしまうため、借地権の買取価格は更地価格の50%程度に落ち着くことが多いのです。
さらに、借地権は譲渡や建て替えに地主の承諾が必要となるなど制約が多く、市場での流通性が低いというリスクを抱えています。将来的に地主との交渉が難航したり、トラブル解決のために費用が発生したりする点を考慮し、あらかじめ査定額を抑えて提示します。
そのため、買取業者に売却する場合は、地主への売却や仲介での売却よりも相場が低くなるのが基本と覚えておきましょう。ただし、確実に買い取ってもらえるため、早期の現金化を希望する人や手間を減らしたい人にとってはメリットがあります。
借地権を投資家などに仲介で売却する場合:更地価格の70%程度が相場
仲介業者を通して借地権を売却する場合の相場は、更地価格の70%程度が目安です。
借地権を仲介で売却する場合、投資家や投資法人など資金力のある層にアプローチできるため、地主や買取業者への売却に比べて高値での取引につながりやすいのが特徴です。
とくに、都心部や商業地など土地の需要が高く希少性があるエリアでは、購入希望者も多く集まりやすく、市場価格に近い水準での売却を期待できます。
ただし、すべての借地権が高値で売却できるわけではありません。立地条件が悪い場合や、地主とのトラブルが生じている場合などは、買主が見つからずに売れ残ってしまう可能性もあります。
仲介での売却は高値を狙える一方、売却まで時間がかかる点や不確実性が高いというリスクがあることを理解しておきましょう。
借地権の売却事例!実際の買取価格も参考にしておこう
借地権の売却相場を紹介してきましたが、実際の売却価格は立地条件や地主との関係性、建物の有無などによって変動します。
ここでは、弊社クランピーリアルエステートで取り扱った借地権の売却事例を紹介します。買取業者への相場感をつかむうえでの参考にしてみてください。
- 築50年以上の木造戸建の借地権を2,900万円で買取した事例
- 相続した木造アパートの借地権を3,500万円で買取した事例
築50年以上の木造戸建の借地権を2,900万円で買取した事例
築年数の古い木造戸建を所有していたご夫婦からご依頼いただいた借地権売却の事例です。
また、ご夫婦は地主から更新料300万円を請求されていたことに加え、建物の老朽化が進み修繕費もかさむ状況にあり、早期の現金化を希望されていました。
こうした背景から、当社では条件を総合的に考慮し、相場よりもやや高めの2,900万円での買取を実施しました。ご夫婦からは「更新料を支払うよりも助かった」とご満足いただけました。
借地権を買い取る際には相場を参考にしつつ、所有者の事情や建物の状態、地主との関係性も考慮して決定します。上記の事例のように、状況によっては相場を上回る金額での売却も可能です。
相続した木造アパートの借地権を3,500万円で買取した事例
都内にある借地権付き木造アパートを相続された方からご相談いただいた事例です。
借地権付きアパートの場合、入居者の有無や契約内容によって査定額が左右されますが、本件では一般的な相場は約3,000万円と見込まれていました。
しかし、相続人の方が遠方にお住まいで管理が難しいことから、できるだけ高い価格での売却を希望されていました。当社ではアパートの収益性を重視して評価をし、結果として3,500万円での買取を実現しました。
借地権付きアパートのように賃貸収益を生む物件は、建物の状態や立地条件だけでなく、入居率や賃料収入といった収益性をどのように評価するかで査定額が大きく変わります。
とくに、収益化のノウハウを持つ買取業者であれば「安定した賃貸運営が可能」と判断し、相場以上の価格を提示できる場合があります。
借地権の売却相場を調べる方法
借地権の売却相場は、売却先や建物の状況、地主との関係によっても異なりますが、おおよその相場を調べることは可能です。具体的な手順は以下のとおりです。
- 土地の評価額を算出して更地価格を把握する
- その土地の借地権割合を調べる
- 借地権評価額を算出する
1. 土地の評価額を算出して更地価格を把握する
借地権の相場を調べるためには、まず「土地の評価額(更地価格)」を算出する必要があります。土地の評価額を求める方法には、大きく分けて「路線価方式」と「倍率方式」の2つがあります。
路線価方式は、道路に面する土地1㎡あたりの価格(路線価)を用いて計算する方法です。相続税や贈与税の計算にも利用される基準であり、都市部や主要道路沿いの宅地など多くの土地で路線価方式が採用されます。
具体的な計算方法は以下のとおりです。
路線価は、国税庁の「財産評価基準書」で公開されている「路線価図」に記載されています。面積については、登記簿や地積測量図などで確認しましょう。
一方、倍率方式は路線価が定められていない土地で用いられる計算方法です。
固定資産税評価額は、毎年4月~5月頃に送付される「固定資産税の納税通知書」で確認できます。倍率は、国税庁の「財産評価基準書」で公開されている「評価倍率表」に記載されています。
上記いずれかの方法で土地の評価額を算出できたら、次のステップに進みましょう。
2. その土地の借地権割合を調べる
土地の評価額を算出したあとは、その土地に設定されている「借地権割合」を確認します。
借地権割合は国税庁が公表している「財産評価基準書」の「路線価図」で確認できます。
路線価図では、たとえば「40D」というように「数字+アルファベット」で表記されており、数字部分が1㎡あたりの路線価、アルファベット部分が借地権割合を意味します。アルファベットはAからGまでの7段階があり、それぞれ30%から90%まで10%刻みで設定されています。
| 記号 | 借地権割合 |
|---|---|
| A | 90% |
| B | 80% |
| C | 70% |
| D | 60% |
| E | 50% |
| F | 40% |
| G | 30% |
たとえば、路線価図に「40D」と記載されている場合、路線価は4万円/㎡、借地権割合は60%となります。
3. 借地権評価額を算出する
土地の評価額と借地権割合を確認できたら、次は「借地権評価額」を算出します。算出方法はシンプルで、以下の式を用います。
たとえば、土地の面積が200㎡、路線価が12万円、借地権割合が70%だった場合を考えてみましょう。
2,400万円×70%=1,680万円(借地権評価額)
上記の事例では、借地権評価額は「1,680万円」となるため、売却の際にはこの価格が基準とされます。
ただし、借地権評価額はあくまで税務上の基準としての目安であり、売却価格を保証するものではありません。実際の売却価格は、土地の立地条件、建物の状態や入居状況、地主との関係性など、さまざまな要因によって変動します。
したがって、借地権評価額はあくまで理論上の参考値と考えておき、実際の売却価格を知りたいときは専門の不動産会社に依頼しましょう。
借地権の売却の流れ!売却先ごとの手続きを紹介
借地権の売却の流れについて、以下の売却先ごとに紹介します。
- 地主に借地権を売却する場合の流れ
- 専門の買取業者に借地権を売却する場合の流れ
- 投資家などに仲介で借地権を売却する場合の流れ
地主に借地権を売却する場合の流れ
地主に借地権を売却する場合の流れは以下のとおりです。
- 借地権に詳しい不動産会社へ査定を依頼する
- 地主と借地人で売却の条件を交渉する
- 地主と売買契約を締結する
- 借地権の引き渡しと決済
1.借地権に詳しい不動産会社へ査定を依頼する
地主に借地権を売却する際は、まず借地権取引に精通した不動産会社に相談し、査定を依頼しましょう。借地権は通常の土地取引とは異なり、地主との交渉や承諾料の取り扱いなど専門的な知識が求められます。経験のある不動産会社に依頼することで、価格の算定だけでなく、必要書類の準備や契約手続きまで一貫したサポートを受けられます。
また、地主との個人間のやり取りだけで売却を進めてしまうと、条件交渉が難航したり感情的な対立に発展したりする可能性があります。そのため、中立的な立場で調整してくれる不動産会社に仲介してもらうことが大切です。
2.地主と借地人で売却の条件を交渉する
次に、査定結果をもとに、地主と借地権の売却条件を交渉しましょう。不動産会社に依頼している場合、借地人自身ではなく不動産会社が主体となって交渉を進めていきます。
交渉では売却価格だけでなく、「建物を解体して更地にするのか、残したまま引き渡すのか」「実際の引き渡し時期はいつにするのか」など具体的な条件についても取り決めます。
3.地主と売買契約を締結する
交渉がまとまり、地主の承諾を得られたら売買契約を締結します。
契約書には売買価格、代金の支払い方法、引渡しの時期など取引に関わる重要事項を明確に記載する必要があります。トラブルを防ぐためにも、宅地建物取引士など専門家に確認してもらうと安心です。
4.借地権の引き渡しと決済を行う
売買契約を結んだあとは、契約条件に基づいて決済と引き渡しをおこないます。
具体的には、所有権移転登記の手続きを進め、建物の所有権を地主に移します。登記は売主と買主が共同でおこなうのが原則であり、必要書類も多いため、準備を整えておきましょう。
所有権移転登記が完了すると同時に売買代金が支払われ、取引は完了です。
専門の買取業者に借地権を売却する場合の流れ
専門の買取業者に借地権を売却する場合の流れは以下のとおりです。
- 複数の業者にで相見積もりを取る
- 査定額や売買条件を確認する
- 地主から譲渡の承諾を得る
- 売買契約を締結する
- 借地権の引き渡しと決済を行う
1.複数の業者で相見積もりを取る
借地権を専門の買取業者に売却する際には、必ず複数の業者に査定を依頼して相見積もりを取りましょう。買取業者によって得意とするエリアや査定基準が異なっており、査定額にも差が生じるためです。
ひとつの業者だけに依頼すると適正な相場を見誤る可能性があるため、最低でも2〜3社以上を比較して、信頼できる業者を選びましょう。
2.査定額や売買条件を確認する
査定額の提示を受けたら、金額だけでなく売却条件の内容もしっかり確認します。
たとえば、引き渡しの時期や契約不適合責任の有無など、取引にかかわる条件は買取業者ごとに異なります。わからないことがあれば質問し、契約の内容を明確にしておきましょう。
3.地主から売却の承諾を得る
買取業者など第三者に借地権を売却する際には、地主の承諾が必須です。地主の承諾を得ないまま売買契約に進むと契約違反となり、借地契約を解除される恐れがあります。
そのため、買取業者と売買契約を結ぶ前に必ず地主からの承諾を得ましょう。地主からの承諾を得られたら譲渡承諾料や支払い期限などについて取りまとめ、借地権譲渡承諾書を作成します。
4.売買契約を締結する
条件面で合意に至ったら、売買契約を締結します。契約書には売買価格、代金の支払い方法、引き渡し時期などが記載されています。
専門の買取業者に依頼する場合、契約書は業者のほうで用意してもらえます。内容をしっかりと確認のうえ、問題なければ売買契約を締結しましょう。
5.借地権の引き渡しと決済を行う
契約締結後は、決済と借地権の引き渡しをおこないます。
所有権移転登記を先におこない、その後に売買代金が買取業者から支払われます。なお、買取業者は司法書士などの専門家と提携している場合が多く、登記の手続きは一任できるのが基本です。
所有権移転登記と売買代金の支払いが完了すれば、取引は完了です。
投資家などに仲介で借地権を売却する場合の流れ
投資家などに仲介で借地権を売却する場合の流れは以下のとおりです。
- 借地権に強い不動産会社へ相談し、査定を依頼する
- 地主に承諾を得るための交渉をする
- 売却活動をして買主を見つける
- 売買契約を締結する
- 借地権の引き渡しと決済を行う
1.借地権に強い不動産会社へ相談し、査定を依頼する
投資家などに仲介を通じて借地権を売却する場合、まずは借地権取引の実績がある不動産会社に相談し、査定を依頼します。
一般的な土地売買と異なり、借地権は契約内容が複雑で地主との交渉も必要になるため、専門性のある会社を選ぶことが重要です。
2.地主に承諾を得るための交渉をする
買取業者に売却するときと同様、第三者に借地権を売却する際には、必ず地主の承諾が必要です。承諾を得るために価格や建物の扱いなどについて地主と交渉をおこない、取り決めた内容を借地権譲渡承諾書にまとめましょう。
3.売却活動をして買主を見つける
地主の承諾を得たら、不動産会社を通じて売却活動をおこないます。借地権の購入希望者の多くは投資家や法人であり、物件の収益性や立地条件が評価のポイントになります。
購入希望者が見つかったら、条件の交渉や内覧などの対応をおこないます。お互いが合意すれば交渉成立となり、売買契約の締結に進みます。
4.売買契約を締結する
次に、買主と具体的な売買条件について決めていきます。売却金額や引き渡しの時期、決済方法などについて合意が得られれば、売買契約を締結します。
なお、売買契約書は仲介業者が用意するのが基本ですが、内容に誤りがないかどうかはしっかりと確認しましょう。
5.借地権の引き渡しと決済を行う
売買契約の締結後は、所有権移転登記の手続きをおこない、借地権を買主に引き渡します。その後で買主から売却代金が支払われ、取引は終了です。
借地権売却にかかる費用・税金の一覧
借地権を売却する際には、以下のような費用や税金が発生します。実際に売却をする前に、どのような費用がかかるのかを把握しておきましょう。
| 費用・税金 | 目安額 | かかるタイミング |
|---|---|---|
| 仲介手数料 | 売買価格×3%+6万円+消費税(上限) | 不動産会社に仲介を依頼して売却するとき |
| 譲渡承諾料 | 借地権価格の10%程度 | 地主に借地権の譲渡を承諾してもらうとき |
| 解体費用 | 1坪3〜8万円程度 | 建物を更地にして引き渡すとき |
| 印紙税 | 200円~60万円 | 売買契約書を作成するとき |
| 登録免許税 | 所有権移転登記:固定資産税評価額×2%または0.3% 抵当権抹消登記:不動産の数×1,000円 |
建物の移転登記・抹消登記をおこなうとき |
| 譲渡所得税 | 課税譲渡所得の約20%~40% | 売却益が発生したとき |
仲介手数料
仲介手数料とは、不動産会社に売却を依頼し、実際に取引が成立した際に支払う報酬のことです。
仲介手数料が発生する場面は、不動産会社に仲介を依頼して売却を進める場合です。複数の会社に同時に依頼できる一般媒介契約を選んだとしても、実際に成約に結びつけた会社にのみ仲介手数料を支払います。
仲介手数料の金額は不動産会社によって異なりますが、売買価格に応じて法律で上限が定められています。
| 売買価格 | 仲介手数料の上限 |
|---|---|
| 200万円以下 | 売買価格×5.5% |
| 200万円超~400万円以下 | 売買価格×4.4% |
| 400万円超 | 売買価格×3.3% |
売買価格が200万円を超える場合、それぞれの価格帯ごとに計算して合計しなければならないため、計算方法が複雑になりがちです。そのため、実務では以下の速算式を用いて計算します。
| 売買価格 | 仲介手数料の上限 |
|---|---|
| 200万円以下 | 売買価格×5%+消費税 |
| 200万円超~400万円以下 | 売買価格×4%+2万円+消費税 |
| 400万円超 | 売買価格×3%+6万円+消費税 |
たとえば、借地権を1,000万円で売却したケースで考えてみましょう。速算式を用いると、仲介手数料の上限は以下のように計算できます。
1,000万円×3%+6万円+消費税=39万6,000円
【計算過程】
1,000万円×3% = 30万円
30万円+6万円 = 36万円
36万円×10%(消費税)=3万6,000円
36万円+3万6,000円=39万6,000円
このように、速算式を使うことでシンプルに仲介手数料の上限を計算できます。仲介を依頼して査定額の見積もりをもらった後は、上記の速算式を用いてどの程度の仲介手数料が発生するのかを確認しておきましょう。
譲渡承諾料
譲渡承諾料とは、借地権を第三者に売却や贈与などで移転する際に、地主から承諾を得るために支払う費用のことです。
借地権は土地を借りて利用する権利であるため、他人へ譲渡する際には所有者である地主の同意が必要となります。譲渡承諾料の支払いは法律で義務付けられているわけではありませんが、地主との関係を保ちながらスムーズに合意を得るためにも、実際の取引では支払うケースが大半を占めています。
譲渡承諾料の金額に関して明確な決まりはありませんが、「借地権価格の10%程度」になることが多いです。
たとえば、更地価格が3,000万円、借地権割合が60%のケースで考えてみましょう。
1,800万円×10%=180万円(譲渡承諾料)
地域の慣習や地主との関係によって金額が変動することはありますが、目安として「借地権価格の10%程度」と考えておくと良いでしょう。最終的に譲渡承諾料がいくらになるのかは、地主との交渉によって決まります。
なお、上記の相場よりも著しく高額な譲渡承諾料を請求された場合は、専門の不動産会社や弁護士などに相談し、交渉を代行してもらうことをおすすめします。
解体費用
解体費用とは、借地上に建物が存在する場合に、その建物を取り壊して更地に戻すために必要となる費用のことです。
借地権取引においては、建物付きの状態で売却できるケースもありますが、地主や購入希望者が更地にすることを望んでいる場合、建物を解体しなければなりません。解体にかかる費用は、原則として借地人が負担します。
解体費用の目安は建物の構造によって異なりますが、目安は以下のとおりです。
| 建物構造 | 相場 (坪単価) |
|---|---|
| 木造 | 3万円~5万円 |
| 鉄骨造 | 4万円~7万円 |
| RC造(鉄筋コンクリート造) | 6万円~8万円 |
たとえば、30坪の木造住宅を解体する場合、90万円〜150万円程度の解体費用がかかります。
ただし、上記はあくまでも目安であるため、実際に解体する際には複数の業者から見積もりを取り、正確な金額を把握しておきましょう。
印紙税
印紙税とは、不動産の売買契約書など、金銭の授受を伴う契約書に課される税金のことです。契約書に収入印紙を貼り付け、消印することで納付をおこないます。
借地権を売却する際には必ず売買契約書を作成するため、売却先にかかわらず必ず印紙税を納めなければなりません。
税額は契約金額に応じて異なっており、取引額が高額になるほど印紙税の負担も大きくなります。印紙税の軽減税率・本則税率を以下にまとめました。
| 売買金額 | 軽減税率 | 本則税率 |
|---|---|---|
| 10万円超50万円以下 | 200円 | 400円 |
| 50万円超100万円以下 | 500円 | 1,000円 |
| 100万円超500万円以下 | 1,000円 | 2,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 5,000円 | 1万円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 1万円 | 2万円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 3万円 | 6万円 |
| 1億円超5億円以下 | 6万円 | 10万円 |
| 5億円超10億円以下 | 16万円 | 20万円 |
| 10億円超50億円以下 | 32万円 | 40万円 |
| 50億円超 | 48万円 | 60万円 |
たとえば、借地権の売買価格が2,000万円のケースで考えてみましょう。軽減措置が適用されれば印紙税は1万円、なければ2万円となります。
軽減税率が適用される条件は以下のとおりです。
- 借地権含む不動産の譲渡に関する契約書であること
- 売買契約書の記載金額が10万円を超えるものであること
- 平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成された契約書であること
収入印紙は、郵便局や法務局、役所などで購入できます。借地権の売却金額が決まったら、軽減税率が適用されるかどうかを確認のうえ、収入印紙を用意しておきましょう。
登録免許税
登録免許税とは、不動産に関する登記をおこなう際に国に納める税金のことです。
借地権は「土地を借りる権利」であるため、土地に関する登録免許税が発生することはありません。登録免許税が発生するのは、建物に関して以下の登記をおこなうケースです。
- 所有権移転登記:建物の所有権を移す場合に必要
- 抵当権抹消登記:抵当権が設定されている場合に必要
借地権の売却とともに建物も譲渡する場合、所有権移転登記が必要となり、「固定資産税評価額×2%」の登録免許税が課されます。ただし、令和9年3月31日までは軽減措置が設けられており、住宅用家屋として要件を満たす場合には税率が「0.3%」に引き下げられます。
抵当権抹消登記は、借地権付き建物に住宅ローンが残っている場合に、抵当権を外すための手続きです。登録免許税は「不動産の数×1,000円」で計算され、建物1棟あたり1,000円が目安となります。
たとえば、固定資産税評価額1,500万円の建物を1棟売却するケースで考えてみましょう。
1,500万円×2%(本則税率)=30万円
1,500万円×0.3%(軽減税率)=4万5,000円
【抵当権抹消登記】
建物1棟×1,000円=1,000円
【合計】
本則税率の場合:30万1,000円
軽減税率の場合:4万6,000円
このように、登録免許税は登記の種類によって大きく異なるため、司法書士などの専門家にも相談しながら手続きを進めましょう。
譲渡所得税
譲渡所得税とは、不動産を売却して利益が生じた際に課される税金のことです。
内訳は所得税と住民税に分かれており、これらを総称して譲渡所得税と呼びます。借地権を売却して利益が出た場合にも、譲渡所得税を納める必要があります。
譲渡所得税を計算する際には、まず以下の計算式を用いて「課税譲渡所得」がいくらになるのかを算出しましょう。
収入金額とは借地権を売却して得た売却代金のことを指します。取得費には建物購入時の代金や関連費用、譲渡費用には売却にかかる仲介手数料や譲渡承諾料などが該当します。
課税譲渡所得が算出できたら、次は建物の所有期間に応じて以下の税率をかけましょう。
| 所得の区分 | 所有期間 | 税率 |
|---|---|---|
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 所得税:15.315% 住民税:5% 合計:20.315% |
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 所得税:30.63% 住民税:9% 合計:39.63% |
参照:長期譲渡所得の税額の計算|国税庁
参照:短期譲渡所得の税額の計算|国税庁
たとえば、収入金額が3,000万円、取得費が2,200万円、譲渡費用が300万円とした場合、譲渡所得税は以下のように計算できます。
【長期譲渡所得の場合】
500万円×20.315%=約101万6,000円
【短期譲渡所得の場合】
500万円×39.63%=約198万2,000円
なお、借地権を売却した際に利益が出なければ譲渡所得税が課税されることはありません。利益が発生した場合のみ、翌年の2月16日から3月15日までに確定申告をおこない、税金を納付する必要があります。
まとめ
借地権を売却する際の相場は、借地権割合を基準に決められることが多いですが、売却先によっても相場は変動します。
地主に売却する場合は、更地価格の50%〜70%程度が目安となります。地主にとっては土地を自由に活用できるメリットがあるため、良好な関係を築いていれば比較的スムーズに進みやすいでしょう。
専門の買取業者に依頼する場合は、更地価格の50%程度が相場となります。他の売却方法に比べて相場は落ちるものの、スピーディーに現金化できる点が大きなメリットです。
投資家などに仲介を通じて売却する場合は、更地価格の70%前後と高めの価格で売れる可能性があります。ただし、立地や地主との関係性など、条件によっては売れ残るリスクがある点には留意しておきましょう。
よくある質問
相続した借地権をすぐに売却することはできますか?
相続登記が完了していれば、借地権を売却することは可能です。相続登記が済んでいない場合は、まずは相続人に名義変更をしなければなりません。
なお、第三者に売却する際には地主の承諾が必要になります。登記を終えたうえで地主の承諾を得ていれば、相続直後でも売却を進められます。
地主がどうしても承諾してくれない場合はどうすれば良いですか?
正当な理由なく、地主が借地権の譲渡を拒んでいる場合は「借地非訟(しゃくちひしょう)」を申し立てる方法があります。裁判所の許可を得ることで、地主の承諾がなくても借地権の譲渡が可能となります。
ただし、裁判所への申し立てや審理には時間と手間がかかるため、あくまでも最終手段として検討しましょう。




