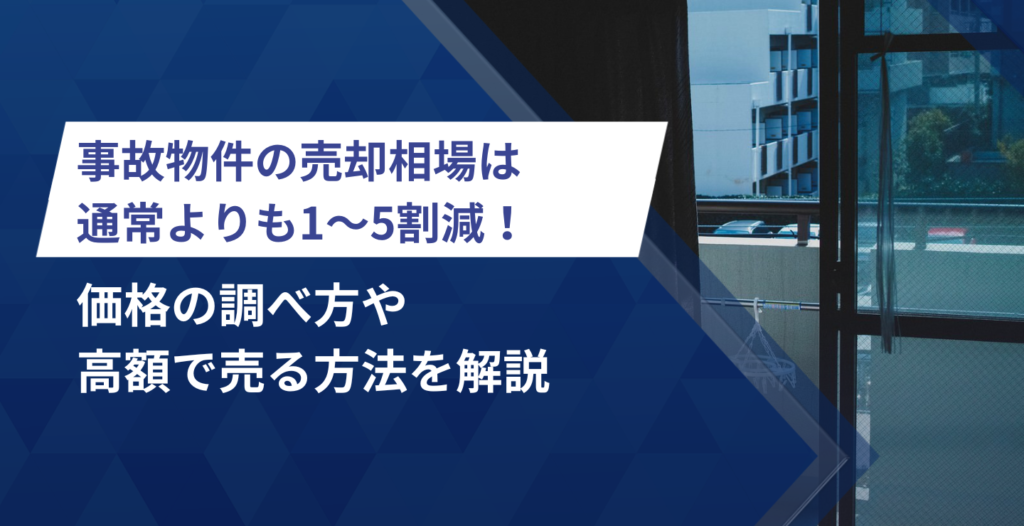事故物件の告知義務の完全マニュアル!告知が必要なケースや時効の年数は?
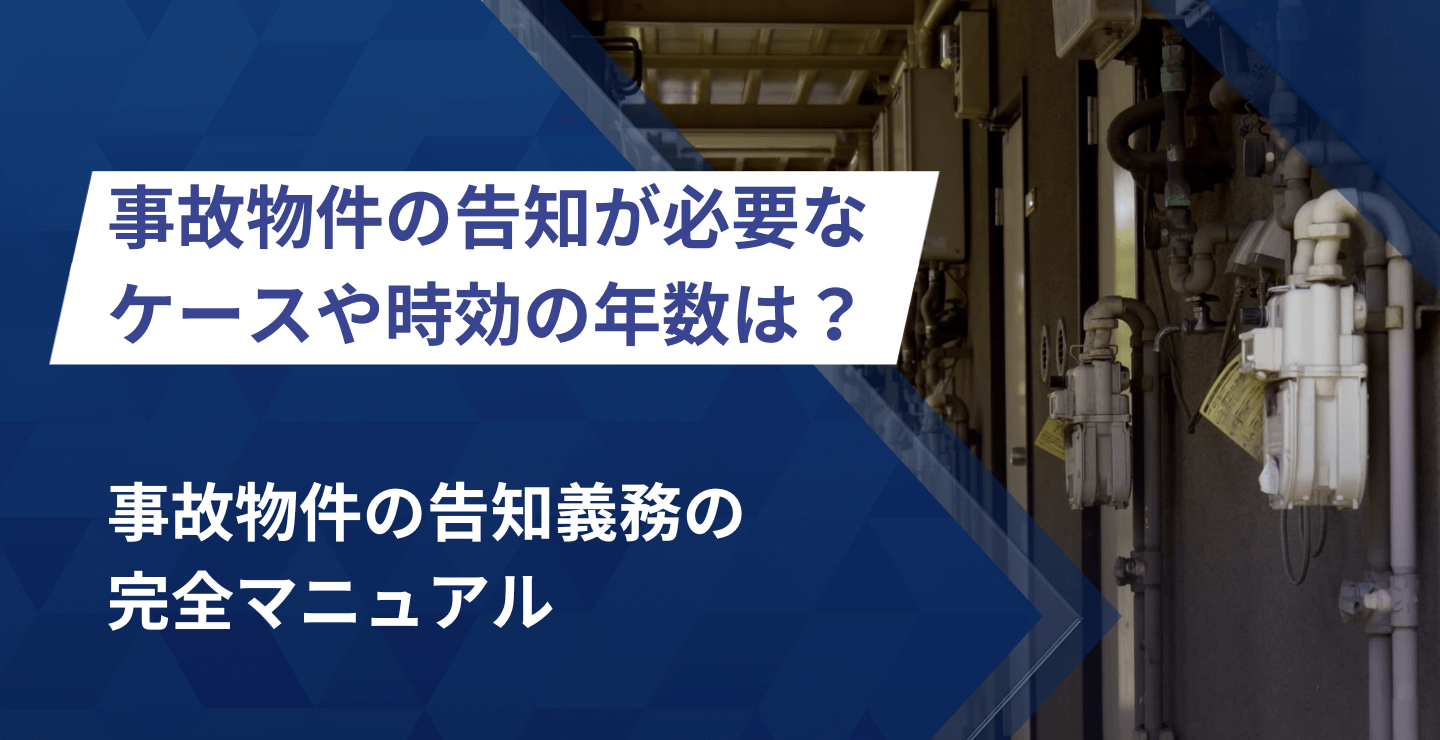
事故物件を所有している方から弊社によく寄せられるのが、「人の死があったことを買主や借主にどこまで伝えなければならないのか」というご相談です。
結論として、事故物件には原則として告知義務が生じ、売買や賃貸を行う際には人の死の事実を取引相手に伝える必要があります。そして、賃貸の場合は人の死が起きてから原則3年の時効がありますが、売買の場合には時効が定められていません。
不動産取引では、取引相手が契約をするかしないかを検討する際に重大な影響を与えうる情報は事前に伝えなければならないと考えられています。事故物件における人の死があった事実は、取引相手が「買う」「借りる」の判断を左右し得る情報であるため、原則告知義務が生じるのです。
人の死があった事実に対してどれだけの抵抗を感じるのかは人によって異なり、明確に基準を定められるものではないため、事故物件の告知義務が法令で明確に定められているわけではありません。
しかし、事故物件が今後増加するリスクを見込んで、2021年10月より国土交通省が定めた宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドラインでは、告知義務が生じる・生じないケースとして一定の基準が示されました。
| 具体例 | |||
|---|---|---|---|
| 告知義務が生じるケース |
・他殺・自殺・事故死などがあった物件 ・人の死が原因の特殊清掃を行った物件 ・共用部分で人の死があった集合住宅 |
||
| 告知義務が生じないケース |
・不慮の事故や自然死・病死などがあった物件 ・事故物件の隣接住戸や日常生活で使用しない共用部分で人の死があった集合住宅 |
||
他殺や自殺があった物件は告知義務が生じ、売買・賃貸にかかわらず取引相手へ事前に伝えなければなりません。告知義務を怠った場合、契約解除や損害賠償請求につながるリスクがあります。
当記事では、事故物件の告知義務の完全マニュアルをテーマとして、告知義務の概要から告知が必要な基準、時効を迎える場合など網羅的に解説していきます。事故物件の売却・賃貸を検討している場合には参考にしてみてください。
目次
事故物件の告知義務はガイドラインで定められている!告知義務が生じる理由
事故物件の売買や賃貸では、人の死があった事実を買主や借主に伝えなければならない「告知義務」が原則として生じます。これは法律に明文の規定があるわけではありませんが、取引の公平性を確保するため、2021年10月に国土交通省が「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を公表し、実務の基準が示されました。
大前提として、不動産取引では、売主や貸主と比べて買主・借主は不動産に関する情報が圧倒的に少なく、重大な事実が伏せられると公平な判断ができません。特に人の死があった物件は「心理的瑕疵物件」とされ、購入や賃借を検討する人に強い抵抗感を与え、契約の可否を左右する重要な情報になります。
そのため、事故物件を売却・賃貸する場合には、取引相手が適切に判断できるよう人の死の事実を告知しなければなりません。告知を怠れば契約解除や損害賠償といった法的トラブルにつながる可能性があるため、実務上も極めて注意が必要です。
「事前に事故物件であると告知されていれば契約しなかった」という事態を避けるためにも、事故物件を売ったり貸したりする場合、取引先に対して事前に人の死があった事実を原則告知しなければなりません。
事故物件の告知義務に関するルールが改正された理由
事故物件の告知義務に関するルールは、2021年10月に国土交通省が公表した「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によって明確化されました。
それ以前も、不動産取引では「契約の可否に重大な影響を与える事実は告知すべき」とされていましたが、具体的な判断基準はなく、実務上は不動産会社の裁量に委ねられていました。
そのため、告知義務の要否が業者ごとに異なり、取引トラブルや不信感につながるケースが少なくなかったのです。
さらに、人の死には自殺・他殺・事故死だけでなく、老衰や病死といった自然死も含まれます。これらを一律に「事故物件」と扱ってしまうと、不動産の貸主が高齢者の入居を避ける傾向が強まり、社会問題化することも懸念されていました。
こうした背景から、ガイドラインは「買主や借主が適切に判断できるようにすること」「高齢者への賃貸入居を不当に制限しないこと」を目的に制定されたのです。
また、厚生労働省が公表する「人口動態調査」によれば、自宅で亡くなる方の数は年々増加しています。
高齢化が進む今後は孤独死や自然死がさらに増えると予想され、その分事故物件とされる不動産も増加します。将来的に契約トラブルが頻発するリスクを見越し、ガイドラインを通じて告知義務のルールを明確化する必要があったといえるでしょう。
事故物件であることを隠した契約は告知義務違反になる
事故物件を所有している方の中には、「人の死があった事実を伝えずに売ったり貸したりできるのではないか」と考える方もいることでしょう。しかし、これは認められません。
人の死を隠して契約を成立させると、告知義務違反となります。告知義務に違反した場合、買主や借主から契約解除や損害賠償請求を受けるリスクがあり、場合によっては多額の賠償金を支払うことにもなりかねません。
実際に、建物内で自殺があった事実を1年以上隠して賃貸借契約を締結した貸主が訴えられ、約114万円の支払いを命じられた裁判例もあります。裁判所は「借主が知っていれば契約を結ばなかった」と判断し、告知義務違反を認定しました。
不動産取引は本来、公正かつ対等であるべきものです。人の死があった事実は取引相手の判断に重大な影響を与えるため、告知を怠ることは公正な取引に反します。告知義務違反を避けるため、また信頼できる不動産取引を行うためにも、事故物件であることは基本的に取引相手に伝える必要があります。
事故物件の告知が必要なケースとは?告知義務があるケース例
前提として、人の死があった事故物件だからといって告知義務が必ずあるわけではありません。ガイドラインで定められているように、事故物件においては告知義務があるケースと義務がないケースがあります。
そして、告知義務があるのかどうかについては、事故物件で起きた人の死やそれが起きた場所などが基準になります。
ここでは、事故物件の告知義務があるケースについて、国土交通省が公表している「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」をもとに解説していきます。事故物件の売買や賃貸を検討している場合には、自身が所有する物件は告知義務があるのかを判断する際に参考にしてみてください。
他殺・自殺・事故死などがあった物件
「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」では、人の死が物件の購入や貸借に影響を及ぼす場合、事故物件の告知義務が生じるという旨が記載されています。また、とくに事件性、周知性、社会に与えた影響が高い場合には、告知が必須とされています。
そのため、他殺や自殺、事故死があった事故物件の場合、原則的には告知義務が生じるため、売買や賃貸の際にその事実を伝えなければなりません。
人の死があり特殊清掃を行った物件
「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」では「特殊清掃等が行われた場合は発覚時期などを告げる必要がある」と記載されています。
そのため、人の死が原因で特殊清掃を行った事故物件の場合、原則的には告知義務が生じるため、売買や賃貸の際にその事実を伝えなければなりません。
なお、基本的に事故物件は心理的瑕疵物件に該当しますが、特殊清掃を行った事故物件は物理的瑕疵物件としても扱われることがあります。
物理的瑕疵とは、物件内にある物理的な欠陥のことです。遺体の放置などがあると物件自体にダメージを与えることがあり、そのダメージが原因で物理的瑕疵物件として扱われることがあるのです。
物理的瑕疵も取引の判断において重大な影響を及ぼす可能性があるため、人の死があった事実と同様に買い手や借り手に伝えなければなりません。特殊清掃を行った事故物件の場合は、「人の死があったこと」「特殊清掃を行ったこと」の2つを必ず相手に伝えるようにしましょう。
共用部分で人の死があった集合住宅
「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」には、マンションなどの集合住宅における共用部分で人の死があった場合の告知義務に関する記載があります。
③賃貸借取引及び売買取引の対象不動産の隣接住戸又は借主若しくは買主が日常
生活において通常使用しない集合住宅の共用部分において①以外の死が発生した
場合又は①の死が発生して特殊清掃等が行われた場合
引用元 宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン
この記載を踏まえれば、買い手や借り手が日常生活で使用するような共用部分で人の死が起きた場合、告知義務が生じると言えます。集合住宅のなかで日常生活で使用するような共用部分の具体例には、下記が挙げられます。
- 共用の玄関
- エレベーター
- 廊下や階段
たとえば、共用の玄関で人の死があったマンションの場合、買い手や借り手にその事案を伝える義務があります。つまり、所有している部屋の外で起きた事案であっても、売買や賃貸の際には告知義務が生じるケースがあるのです。
人の死があった物件でも告知義務が生じないケースもある
前述したように、人の死があった事故物件だからといって、必ず告知義務が生じるわけではありません。場合によっては、人の死があった事故物件であっても、告知義務が生じないケースもあります。
「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を参考にすると、下記のケースでは人の死があった物件でも告知義務が生じないとされています。
- 不慮の事故や自然死・病死などがあった物件
- 事故物件の隣接住戸や日常生活で使用しない共用部分で人の死があった集合住宅
ここからは、人の死があった物件でも告知義務が生じないケースについて解説していきます。
不慮の事故や自然死・病死などがあった物件
自然死や日常生活における不慮の死があった物件であれば、告知義務が生じません。これは、居住用の不動産において、自然死や日常生活における不慮の死は発生しうる事案であり、心理的瑕疵には該当しないとの判例が出ていることが理由になります。
- 老衰
- 病死
- 階段からの転落
- 入浴中の溺死や転倒事故
- 食事中の誤嚥(ごえん)
事故物件の隣接住戸や日常生活で使用しない共用部分で人の死があった集合住宅
人の死が発生した場所が隣接する物件や集合住宅においての普段使用しない共用部分である場合、告知義務が原則生じません。実際に、国土交通省のガイドラインには、下記のように記載されています。
賃貸借取引及び売買取引において、その取引対象ではないものの、その隣接住戸又は借主もしくは買主が日常生活において通常使用しない集合住宅の共用部分において①以外の死が発生した場合又は①の死が発生して特殊清掃等が行われた場合は、裁判例等も踏まえ、賃貸借取引及び売買取引いずれの場合も、原則として、これを告げなくてもよい。ただし、事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案はこの限りではない。
引用元 宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン
そのため、隣の住宅やマンションのパイプスペースで人の死があった場合、買い手や借り手に対する告知義務は原則生じません。
ただし、人の死に事件性や周知性、社会に与えた影響などが高い場合、例外として告知義務が生じます。具体的には、「隣の家やマンションのパイプスペースで殺人が起きた」のようなケースが該当します。
事故物件の告知義務はいつまで?
事故物件の告知義務には時効も定められているケースがあります。
- 売買契約:原則時効なし
- 賃貸契約:3年程度
簡単にいえば、事故物件を賃貸物件として貸し出す場合、人の死から3年が経過していれば、原則的には告知義務がなくなります。一方、事故物件を売却する場合は時効が定められていないため、人の死から何年が経過しても告知義務は原則生じます。
売買契約:原則時効なし
国土交通省が定めるガイドラインには、人の死があった物件を売却する場合の時効は定められていません。そのため、事故物件を売却する場合、人の死から何年が経過していても告知義務は生じます。
とはいえ、不慮の事故や自然死・病死があった物件の場合は告知が不要であるため、そもそも告知義務が生じません。
賃貸契約:3年程度
事故物件を賃貸物件として貸す場合、人の死から3年程度が経過していれば、その事案について告知する必要がないと定められています。
②【賃貸借取引】取引の対象不動産・日常生活において通常使用する必要がある集合住宅の共用部分で
発生した①以外の死・特殊清掃等が行われた①の死が発生し、事案発生(特殊清掃等が行われた場合は
発覚)から概ね3年間が経過した後
引用元 宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン
そのため、時効を迎えたうえで事故物件を賃貸物件として貸す際には、貸し手から人の死があった事案を伝える必要は原則ありません。
ただし、宅地建物取引業法第47条1項では、故意に事実を告げる行為は禁止されています。そのため、貸し手から人の死を伝える義務はなくなっても、借り手から人の死があったことを尋ねられた場合にはその事案について必ず伝える必要があります。
また、事件性、周知性、社会に与えた影響が高いような事案であれば、3年が経っても告知義務はなくなりません。そのため、「人の死から3年が経過すれば人の死があったことを隠していい」というわけではありません。
「事故物件は一度住めば告知義務が生じない」というわけではない
ガイドラインが制定されるまでは、不動産会社の判断で事故物件に関する告知がされていました。なかには、「誰かが一度住んだ物件は事故物件として告知しない」というスタンスの不動産会社もありました。
しかし、ガイドラインが制定された現在では、誰かが一度住んだとしても告知義務はなくなりません。誰かが住んだからといって、事故物件の心理的瑕疵はなくならないためです。
そのため、賃貸契約の場合は3年程度が経過するまでは、誰かが住んだ場合でも告知義務が生じます。また、人の死があってから一度誰かが住んだ事故物件を売却する場合には、何年が経過したとしても告知義務が生じます。
事故物件の売却や賃貸の契約時に告知するべき事項
国土交通省のガイドラインでは、告知義務が生じる場合に告知するべき事項について下記のように記載されています。
なお、告げる場合は、宅地建物取引業者は、前記3.の調査を通じて判明した点
について実施すれば足り、買主・借主に対して事案の発生時期(特殊清掃等が行わ
れた場合には発覚時期)、場所、死因14(不明である場合にはその旨)及び特殊清掃
等が行われた場合にはその旨を告げるものとする。
引用元 宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン
これをまとめると、事故物件の告知義務を果たす際には、下記の項目を買い手や借り手に伝える必要があるといえます。
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 発生時期 | 人の死がいつ発生したのかについて。特殊清掃を行った場合は、いつ特殊清掃が入ったのかを告知する。 |
| 発生場所 | 人の死がどこで起きたのかについて。共用部分で起きた場合、その場所を明確に伝える。 |
| 死因について | 「病死」「他殺」「自殺」などと人の死の原因について告知する。 |
| 特殊清掃の有無 | 特殊清掃を行ったかどうかについてを告知する。 |
なお、これらの情報を1つでも伝えなかった場合、事故物件の売買や賃貸の契約が解消される可能性があり、場合によっては損害賠償を請求されることもあります。そのため、事故物件の売買や賃貸の契約の際には、少なくとも上記の事項を伝えるようにしてください。
事故物件の心理的瑕疵以外にも告知するべき瑕疵がある
前提として、不動産取引を公平に行うためにも、売り手や貸し手はその物件の状態について、可能な限り取引相手に伝えるべきとされています。そのため、事故物件が抱える心理的瑕疵以外にも、取引の際には事前に告知しておくべき瑕疵があります。
具体的には、下記のような瑕疵がある場合、それについても告知義務が生じます。
| 概要 | |
|---|---|
| 物理的瑕疵 | その物件自体が抱える物理的な欠損 |
| 環境的瑕疵 | その物件の周辺環境が抱える瑕疵 |
| 法律的瑕疵 | その物件や土地が抱えている法的な問題 |
これらの瑕疵があるにもかかわらず不動産取引をした場合、その瑕疵が原因で契約解除または損害賠償の請求となる可能性があります。そのため、事故物件であることを伝えたとしても、他の瑕疵を伝えなければ、損害賠償を請求されてしまう可能性もあるのです。
ここからは、事故物件の心理的瑕疵以外にも告知するべき瑕疵について、それぞれ解説していきます。
物理的瑕疵
物理的瑕疵とは、その物件が抱える物理的な欠陥のことです。具体的には、下記のような欠陥があると、物理的瑕疵物件としても扱われます。
- 建築資材にアスベストが使用されている
- 柱などに使われている木材がシロアリに食い荒らされている
- 雨漏りがある
- 地盤がゆがんでいたり、沈んでいたりする
- 化学物質などで土壌が汚染されている
- 土地の境界があいまいで、周囲の物件が自分の土地を侵食している
- 地中に障害物や埋蔵物がある
- 壁にひび割れが起きている
- 耐震強度が国の基準を満たしていない
環境的瑕疵
環境的瑕疵とは、その物件の周辺環境が抱える瑕疵のことです。物件自体に問題がなかったとしても、その周辺環境に問題がある場合には環境的瑕疵物件として扱われます。
環境的瑕疵物件として扱われる例としては、下記が挙げられます。
- 周囲に繁華街があり、騒音トラブルが頻繁に起きる
- 周囲に暴力団の事務所がある
- 近所に暴力団構成員が住んでいる
- 周囲に火葬場や産業廃棄物処理施設がある
- 周囲に悪臭を放つような建物がある
法律的瑕疵
法律的瑕疵とは、その物件や土地が抱えている法的な問題のことです。
土地や建物に対しては「都市計画法」「建築基準法」「消防法」などの法律が適用されます。法律で定められた基準を満たしている必要がありますが、土地や建物によっては基準を満たさないものもあり、それらは法律的瑕疵物件として扱われます。
法律的瑕疵物件として扱われる物件の例としては、下記が挙げられます。
- 接道義務を満たしておらず再建築不可である
- 市街化調整区域内にあり再建築不可である
- 計画道路指定を受けており建築の制限がある
- 火災報知機やスプリンクラーなどの防災設備が古い
- 構造上の安全基準を満たしていない
- 建ぺい率を違反している
事故物件の売却を検討しているなら専門の買取業者に依頼する
事故物件の売却を検討している人もいることでしょう。事故物件の売却であれば、専門の買取業者に依頼することも視野に入れてみてください。
前提として、事故物件は心理的に購入を敬遠されやすいため、仲介を依頼しても買い手が現れないケースも少なくありません。また、専門ではない買取業者に依頼しても、その物件を活用するのが難しく、買取自体を断られてしまう可能性もあります。
一方、専門の買取業者であれば物件を活用するノウハウがあるため、他社から断られたような事故物件であっても積極的に買い取ってもらえることに期待できます。
また、事故物件専門の買取業者では、残置物があってもそのままの状態で買い取ってもらえるのが一般的であり、お祓いや供養、特殊清掃を行ってもらえる業者もあります。
そのような業者であれば契約不適合責任が免除されるのが一般的であるため、心理的瑕疵以外の瑕疵があったとしても責任を問われるリスクを抑えられます。
「事故物件がなかなか売れない」「なるべく早く事故物件を売りたい」という場合、まずは専門の買取業者を検討するのが得策といえるでしょう。
まとめ
事故物件の告知義務に関しては、国土交通省のガイドラインで基準などが定められています。売却・賃貸にかかわらず、人の死があった物件であれば、事前に取引相手へその事案を原則伝えなければなりません。
賃貸契約であれば人の死があってから3年程度で時効となりますが、売買契約であれば時効は定められていません。そのため、少なくとも人の死から3年が経過していない場合、基本的には人の死があったことを取引相手に隠すことはできません。
とはいえ、人の死があったからといって、必ず告知義務が生じるわけではありません。不慮の事故や自然死・病死があった物件は、告知義務が生じません。
事故物件を売却・賃貸する場合、自身が所有する物件に告知義務が生じるのかどうかを確認しておくのがよいでしょう。
なお、心理的瑕疵以外にも、告知義務が生じる瑕疵もあります。事故物件を取引する場合、物理的瑕疵や環境的瑕疵、法律的瑕疵がないかも調べておくのが大切です。
事故物件の告知義務に関するFAQ
マンションの他の部屋で人の死があった場合は告知義務がありますか?
基本的にはその部屋に告知義務が生じ、他の部屋は告知の必要がありません。しかし、事件性や周知性、社会に与えた影響が高い場合には、人の死が起きた部屋の隣の部屋も告知義務が生じます。
事故物件であることはバレてしまうのでしょうか?
売買や賃貸の契約時にはバレない可能性がありますが、契約後に知られる可能性は大いにあります。その際には契約解除や損害賠償の請求になる恐れがあるため、必ず告知義務は果たしましょう。
事故物件の告知義務を守らないとどのような処分が下りますか?
2年以下の懲役または300万円以下の罰金の対象になります。