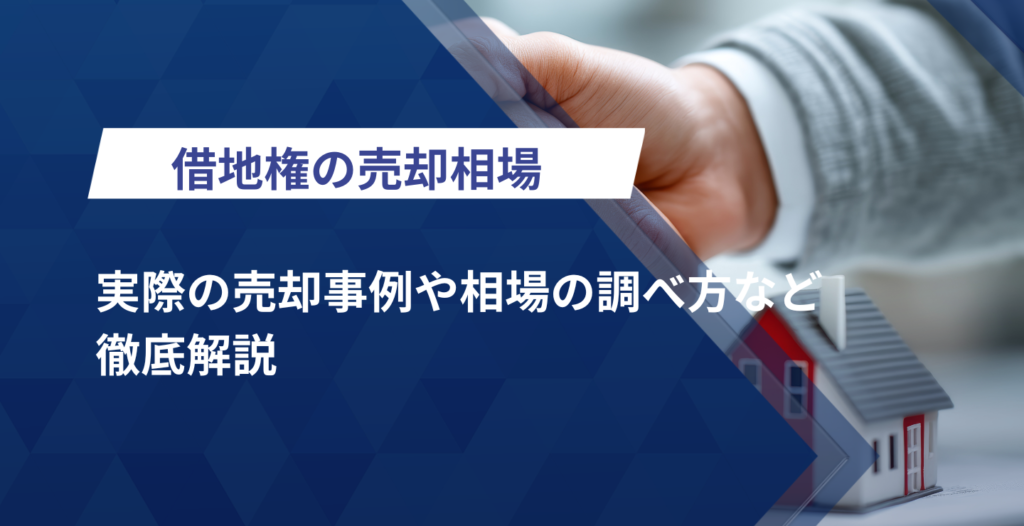借地権相続を徹底解説!知っておくべき基本情報から相続手続きの流れまで解説

弊社では、「自宅が借地に建っているが相続できるのか」「相続した借地権を売却したいがやり方がわからない」などのご相談をいただくことがあります。
借地権とは、自宅など建物を所有することを目的に、他人が所有する土地を借りる権利のことです。土地そのものを所有しているわけではありませんが、借地人が亡くなった際には、現在の契約条件のまま相続財産として引き継ぐことができます。
借地権を相続する際の流れは以下が基本となります。
- 借地権の内容を確認する
- 相続人で遺産分割協議を行う
- 相続があったことを地主に連絡する
- 相続登記を行う
借地権には、主に「旧借地権」「普通借地権」「定期借地権」の3つの種類があり、それぞれで契約期間や更新の可否などが異なります。そのため、まずは契約内容を確認するところから始めましょう。
契約内容の確認が取れたら、相続人全員で遺産分割協議をおこない、誰が借地権を相続するのかを決定します。借地権の相続で地主の承諾を得る必要はありませんが、今後の関係性を損なわないためにも、相続があったことを地主に連絡しておきましょう。
遺産分割協議が終わったあとは、法務局で建物の相続登記(名義変更)をおこない、相続手続きは完了です。相続後は、借地権を取得した人が地代や固定資産税の支払いなどを引き継ぎます。
なお、借地権を相続する際には、相続人や地主との間でトラブルが起こることもあります。とくに「誰が相続するのか決まらない」「地主から借地権の売却許可がおりない」などは、弊社でもご相談が多い事例です。
借地権の相続でトラブルが起きた場合、無理に自力で解決しようとせず、弁護士や司法書士などの専門家に依頼しましょう。
弊社クランピーリアルエステートは、借地権の相続など複雑な権利関係や手続きによってお困りの方の悩みを解消することを1つの理念として、借地権の買取を行っています。
地主との交渉や契約内容の整理、承諾料・更新料の確認など、借地権特有の煩雑な手続きも、すべてワンストップでサポートしています。弁護士と連携し、法的な観点からもサポートをおこなうことで、手続きの滞りやトラブルを未然に防ぎます。
「借地権を相続すべきか悩んでいる」「相続した借地の扱いに困っている」といった方は、ぜひクランピーリアルエステートへご相談ください。
目次
借地権は相続財産として扱われる!借地権の種類とは?
借地権とは、他人が所有する土地を借りて建物を建てる権利のことです。
土地そのものを所有しているわけではありませんが、法的には財産としての価値を持つため、相続の対象に含まれます。つまり、被相続人が借地権を保有していた場合、その権利は相続人へと引き継がれることになります。
なお、借地権にはさまざまな種類があるため、どのような契約形態になっているのかを事前に確認することが大切です。主な種類は以下の3つです。
| 種類 | 概要 | 契約期間 |
|---|---|---|
| 旧借地権 | 1992年の法改正前に契約された借地権で、借地人の希望により契約更新が可能 | 木造などは30年、鉄骨造などは60年 (更新後は木造20年、鉄骨造30年) |
| 普通借地権 | 現行法に基づく借地権で、契約期間満了後も更新が可能 | 当初30年、1回目の更新20年、以降10年ずつ |
| 定期借地権 | 現行法に基づく借地権で、契約期間が満了すると土地を返還する | 50年以上 |
旧借地権
旧借地権とは、1992年8月1日に借地借家法が施行される以前に締結された借地契約のことです。契約期間は建物の種類によって以下のように異なります。
| 建物の種類 | 初回契約期間 | 更新後の契約期間 |
|---|---|---|
| 非堅固建物 (木造など) |
20年または30年 | 20年 |
| 堅固建物 (鉄骨造など) |
30年または60年 | 30年 |
旧法では借地人側の権利が非常に強く、契約期間が満了しても借地人が更新を希望すれば、原則として自動的に更新が認められます。そのため、旧借地権で契約をしている場合、実質的には土地を半永久的に利用し続けることが可能です。
また、一度旧法で契約した借地権は、契約更新後も自動的に新法(現行の借地借家法)に切り替わることはありません。新法を適用するためには、地主と借地人の合意が必要となるため、現在も旧法のまま存続しているケースが多くみられます。
旧借地権かどうかを確認するには、まず借地契約書を確認しましょう。契約締結日が1992年7月31日以前であれば、旧借地権に該当します。
契約書が見当たらない場合は、地主に確認するか、法務局で登記事項証明書を取得し、登記年月日などから判断することも可能です。
普通借地権
普通借地権は、現在の借地借家法に基づいて設定される一般的な借地契約の形態で、主に居住用の建物を建てるために利用されます。
契約期間は原則30年以上とされており、期間が満了した際には、借地人の希望により契約更新ができます。1回目の更新では20年以上、2回目以降は10年以上の期間で更新が可能です。
普通借地権の特徴は、長期間にわたって借地人の居住権が保護される点にあります。地主が契約の更新を拒むには正当な理由が必要であり、単に「土地を返してほしい」という一方的な理由では拒絶できません。
正当事由に該当するかどうかは、地主と借地人の土地利用の必要性や土地の利用状況、地主側が立ち退き料を支払う意思があるかどうかなど、さまざまな事情を考慮して決められます。
普通借地権かどうかを確認するためには、契約書に記載された契約期間や契約内容をチェックしましょう。
契約期間が30年以上に設定されており、さらに更新が可能である旨が明記されている場合は、普通借地権に該当します。また、被相続人が過去に契約更新をしていた履歴があれば、普通借地権である可能性が高いです。
契約書が見つからず更新していたかどうかも不明な場合は、地主に確認を取るか、法務局で登記事項証明書を取得しましょう。
定期借地権
定期借地権は、1992年(平成4年)に施行された借地借家法によって新たに設けられた制度で、一定期間だけ土地を借りられる借地権のことを指します。
契約期間は原則50年以上と定められており、期間満了後の更新は認められていません。契約が終了すると、借地人は建物を取り壊して更地にし、地主へ土地を返還する義務があります。
ただし、地主と借地人の双方が合意すれば、「再契約」という形で土地を借り続けることは可能です。
定期借地権に該当するかどうかを確認する際には、契約書を確認しましょう。契約期間が50年以上に設定されており、「更新不可」「期間満了後は土地を返還する」といった文言が記載されていれば、定期借地権にあたります。
契約書が見つからない場合、地主に連絡を取って契約形態を確認するか、法務局で登記事項証明書を取得しましょう。
借地権を相続することのメリット・デメリット
借地権を相続することのメリットとデメリットは以下のとおりです。
| メリット | デメリット |
|---|---|
|
・相続人は新たに地主と契約を結び直す必要がなく、そのまま借地権を引き継げる ・契約期間は原則30年以上と長期で安定している ・土地の固定資産税を負担する必要がない ・普通借地権や旧借地権の場合、更新すれば半永久的に土地を利用できる |
・建物の固定資産税は相続人の負担となる ・相続後に空き家となる場合、維持管理や修繕の負担が大きくなる ・老朽化が進むと近隣からの苦情対応や業者への委託費用が発生する ・地主に対して毎月地代を支払う必要があり、金銭的負担が続く ・借地権の売却や譲渡、建物のリフォームには地主の承諾が必要 ・定期借地権の場合、契約満了時に建物を取り壊して更地で返還する必要がある |
借地権を相続することのメリット
借地権を相続することのメリットは以下のとおりです。
- 新たに地主と契約を結び直す必要がなく、そのまま借地権を引き継げる
- 契約期間は原則30年以上と長期で安定している
- 普通借地権や旧借地権の場合、更新すれば半永久的に土地を利用できる
- 土地の固定資産税を負担する必要がない
借地権を相続する際、相続人は新たに地主と契約を結び直す必要はありません。もしも借地上の建物に住んでいる場合、これまで通りの環境で暮らし続けることができる点は、相続人にとって大きなメリットといえます。
また、借地借家法では契約期間が原則30年以上とされており、長期的に安定して土地を利用できることも特徴です。とくに、普通借地権や旧借地権であれば、更新によって半永久的に土地を使い続けることが可能です。
さらに、土地そのものを所有しているわけではないため、土地の固定資産税を負担する必要がないのも経済的なメリットです。
借地権を相続することのデメリット
借地権を相続することのデメリットは以下のとおりです。
- 建物の固定資産税は相続人の負担となる
- 地主に対して毎月地代を支払う必要があり、金銭的負担が続く
- 相続後に空き家となる場合、維持管理や修繕の負担が大きくなる
- 老朽化が進むと近隣からの苦情対応や業者への委託費用が発生する
- 借地権の売却や譲渡、建物のリフォームには地主の承諾が必要
- 定期借地権の場合、契約満了時に建物を取り壊して更地で返還する必要がある
借地権を相続する場合、建物の固定資産税や毎月の地代を支払う義務が生じます。仮に建物に居住していない場合でも、相続した場合は借地権の所有者となるため、支払いを拒否することはできません。
また、建物が空き家になる場合には、定期的な管理や清掃、修繕などが必要です。老朽化が進めば修繕費用も増え、遠方に住んでいる相続人にとっては大きな負担になります。管理を業者に依頼する場合は、委託費用も別途かかります。
さらに、建物のリフォームや増改築、借地権の売却などをおこなう際には、地主の承諾が必要です。スムーズに同意が得られない場合には、交渉や手続きが長引く可能性もあります。
借地権の契約形態にも注意が必要です。定期借地権の場合には契約更新ができず、契約満了時には建物を取り壊して更地で返還しなければなりません。解体費用は借地人の負担となるため、将来的に大きな出費が発生することになります。
借地権は相続するべき?相続を検討する際の判断ポイント
借地権を相続すると住まいとして利用し続けられる一方、地代の支払いや建物の維持管理など、長期的な負担も伴います。そのため、借地権を相続するべきかどうか迷ったときは、以下のポイントを総合的に考慮して判断しましょう。
- 相続した借地を自宅や賃貸として利用する予定があるか
- 地代や建物の維持費を継続的に支払える経済状況か
- 地主との関係が良好であり、承諾が得やすい状況にあるか
- 他にマイナスの財産(借金など)が多く、相続放棄を検討する状況ではないか
- 更新が可能な契約形態(旧借地権・普通借地権)かどうか
- (定期借地権の場合)契約満了まで十分な期間が残っているか
相続した借地をそのまま自宅として使う場合や、賃貸として収益を得たい場合には、借地権を引き継ぐメリットが大きいです。将来的に建物を増改築したりリフォームしたりする予定がある場合、地主の承諾が得られそうかどうかもあわせて確認しておきましょう。
反対に、「住む予定がなく、賃貸としての収益化も難しい」「地主との関係性が悪い」などの事情がある場合、相続放棄や売却も視野に入れてみてください。
なお、相続放棄を検討する際には、「プラスとなる財産がどの程度あるか」の確認が必要です。相続放棄をすると、借地権だけでなく、原則としてその他の財産もすべて手放さなければならないためです。
借金などマイナスの財産が多ければ相続放棄をしても問題ありませんが、預貯金や有価証券などプラスの財産が多い場合は、相続放棄をすべきかどうかを慎重に検討する必要があります。
また、契約形態の確認も重要です。旧借地権や普通借地権であれば契約更新が可能ですが、定期借地権は契約満了後に土地を返還しなければなりません。とくに定期借地権の場合、契約満了までどの程度の期間が残されているかも必ず確認しましょう。
借地権を相続するときの流れ
借地権を相続するときの大まかな流れは以下が基本です。
- 借地権の内容を確認する
- 相続人で遺産分割協議を行う
- 相続があったことを地主に連絡する
- 相続登記を行う
1. 借地権の内容を確認する
借地権を相続する際は、まず「どのような条件で土地を借りているのか」を必ず確認しましょう。確認すべき主な項目は以下のとおりです。
- 借地権の種類(旧借地権・普通借地権・定期借地権)
- 契約期間
- 地主(土地の所有者)
- 地代
- 更新料
- 建物買取請求権の有無
上記の項目は、借地を相続すべきかを検討するうえで重要な情報となります。
確認の際は、まず「土地賃貸借契約書」や「賃貸借契約書」といった契約書類を探しましょう。契約書には地主の氏名や地代、契約期間などの基本情報が記載されています。
契約書が見つからない場合は、法務局で「登記事項証明書」を取得し、借地権の登記があるかどうかを確認します。登記がある場合は「賃借権設定」として記載されており、地代や存続期間などの情報を確認できます。
2. 相続人で遺産分割協議を行う
相続人が複数いる場合は「誰が借地権を引き継ぐのか」を決めるために、相続人全員で遺産分割協議をおこなう必要があります。
遺産分割協議では、借地権を含むすべての相続財産について、それぞれの分け方を話し合います。借地権などの不動産や預貯金、有価証券、自動車などプラスの財産のほか、借金や税金などマイナスの財産も相続の対象となります。
話し合いがまとまったら、決定した内容を「遺産分割協議書」にまとめて全員が署名・押印します。遺産分割協議書は、借地権の名義変更をする際に必要となる書類なので、大切に保管しておきましょう。
なお、協議を進める中で意見が対立した場合には、弁護士など専門家に同席してもらうことも検討しましょう。また、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、調停委員に仲介してもらいながら話し合うことも可能です。
3. 相続があったことを地主に連絡する
借地権を相続した場合、契約上は被相続人の地位をそのまま引き継ぐため、地主の承諾や新たな契約締結は必要ありません。相続人は自動的に借地人の立場を引き継ぎ、従前の条件で地代の支払いなどを継続することになります。
ただし、法的には承諾が不要であっても、地主との関係性を良好に保つためには、相続が発生したことを連絡しておくのが望ましい対応です。
地主にとっても、誰が新たな借地人になるのかは重要な情報であり、事前に伝えておくことで今後のトラブル防止にもつながります。
連絡の際は「被相続人が亡くなったこと」「借地権を相続した人の連絡先」「地代支払いに利用する口座情報」など、必要な情報を簡潔に伝えましょう。
法定相続人以外の人への遺贈の場合は地主の許可が必要になる
前述したとおり、借地権の相続で地主の許可を得る必要はありませんが、被相続人の意思で法定相続人以外の人へ遺贈する場合は、地主の許可が必要になります。
たとえば、被相続人に配偶者と子どもがいる場合、両親や兄弟姉妹は法定相続人にはなりません。このケースで被相続人が両親や兄弟姉妹に借地権を引き継ぎたいと考えた場合、相続ではなく遺贈という扱いになります。
しかし、法定相続人でなければ借地権を引き継ぐ立場にはないため、地主の承諾を得る必要があります。そのため、遺贈を受けた人は、地主と話し合いの場をもうけ、譲渡の許可を取りましょう。
なお、話し合いの際には地主から「譲渡承諾料」を請求されることがあります。契約書に金額の定めがある場合はその内容に従いますが、明記がない場合は残りの契約期間や地代などを考慮し、当事者間で金額を協議して決定します。
譲渡承諾料の金額に法的な決まりはありませんが、借地権価格の約10%が目安です。相場よりも高額な譲渡承諾料を請求された際は、弁護士などの専門家に相談し、交渉を代行してもらうことも検討しましょう。
4. 相続登記を行う
遺産分割協議によって、誰が借地上の建物を相続するかが決まったら、次におこなうのが相続登記です。
相続登記は、不動産の所有権を公的に証明するための重要な手続きです。相続登記をしなければ売却や賃貸などもできないため、相続後は必ず手続きをおこないましょう。
また、2024年4月1日からは相続登記が義務化されました。相続や遺言によって不動産を取得した場合、所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記を申請する必要があります。また、遺産分割協議が成立した場合は、協議成立の日から3年以内が期限となります。
なお、2024年3月31日以前に発生した相続についても義務化の対象となり、3年間の猶予期間が設けられています。つまり、2027年4月1日までに相続登記を済ませなければなりません。
正当な理由なく期限を過ぎた場合は、10万円以下の過料の対象となります。借地権を相続した場合、早めに建物の相続登記を済ませましょう。
参照:相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)|法務局
借地権を相続することのトラブル!相続前・相続時・相続後のタイミング別に紹介
借地権は通常の土地所有と比べて権利関係が複雑であるため、相続することでトラブルが生じるケースがあります。実際、弊社にも借地権の相続に関する相談が多数寄せられています。
ここでは、借地権の相続前・相続時・相続後のタイミング別に、実際にあったトラブル事例を紹介します。
借地権を相続する前のトラブル
借地権を相続する前に起こりやすいトラブル事例は以下のとおりです。
- 借地権の名義が整理されていないことで起こるトラブル
- 借地契約書が見つからない・内容が不明なことで起こるトラブル
借地権の名義が整理されていないことで起こるトラブル
借地権の名義が整理されていなかったことで、相続手続きが複雑化した事例です。
あるときお父様が亡くなり、借地権の相続登記をしようとしたところ、名義が祖父のままになっており、二世代分の相続登記をしなければならないことが発覚します。
しかし、相続人の中にはすでに高齢になっていた方や亡くなっている方、さらに疎遠で連絡の取れない方もいました。結果として、相続登記の手続きに大幅な時間と労力を要しました。
このように、借地権の名義を放置したままにしておくと、将来的に相続人の数が増え、協議や手続きが難航してしまいます。
借地権は土地を所有しているわけではありませんが、建物は所有しているため、相続の際には建物の名義変更が必要です。相続人に迷惑をかけないためにも、被相続人が亡くなった段階で早めに名義変更を済ませておきましょう。
借地契約書が見つからない・内容が不明なことで起こるトラブル
借地契約書が見つからなかったことで、相続や手続きが滞ってしまった事例です。
地主との話し合いを進める中で、「契約書がないのなら借地関係は認められないのではないか」といった発言もあり、関係が一時的にこじれてしまいました。
最終的には、過去の地代の振込明細や領収書、建物の登記事項証明書などを集めて借地権の存在を証明し、改めて契約内容を確認・再作成することで問題は解決しました。
借地契約書が見つからなくても借地権そのものが消滅するわけではありませんが、条件の確認や手続きがスムーズに進まないことがあります。
借地権は契約期間が長いこともあり、契約書が紛失しやすいため、地代の支払い記録や過去の通知書などは大切に保管しておきましょう。また、契約内容が不明な場合には、地主と協議のうえで契約内容を明確にし、契約書を再作成しておくと今後のトラブルを防げます。
借地権の相続時のトラブル
借地権を相続する際に起こりやすいトラブル事例は以下のとおりです。
- 遺産分割協議で起こるトラブル
- 借地権を共有名義にすることで起こるトラブル
遺産分割協議で起こるトラブル
遺産分割協議の際に、借地権付き建物の扱いをめぐって意見が対立した事例です。
建物は築年数が浅く評価額も高かったため、兄弟間で「誰が住むのか」「売却して現金で分けたほうが良いのではないか」と意見が分かれてしまい、話し合いが難航しました。
最終的に長男が居住を希望し、他の相続人に代償金を支払うことで合意に至りましたが、話し合いで揉めたことが原因で兄弟仲が悪化してしまったとのことです。
このように、借地権付き建物の資産価値が高い場合、相続人同士で分割方法をめぐって争いが起こりやすくなります。
とくに、主な相続財産が借地権のみの場合、全員が納得できる落としどころを見つけるのが難しくなります。今回の事例のように、「誰が住むのか」「売却して現金化するのか」といった方向性の違いが原因で、協議が長期化するケースも少なくありません。
相続時には早めに専門家へ相談し、建物の評価額や借地権の取り扱いを明確にしたうえで、公平な分割方法を検討することが大切です。
借地権を共有名義にすることで起こるトラブル
借地権を共有名義にしたことで、売却が進まずトラブルとなった事例です。
ご相談者様と弟は売却に合意していたものの、妹に「思い出があるからやっぱり売却したくない」と反対されてしまいます。共有名義のため、全員の同意がなければ売却ができず、結局話し合いはまとまらないまま建物は放置されてしまいました。
建物が放置されている間も地代や固定資産税、修繕費などの維持費がかさんでいき、負担から解放されたいとのことで弊社までご相談いただきました。最終的に、弊社でご相談者様の共有持分を買い取る形で問題を解決しました。
このように、共有名義の不動産は売却・修繕・建て替えなど、重要な判断をする際に共有者全員の同意が必要となります。1人でも反対する人がいると手続きが進まなくなり、結果として不動産を活用できないまま、維持費だけがかかる状態に陥ってしまいます。
将来的なトラブルを防ぐためにも、共有名義を避けて単独名義で相続するのがおすすめです。
借地権を相続した後のトラブル
借地権を相続した後に起こりやすいトラブル事例は以下のとおりです。
- 地主から建て替えや売却などの同意が得られないことで起こるトラブル
- 地代の滞納があることで起こるトラブル
地主から建て替えや売却などの同意が得られないことで起こるトラブル
地主から建て替えや売却の同意が得られず、手続きが進まなかった事例です。
そこで弊社が仲介に入り、これまでの地代の支払い履歴や借地契約の経緯を整理したうえで、地主との交渉を重ねていきました。最終的には、承諾料を支払う形で売却の同意を得ることができました。
借地権の建て替えや売却をおこなう際には、原則として地主の承諾が必要です。承諾が得られないまま進めてしまうと契約違反とみなされ、契約解除や損害賠償請求を受ける恐れがあります。
地主との関係性や過去の支払い状況によって対応が変わるため、無理に自分で交渉をせず、専門の不動産会社や弁護士に相談して慎重に進めることが大切です。
地代の滞納があることで起こるトラブル
被相続人が生前に地代を滞納していたことで、相続後にトラブルとなった事例です。
状況を確認したところ、被相続人が体調を崩していた時期から支払いが滞っていたことが判明しました。このままでは契約解除の可能性もあったため、弊社が物件を素早く買取し、売却代金の一部から滞納分を清算しました。
結果として地主との契約関係も円満に整理でき、無事に問題を解決できました。
借地契約では、被相続人が滞納していた地代の支払い義務も相続人が引き継ぐことになります。滞納期間が長い場合や金額が高額な場合には、一括での支払いが難しいケースもあります。
放置すれば契約解除に発展する恐れもあるため、早めに状況を確認し、必要に応じて売却することも検討しましょう。
相続した借地権を処分する方法
借地権を相続したものの、建物を利用する予定がなく、手放したいと考える方は多いものです。相続した借地権を処分する方法と、それぞれ向いているケースを以下にまとめました。
| 方法 | 向いているケース |
|---|---|
| 地主に売却する | ・地主との関係が良好で交渉できそうな場合 ・地主が買取の意向を示している場合 ・借地契約の残存期間が短い場合 |
| 借地権専門の買取業者に売却する | ・早期に現金化したい場合 ・地代滞納や共有名義などの問題を抱えている場合 ・建物が老朽化している場合 |
| 借地権付き建物として仲介で売却する | ・できるだけ高く売却したい場合 ・建物の状態や立地条件が良く、残存期間が十分ある場合 |
地主に売却する
借地権を処分する際には、まず地主に買い取ってもらえるかどうかを確認しましょう。第三者に売却する場合と比べて手続きがスムーズに進む傾向にあり、余計な費用もかかりにくいのが特徴です。
通常、借地権を第三者に譲渡する場合には、地主の承諾を得るために「譲渡承諾料」が発生します。譲渡承諾料の金額に法的な決まりはありませんが、借地権価格の10%程度が相場です。
しかし、地主が買主であれば譲渡承諾料は不要となり、その分のコストを抑えられます。また、地主側も土地を完全所有に戻せるメリットがあるため、条件次第では話がまとまりやすいでしょう。
地主に売却する方法は、地主との関係が良好で、できるだけ早く借地権を整理したい方に向いています。また、借地権の残存期間が短く、第三者への売却が厳しい場合にも地主への売却がおすすめです。
ただし、地主に借地権を買い取る義務はないため、資金状況や将来の土地活用の計画によっては断られることもあります。さらに、売却価格の交渉が難航するケースも多く、「少しでも高く売りたい」と考える場合には、買取業者や仲介での売却を検討した方が利益が大きくなる可能性があります。
なお、地主に売却する場合の売却相場は、更地価格の50%〜70%程度が目安です。借地人から買取を依頼した場合は更地価格の50%程度、地主から買取を依頼した場合は更地価格の60~70%程度になることが多いです。
借地権専門の買取業者に売却する
借地権をできるだけ早く現金化したい場合には、借地権専門の買取業者に売却する方法が向いています。
買取業者は、取得した借地権を転売したり地主と交渉して所有権ごと取得したりすることで利益を得るビジネスモデルを採用しています。購入後の活用方針が明確であることから、スピーディーな対応が可能です。
また、借地権専門の買取業者に売却する方法では、仲介のように買主を探す必要がなく、査定から契約までの流れが短期間で完了します。早ければ1か月以内に売却が成立することもあり、時間的な余裕がない方や相続後すぐに資金化したい方に向いています。
さらに、地主との交渉や承諾料の手続き、法的トラブルのサポートなどをしてくれる場合もあり、煩雑なやり取りを減らすことができます。
一方で、買取業者は仕入れた借地権を再販して利益を得るため、売却価格は市場価格よりも低く設定される傾向にあります。立地条件などによっても異なるものの、目安として更地価格の50%前後となることが多いです。
なお、弊社クランピーリアルエステートでは、借地権を含む訳あり物件の買取を専門としています。地主との交渉から売買契約、法的な確認までをワンストップで対応しており、煩雑になりがちな売却手続きをスムーズに進めることが可能です。
借地権の売却では地主の承諾や承諾料の取り扱いなど、専門的な判断が求められる場面が多くあります。弊社では、弁護士と連携しながら法的リスクにも配慮し、交渉から契約締結までを丁寧にサポートしています。
「地主との話が進まない」「手続きが複雑で不安」といったお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度クランピーリアルエステートへご相談ください。
借地権付き建物として仲介で売却する
借地権を少しでも高額で売却したい場合、借地権付き建物として仲介で売却する方法がおすすめです。
仲介では、不動産市場を介して広く購入希望者を募るため、より多くの候補者から好条件での売却を狙える点が特徴です。建物の状態や立地などによって売却価格は異なりますが、更地価格の70%以上で売却が成立するケースもあります。
また、仲介業者に依頼すれば、買主との条件交渉や契約手続きを代行してもらえます。ほかにも地主との承諾交渉や必要書類の調整など、複雑になりがちな借地権の取引は、すべて不動産会社に一任できます。
一方で、仲介の場合は買主が見つかるまで時間がかかるというデメリットもあります。市場動向や物件の条件によっては数か月以上かかることもあり、早期に資金化したい人には不向きです。
また、第三者に売却する際には地主の承諾が必要となるのが基本であり、譲渡承諾料として借地権価格の10%程度を支払うケースが多いです。
スピードよりも売却価格を重視したい方や、建物の状態が良好で地主の理解が得られそうな場合には、仲介による売却を検討してみてください。
まとめ
借地権は、建物の所有を目的とした土地の使用権であり、相続の際には相続財産として引き継がれる資産です。相続することで借地上の建物をそのまま利用できる点はメリットですが、地代の支払いや維持管理の負担など、一定のデメリットも存在します。
相続するかどうかを判断する際は、借地を今後も利用する予定があるか、地代や修繕費を無理なく支払えるか、地主との関係が良好かといった観点から検討することが大切です。
また、借地権の相続では名義変更や契約書の有無などが原因でトラブルに発展するケースもあります。法的トラブルを自力で解決するのは難しいため、弁護士や借地権に詳しい不動産会社などの専門家に早めに相談しましょう。
弊社クランピーリアルエステートでは、借地権をはじめとする訳あり不動産の買取を専門としており、地主との交渉や契約条件の整理、登記手続きまでを一括でサポートしています。
「地主と揉めている」「相続登記が済んでいない」「地代の滞納がある」「共有名義で相続している」など複雑な事情がある場合でも、弁護士と連携して法的なリスクを最小限に抑えながらスムーズな取引を実現します。
状況に応じて最適な解決策をご提案しているため、借地権の相続でお困りの方は、ぜひ一度弊社にご相談ください。
よくある質問
借地権を相続する際に名義変更料は必要ですか?
借地権を法定相続人が相続する場合、名義変更料(譲渡承諾料)は不要です。相続では、借地権が契約上の地位をそのまま承継する形で引き継がれるため、地主の承諾を得る必要もありません。
ただし、法定相続人以外の第三者に借地権を遺贈する場合には、地主の承諾が必要になります。遺贈の際には、借地権価格の10%程度を目安とした譲渡承諾料が求められるケースがあります。
借地権を相続しない方法はありますか?
相続放棄の手続きをすれば、借地権を引き継がずに済みます。
ただし、相続放棄をすると借地権だけでなく、預貯金や不動産などのプラスの財産もすべて放棄することになります。借金や滞納地代などマイナスの財産が多い場合には有効ですが、プラスの財産が多い場合には結果的に損をする可能性もあります。
なお、相続放棄は、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申し立てが必要です。判断が難しい場合は、弁護士などの専門家へ相談しましょう。