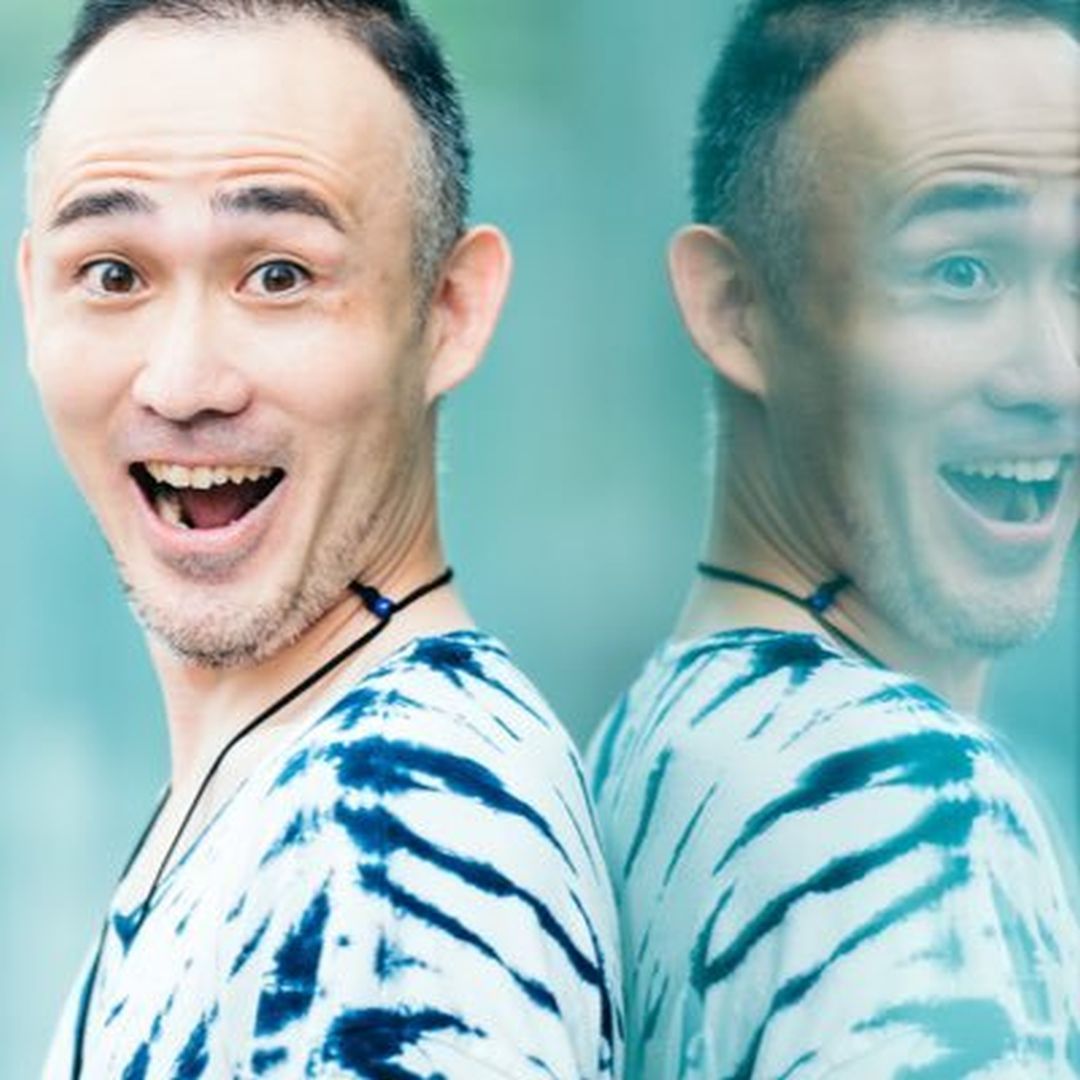共有名義不動産を賃貸に出すトラブルは?解決方法や賃貸の条件もあわせて解説

複数人が同じ不動産を所有する「共有名義不動産(共有不動産)」にてアパートなどを経営すると、入居者とのトラブルだけではなく、共有者同士のトラブルにも注意が必要です。ただでさえ入居者や建物の管理が大変であるにもかかわらず、同じ管理者であるはずの共有者とのいさかいに対して、頭を抱える賃貸経営者は後を絶ちません。
実際、共有名義の不動産買取を専門としている弊社でも、賃貸に出した共有不動産にてトラブルが起きてしまい、相談者さまに解決法の提示をしたり、解決が難しい場合には持分のみを買い取らせていただいたりといった事例が多くあります。
共有名義不動産の賃貸経営における共有者とのトラブルは、主に「不動産の管理や運営の意見対立」「家賃収入の分配」「税金などの支払い」「共有者による入居の賃料支払い」という4つのパターンに分けられます。
| 共有名義不動産の賃貸におけるトラブル事例 | 解決法 |
|---|---|
| 建物の修繕などの管理や運営方針について意見が割れる | ・共有状態を解消して自分が単独で運営するか、自分が管理から離れる ・共有持分買取請求権を行使して不当に管理負担から逃れる人の共有持分を買い取る |
| 管理の代表者が他共有者に家賃収入を分配しない | ・話し合いで解決しないなら、不当利得返還請求や訴訟にて家賃収入を取り戻す |
| 税金や管理費の支払いなどの支払いが誰かに偏る | ・共有持分買取請求をして、税金や管理費の支払いを渋る共有者の共有持分を買い取る |
| 共有者が賃料を払わずないまま住んでいる | ・不当利得返還請求で未払いの家賃を請求する |
上記のうち、家賃関係のトラブルは弊社にも多く寄せられます。
共有者同士で賃貸経営や管理をしていると、会社経営などと同じくお金関係で揉めるケースは珍しくありません。このようなトラブルが起きてしまった場合、話し合いで解決できなければ、民法に基づいた請求や訴訟で問題解決を目指すのが基本です。
また、共有名義不動産の賃貸によるトラブルの解消や回避には、共有状態自体を解消する方法も有効です。共有状態の解消方法としては「共有物分割請求をする」「共有持分のみを他共有者や買取業者へ売却する」「共有名義不動産全体を売却する」という方法が挙げられます。
本記事では、共有名義不動産の賃貸に関するよくあるトラブルと解消法をメインに、賃貸に出すための条件や流れなどを解説していきます。また、トラブル回避のために共有状態を解消するための方法も紹介しますのでぜひ参考にしてみてください。
目次
共有名義不動産を賃貸する場合によくあるトラブルと解消法
共有名義不動産は、複数人で所有している関係上、共有状態ならではの賃貸トラブルが起こりやすいです。
共有名義不動産を賃貸する場合によくあるトラブルおよび解決方法は、主に次の通りです。
| 共有名義不動産の賃貸におけるトラブル事例 | 解決法 |
|---|---|
| 建物の修繕などの管理や運営方針について意見が割れる | 共有状態を解消する 共有持分買取請求権や持分買取請求訴訟をおこなう |
| 管理の代表者が他共有者に家賃収入を分配しない | 不当利得返還請求や訴訟をおこなう |
| 税金や管理費の支払いなどの支払いが誰かに偏る | 共有持分買取請求権や持分買取請求訴訟をおこなう |
| 共有者が賃料を払わずないまま住んでいる | 不当利得返還請求や訴訟をおこなう |
トラブルが起きた場合、共有者との話し合いで解決を目指すのが基本ですが、場合によっては話し合いでの解決が困難な場合も少なくありません。その場合、「弁護士を通して訴訟を起こす」「買取業者などに持分を売却して共有状態から抜け出す」など、共有者以外の第三者の介入によってトラブルを解消せざるを得ない状況にもなりかねません。
そのため、共有名義不動産を賃貸に出す場合、まずは共有者と今後の管理や運用についてしっかり話し合ったうえで、トラブルを未然に防げる状況を作っておくことが大切です。
建物の修繕などの管理や運営方針について意見が割れる
共有者は、共有名義不動産のあり方について全員が同じ意見を持っているとは限りません。建物の修繕などの管理や共有名義不動産の運営方針について、共有者同士で意見が割れるトラブルはよくあることです。
実際に弊社が共有持分を買い取らせていただいた事例でも、共有状態の不動産の管理などに関して共有者と揉めてしまい、共有持分の売却に至った売主さまも多数いらっしゃいます。
共有名義不動産について意見が対立しやすい背景には、不動産を賃貸に出す際の共有者の同意の必要性が関係しています。
前提として、共有名義不動産においては共有者全員がその物件を使用する権利があります。そのため、共有者の誰かが単独で不動産全体を勝手に使用することはできず、修繕や管理の際には共有者から同意を得る必要があるのです。
これについては、下記のように民法第251条によって定められています。
各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。
e-Gov法令検索 民法(第251条)
たとえば、不動産の老朽化が進んだことで大幅なリノベーションをしたいと考えていても、他の共有者から反対されて同意が得られない場合を想定します。この場合、リノベーションを「したい派」「したくない派」のように共有者で対立してしまい、トラブルが起きてしまうケースがあるのです。
共有名義不動産を賃貸に出すか出さないかがきっかけでトラブルが起きた場合、まずは共有者間で話し合ったうえで解決を目指すのが基本です。とはいえ、話し合いを重ねるごとにお互いが感情的になってしまい、トラブルが激化してしまうことも多く、むしろ話し合いでは解決できない関係性になってしまうこともあります。
共有者同士で意見が分かれてまとまらないときは、共有名義状態を解消してトラブル解決を図ることも手です。「自分だけの単独名義にして自由に賃貸に出せるようにする」または「自分の所有権を放棄して他の共有者に運営を任せる」といった方法なら、少なくとも自分がトラブルに巻き込まれることはなくなります。
なお、共有状態を解消する方法については、「共有名義不動産の賃貸トラブルに悩むなら共有状態の解消も検討を」の見出しにて詳しく解説しています。
管理の代表者が他共有者に家賃収入を分配しない
共有名義不動産にて賃貸を経営する場合、入居者の家賃は一旦代表者へ一括入金されるのが基本です。その場合、代表者が共有持分割合などに基づいて、各共有者へ家賃を分配します。
しかし、代表者が他共有者へ家賃を分配せずにそのまま独占してしまうことも少なくありません。その場合、本来賃料の一部をもらえるはずだった共有者と賃料を独占した代表者で対立してしまいトラブルが起きてしまうことがあります。
もし管理の代表者が家賃分配を拒否しているときは、他共有者は自分が得られるはずの利益に対して「不当利得返還請求」を起こせる権利を行使できます。
不当利得返還請求とは、法律上の原因なく他人の財産や労務によって利益を得た人に対し、損失を被った人が当該利益の返還を求める請求です。民法第703条や704条で定められており、不当利得返還請求をできる権利を不当利得返還請求権と呼びます。
第七百三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
(悪意の受益者の返還義務等)
第七百四条 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
e-Gov法令検索 民法
不当利得返還請求にて請求できるのは、「家賃収入✕共有持分割合」で算出した金額が上限になります。内容証明郵便を利用して相手に通知すれば、話し合いに応じない相手に対しても賃料を請求したという事実を残せます。
それでも相手が家賃の返還に応じないときは、裁判所にて不当利得返還請求訴訟を提起し、裁判の判決をもって賃料を取り返すことも手です。
とはいえ不当利得返還請求訴訟まで進むと弁護士への依頼料や裁判の準備に必要な労力などが発生するため、可能な限り共有者同士の話し合いの段階での解決を目指すのがよいでしょう。
税金や管理費の支払いなどの支払いが誰かに偏る
民法第253条では、共有名義不動産において発生する固定資産税などの税金や管理に関するランニングコストなどは、各共有者がそれぞれで共有持分割合に応じて負担するように定められています。
各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
e-Gov法令検索 民法(第251条)
また、固定資産税や都市計画税に関しては、地方税法第10条2項でも「共有物や共有使用物などによって生じた物件に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を追う」と定められています。
このように法令では定められていますが、実際には「他の共有者が支払いを拒んでいる」「共有者の行方がわからない」といった理由から代表者1人だけで支払っているケースは少なくありません。
もし他の共有者が固定資産税の負担を拒否しているときは、民法第253条に基づく「共有持分買取請求権」を行使し、税金や管理費を支払わない共有者の共有持分を買い取ることを検討しましょう。「他の共有者の分まで自分が負担するなら、お金を払わない共有者の所有権を自分がもらえばよい」というイメージです。
共有持分買取請求権を行使すれば、立替分の支払いや管理費を1年を超えて拒否を続ける共有者の共有持分を、相当の対価を支払って取得できます。共有持分買取請求権は拒否できないうえに、他共有者の同意なく行使可能です。
共有者が賃料を払わずないまま住んでいる
賃貸運営している共有名義不動産の一室に、他共有者が賃料を支払わずにタダで住んでいるケースもあるかもしれません。状態としては「共有者が共有名義不動産における、自分の共有持分割合分を利用している」とも言えるため、無償で住んでいるからといってそれだけで違法な占有・使用には該当しません。
とはいえ、物件に居住していない共有者からすれば、賃料を支払わない共有者に対して不満が生じてしまうこともあるでしょう。この場合、共有者間で対立が起きてしまいトラブルが発生してしまうケースがあります。
なお、民法第249条では「他共有者の合意がないと、自分の共有持分割合を超える使用をするときに、超えた分の使用対価を他共有者へ償還する必要がある」と定められています。
各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
2 共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。
3 共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。
e-Gov法令検索 民法(第249条)
つまり共有者が無償で共有名義不動産の一室に住んでいる場合は、その共有者の共有持分割合を超える範囲において賃料の請求が可能です。賃料を請求するときは、管理の代表者が他共有者に家賃収入を分配しないで解説した不当利得返還請求で支払いを求めます。
共有名義不動産を賃貸に出すための条件
共有名義不動産を賃貸に出す行為は民法上の変更に該当します。民法では、共有物に変更を加える場合、持分割合の過半数を超える同意が必要と定められています。
共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。
e-Gov法令検索 民法(第252条)
つまり、共有名義不動産を賃貸に出すための条件は、持分割合の過半数を超えるように共有者からの同意を得ておくことと言えるのです。
また、賃貸借契約の期間に応じてどれだけの同意が必要になるかが変わります。2023年4月1日の民法改正後における、共有名義不動産を賃貸する際の条件は次の通りです。
| 共有名義不動産の賃貸借期間 | 契約期間の長さ | 必要な同意数 |
|---|---|---|
| 短期賃貸借 | 概ね3年以内 | 共有者の共有持分割合の過半数 |
| 長期賃貸借 | 概ね3年超 | 共有者全員 |
共有名義不動産を短期的に賃貸に出す場合は半数の同意が必要
共有名義不動産を短期的に賃貸に出す場合は、共有者の共有持分の過半数の同意が必要です。たとえば共有持分割合がA40%、B20%、C20%、D20%なら、AとBの同意があれば短期的な短期賃貸借を成立させられます。
民法第602条で定められた短期賃貸借期間では、建物の場合は3年、土地の場合は5年と定められています。とはいえ、実務的にはケースバイケースで判断されることが多く、一般的な賃貸借契約は2年程度であることから大体は短期賃貸借となると想定されます。
共有名義不動産を長期的に賃貸に出したい場合は全員の同意が必要
前述した建物における短期賃貸借の期間を超える賃貸借契約(3年超)を結ぶときは、原則として長期賃貸借に該当します。長期賃貸借は売却と同じく変更行為に該当するため、共有名義不動産の共有者全員の同意がなければ成立しません。
長期賃貸借が管理行為ではなく変更行為に該当する理由は、長期的契約による拘束で不動産の利用処分が困難になるからだと解されています。
共有名義不動産を賃貸に出す際の流れ
共有名義不動産を実際に賃貸に出す際の流れは、主に次の通りです。
- 他共有者の合意を取る
- 賃貸の方法を選択する
- 管理を委託する不動産会社に賃料査定を依頼して契約する
- 入居者募集&賃貸借契約の締結
他共有者の合意を取る
共有名義不動産を貸し出すために、必要な分だけ共有者の同意を得ます。短期賃貸借なら、共有持分の過半数が必要です。共有者の半数ではなく、共有持分割合の過半数なので注意しましょう。
法律上は必要な同意を得られれば貸し出せる一方、実際には共有者全員に何かしらの報告をするべきです。同意した共有者以外に報告せず無断で進めると、共有者同士の関係が悪化したりトラブルが発生したりするリスクがあります。それだけではなく、共有者同士の揉め事が原因で入居者に迷惑がかかって定着しない可能性があります。
入居者と賃貸借契約を結ぶときは、原則として共有者全員に連絡し、民法上の同意に加えて気持ちの面での合意を形成するのが無難でしょう。
賃貸の方法を選択する
共有者から必要な同意を得たときは、どのような方法で賃貸するかを決定します。主な賃貸の方法は次の3つです。
- 自主管理
- 管理委託
- サブリース
自主管理|自分たちでアパート経営全般を行う方法
自主管理とは、他の業者に依頼せずすべて自分たちでアパート経営全般をおこなう方法です。一般的には、入居者の募集、家賃の徴収、不動産の維持管理などを自分たちで対応します。専門知識や経験がある人は、自分で契約書の作成や図面作成まで対応することも可能です。
自主管理のメリットは、外部委託料がかからず売上が減らない、家賃や管理方法を自分たちで決められる、入居者の意見を直接聞けるなどが挙げられます。一方で、経営にかかる労力・時間が増える、不動産に関する専門知識が必要になるといった点が自主管理のデメリットとして挙げられます。
なお自主管理を選ぶ場合でも、入居者の募集と契約業務は不動産会社に依頼し、入居者の対応は自分たちでおこなう方法が効率的かつスムーズです。不動産会社に募集や契約業務を任せるときは、一般媒介、専任媒介、専属専任媒介のいずれかの契約を選んで締結します。
売主への縛りが多い代わりにもっとも積極的な販売活動が期待できる
| 媒介契約の種類 | 概要 |
|---|---|
| 一般媒介 | 1社だけでなく複数の不動産会社と重複して依頼できる 募集が入居したい人の目に留まる可能性が上がる |
| 専任媒介 | 契約を結んだ1社と貸主のみが募集行為をおこなえる 一般媒介よりも不動産会社の積極的な販売活動を期待しつつ自分でも募集できる |
| 専属専任媒介 | 契約を結んだ1社のみが募集行為をおこなえる |
管理委託|アパート経営全般を不動産会社に委託する方法
管理委託とは、アパート経営全般を不動産会社や管理会社に依頼する方法です。
管理委託をした場合、共有名義不動産の所有者たちがおこなうのは「本当に入居させるかの最終判断」「設備のメンテナンスや修理などに関する最終判断」などの承認行為です。募集、契約、維持管理に加えて、入居者との直接やり取りや家賃請求などもすべて委託先に一任できます。
管理委託のメリットは、専門家の経営・管理によるトラブルの低減や回避につながる、入居者の満足度が向上する、遠方にある不動産を管理・運用できるなどが挙げられます。一方で、管理委託手数料や仲介手数料などが発生する分だけ売上が減少するのがデメリットです。
サブリース|サブリース会社に賃貸して入居者を転貸する方法
サブリースとは、貸主がサブリース会社に貸し出した後、サブリース会社が入居者に貸し出す「転貸」をおこなう方法です。家賃・敷金礼金の設定・預かりから入居審査、契約行為、維持管理費用の支出(経年劣化は所有者の負担となるケースが多い)などをすべてサブリース会社が代行します。回収した家賃はサブリース会社が受け取り、貸主はサブリース会社からサブリース賃料を得ます。
サブリース会社のメリットは、経営・管理関係全般を任せられることに加えて、入居者がいなくても収入を得られる点です。貸主はサブリース会社に貸し出しており、貸主にお金を支払うのは入居者ではなくサブリース会社だからです。サブリース会社は、貸主に対して空室や家賃滞納に関する保証を含めてサブリース賃料として貸主に支払います。
ただし管理委託と比較すると、サブリースのほうが費用が高額になるのが一般的です。サブリース会社は「貸主から相場より安く借り、さらにそれを相場として転貸して利益を得る」というビジネスモデルであり、貸主側の手元に入る家賃は満室時の相場の80〜90%となります。
管理を委託する不動産会社に賃料査定を依頼して契約する
不動産会社に管理を委託する場合は、委託先に賃料査定を依頼します。賃料査定とは、賃貸物件とする予定の不動産において、適切な賃料を算出してもらうことです。
不動産会社の賃料査定は担当者の専門知識・実務経験、不動産の間取りや設備、周辺環境、取引情報などを基に算出するため、一般の人が設定する賃料よりも実態に合った金額に設定しやすくなります。より正確性の向上や偏りの防止につなげるには、賃料査定を複数の不動産会社に依頼するのがよいでしょう。
加えて、自分でも家賃相場を調べて比較すれば、相場から外れた査定をしている不動産会社を判断しやすくなります。
入居者募集&賃貸借契約の締結
不動産会社や管理会社を決めたら、入居条件を決めて実際に入居者を募集します。
管理委託の場合、広告掲載などの販売活動、入居希望者への説明や内覧などは、原則として不動産会社や管理会社が対応してくれます。自主管理のときは、自分で対応する範囲を確認しておきましょう。
募集を見た入居希望者が入居意思を固めて応募してきたときは、入居者に関する情報が記載された入居申込書を確認します。入居者の確認は管理委託でも貸主自身がおこなうのが一般的です。入居者の勤務先、年収、保証人の有無などを確認し、最終的に入居希望者と賃貸借契約を結ぶのかを決定します。
共有名義不動産を賃貸に出す場合の2つの注意点
共有名義不動産を賃貸に出す場合、共有名義不動産ならではの注意点が存在します。以下では、共有名義不動産を賃貸に出す場合の注意点である「共有者間でも契約書を締結しておく」「賃貸借契約の解除には過半数の同意が必要」の2点を解説します。
共有者間でも契約書を締結しておく
賃貸借契約を締結するときは、入居者だけでなく共有者間でも契約書を取り交わしておくことをおすすめします。賃貸借契約に関して共通の決まりごとを明確にしておき、後からトラブルに発展するのを防ぐ意味があります。
契約書には、「賃料をどのように分配するのか」「修繕が発生したときの負担割合はどのくらいか」「賃貸借契約における代表者は誰か」などを記載しましょう。契約書を作成する際には、弁護士や行政書士などの専門家の監修の下で、法的効力や実効性に問題のないものを作成してください。
また共有者同士が家族や友人などの親しい間柄でも、なあなあにせず契約書は作成しておきます。取り決めなかったことでトラブルとなり、親しかった人間関係が悪化するリスクがあります。
賃貸借契約の解除には過半数の同意が必要
共有名義不動産における借主との賃貸借契約は、契約解除をする場合でも、共有持分割合の過半数の同意が必要です。ここで言う解除とは「契約満了にともなう貸主・借主の同意の下でおこなわれた解除」ではなく、「借主側になんらかの瑕疵があって貸主側から借主に解除を申し出るケース」です。
ただし、共有持分の過半数の同意を得て解除を申し出たとしても、借主との賃貸借契約を一方的に解除できるわけではありません。途中解除が認められる正当な理由がない限り、原則として解除はできないとされています。
解除に至る正当な理由として、「借主が重大な契約違反をしている」「借主が家賃滞納を繰り返している」「借主が騒音、異臭、嫌がらせなどの迷惑行為をしている」などが挙げられます。
共有名義不動産の賃貸トラブルに悩むなら共有状態の解消も検討を
共有名義不動産の賃貸トラブルが発生したときは、共有名義を維持したままで問題を解決するよりも、そもそも共有状態を解消したほうが抜本的な対策になるケースがあります。「自分1人で運営したい」「経営・管理は他に任せて自分だけ所有権を手放したい」という場合は、共有名義状態の解消を検討してみましょう。
不動産の共有状態を解消する方法は、主に次の4つです。
- 共有物分割請求をする
- 他共有者に自分の持分を売却する
- 専門の買取業者に自分の持分を売却する
- 共有者全員の合意のもと不動産全体を売却する
それぞれの詳細を見ていきましょう。
共有物分割請求をする
共有物分割請求とは、共有状態となっている不動産について、共有者の1人が共有状態の解消を求める手続きです。民法第256条にて、「各共有者はいつでも共有物の分割を請求できる(5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をあらかじめしておくのは可能)」と定められています。
共有物分割請求を起こされると、他共有者はその請求を原則として拒否できません。そのため、合法的に共有状態の解消に向けて手続きを進められます。
まずおこなうのが、「共有物分割請求協議」による話し合いです。協議でも決まらないときは家庭裁判所にて話し合う「共有物分割請求調停」や、裁判所にて裁判官に判決を下してもらう「共有物分割請求訴訟」を提起します。
共有物分割請求訴訟は「調停前置主義」ではないため、調停を経なくてもそのまま訴訟の提起が可能です(離婚裁判などは先に離婚調停が必要になる)。また民法第258条にて「共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、または協議できないときは、その分割を裁判所に請求できる」と定められています。
賃貸経営している共有名義不動産の場合だと、主に「代償分割」か「換価分割」になると考えられます。他には「現物分割」が考えられますが、現物分割は賃貸アパートといった建物に適用するのが難しい方法です。現物分割なら、「賃貸アパート+土地」と「残りの土地すべて」といった分け方になると思われます。
| 共有物分割請求の種類 | 概要 |
|---|---|
| 代償分割 | 共有者の1人が他の共有持分を買い取りその分の代償金を支払う方法 |
| 換価分割 | 共有名義不動産をすべて売却し共有持分割合に応じて売却代金を分配する方法 |
| 現物分割 | 土地を分筆で分けるなど不動産を物理的に区分してそれぞれを単独名義で登記する方法 |
参考:e-Gov法令検索「民法第256条」
参考:e-Gov法令検索「民法第258条」
他共有者に自分の持分を売却する
自分の共有持分を他共有者に売却すれば、自分だけ共有名義不動産の所有権を手放せます。自己の共有持分だけの売却なら、他共有者の同意を得る必要がありません。
とはいえ、共有持分だけを欲しがる一般の人はほとんどいないため、一般の不動産市場だと共有持分を売却するのは難しいでしょう。しかし、共有名義不動産における他共有者になら売却できるかもしれません。他共有者は自己持分割合が増えると、共有名義不動産における影響力が増すメリットが大きいからです。
売却相場は、「共有名義不動産全体の市場価値✕共有持分割合」です。
専門の買取業者に自分の持分を売却する
自分の共有持分を、専門の買取業者に売却することで共有状態を解消する方法があります。
不動産の買取業者とは、不動産を直接買い取るサービスを提供する事業者です。買い取った不動産を、リフォームや修繕してから賃貸・転売などに活用して利益を得ます。
そして専門の買取業者とは、「共有持分専門の買取業者」や「訳あり物件専門の買取業者」などを意味します。
共有名義不動産の共有持分は、権利関係が複雑になるため、一般的な不動産会社や買取業者では対応を断られるケースも珍しくありません。一方で専門の買取業者なら買い取った後でも共有持分を活用できるノウハウを持っているため、適切な査定と買取に対応してくれます。直接買い取りで他に買手を探す必要もないことから、数日~1か月と非常に早い期間で売却できます。
ただし買取業者は買取対応後におこなうリフォームや修繕分の費用も査定額に含めるため、他共有者に売却するときよりも売却相場は低くなる傾向があります。とはいえ、確実かつスピーディーに売却して共有状態を解消したいときは、専門の買取業者への共有持分売却を推奨します。
共有者全員の合意のもと不動産全体を売却する
共有名義不動産における共有者全員の同意が得られれば、共有名義不動産全体を売却できます。
共有名義不動産全体を売却するメリットは、共有状態ではない、普通の不動産と同等の価格で売りやすい点です。共有者全員が売却するなら買手は単独名義の不動産を購入するのと同じであるため、通常の不動産と同じ売却価格で売っても需要が見込まれるからです。
共有者全員の同意を得るのは大変かもしれませんが、共有者全員に売却の意志があるなら不動産全体の売却を検討してみてください。
まとめ
共有名義不動産を賃貸物件として経営・管理する場合、共有者同士で経営方針を合わせたり収支・利用方法について特定の誰かに偏らないようにしたりなど、共有名義不動産ならではのトラブルに対応する必要があります。
トラブルリスクの低減・回避を第一に考えるなら、共有状態の解消を優先するのがよいでしょう。共有状態の解消は、共有物分割請求、自己の共有持分の売却、共有名義不動産全体の売却などの方法が挙げられます。単独名義で賃貸を経営・運用するなら、自分がすべての共有持分を買い取る、共有物分割請求にて代償分割をおこなうなどの方法が考えられます。
共有名義不動産を賃貸に出すときは、賃貸借契約を結ぶ前に共有者同士で話し合う、不動産会社や管理会社を選ぶ、入居者を募集して賃貸借契約を締結するという流れで進めていきます。賃貸に出すときは、共有者間での契約書作成や賃貸借契約解除時の共有者の同意についても確認してみてください。