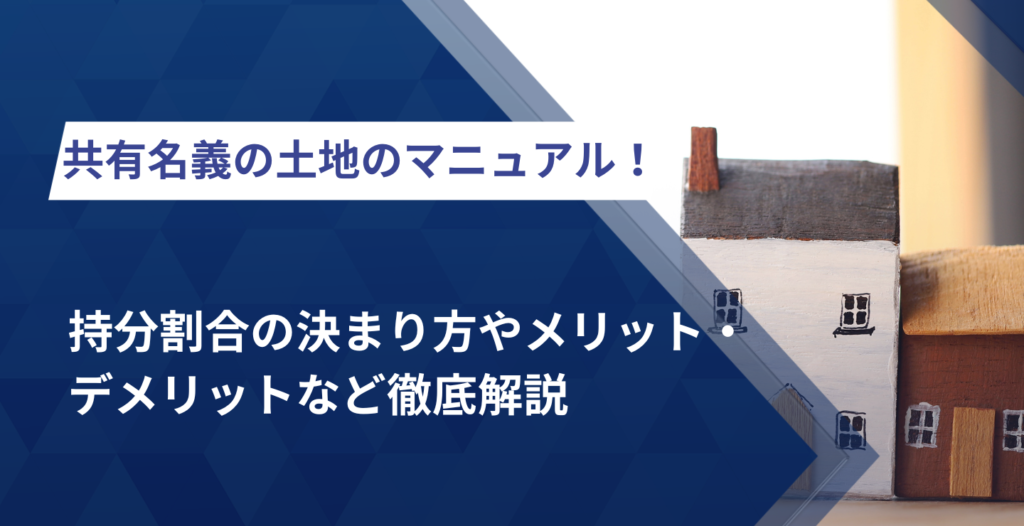不動産相続でもめるよくあるトラブル9選!予防方法や回避方法も解説

不動産は、相続財産のなかでも揉めることが多く、トラブルも起こりやすいです。実際、弊社にも「不動産の相続で意見がまとまらない」「感情的な争いに発展してしまった」などのご相談をいただくことがあります。
その原因として、不動産は現金のように平等に分けることが難しく、また共有名義にした場合は共有者同士の意思の統一が取りにくい点が挙げられます。共有名義の不動産を活用するためには共有者の同意が必要であり、反対する人がいれば身動きが取れない状態に陥ってしまいます。
さらに、「誰が相続するのか」「どのように活用するのか」などの意見の食い違いに加え、「親の介護をどれだけ担ったか」「生前贈与を受けていたか」など、感情的な対立が起こることもあります。
不動産の相続に関するトラブルを避けるためには、以下のような対処法が有効です。
- 遺言書を準備しておく
- 法定相続人を事前に確かめておく
- 相続人同士で話し合いをしておく
- 単独名義で相続する
- 相続時に不動産を売却して現金で分ける
被相続人の生前であれば、あらかじめ遺言書を準備しておきましょう。また、法定相続人を事前に確認のうえ、相続人同士で不動産の取り扱いについて事前に話し合っておくと、相続が発生した際に慌てずに済みます。
相続が発生した際には、将来的なトラブルを避けるためにも、共有名義ではなく単独名義で相続するか、不動産を売却して現金で分ける方法がおすすめです。
なお、すでに共有名義で相続している場合は、専門の買取業者に自分の持分だけを売却する方法を検討してみてください。自分の持分のみであれば共有者の同意が必要ないうえ、共有関係から早期に抜け出すことが可能です。
目次
- 不動産の相続は揉めやすい!その原因とは?
- 実際に不動産相続で揉めてしまったトラブル事例
- 相続したい人が複数人おり話がまとまらない
- 相続人は複数いたが、誰も相続したがらず不動産の押し付け合いになった
- 不動産の評価方法や評価額で折り合いがつかなかった
- 不動産の分割方法で意見が食い違った
- 不動産を取得した相続人から代償金が支払われていない
- 家を建てたい・売りたいなど、不動産の活用方法で揉めた
- 遺産となる自宅に人が住んでおり占領されていた
- 親と同居し介護をしていた相続人とそれ以外の相続人でもめた
- 相続税や譲渡所得税などの税金が支払えない・負担割合が公平ではない
- 相続する前から不動産が共有名義になっており相続をきっかけにさらに権利関係が複雑化した
- 前の代で相続登記がされておらず相続手続きが困難になっていた
- 不動産が空き家のままで劣化しており、いわゆる【負動産】になっていた
- 相続することが決まったものの登記しないまま放置してしまう
- 相続したものの維持管理せず近所に迷惑をかけている
- トラブルを回避するために不動産を共有名義で相続するのは避けるべき
- 不動産相続でもめるのを事前に防ぐ方法
- すでに不動産の相続トラブルが起きている場合の対処法
- 不動産相続に関する相談先
- 不動産相続のもめ事を回避するなら不動産の売却も有効な選択肢
- まとめ
不動産の相続は揉めやすい!その原因とは?
不動産の相続は、相続人同士で意見が対立しやすく、揉めることが多いものです。不動産の相続が揉めやすい原因は以下のとおりです。
- 不動産は公平に分けるのが非常に困難なため
- 共有で相続しても一所有者の意思で自由に利用できないため
不動産は現金のように均等に分けられないうえ、共有名義で相続してしまうと自由に活用ができません。
また、不動産に限らず、もともと相続人同士の関係性が悪かったり、相続内容が不公平だったりすると揉めやすくなります。たとえば、生前贈与や遺言書などで特定の相続人のみが多くの財産を受け取っていると、揉める原因となり得ます。
次の項目から、不動産の相続が揉めやすい原因について詳しく見ていきましょう。
不動産は公平に分けるのが非常に困難なため
不動産は現金のように均等に分けることが難しく、相続トラブルの大きな原因になりやすい財産です。とくに建物は物理的に分割するのが不可能であり、「誰が相続するのか」で揉めるケースが少なくありません。
また、土地であっても形状や立地条件によっては公平に分けることが困難です。たとえば、道路に面している部分とそうでない部分では価値が異なるため、単純に面積で分けても平等にはなりません。
不動産のほかに預貯金や有価証券などの財産が多くあれば、「相続人Aが不動産を取得し、相続人Bが不動産の評価額相当の現預金を取得し、残った財産を均等に分ける」といった方法が取れます。しかし、実際には遺産が不動産とわずかな貯金しかなく、公平に分けるのが困難というケースも多いです。
三菱UFJフィナンシャル・グループが実施した「退職前後世代が経験した資産承継に関する実態調査」によると、相続財産の平均額は3,273万円、中央値が1,600万円、なかでも不動産の割合が5割弱ともっとも高い結果となっています。
遺産の大半を不動産が占めていたとしても、相続人同士で合意して売却すれば現金で平等に分けられますが、思い入れや立場の違いなどにより、売却や分配がスムーズに進まないことも多いです。実際、弊社にも以下のようなご相談が寄せられたことがあります。
- 自分は売却を希望しているが、弟が「思い出があるから売りたくない」と反対している
- 長男だけ親から住宅購入資金の援助を受けていたため、他の相続人で不動産の売却代金を分けたいが、長男に反対されている
- 長女で最後まで親の介護をしており、生活費も出していたため、他の兄弟に不動産を譲りたくない
このように、不動産は物理的にも心理的にも分けにくい性質を持つため、公平な相続が難しく、結果的にトラブルへ発展しやすいです。
共有で相続しても一所有者の意思で自由に利用できないため
不動産を共有名義で相続した場合、各相続人はそれぞれが共有持分を所有することになります。
共有持分とは、不動産全体における所有権の割合を示すものです。たとえば、兄弟2人で均等に半分ずつ不動産を所有する場合、2分の1ずつ共有持分を持つことになります。
一見すると平等な分配方法に見えますが、不動産を共有名義で相続すると、自由に売却・建て替え・賃貸などの活用ができないという制約が生じます。
不動産に変更を加えたり活用したりするためには、他の共有者からの同意を得る必要があるからです。共有名義不動産の法律行為は「変更行為」「管理行為」「保存行為」の3つがあり、それぞれ求められる同意の条件が異なります。
| 法律行為 | 概要 | 同意の条件 |
|---|---|---|
| 変更行為 |
・売却 ・建物の解体 ・建物の建て替えや増改築 ・不動産への抵当権設定 |
共有者全員 |
| 管理行為 |
・リフォーム ・不動産の賃貸契約 |
共有持分の過半数 |
| 保存行為 |
・相続人全員のための相続登記 ・建物の修繕 ・軽微なリフォーム ・明け渡し要求 ・火災や災害時の建物滅失登記 |
なし |
不動産の売却や建物の取り壊しなどの変更行為は共有者全員、賃貸やリフォームなどの管理行為には共有持分の過半数の同意が必要です。
たとえば、兄弟2人で2分の1ずつ共有持分を所有している場合、どちらか1人でも反対すれば変更行為も管理行為も実行できません。なお、不動産の現状を維持するための保存行為であれば、共有者の同意を得ずとも1人で実行できます。
共有名義の不動産は1人の判断では活用できず、共有者の誰かが反対すれば手続きが進まないというリスクを抱えています。相続当初は関係が良好でも、売却や修繕などのタイミングで意見が割れ、結果的に活用できない不動産となってしまうケースも少なくありません。
実際に不動産相続で揉めてしまったトラブル事例
弊社では、不動産の相続に関する相談が寄せられることも多く、なかにはトラブルを抱えているケースもあります。具体的には、以下のようなトラブルが報告されています。
- 相続したい人が複数人おり話がまとまらない
- 相続人は複数いたが、誰も相続したがらず不動産の押し付け合いになった
- 不動産の評価方法や評価額で折り合いがつかなかった
- 不動産の分割方法で意見が食い違った
- 不動産を取得した相続人から代償金が支払われていない
- 家を建てたい・売りたいなど、不動産の活用方法で揉めた
- 遺産となる自宅に人が住んでおり占領されていた
- 親と同居し介護をしていた相続人とそれ以外の相続人でもめた
- 相続税や譲渡所得税などの税金が支払えない・負担割合が公平ではない
- 相続する前から不動産が共有名義になっており相続をきっかけにさらに権利関係が複雑化した
- 前の代で相続登記がされておらず相続手続きが困難になっていた
- 不動産が空き家のままで劣化しており、いわゆる【負動産】になっていた
- 相続することが決まったものの登記しないまま放置してしまう
- 相続したものの維持管理せず近所に迷惑をかけている
ここからは、筆者が実際に対応した不動産の買取事例を紹介します。なお、個人情報に配慮し、内容の一部を編集・再構成しています。
相続したい人が複数人おり話がまとまらない
相続人が複数いる場合、「誰が不動産を引き継ぐのか」をめぐって話し合いが長引くケースは珍しくありません。実際に、弊社にも以下のような相談が寄せられました。
意見が食い違ったまま協議が7か月以上進まず、相続全体の話し合いも滞っていました。最終的には弊社で共有持分の買取をし、問題を整理しました。
不動産の相続では、本来トラブルを避けるために1人が相続するのが望ましいとされています。しかし、不動産に住んでいる兄弟や家督相続にこだわる長男などが「自分が相続すべき」と主張すると、感情面での対立が起きやすくなります。
話し合いが長引けば、相続税申告の期限である10か月を超過してしまい、延滞税や加算税などのペナルティを受けることになります。
「誰が相続するのか」で揉めた場合、相続人同士で話し合って折り合いをつけるしかありません。どうしても解決できないときは、弁護士や司法書士、買取業者などの専門家に相談しながら話し合いを進めましょう。
相続人は複数いたが、誰も相続したがらず不動産の押し付け合いになった
複数の相続人がいても、不動産の資産価値が低かったり遠方に住んでいたりすると、誰も相続したがらず押し付け合いになってしまうケースがあります。実際に、弊社にも以下のような相談が寄せられました。
しかし、全員が県外に住んでいたうえ、老朽化した建物の維持や草刈り、固定資産税の支払いなどの負担もあり、相続希望者がいない状況でした。
「誰が相続するのか」と不動産の押し付け合いになってしまい、相続登記も進まず、最終的に弊社にご相談いただきました。
上記のように、不動産の築年数が古い場合、賃貸や居住などでの活用が困難です。また、不動産を使用しているかどうかにかかわらず、固定資産税の支払いは必須であるため、相続することで大きな負担を抱えてしまいます。
誰も不動産を相続したくないケースの場合、訳あり物件専門の買取業者へ相談することで、固定資産税や維持管理の負担を回避することが可能です。
不動産の評価方法や評価額で折り合いがつかなかった
不動産の評価方法や評価額で折り合いがつかず、相続の際に揉めるというケースも見られます。実際に、弊社にも以下のようなご相談が寄せられました。
税理士に依頼して路線価をもとに評価したところ、約5,000万円という結果になります。しかし、別の兄弟が不動産会社に査定を依頼したところ「時価なら7,000万円はある」と主張しました。
結果的に、誰の評価を基準にするのかで争いが生じ、「高く評価すると代償金を多く払うことになるから困る」「低く見積もられては損をする」といった感情的な対立に発展してしまいました。
上記のケースのように、不動産の評価額は「時価(実勢価格)」「公示価格」「路線価(相続税評価額)」「固定資産税評価額」などの算定方法によって異なります。それぞれの算定方法の概要は以下のとおりです。
| 算定方法 | 概要 |
|---|---|
| 実勢価格(時価) | 実際の市場取引で成立する価格であり、景気や需要によって変動する |
| 公示価格 | 国土交通省が毎年公表する、標準地の1㎡あたりの価格 |
| 路線価 | 国税庁が毎年公表する、道路に面する土地の1㎡あたりの評価額 |
| 固定資産税評価額 | 市区町村が固定資産税を算出するために評価した金額 |
同じ不動産であっても、どの算定方法を採用するのかによって、不動産の評価額に大きな差が生じることがあります。
もしも不動産の評価額が低ければ、不動産を取得する相続人にも、他の財産を取得する余地が残ります。一方、不動産の評価額が高ければ不動産以外の財産を相続できない可能性があるため、「不動産を相続する人」にとっては、評価額が低い算定方法が望ましいのです。
反対に、「不動産を相続しない人」は、評価額が高い算定方法を採用し、自分の取り分を多くしたいと考えるでしょう。このように、評価額の算定方法によって各相続人の取り分が大きく変わってくるため、折り合いがつかずに対立してしまうケースがあります。
どの算定方法を採用すべきかは専門知識がなければ判断が難しいため、税理士や不動産会社に相談しながら決めるのがおすすめです。
生前贈与の場合は贈与時点の評価額を採用
被相続人が生前に相続人の1人へ自宅などの不動産を贈与していた場合、その不動産は「特別受益」として扱われることがあります。
ただし、被相続人が「不動産の贈与分は持ち戻さなくてよい」と明確に意思を示していた場合は、加算の対象になりません。意思表示がない場合は、生前贈与時点の評価額をもとに相続財産へ加算されます。
このとき問題になるのが、「どの算定方法を採用するか」です。前述したとおり、算定方法によって不動産の評価額は大きく異なるため、相続人同士の主張が対立しやすくなります。一例として、以下のような事例があります。
生前贈与時点の基準で、自宅の評価額は路線価を使えば2,800万円、時価で評価すれば3,600万円と算定されました。
長男は「路線価の2,800万円を採用し、自分が現金100万円を取得すればお互い2,900万円ずつとなり、バランスが取れる」と主張します。しかし、次男は「時価の3,600万円を採用し、自分が現金をすべて取得したうえで代償金600万円を支払ってほしい」と反論します。
お互いの主張は平行線をたどり、争いに発展しました。
評価額の違いによって、現金や他の遺産の取り分が大きく変わるため、話し合いが難航するケースも少なくありません。このようなトラブルを避けるためには、贈与の段階で持戻し免除の意思を明確に示しておくこと、また評価方法について相続人間で事前に合意しておくことが大切です。
不動産の分割方法で意見が食い違った
不動産の分割方法にはいくつかの種類があり、相続人の価値観や状況によっては、分割方法をめぐって対立してしまうことがあります。不動産の分割方法は、主に以下の4種類です。
| 分割方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 現物分割 | ・不動産をそのままの状態で分割できる ・単独名義で所有できる |
・土地や建物の形状によっては分割が難しい ・土地を物理的に分割すると価値が下がってしまう |
| 代償分割 | ・相続を希望する人の単独名義で相続できる ・他の相続人に代償金を支払うため公平性が保てる |
・代償金を準備できないと成立しない |
| 換価分割 | ・不動産を売却して現金化するため、公平に分けられる ・使っていない不動産を手放すことができる |
・売却に反対する相続人がいると手続きが進まない |
| 共有分割 | ・不動産を複数人で共有するため、比較的スムーズに話が進みやすい | ・利用や管理の際に全員の同意が必要となる ・次の相続が発生した際に権利関係が複雑化する |
このように、不動産の分割方法にはそれぞれメリットとデメリットがあります。どのような分割方法があるのかをしっかりと把握したうえで、相続人全員が納得する方法を選ぶ必要があるのですが、意見が対立することも多いのが実情です。
実際、弊社にも不動産の分割方法をめぐって、以下のようなご相談が寄せられたことがあります。
しかし、兄弟は「思い出のある実家だから残したい」と売却に反対しました。
両者の主張は平行線のまま話し合いが進まなかったため、自身の持分のみを弊社に売却していただき、共有状態を解消することとなりました。
不動産の分割方法をめぐって揉める代表的な事例は、「不動産という形ある資産をどのように公平に扱うか」という価値観の違いです。
上記のケースのように、「売却して現金を公平に分けたい」と希望する人もいれば、「思い出があるため、売却せず相続人同士で管理していきたい」と考える人もいるためです。
なかでも、自宅や実家など感情が強く関わる物件は、売却するのか残すのかで対立が起こりやすく、結果的に協議が長期化するリスクがあります。話し合いがまとまらないまま放置すれば、建物の老朽化や固定資産税の負担など、新たな問題を抱えることにもなります。
話し合いで折り合いがつかない場合は、司法書士や弁護士など専門家を交えて、客観的なアドバイスを受けながら整理していくのが望ましいでしょう。
不動産を取得した相続人から代償金が支払われていない
代償分割で不動産を相続することになった場合、不動産を取得した相続人から代償金が支払われないといったトラブルが生じる可能性があります。
代償分割とは、相続人のうち一人が不動産などの現物資産を相続する代わりに、他の相続人へ金銭(代償金)を支払って公平性を保つ方法です。
不動産など物理的に分けにくい財産がある場合に選ばれる方法ですが、現金の支払い能力が求められるため、実際にはトラブルに発展するケースも多くみられます。実際、弊社にも以下のようなご相談が寄せられたことがあります。
しかし、長男は住宅ローンの返済や生活費の負担が重く、約束していた代償金を支払えないまま数年が経過します。
次男は「自分だけが損をしている」と不満を募らせ、関係性が悪化してしまいました。
代償金が支払われないまま時間が経つと、相続人同士の信頼関係が崩れるだけでなく、損害賠償や履行請求など法的トラブルに発展することもあります。
そのため、代償分割を選択する際には「本当に支払い能力があるのか」「いつまでに支払うのか」を明確にすることが大切です。不動産の取得を希望する人に支払い能力がない場合は、換価分割や現物分割など別の分割方法を検討しましょう。
家を建てたい・売りたいなど、不動産の活用方法で揉めた
不動産を共有名義で取得した場合、「家を建てたい」「売却して現金にしたい」など、不動産の活用方法で揉めるケースが多くみられます。実際、弊社にも以下のようなご相談が寄せられたことがあります。
建物が老朽化していたため、建て替えや売却を希望していましたが、建物に居住している共有者と意見が合わず、活用できないまま時間が経過します。
その後、共有者が独断でリフォーム工事をおこなったことで関係がさらに悪化し、ご相談者様は資産の管理や活用が進められない状況に陥りました。
最終的に、自身の持分のみを弊社に売却していただき、共有状態を解消することで問題を整理しました。
このように、不動産の利用方針が一致しない場合、共有関係を続けても活用できず、持っていても意味がない財産になりかねません。前述したとおり、建て替えや売却をするためには共有者全員の合意が必要となるため、意見が対立すると何もできず時間だけが経過してしまいます。
とくに、相続する不動産が土地のみの場合、建物付きよりも自由度が上がることから相続人同士で活用方法について揉めることが多くなります。たとえば「家を建てるために残しておきたい」「分筆して単独名義にしたい」「全体を売却して現金化したい」などです。
意見が対立して不動産の活用が難しい場合、専門の買取業者に自分の持分のみを売却するのも一つの手段です。自分の持分だけであれば共有者の合意なしで売却ができるうえ、面倒な共有関係からも抜け出せます。
遺産となる自宅に人が住んでおり占領されていた
遺産となった不動産に人が住んでいる場合、相続した不動産を自由に使うことができません。
たとえば、相続人の1人が長年居住しており、不動産を占拠している状態などが挙げられます。また、不動産の所有権を持っていない第三者が居住しているケースも存在します。
実際、弊社にも以下のようなご相談が寄せられたことがあります。
しかし、共有者は父の内縁関係にあった方の親族で、連絡も取れず、相続関係の確認も困難な状態でした。現地は空き家だと考えられていましたが、調査を進めたところ、第三者が居住していることが判明しました。
ご相談者様は不法占拠のような状況に困惑し、対応に苦慮していましたが、弊社が現地確認と共有関係の調査をおこない、最終的に持分を買取することで問題を解消しました。
相続した不動産が誰かに占有されている場合、たとえ自分が所有権を取得したとしても、自由に利用したり売却したりすることが難しくなります。また、相続人以外の人物(被相続人の愛人など)が居住しているケースでは、立ち退き交渉や法的手続きを要することもあります。
トラブルを避けるためには、相続が判明した時点ですぐに現地の状況を確認し、誰が居住しているのかを明確にしておくことが大切です。自力での対応が難しい場合は、弁護士などの専門家や買取業者に相談し、所有権の整理や現地対応を進めましょう。
親と同居し介護をしていた相続人とそれ以外の相続人でもめた
親と同居し介護を担っていた相続人がいる場合、相続の話し合いでトラブルに発展するケースは少なくありません。
被相続人の介護をしていた相続人には「寄与分」が認められ、他の相続人よりも相続財産を多く取得することが可能です。しかし、寄与分に対して他の相続人から不満の声が生じ、遺産分割がスムーズに進まないケースも多くみられます。
実際、弊社にも以下のようなご相談が寄せられたことがあります。
母親が亡くなった後、遺産分割の話し合いが始まり、長女が寄与分を考慮して多めの取り分を主張したところ、兄弟から「実家に住んでいたのだから介護するのは当然」と反発されてしまいました。
その後は感情的な対立に発展してしまい、収集がつかなくなったとのことです。
このように、介護の負担が特定の相続人に偏ると、「どの程度の寄与があったのか」「金銭的にどのくらい評価すべきか」といった点で意見が食い違いやすくなります。
長年にわたって介護を続けていた相続人からすると「寄与分をもらうのは当然」と考えるかもしれませんが、その他の相続人の取り分が減ってしまうことから、反対されることも多いです。
対策として、被相続人の生前から介護の実態を記録し、費用や時間を具体的に残しておくことが大切です。病院の診断書や介護サービスの利用明細などを保管しておくと、寄与分を主張する際の裏付けになります。
相続税や譲渡所得税などの税金が支払えない・負担割合が公平ではない
不動産を相続したり売却したりすると、相続税や譲渡所得税などの税金が発生します。
相続税は遺産を相続した際に発生する税金であり、原則として相続発生から10か月以内に納付する必要があります。また、不動産を売却して現金化する換価分割をおこなうと、譲渡所得税(所得税・住民税)が発生します。
相続税や譲渡所得税は、遺産の相続割合に応じて各相続人が負担するのが原則です。
不動産の評価額にもよりますが、これらの税金は金額が大きくなりやすく、「想像以上に税金がかかってしまった」「納税資金が用意できない」というケースも少なくありません。たとえば、相続財産の大半が不動産の場合は遺産から相続税を確保することができず、やむを得ず土地や建物を売却するケースもあります。
実際、弊社にも以下のようなご相談が寄せられたことがあります。
ところが、遺産のほとんどが築年数の古い一戸建てのみで、現金や預貯金はほとんど残っていませんでした。
不動産の評価額が高かったため相続税が発生しましたが、誰も納税資金を用意できず、やむを得ず実家を売却して資金を確保することになりました。
遺産の大半が不動産で構成されている場合、評価額によっては相続税が高額になり、納税資金が不足してしまうことがあります。相続税が支払えない場合は換価分割で現金を分けることになりますが、売却した翌年に確定申告をおこない、各自で譲渡所得税を納めなければなりません。
納税に関して不安がある場合、相続を開始する段階で税理士に相談し、相続税や譲渡所得税がどの程度になりそうなのかを計算してもらいましょう。あらかじめ税額を把握しておけば、納税に向けての資金計画を立てやすくなります。
相続する前から不動産が共有名義になっており相続をきっかけにさらに権利関係が複雑化した
不動産がもともと共有名義になっている場合、相続をきっかけにさらに権利関係が複雑になることがあります。
たとえば、自分の親と親の兄弟で共有している不動産があるとします。親が亡くなって不動産を相続することになった場合、伯母や伯父など関係性の薄い人物が共有者となります。
仮に伯母・伯父がすでに死亡している場合、その子どもが不動産を引き継いでいる可能性も考えられるでしょう。そうなると、誰が共有者なのかわからなくなったり、親世代の頃よりも共有者が増えたりしてしまいます。
もしも遺産分割の際に話がまとまらず、とりあえず全員で共有してしまうと、子どもや孫など世代間で相続が発生した際に共有者が次第に増え、権利関係が複雑化していきます。
前述したとおり、共有不動産で不動産を相続すると、売却や管理などの重要な判断をおこなう際に共有者の同意が必要となります。権利関係が複雑化するほど同意を得ることが難しくなり、不動産の活用が難しくなってしまいます。
また、共有名義の不動産は「持分を勝手に売却され、見知らぬ第三者が共有者になる」というリスクも抱えています。実際、弊社にも以下のようなご相談が寄せられたことがあります。
ところが数か月後、弟の持分が第三者へ売却されていたことが判明しました。知らない人物が新たな共有者となり、売却や管理に関する話し合いも難航します。
ご相談者様は不安を感じ、最終的に自身の持分を弊社へ売却する決断をされました。土地は不整形で再建築時にセットバックが必要な制限もありましたが、弊社にて現況のまま買取いたしました。
このように、共有名義のまま相続した不動産は、後に第三者が共有者となることで、さらに権利関係が入り組んでしまう可能性があります。
共有者が増えるほど意思決定に時間がかかり、将来的に子どもや孫の代へ相続が引き継がれるたびに合意形成が難しくなっていきます。
トラブルを防ぐためには、相続の段階で共有状態をできるだけ解消しておくことが大切です。たとえば「1人が不動産を単独で取得し、他の相続人には代償金を支払う」「不動産全体を売却して現金を分ける」などの方法があります。
前の代で相続登記がされておらず相続手続きが困難になっていた
不動産の名義が前の世代のままになっている場合、現所有者が相続登記をしようとしても、前の代の登記からやり直す必要があり、手続きが非常に煩雑になります。
たとえば、不動産の名義が祖父母や曽祖父母など古い時代のまま残っているケースが挙げられます。世代が古くなるほど「相続人が増えて所在不明者が出る」「戸籍の取得に時間がかかる」「必要書類が見つからない」などの問題が生じやすく、登記完了まで長期間を要します。
実際、弊社にも以下のようなご相談が寄せられたことがあります。
さらに、土地上には前の代で相続登記されていないアパートが建っており、1室が賃貸中という複雑な状況も重なっていました。
こうした事情から、自身の持分を整理する目的で弊社へご相談いただきました。現地調査と法的確認を経て共有持分を買い取らせていただき、問題を早期に解消いたしました。
このように、前の代で相続登記が行われていない不動産は、名義の古さが原因で手続きが進まないケースが多く見られます。
トラブルを防ぐためには、相続が発生した時点で速やかに相続登記をおこなうことが重要です。2024年4月からは相続登記が義務化され、正当な理由なく3年以内に登記をしない場合、10万円以下の過料が科されます。
相続を次世代へ円滑に引き継ぐためにも、名義が古いままの不動産は早めに登記を進めるか、手放すかのどちらかで対処しましょう。
参照:相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)|東京法務局
不動産が空き家のままで劣化しており、いわゆる【負動産】になっていた
相続した不動産を空き家のまま長期間放置してしまうと、老朽化や倒壊の危険性が高まり、「特定空き家」に指定されることがあります。
特定空き家とは、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、以下のような状態にある空き家のことを指します。
- 倒壊などの危険がある状態
- 衛生上有害となる恐れがある状態
- 景観を著しく損なっている状態
- 周辺の生活環境を悪化させている状態
特定空き家に指定されると、行政から修繕や撤去の指導を受けるだけでなく、固定資産税の軽減措置も適用外になります。
通常、住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」が適用され、固定資産税が最大6分の1まで軽減されています。しかし、特定空き家に指定されると特例の適用外となり、固定資産税が最大6倍に跳ね上がることもあります。
固定資産税の負担が跳ね上がると、活用できないどころか維持管理費ばかりがかかる、いわゆる「負動産」になってしまいます。
実際、弊社でも老朽化した空き家の買取をした事例があります。
売主様自身も別の地域に転居し、かつて居住していた家は空き家の状態に。建物の外壁や屋根の劣化が進み、近隣からも苦情が寄せられるようになっていました。
今後の管理や固定資産税の負担を考え、最終的に弊社へ共有持分をご相談いただきました。対象の不動産は空き家になってから急速に劣化が進んでいたため、弊社で早急に調査・手続きをおこない、現況のまま買取いたしました。
空き家を負の財産にしないためには、定期的な点検や清掃をおこない、状態を維持することが大切です。
今後住む予定がない場合や、共有者間で活用方針が決まらない場合には、早めに売却や買取を検討しましょう。放置すればするほど、資産価値が下がり修繕費も膨らむため、早期の対応が結果的に負担を軽減することにつながります。
相続することが決まったものの登記しないまま放置してしまう
相続人が決まり、誰が不動産を引き継ぐのかが明確になっていても、登記をせずにそのまま放置してしまうケースがあります。実際、弊社にも以下のようなご相談が寄せられています。
調査の結果、母は「落ち着いたら登記すればいい」と手続きを後回しにしたまま、10年以上が経過していたとのことです。母が亡くなり、登記がおこなわれていなかった実家は、祖母・母・子世代の三代にわたる相続関係となってしまいました。
結果として、名義が古いまま相続人が増え、連絡が取れない親族も出てきたため、登記や売却の手続きが難航したことで弊社にご相談いただきました。
このように、相続登記を怠ると、次の世代でさらに相続が発生した際に権利関係が複雑化し、名義変更や不動産活用が難しくなります。登記が完了していなければ、売却や担保設定、賃貸契約などの不動産取引もできません。
また、2024年4月からは相続登記が義務化され、相続によって不動産を取得したと知った日から3年以内に登記をしなければ、10万円以下の過料が科されます。遺産分割協議が成立した場合も、成立日から3年以内に相続登記をする必要があります。
「いつかやろう」と思っているうちに、関係者が亡くなったり、連絡が取れなくなったりするケースは珍しくありません。相続人が決まった段階で、速やかに登記を完了させておくことが、将来のトラブルを防ぐ最も確実な方法です。
相続したものの維持管理せず近所に迷惑をかけている
相続によって不動産を引き継いだものの、遠方に住んでいたり多忙であったりして、維持管理を怠ってしまうケースは少なくありません。
とくに戸建住宅の場合は定期的に手入れをしなければ、建物の老朽化や雑草の繁茂、害虫の発生などが進み、近隣トラブルに発展する恐れがあります。実際、弊社にも以下のようなご相談が寄せられたことがあります。
普段は関東で暮らしており、実家のある地方には年に一度しか帰省できなかったため、管理はほとんど手つかずの状態になっていたとのことです。
数年が経つうちに庭木の枝が隣家の敷地まで伸び、風で落ちた枝が隣家の車を傷つけてしまいました。さらに屋根瓦の一部が台風で飛ばされ、近隣住民から苦情が相次いだことでようやく現地の状況を知り、慌てて対応することになりました。
最終的には弊社にご相談いただき、空き家のまま買取をさせていただきました。
このように、不動産を放置すると、倒壊や火災といった危険だけでなく、思わぬ形で周囲に損害を与えるリスクがあります。また、人が住んでいない家は防犯面でも狙われやすく、放火や不法侵入の被害につながることもあります。
相続した不動産は、定期的に現地を確認して清掃や草木の手入れをおこなうほか、近隣住民との関係を保つことが大切です。遠方に住んでおり管理が難しい場合は、早めに売却することも検討しましょう。
トラブルを回避するために不動産を共有名義で相続するのは避けるべき
相続人同士のトラブルを回避したいからといって、不動産を共有名義で相続するのは避けるべきといえます。
共有名義で相続すると、あとから「不動産を活用できない」「売却に反対されている」などの問題が生じる可能性があるためです。相続時に不動産を売却して現金で分けるか、不動産の取得を希望する人の単独名義で相続し、共有名義を回避しましょう。
なお、共有名義で相続してしまった場合は、相続後に自分の持分のみを売却して共有名義から抜け出す方法がおすすめです。自分の持分のみであれば共有者の同意は必要ありません。
ここでは、不動産の共有名義を避けるべき理由について詳しく解説します。
面倒だから「とりあえず共有名義で相続する」と後で苦労することになる
不動産を相続する際、「とりあえず平等に分けておけばいい」と安易に共有名義にしてしまうケースがあります。しかし、共有名義は一見公平に思えても、後々の管理や処分をめぐってトラブルに発展することが少なくありません。
共有名義の最大の問題は、売却や賃貸、リフォーム、建て替えなど、重要な決定をする際に共有者の同意が必要になる点です。
たとえば、共有者の1人が「売却して現金化したい」と考えても、他の共有者が「思い出の家を残したい」「賃貸にして収益化したい」と反対すれば、手続きを進められません。不動産を使用していなくても、固定資産税や修繕費などの維持管理費は生じるため、話し合いが長引くほど負担だけが続いてしまいます。
また、共有者の中に遠方に住んでいる人や連絡が取りにくい人がいれば、意見をまとめるのがさらに難しくなります。共有状態を放置すると、次の世代の相続で共有者がさらに増え、権利関係が複雑化していくリスクもあります。
相続当初は良好な関係でも、時間の経過や価値観の違いによって対立が生じるケースは珍しくありません。「とりあえず共有名義で相続する」と、結果的に売ることも使うこともできない負の財産になってしまう可能性があるため、できるだけ共有名義は避けましょう。
もめ事を防ぐなら単独名義で相続するか相続後に持分を売却する
不動産の相続では、相続人全員の合意を得られている場合、最初から単独名義にして登記をするのが理想です。単独名義であれば、不動産の売却やリフォーム、賃貸活用などが1人の判断で進められるため、共有者間での意見の食い違いによるトラブルを避けられます。
なお、単独名義にする過程では「公平さに欠けるのでは」といった感情的な対立が生じる場合もあります。しかし、共有状態を続けるよりは後々のもめ事を大幅に減らせるため、遺産分割協議で納得のいくまで話し合いをし、誰か1人の単独名義で相続を進めましょう。
すでに共有名義で相続してしまっており、不動産を活用する予定がなければ、自分の持分だけを専門の買取業者に売却する方法がおすすめです。持分を売却すれば早期に共有関係から抜け出すことができ、今後のトラブルや管理負担を回避できます。
不動産相続でもめるのを事前に防ぐ方法
不動産相続でのもめ事を事前に防ぐためにも、以下のような準備を進めておきましょう。
- 遺言書を準備する
- 法定相続人を確かめておく
- 相続人同士で事前に話し合いをしておく・まめにコミュニケーションをとる
なお、不動産の活用予定がなければ売却を検討するのもおすすめです。詳細は「不動産相続のもめ事を回避するなら不動産の売却も有効な選択肢」の項目で解説しているため、あわせて参考にしてみてください。
遺言書を準備する
不動産相続でのもめ事を防ぐためには、生前に遺言書を準備しておくことが効果的です。遺言書があれば原則としてその内容が優先されるため、相続人同士で遺産分割協議をおこなう必要がなく、トラブルが発生する可能性を大きく減らせます。
ただし、形式に不備があったり、内容に偏りがあると、遺言書の効力を巡って新たな争いが生じる可能性があります。
とくに自筆証書遺言の場合は全文を自分で書く必要があり、日付や署名、押印などの要件を満たしていなければ無効とされてしまいます。また、保管場所が自宅の場合は、改ざんや紛失のリスクもあるため注意が必要です。
そのため、より確実に相続人の意思を反映させたい場合は、公証人が作成する「公正証書遺言」を選ぶのが安心です。
費用はかかりますが、相続人同士の争いを防ぎ、確実に意志を伝えるという意味で公正証書遺言は最も信頼性の高い方法です。
また、遺言内容を決める際は、相続人全員の「遺留分」に配慮し、誰かが不利益を被らないようにバランスを取ることも大切です。遺留分とは、配偶者や子どもなどの一定の相続人に保障されている最低限の取り分のことです。
可能であれば、被相続人と相続人全員で話し合いながら遺言の内容を取り決めていき、公正証書遺言として残しましょう。
法定相続人を確かめておく
相続手続きを円滑に進めるためには、法定相続人が誰なのかを事前に把握しておくことも大切です。
相続では、不動産の名義変更や遺産分割協議など、法定相続人全員の同意や署名・押印が必要となる手続きが多くあります。誰が相続人なのかを把握していないと、必要書類がそろわなかったり、同意が得られず手続きが進まなかったりなどのトラブルにつながります。
なお、遺産分割協議に期限はありませんが、相続税の申告期限は「相続があったことを知った日から10か月以内」と定められています。そのため、実際には被相続人が亡くなってから10か月以内に、相続人や財産の調査、遺産分割協議などを済ませなければなりません。
このように、相続には期限が設けられているため、あらかじめ法定相続人を確認し、連絡を取れる状態にしておきましょう。事前に相続人調査をしておけば、計画的に相続を完了させやすくなります。
相続人同士で事前に話し合いをしておく・まめにコミュニケーションをとる
相続トラブルを防ぐためにも、相続が発生する前から家族間で話し合いをしておきましょう。親子や兄弟姉妹の間で日頃からまめにコミュニケーションを取っておくことで、誤解や感情的な対立を防ぎ、円満な相続が可能になります。
弊社にも、相続が発生してから慌てて話し合いを始め、限られた時間の中で意見がまとまらず、感情的なすれ違いが生じてしまったというご相談が寄せられています。
「誰がどの不動産を相続するか」「売却して分けるか」「将来的にどう活用するか」といった話には金銭がかかわるため、相続人同士の関係が良好でも揉めることがあります。
そのため、被相続人の生前に資産の内容や評価額を把握し、あらかじめ方向性を共有しておきましょう。家族間でしっかり話し合うことで、後になって「聞いていなかった」「不公平だ」などの不満が生じるのを防げます。
すでに不動産の相続トラブルが起きている場合の対処法
すでに不動産の相続トラブルが起きている場合、以下のような対処法を検討しましょう。
- 遺産分割調停を申し立てて裁判所の力を借りる
- 裁判外紛争解決手続(ADR)で紛争を解決する
なお、不動産の相続トラブルに巻き込まれたくない場合、売却するのも選択肢のひとつです。詳細は「不動産相続のもめ事を回避するなら不動産の売却も有効な選択肢」の項目で解説しているため、あわせて参考にしてみてください。
遺産分割調停を申し立てて裁判所の力を借りる
遺産分割協議で合意が得られなかった場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることで、第三者の立場から公平に調整を進めてもらうことができます。
遺産分割調停では、裁判官と調停委員が中立の立場で双方の意見を聞き、相続人間の利害や感情を整理しながら合意点を探ります。必要に応じて、不動産の鑑定や資料提出を求められることもあり、客観的な情報をもとに話し合いを進められます。
調停で合意に至った場合には、法的拘束力のある「調停調書」が作成され、相手方が合意内容に従わない場合でも強制執行が可能です。
なお、調停で話がまとまらなかった場合は「審判」に移行し、裁判官が不動産や財産の内容、当事者の事情を総合的に考慮したうえで分割内容を決定します。審判の結果は法的効力を持ち、当事者はその内容に従う義務があります。
家庭裁判所の手続きを利用することで、感情的な対立を抑えつつ法的に有効な形で遺産分割を確定さられるため、話し合いが難航している場合に有効な解決手段です。
参照:遺産分割調停|裁判所
裁判外紛争解決手続(ADR)で紛争を解決する
相続トラブルをできるだけ穏便に解決したい場合には、裁判を起こさずに第三者の専門家が仲介する「裁判外紛争解決手続(ADR)」を利用する方法があります。
ADR(Alternative Dispute Resolution)とは、公正・中立な立場の第三者が当事者双方の意見を丁寧に聞き取り、合意形成を図る手続きのことです。
裁判のように公開の場で争う必要がなく、話し合いによって円満な解決を目指す点が特徴です。手続きは非公開でおこなわれるため、プライバシーを守りながら問題を解決できるというメリットもあります。
不動産相続に関するトラブルで利用できる代表的なADR機関には、弁護士が仲裁に入る「弁護士会の紛争解決センター」や、不動産に特化した「日本不動産仲裁機構の不動産ADRセンター」などがあります。
いずれも専門知識をもつ第三者が公正な立場から話し合いを進めるため、感情的な対立を和らげながら合意点を見出しやすいのが特徴です。
裁判よりも手続きが簡易で費用も抑えられるため、「できるだけ話し合いで解決したい」「関係をこじらせたくない」と考える場合には、ADRの活用を検討するとよいでしょう。
不動産相続に関する相談先
不動産相続に関して、困ったことがあれば専門家に相談しましょう。主な相談先と対応できる内容は以下のとおりです。
| 相談先 | 相談・解決できる内容 |
|---|---|
| 弁護士 | 遺産分割の争い、調停や訴訟、遺言書の作成、相続放棄など法律に関するトラブル全般 |
| 税理士 | 相続税や譲渡所得税の申告・節税対策、納税資金の確保方法など、税金に関すること全般 |
| 司法書士 | 相続登記や名義変更など不動産に関する登記手続きや、遺産分割協議書の作成、法定相続情報一覧図の取得手続きなど |
| 行政書士 | 遺言書や遺産分割協議書など書類作成の代行 |
法的トラブルなら弁護士、税金の相談なら税理士、不動産登記に関する相談なら司法書士、書類作成の依頼なら行政書士に依頼するのがおすすめです。
不動産相続のもめ事を回避するなら不動産の売却も有効な選択肢
相続をめぐるトラブルの多くは、不動産をどのように分けるかで意見が対立することから発生します。相続でのもめ事を回避するためには、使う予定のない不動産を売却することも有効な選択肢となります。
被相続人、つまり親の立場であれば、生前のうちに不動産を売却して現金化しておくことで、相続財産を平等に分配しやすくなります。現金であれば分け方が明確なため、遺産分割協議がスムーズに進み、相続人同士の争いを防げます。
一方、すでに共有状態で不動産の相続が完了している場合は、自分の共有持分のみを売却することも検討しましょう。持分の売却に共有者の同意は必要ないため、「他の共有者と活用方針が合わない」「関係性が悪く、話し合いができない」などのケースにおいて有効な手段です。
まとめ
不動産は現金のように平等に分けられないため、相続の際にもめ事が起きやすくなります。
とくに共有名義で相続した場合は、売却やリフォーム、建て替えなどのたびに全員の同意が必要となり、話がまとまらないまま年月が経ってしまうケースも少なくありません。
トラブルを避けるためには、生前のうちに公正証書遺言を用意したり、法定相続人を確認したりして、相続に備えることが大切です。また、相続人同士が日頃からコミュニケーションをとり、互いの考えを理解しておくことで、感情的な対立を防げます。
なお、「すでに共有名義で不動産を相続している」「相続人との関係が悪く、話し合いにならない」などの状況の場合、専門の買取業者に相談するのも一つの手段です。共有名義から抜け出すことで、将来的なトラブルや維持費の負担を避けられます。