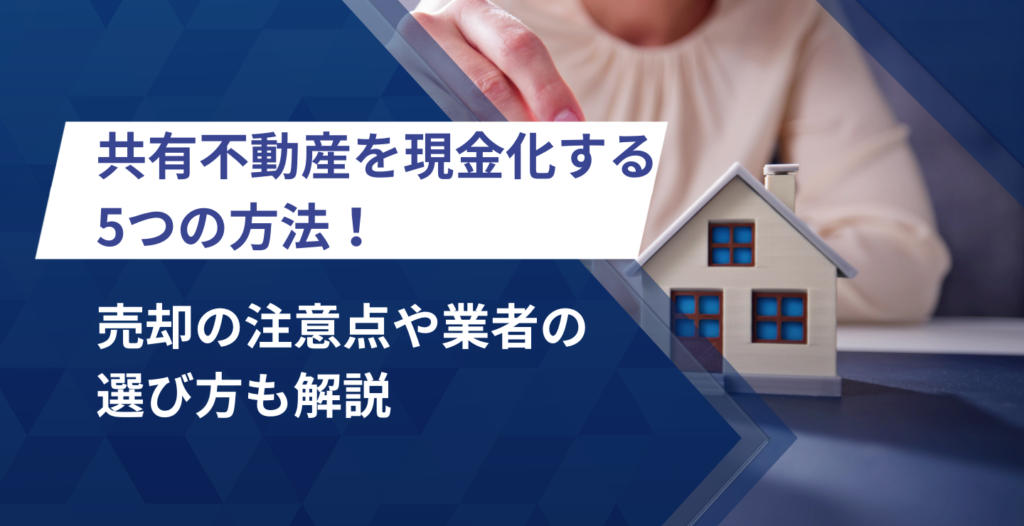共有持分とは?権利やリスク、共有状態を解消する方法について解説

兄弟で親の遺産を相続したときや夫婦が共同で不動産を購入する場合など、1つの不動産を複数名で所有することになるケースは少なくありません。そのとき、各共有者が同じ割合を所有することもあれば、異なる割合で所有することもあります。
共有持分とは、各共有者が持つ所有権の割合のことです。たとえば持分割合が2分の1なら、「不動産全体に対して2分の1の権利を持っている」ということであり、2分の1の範囲内で不動産全体を使用できます。
不動産を共有することには、「相続税の節税」や「住宅ローンが組みやすくなる」「共有者それぞれが住宅ローン控除を受けられる」といったメリットがあります。
しかしその一方で、単独で不動産全体を売却したり不動産を賃貸に出したりといったことができないデメリットがある点に注意が必要です。不動産全体を売却したり賃貸に出したりする場合は他の共有者の同意が必要になり、意見の食い違いからトラブルになる可能性があります。
相続によって権利関係が複雑化したり、共有者が共有持分を売却することによって見知らぬ第三者と共有関係になってしまったりするリスクも考えられるため、できれば共有状態の解消を検討したほうがよいでしょう。
この記事では、共有持分の権利やリスク、共有状態の解消方法について解説します。共有持分のトラブル事例も紹介しているため、ぜひ最後までご覧ください。
目次
共有持分とは共有者がそれぞれ持つ所有権の割合
「共有持分」とは、1つのものを2人以上で共有しているときに、それぞれが持つ所有権の割合のことをいいます。たとえば土地の所有者が亡くなり、その子どもであるA・Bが土地を相続した場合、遺産分割前の共有持分はA・Bともに「2分の1」です。
なお、この2分の1とは、「土地の2分の1を所有している」という意味ではなく、それぞれが「土地全体に対して2分の1の権利を有している」ということです。
また、「共有名義」という言葉が使われることもありますが、共有名義は共有持分とは異なり、1つのものを2人以上が共有している状況そのものを指します。
共有持分が発生するケース
以下のとおり、共有持分はさまざまな状況で発生します。
- 亡き親の不動産を兄弟姉妹で受け継いだ
- 夫婦で共同してマイホームを購入した
- 親子で建築費用を出し合って二世帯住宅を新築した
- 複数名で私道を共有・利用している
亡き親の不動産をその子どもたちが受け継げば、不動産は共有になります。たとえば、3人の子どもが民法で定められている「法定相続分」どおりに相続した場合、それぞれの共有持分は3分の1ずつです。
夫婦でペアローンを組んだり費用を出し合ったりしてマイホームを購入したときは、以下のように費用負担割合と持分割合を統一させるのが一般的です。
▼3,000万円の住宅を購入し、夫が2,000万円・妻が1,000万円負担したケース
| 夫の共有持分 | 3分の2 |
|---|---|
| 妻の共有持分 | 3分の1 |
親子で「親子リレーローン」を組んで二世帯住宅を建築するのもよくあるケースです。この場合も夫婦が共同でマイホームを購入したときと同様に、出資額と持分割合を統一させます。
そのほか、共同で利用している私道を複数名で所有しているパターンも珍しくありません。
なお、共有持分には以下のようなメリットがあります。
- 相続税の節税になる
- 住宅ローンが組みやすくなる
- それぞれが「住宅ローン控除」を受けられる
不動産を共有していることで、相続税の節税になります。共有不動産全体ではなく共有持分が相続税の課税対象になるためです。
たとえば3,000万円の不動産を2分の1ずつ所有している共有者のうち、片方が亡くなったとします。このケースで課税対象になるのは「亡くなった共有者の持分」です。つまり、1,500万円が課税対象になるということです。
また、住宅ローンが組みやすくなるというメリットもあります。中には夫婦2人で組む「ペアローン」や親子2代にわたって返済していく「親子リレーローン」など、借入審査の際に共有者の収入を合算できるものもあるためです。
「1人では審査に通りそうにない」という状況で有効でしょう。
そのほか、それぞれが「住宅ローン控除」を受けられるのもメリットの1つです。
住宅ローンを組んでマイホームの新築や増築を行う際に、ローン残高の0.7%を最大13年間にわたって所得税から控除できる制度のこと。
たとえば働いている夫婦がペアローンを組んでいる場合、2人ともが住宅ローン控除を受けられます。
離婚時の財産分与で共有名義不動産はどうするべきかについて知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
共有持分で共有者が持つ権利
各共有者は、共有持分について以下の権利を持っています。
| 行為 | 概要 | 具体例 |
|---|---|---|
| 使用 | 共有持分に応じて使用できる | ・共有者全員で共同使用する ・それぞれの持分の範囲内で自宅や事務所として使用する など |
| 変更 | 共有者全員の合意が必要 | ・売却 ・贈与 ・長期賃貸借契約 など ※軽微な変更については「持分の過半数の同意」で行える |
| 管理 | 共有者の持分価格の過半数の合意が必要 | ・共有物の改装 ・共有地の整地 ・短期賃貸借契約 など |
| 保存 | 各共有者が単独で判断できる | ・修繕 ・不法占拠者に対する建物明渡請求 など |
ただし権利がある一方で、売却には共有者全員の同意が必要であるなど、それぞれの意思だけでは行えないことも多いです。
それぞれ解説します。
使用(共有持分に応じて使用できる)
各共有者は、それぞれの共有持分に応じて共有物全体を使用する権利を持っています。
共有物の使用について、民法は以下のように定めています。
(共有物の使用)
第二百四十九条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
2 共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。
3 共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。
主な使用行為には以下のものがあります。
- 共有者全員で共同使用する
- それぞれの持分の範囲内で自宅や事務所として使用する
- 特定の共有者が単独で使用する
- 第三者と賃貸借契約を結び、家賃を持分に応じて分ける
- 特定の共有者に無償で貸す
共有不動産を共有者の1人が単独で使用することは可能です。
しかし持分の範囲を超えて使用するのであれば、他の共有者に対して対価を支払わなければなりません。特定の共有者が共有不動産を独占していると、他の共有者は共有不動産を使用できず不公平が生じるためです。
使用料の計算方法は以下のとおりです。
例を見てみましょう。
以下のケースでは、次男は長男に対して月2万5,000円の使用料を請求できます。
・持分割合:2分の1ずつ
・長男が1人で共有不動産に居住している
・周辺の家賃相場:月5万円
使用料=5万円×1/2=2万5,000円
このように、周辺の家賃相場をもとに算出します。
ただし、中には使用料を請求できないケースもあります。詳しくは「共有者の一人が不動産を独占している」で解説しているため、チェックしてみてください。
変更(共有者全員の合意が必要)
変更行為は、後述する「管理」の範囲を超えて共有不動産の性質や用途を変更する行為です。たとえば共有不動産の取り壊しや売却などが該当します。
「変更」と一口にいっても、軽微なもの(形状または効用の著しい変更をともなわないもの)とそれ以外に分類されます。
主な変更行為は以下のとおりです。
| 軽微な変更行為 | ・砂利道のアスファルト舗装 ・外壁・屋上の修繕 ・共有地の分筆・合筆 |
|---|---|
| それ以外の変更行為 | ・売却 ・贈与 ・長期賃貸借契約 ・増築・改築 ・大規模な修繕 ・共有不動産全体への抵当権設定 ・解体 ・建て替え ・共有地の造成 |
「長期賃貸借契約」とは、契約期間が以下に該当するものを指します。
- 山林(樹木の栽植・伐採が目的):10年以上
- 1以外の土地:5年以上
- 建物:3年以上
- 動産:6カ月以上
なお、変更行為について、民法は以下のように定めています。
第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。
2 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、当該他の共有者以外の他の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができる。
変更行為は、共有者全員の同意がなければ行えません。
ただし裁判所の許可を得られれば、「共有者がわからない」「共有者の居場所がわからない」といったケースでも、所在不明共有者以外の共有者だけで変更行為が行えます。軽微なものに関しては、共有者全員ではなく「持分の過半数」の同意で行えるとされています。
なお、自分の共有持分だけなら、単独での売却が可能です。他の共有者の同意は必要ありません。
共有名義不動産の建て替え、取り壊しの注意点や流れについては以下の記事で解説しています。あわせてチェックしてみてください。
管理(共有者の持分価格の過半数の合意が必要)
管理行為は、共有不動産の性質を変えない範囲内で利用したり改良したりする行為のことです。
主な管理行為は以下のとおりです。
- 共有物の改装
- 共有地の整地
- 短期賃貸借契約
- 共有物の使用方法決定
- 賃料の減額
- 賃貸借契約の解除・取消し
「短期賃貸借契約」とは、以下の期間を超えないものを指します。
- 山林(樹木の栽植・伐採が目的):10年
- 1以外の土地:5年
- 建物:3年
- 動産:6カ月
なお、管理行為について、民法は以下のように定めています。
(共有物の管理)
第二百五十二条 共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。
2 裁判所は、次の各号に掲げるときは、当該各号に規定する他の共有者以外の共有者の請求により、当該他の共有者以外の共有者の持分の価格に従い、その過半数で共有物の管理に関する事項を決することができる旨の裁判をすることができる。
一 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
二 共有者が他の共有者に対し相当の期間を定めて共有物の管理に関する事項を決することについて賛否を明らかにすべき旨を催告した場合において、当該他の共有者がその期間内に賛否を明らかにしないとき。
3 前二項の規定による決定が、共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
4 共有者は、前三項の規定により、共有物に、次の各号に掲げる賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利(以下この項において「賃借権等」という。)であって、当該各号に定める期間を超えないものを設定することができる。
一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等 十年
二 前号に掲げる賃借権等以外の土地の賃借権等 五年
三 建物の賃借権等 三年
四 動産の賃借権等 六箇月
管理行為を行う際も、他の共有者の同意が必要です。ただし、共有者全員の同意が求められる変更行為とは違い、「共有持分の過半数」の同意があれば行えます。
また、共有者やその居場所がわからないケースでも、裁判所の許可が得られれば所在不明共有者を除く共有者の「共有持分の過半数」で管理行為が行えます。
保存(各共有者が単独で判断できる)
保存行為は、共有不動産の状態を維持するために行う行為のことを指します。
主な保存行為は以下のとおりです。
- 修繕
- 不法占拠者に対する建物明渡請求
- 無権利者の抹消登記請求
- 所有権移転登記の申請(法定相続分どおりに相続する場合)
保存行為はほかの行為とは異なり、各共有者が1人で行えます。他の共有者の同意は不要です。他の共有者にとっても利益になると考えられるためです。
たとえば共有不動産に不法占拠者が住みついている場合に、他の共有者の同意なく独断で建物明渡請求を行っても問題ありません。
なお、保存行為について、民法は以下のように定めています。
5 各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。
共有持分には様々なリスクが伴う
「共有持分が発生するケース」でも解説したとおり、不動産を共有することには「相続税の節税」や「住宅ローンの審査に通りやすくなる」といったメリットがあります。
しかし不動産を共有状態のままにしておくと、以下のような問題が生じやすくなります。
- 単独で建物全体の売却や大規模なリフォームができない
- 相続によって共有者が増える可能性がある
- 過半数の共有持分がないと管理行為(賃貸など)を行えない
- 各共有者が単独で勝手に保存行為を行える
- 共有者が共有持分を売却してしまうと見知らぬ第三者と共有状態になる可能性がある
- 他の共有者から分割請求を受ける可能性がある
それぞれ解説します。
単独で建物全体の売却や大規模なリフォームができない
共有状態のままでは、単独で不動産全体の売却や大規模なリフォームができません。前章でも解説したとおり、共有不動産の変更行為を行うには、原則共有者全員から同意を得なければならないためです。
共有者のうち1人でも反対していたり連絡がつかない状態になっていたりすると、建物の解体や建て替え、増改築などもできません。
また、管理行為にも「共有持分の過半数の同意」が必要であるため、たとえば「短期賃貸借契約を結びたい」と思っても、同意が過半数に満たなければ貸し出せません。
そのため不動産の処分方法について共有者間で意見が合わず、トラブルに発展するおそれがある点に注意が必要です。
なお、所在がわからない・連絡がつかない共有者がいる場合でも、変更行為を行う手段はあります。ただし、裁判所への申立てに手間や時間がかかるうえ、弁護士に手続きを依頼すれば当然費用が発生します。
| 所在等不明共有者 持分取得申立て |
共有者やその所在がわからないときに、裁判所に申立てて所在不明共有者の持分を取得する手続き。取得する持分の時価相当額を供託する必要がある。 |
|---|---|
| 所在等不明共有者 持分譲渡の権限付与の申立て |
共有者やその所在がわからないときに、裁判所に申立てて所在不明共有者の持分を第三者に売却する権限を得る手続き。第三者に共有不動産全体を売却する必要がある。 |
参照:所在等不明共有者持分取得申立てについて|裁判所
参照:所在等不明共有者持分譲渡の権限付与の申立てについて|裁判所
手間や費用をかけずに共有不動産のトラブルから抜け出したいなら、自分の持分だけを専門の買取業者に売却するのがおすすめです。自分の持分だけであれば、他の共有者に相談することなく自分の意思だけで売却できるためです。
共有者の所在がわからないときに不動産を売却する方法については、以下の記事で解説しています。ぜひ参考にしてください。
相続によって共有者が増える可能性がある
相続が発生することによって、共有者が増える可能性があります。共有者の1人が亡くなり相続が発生すると、その配偶者や子ども、孫などが相続人になるためです。
共有者やそれぞれの相続人が多ければ、その分共有者は芋づる式に増えていきます。たとえば今は共有者が2人しかいなくても、それぞれ3人に相続すれば6人、さらに3人ずつ相続すればあっという間に18人です。
このように、共有者が多くなると権利関係が複雑になり、共有者同士でありながら面識がなかったり、「どこの誰が共有者かわからない」という状態に陥ったりする可能性があります。その結果、共有不動産の処分や活用方法について話し合えず、不動産を放置せざるを得なくなることもあるでしょう。
たとえば売却を検討していても、相続を繰り返し共有者が何人いるのかすらわからなくなると、共有者を探し出すだけでも至難の業です。手間や時間がかかるうえ、弁護士や司法書士といった専門家に調査を依頼すると当然費用がかかります。
そのため共有状態は、できるだけ早く解消したほうがよいでしょう。
「相続関係が複雑であるため、いっそ相続放棄をしたい」と考えている人は、以下の記事を参考にしてください。
過半数の共有持分がないと管理行為(賃貸など)を行えない
共有不動産に対して、共有地の整地や短期の賃貸借契約といった管理行為を行うには、共有持分の過半数の同意が必要です。
同意が得られなければ、たとえば家賃収入を得る目的で共有持分を所有していたとしても目的を果たせません。活用したくても同意を得られないせいで活用できず、宝の持ち腐れになってしまう可能性があります。
また、収益を得られなくても、修繕費や維持費、固定資産税・都市計画税などの支払いは発生します。
他の共有者との意見が合わない・合いそうにない場合は、早めに共有関係から抜け出したほうがよいでしょう。
各共有者が単独で勝手に保存行為を行える
各共有者が単独で保存行為を行えることが、トラブルにつながる可能性があります。
単独での保存行為が認められている理由は「保存行為が他の共有者にとっても利益になる」ことであるため、保存行為自体が他の共有者に不利益を与えるわけではありません。
実際、「破損していた屋根や壁を修繕した」「不法占拠者がいたため建物明渡請求をした」といった内容であれば、他の共有者にとって不利益にはならないでしょう。
しかしとくに修繕を必要とする状態ではないにもかかわらず、ただ「見栄えを良くしたい」「古くなったから全体的に修繕したい」というような理由で修繕を行ってしまうと、保存行為ではなく変更行為に該当してしまう可能性があります。
たしかに、「保存行為であれば他の共有者の同意がいらない」ことは間違いではありません。しかし、「保存行為の範囲内におさまるかほかの行為に該当してしまうか」の見極めは難しく、意図せず変更行為や管理行為を行ってしまうケースも考えられます。
保存行為を超える行為をしてしまった場合、他の共有者から損害賠償を請求される可能性もあるため、事前に他の共有者と打ち合わせたり、判断に迷うなら専門家に相談したりしながら慎重に進めていく必要があるでしょう。
共有者が共有持分を売却してしまうと見知らぬ第三者と共有状態になる可能性がある
共有者が共有持分を売却し、見知らぬ第三者が新たな共有者になる場合があります。自分の共有持分は単独で売却できるため、他の共有者が持分を売却する可能性は十分あるでしょう。
これまで親族間で共有していたケースでも、持分の売却によって第三者が関係者になれば、その第三者が勝手に敷地内を出入りしたり不動産を使用したりすることも考えられます。
また、第三者が共有不動産全体を取得する目的で持分を購入したのであれば、他の共有者からも持分を買い取ろうとするでしょう。
反対に、持分を他の共有者に売却して利益を得るのが目的なら、自分が取得した持分を他の共有者に強引に売りつけようとするかもしれません。そのほか、共有不動産に居住している共有者に対し、使用料を請求する可能性もあります。
なお、共有者が共有持分を売却しなくても、第三者と共有状態になることがあります。たとえば他の共有者が借金や税金を滞納し、強制執行を受けたときです。共有持分が競売にかけられ、第三者が購入することで第三者との共有状態が発生します。
共有不動産が危険だと言われる理由についてさらに詳しく知りたい場合は、以下の記事を参考にしてください。
他の共有者から分割請求を受ける可能性がある
不動産を共有状態のままにしておくと、他の共有者から「共有物分割請求」を受ける可能性があります。
不動産の共有状態を解消するための手続きのこと。各共有者がいつでも請求できる。
一般的に、以下の流れで行われる。
1.共有者全員で共有状態の解消方法について話し合う(共有物分割協議)
2.話し合いがまとまらなければ調停を申し立てる(共有物分割調停)
3.協議や調停でも解決しない場合は訴訟を申し立てる(共有物分割請求訴訟)
※調停は必ずしも行う必要はない。また、協議は必須だが、話し合いに応じてもらえない場合は協議を行わず訴訟を申し立てられる。
話し合いで解決しない場合、裁判所に共有物分割請求訴訟を申し立てられるリスクがあります。
協議や調停では話し合いで解決を目指しますが、訴訟は裁判所の判断によって強制的に共有状態を解消する方法です。裁判所は共有者それぞれの希望や持分割合、実際の利用状況などを考慮して分割方法を決定しますが、裁判所の判断が各共有者にとって最善であるとは限りません。
たとえば「不動産を手放したくないのに競売にかけられた」というように、ケースによっては誰も望んでいない結果になる可能性があります。また、競売では売却価格が市場価格よりも低くなる場合があるため、結果的に損をしてしまう可能性があります。
共有物分割請求訴訟の費用や手順を知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
共有持分のトラブル事例
共有持分について、実際にどのようなトラブルが起きているのでしょうか。
ここでは、共有持分のトラブル事例を2つ紹介します。
- 共有者の一人が不動産を独占している
- 管理費や税金を負担しない共有者がいる
共有者の一人が不動産を独占している
共有持分のよくあるトラブル事例の1つに、特定の共有者が共有不動産を独占しているケースがあります。
たとえば、長男・次男が親から実家を2分の1ずつ相続し、親の死を機に帰ってきた長男が自分の家族とともに実家に住んでいるようなケースです。
この場合、次男は長男と同じ権利を持っているにもかかわらず、実家を使用できません。そのため、不動産の不法占拠者を追い出す「建物明渡請求」ができるようにも思えます。しかし、共有者である長男が共有不動産に住むことは正当な権利であるため明渡請求はできません。
また、次男は長男に対して使用料の請求は認められますが、以下のケースに該当する場合は請求できません。
- 占有者と使用貸借契約を結んでいる
- 被相続人の同居人が被相続人の死後も共有不動産に住み続けている
- 被相続人と不動産を共有していた内縁の配偶者が共有不動産に住み続けている
占有者と他の共有者との間で使用貸借契約を交わしているときは、使用料を請求できません。使用貸借契約によって、すでに無償で貸し借りする約束が成立しているためです。
被相続人の同居人が被相続人の死後、そのまま共有不動産に住み続けるときも使用料を請求できません。被相続人と占有者との間に使用貸借契約があったものと判断されるためです。
しかし、この場合は期間限定です。使用料が請求できないのは遺産分割までで、遺産分割後は不動産を相続した人に対して使用料の支払義務が発生します。
そのほか、被相続人と不動産を共有していた内縁の配偶者が共有不動産に住み続ける場合も同様です。遺産分割は可能ですが、被相続人の相続人は内縁の配偶者に対して使用料を請求できません。
自分の死後もその不動産を内縁の配偶者が使用することについて、被相続人が合意していたと考えられるためです。
管理費や税金を負担しない共有者がいる
管理費や税金を負担しない共有者がいるのも、よくあるトラブル事例の1つです。
たとえば修繕費やメンテナンス費の支払いを理由なく拒否されたり、代表者が立て替えた固定資産税や都市計画税を支払ってくれなかったりといったケースです。
共有不動産にかかる管理費や税金は、本来共有者全員がそれぞれの持分に応じて支払うこととされています。また、税金については、共有者が連帯して納付する義務を負うと定められています。
つまり、共有者の中に支払わない人がいる場合、他の共有者は代わりに納付しなければなりません。
(共有物に関する負担)
第二百五十三条 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
2 共有者が一年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。
第十条の二 共有物、共同使用物、共同事業、共同事業により生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。
なお、固定資産税や都市計画税の納付書は、共有者のうち代表者1人に対して市区町村から送付されます。共有者ごとに分けて送付してほしいと願い出ても、ほとんどの場合対応してもらえないでしょう。
そのため代表者が他の共有者の分もいったん立て替え、あとから持分割合に応じた金額を各共有者に請求します。
たとえば固定資産税・都市計画税の納付額が50万円で、各共有者が以下の持分を有している場合のそれぞれの負担額は以下のとおりです。
・B(5分の1):10万円
・C(5分の1):10万円
上記のケースでは、代表者AはB・Cに対して10万円ずつ請求できます。請求しても他の共有者が支払わない場合、代表者は支払わない共有者に対して「求償権」を行使できます。
ほかの人が支払うべきものを立て替えたときに、立て替えた分の返還を求める権利のこと。まずは口頭や書面などで請求し、支払われない場合は「内容証明郵便」による請求、それでも支払われなければ支払督促や訴訟などを通して回収する。支払督促や訴訟をもってしても回収できないときは、強制執行による差し押さえも可能。
求償権の行使方法については、以下の記事で詳しく解説しています。
【関連記事】共有者が固定資産税を払わないときどうする?死亡時などの対処も解説|イエコン
また、共有者が固定資産税を滞納するとどうなるかについては、以下の記事を参考にしてください。
不動産の共有状態を解消する方法
ここまで解説してきたとおり、不動産を共有状態にしておくとあらゆる問題が発生する可能性があります。そのため、できるだけ早期に共有状態を解消することをおすすめします。
共有状態の解消方法は以下のとおりです。
- 共有者全員が合意して共有不動産全体を売却する
- 共有者に共有持分を売却する
- 土地の場合は分筆する
- 共有持分を第三者に売却する
- 共有持分を放棄する
- 共有物分割請求訴訟を起こす
それぞれ解説します。
共有者全員が合意して共有不動産全体を売却する
まずは、共有者全員が合意して共有不動産全体を売却し、売却代金を持分割合に応じて振り分ける「換価分割」と呼ばれる方法です。
例を見てみましょう。
・持分割合:4分の1ずつ
・共有不動産の市場価格:3,600万円
3,600万円×1/4=900万円
上記のケースでは、各共有者が900万円ずつ分け合います。現金を公平に分けられるため、同意さえ得られればトラブルになりにくいでしょう。共有者全員が「共有不動産を売りたい」と考えている場合に適している解消方法といえます。
ただし、共有不動産全体の売却には、共有者全員の同意が必要です。共有者のうち1人でも売却に反対しているときは、自分の持分だけを他の共有者や第三者に売却するなど、ほかの解消方法を検討すべきでしょう。
共有者に共有持分を売却する
他の共有者に自分の持分を売却するのも、共有状態を解消する方法の1つです。たとえば、兄弟3人が3分の1ずつの持分を所有している場合に、長男・次男が自分の持分を三男にすべて売却するようなケースです。
このように、共有者の1人が他の共有者の持分をすべて買い取り、不動産を単独で取得することを「代償分割」といいます。上記のケースでは、三男が不動産の単独所有者になり、不動産を自由に利用できるようになります。
なお、共有者間で意見が食い違い、共有者の1人がすべての持分を取得できなくても、自分の持分さえ誰かに売却すれば共有関係からの脱却が可能です。この場合、不動産の共有状態は続きますが、「とにかく共有関係から抜け出したい」というケースでは有効な手段でしょう。
ただし、買い取ってくれる共有者がいないときや、買い取る側に持分を買い取れるだけの資金がない場合は選択できない手段です。「持分を売却したいが買い取ってくれる共有者がいない」のであれば、第三者への売却を検討するとよいでしょう。
土地の場合は分筆する
共有しているのが土地なら、共有地を「分筆」し、分筆後の土地を各共有者が単独所有することで共有状態を解消できます。
1つの土地を複数の土地に切り分けるための手続き。分筆のあと「所有権移転登記」を申請すれば、複数に分けた土地を各共有者が単独所有できる。
このように、不動産を現物のままで分割する方法を「現物分割」といいます。単独所有者になれば、それぞれ自分の土地を好きなように利用できます。ほかの法律に問題がなければ、建物を建てたり貸駐車場として利用したりもできるでしょう。
ただし、分筆によって土地の価値が下がる可能性がある点には注意が必要です。また、土地の面積が小さくなりすぎてしまうと、単独所有したところで活用できないかもしれません。
土地の分筆は手続きが難しく、土地によっては隣地との境界を決める「境界確定」から行わなければならないケースもあるため、不動産登記の専門家である「土地家屋調査士」に相談することをおすすめします。
共有地を分筆する際の流れや費用については、以下の記事で詳しく解説しています。あわせて確認してみてください。
共有持分を第三者に売却する
自分の共有持分を第三者に売却すると、不動産自体は共有のままですが共有関係から抜け出せます。
共有不動産全体の売却には共有者全員の同意が必要ですが、共有持分なら自分の意思だけで売却が可能です。そのため不動産全体の売却や他の共有者との売買など、他の方法で共有状態を解消できないときは、共有持分の売却を検討してみることをおすすめします。
注意点は、売却先によっては取引を断られたり買取価格が安くなったりすることです。
共有持分の売却先は以下のとおりです。
| 売却先 | 特徴 |
|---|---|
| 専門の買取業者 | ・買い手が見つかるのを待つ必要がない ・早ければ数日で現金化できる ・物分の買取に長けている ・共有持分の扱いに長けている |
| 一般的な不動産会社 | ・そもそも断られる可能性がある ・買い手がつきにくい ・市場価格より安価になりやすい |
第三者に売却するなら、専門の買取業者に買取を依頼することをおすすめします。一般的な不動産会社では共有持分に対応していない場合があり、断られる可能性があるためです。
また、売却できても、自由に活用できない共有持分を購入しようとする一般の個人は少なく、買い手がつかなかったり売却金額が安くなったりすることが考えられます。
買取業者であれば共有持分の扱いに長けており、数日〜1週間程度で売却できます。買取業者が買い手になるため、買い手が見つかるのを待つ必要もありません。
共有持分の評価額の算定方法や買取価格については、以下の記事を参考にしてください。
なお、共有物分をもめずに売却する方法については、以下の記事で解説しています。ぜひ参考にしてください。
共有持分を放棄する
共有持分を放棄すると、不動産は共有状態のままですが共有状態から抜け出せます。
自分の共有持分を放棄し、他の共有者に無償で渡すこと。
共有持分の放棄について、民法は以下のように定めています。
(持分の放棄及び共有者の死亡)
第二百五十五条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
注意点は、持分を放棄する際に行う「持分移転登記」は、他の共有者と共同で申請しなければならない点です。持分の放棄自体は単独でできるため他の共有者の同意は不要ですが、他の共有者の協力がなければできません。
他の共有者が協力してくれない場合、それでも放棄を希望するなら「登記引取請求訴訟」を提起する必要があります。
持分移転登記の手続きや登記引取請求訴訟については、以下の記事を参考にしてください。
【関連記事】持分移転登記とは?費用や自分で手続きする方法、流れを詳しく解説|イエコン
なお、放棄を選択する前に理解しておくべきなのは、共有持分の放棄には「共有関係から抜け出す以外のメリットがない」ことです。
たとえば、持分を放棄ではなく第三者や他の共有者に売却するなら手元に現金が入りますが、放棄をすると一銭にもなりません。また、メリットは少ないにもかかわらず、共有者に協力を要請したり登記手続きを行ったりしなければならないため、手間がかかります。
はじめから放棄を考えるのではなく、まずは売却できないか検討したほうがよいでしょう。
共有持分の譲渡方法や必要な費用については以下の記事で解説しています。あわせて確認してください。
共有物分割請求訴訟を起こす
共有者から同意や協力が得られない場合に共有状態を解消する方法として、「共有物分割請求訴訟」があります。
裁判所に対して、不動産の共有状態を解消してくれるよう求めること。
共有物の分割について、民法は以下のように定めています。
(裁判による共有物の分割)
第二百五十八条 共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
2 裁判所は、次に掲げる方法により、共有物の分割を命ずることができる。
一 共有物の現物を分割する方法
二 共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法
3 前項に規定する方法により共有物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。
4 裁判所は、共有物の分割の裁判において、当事者に対して、金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることができる。
訴訟は、共有者全員の話し合いがまとまらない場合や、他の共有者が話し合いに応じてくれないときなどに提起できます。「まだ話し合っていない」「話し合いの余地がある」というケースなら、まず他の共有者と話し合いましょう。
訴訟は、以下のように進行します。
- 地方裁判所に申し立てる
- 呼出状が各共有者に送付される
- 口頭弁論が行われる
- 裁判所から判決が言い渡される
裁判所は、以下のうち裁判所が適切と考える方法を選択します。
| 換価分割 | 共有不動産を物理的に分けることで共有状態を解消する方法 |
|---|---|
| 代償分割 | 共有不動産を競売にかけ、売却で得た金銭を持分割合のとおりに分配する方法 |
| 現物分割 | 特定の共有者が不動産を取得する代わりに、他の共有者に持分に相当する金銭を支払う方法 |
裁判所の決定には強制力があるため、望まぬ結果になったとしても、共有者全員が従わなければなりません。
結果に納得がいかない場合、判決を受け取ってから2週間以内であれば上級裁判所に対して不服を申し立てる「控訴」が可能です。
しかし、一審の判決より有利な結果になるとは限らないうえ、他の共有者全員を控訴の相手方にしなければなりません。そのため、控訴するかどうかはよく検討する必要があるでしょう。
共有物分割請求訴訟の費用や手順については、以下の記事を参考にしてください。
共有名義の解消法や解消しないことのリスクについては、以下の記事で詳しく解説しています。
共有名義不動産で現在お困りなら、「株式会社クランピーリアルエステート」への相談をおすすめします。
まとめ
共有持分の権利やリスク、解消方法について解説しました。
共有持分とは、各共有者が持つ所有権の割合のことをいいます。たとえば持分が2分の1なら、「その不動産全体に対して2分の1の権利を有している」ということです。
共有持分には「相続税を節税できる」「住宅ローンが組みやすくなる」といったメリットがあります。
しかしその一方で「単独で売却できない」「相続によって共有者が増える」「他の共有者が分割請求を行う可能性がある」といったリスクがあるため、共有状態のままにしておくことはおすすめできません。
共有状態を解消するには、共有不動産全体の売却や共有持分の売却・放棄、共有物分割請求訴訟など、さまざまな方法があります。他の共有者が同意しているなら共有不動産全体の売却、同意や協力を得られないなら共有持分の売却など、状況に合わせて解消方法を選択しましょう。
共有持分に関するよくある質問
共有持分を売却したほうが良いケースとは?
以下のような状態にあるなら、共有持分を売却したほうがよいでしょう。
- 共有不動産全体を売却したいが他の共有者が同意しない
- とにかく共有関係から抜け出したい
- 共有持分のことで子どもや孫に迷惑をかけたくない
- 早く現金化したい事情がある
共有者の共有持分が競売にかけられたのですが、他の共有者にも影響がありますか?
共有者の持分が競売にかけられたからといって、必ずしも影響を受けるとは限りません。ただし落札者が共有物分割請求訴訟を起こした場合、判決によっては不動産全体が競売にかけられ、持分を失う可能性があります。
他の共有者の持分が競売にかけられたときの対処法については、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。