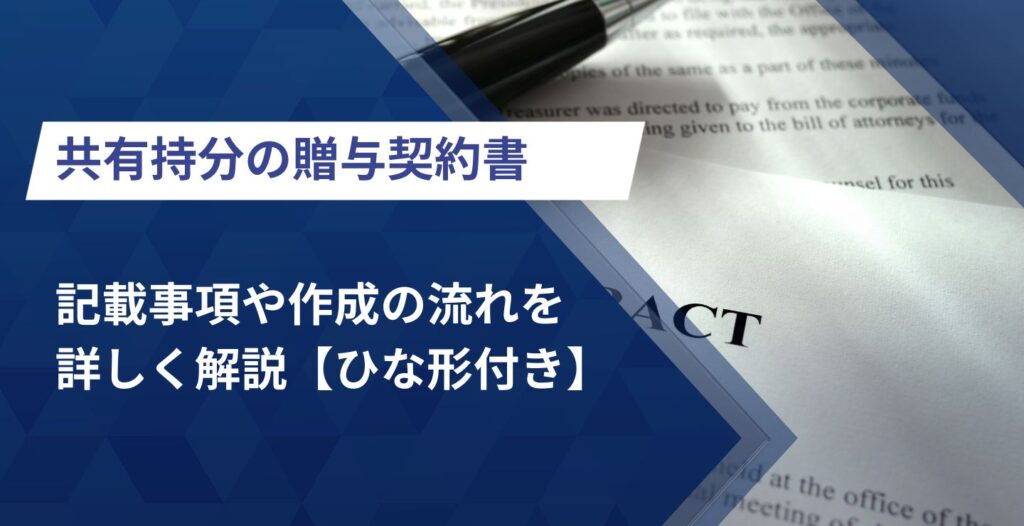共有持分の譲渡方法とは?それぞれの特徴や必要な税金・費用・注意点を解説

共有持分とは、複数人が所有権を有する共有不動産において、どれくらいの割合の所有権を有しているかを表したものです。共有持分割合に応じた不動産の権利を主張できる一方で、共有持分割合を超えた権利は有しないため、活用や処分に制限がかかります。
「共有持分だけだと自由に活用できないし、維持費が負担になるから譲渡を検討している」という人も多いのではないでしょうか。
共有持分は、売却・贈与・放棄・分割の4つの方法で譲渡できます。
- 共有持分を他の共有者や第三者へ売却して現金を得る
- 共有持分を無償で渡す(主に他の共有者への贈与になる)
- 共有持分を放棄して他の共有者全員に分配する
- 分割の手続きによって共有不動産状態そのものを解消する
譲渡方法ごとで発生する税金や費用の違いは次の通りです。
| 共有持分を譲渡する方法 | 発生する税金 | 発生する費用 |
|---|---|---|
| 売買 | 譲渡所得税 | 仲介手数料 登録免許税 印紙税 |
| 贈与 | 贈与税 | 登録免許税 印紙税 |
| 放棄 | 贈与税 | 登録免許税 |
| 分割 | 譲渡所得税(換価分割もしくは代償分割の場合) 贈与税(現物分割の場合) |
登録免許税 印紙税 |
それぞれの譲渡方法は、異なるメリット・デメリット、発生する税金、譲渡された共有者への影響が存在します。
売買で譲渡するメリットは、まとまった現金が手に入ることです。また不動産会社に売買のサポートを依頼すれば、販売活動、契約締結、登記関係なども不動産会社と一緒に進められるのも売買の特徴だと言えます。ただし仲介による売買だと仲介手数料の支払い、不動産会社の直接買取だと業者や共有者とのトラブルのリスクなどのデメリットが考えられます。
贈与は無償で相手へ譲渡する行為で、贈与相手を自分で選びやすいメリットのがメリットです。一方で贈与側は金銭を得られない、受贈側は贈与税や不動産取得税の支払いが発生するというデメリットがあります。
放棄による譲渡なら、共有者の同意を得ずに自分の意志だけで共有持分を手放せるので、とにかく共有持分の所有権をなくしたい人に向いています。放棄された共有持分は他の共有者に帰属しますが、贈与と同じく帰属した共有者に税金がかかる点に注意が必要です。
分割は、状況に応じて「現物分割」「換価分割」「代償分割」のうちいずれかをおこないます。それぞれの方法で、分割後の所有権やメリット・デメリットが異なります。
「どの方法で共有持分を手放せば得になるのか」は、事前にしっかりと確認しておきましょう。また、譲渡前にはトラブルを避けるために、「共有者との話し合い」「住宅ローンの残債の確認」「共有持分割合の確認」などの準備を忘れないようにしてください。
この記事では、共有持分の譲渡方法について詳しく解説するほか、譲渡で発生する税金や費用、注意点を紹介します。譲渡を検討している方は、参考にしてください。
目次
共有持分は譲渡できる!同意や登記の必要性
共有持分が発生しているということは、同じ不動産において自分以外にも所有権を有する共有者が存在していることになります。しかし、自己の共有持分部分だけなら、他の共有者の同意を得ずとも、自分の意思だけで譲渡できます。
以下では共有持分の譲渡方法を理解するうえで欠かせない、共有持分の譲渡について基本的な部分をあらためてまとめました。
自己の共有持分だけなら同意不要!ケース別の同意の必要性について
自己の共有持分だけを譲渡するなら、他の共有者の同意は不要です。共有持分は他の共有者の所有権が及ばない、自分の持ち物として扱われるからです。
(所有権の内容)
第二百六条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
e-Gov法令検索 民法第206条
しかし「自分の共有持分だけ」と表現したように、他の共有者の共有持分が及ぶ範囲の譲渡は、あなたの意思だけでは決定できません。
そして共有不動産全体を譲渡するときは、共有者全員の同意が求められます。譲渡は民法における変更行為(共有物の主要な用途・形状・性質などを変更する行為)に該当するため、民法第251条に適用を受けるからです。
(共有物の変更)
第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。
2 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、当該他の共有者以外の他の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができる。
e-Gov法令検索 民法第251条
本記事で紹介する譲渡方法のいずれも、共有不動産全体を譲渡する場合は共有者全員の同意が不可欠になります。共有不動産の譲渡は、他の共有者の影響を大きく受けると言えるでしょう。
なかには、「他の共有者と連絡が取れない」「共有者が死亡していた」といったトラブルも存在します。こうしたトラブルが発生したときは、民法第251条2項の手続きや相続財産清算人の選任などの法的手続きが必要です。
その他共有持分の同意に関しては、以下の関連記事にて詳細をわかりやすく解説しています。
譲渡する時は持分移転登記をおこなう
自己の共有持分や共有不動産全体を譲渡したときは、譲渡先を名義人とするための登記が必要です。
たとえば自分の共有持分のみを移転するときは、「持分移転登記」をおこないます。持分移転登記とは、移転する共有持分のみの名義人を変更する手続きです。一方で共有不動産のすべてを譲渡し所有権を100%移転するときには、「所有権移転登記」をおこないます。
持分移転登記・所有権移転登記のいずれも義務化はされていないため、登記手続きをしなくても罰則はありません。しかし登記しないと譲渡先の所有権である事実が第三者へ法的に主張できず、後々トラブルに発展する可能性が高いです。
どちらかというと登記しないデメリットは譲渡先が被りますが、トラブルが発生した際に譲渡先からこちら側への責任の追求や関係悪化などのリスクが想定されます。そのため、いずれの譲渡方法を選択したとしても、譲渡したときは譲渡先と一緒に迅速な登記対応をしたほうがよいでしょう。
もし共有不動産を相続で取得した後に相続登記をせず被相続人名義のままだったときは、すぐに相続登記を進めましょう。被相続人の名義のままだと、売却できない、銀行融資における担保設定ができないなどのリスクがあります。そもそも相続登記は2024年4月1日より義務化されているため、必ず対応するようにしてください。
持分移転登記については、以下の記事で詳細を解説しています。
共有持分の譲渡方法は4つ!それぞれのメリット・デメリットを解説
共有持分の譲渡方法は、「売買」「贈与」「放棄」「分割」の4つです。
共有持分は通常の不動産と比較して、一般の不動産市場での取り扱いが難しい背景があります。そのため共有持分の譲渡は、通常の売買や贈与とは異なる点を意識する必要があります。
以下では、共有持分の売買、贈与、放棄、分割という4つの譲渡方法のメリット・デメリットを解説します。
売買での譲渡なら現金化できる
共有持分の売買とは、自分の共有持分を他の人へ売却する譲渡方法です。自分の共有持分を売買して得た売却代金は、他の共有者に分配することなく全額を自分の収入として現金化できます。
とはいえ、共有持分は「共有不動産の一部だけ」という特性上、一般の人からの需要はほとんど見込めません。一般の人が共有持分を取得したところで共有不動産に住んだり転売したりなどは現実的に困難であり、購入するメリットがほとんどないからです。
原則としては一般の人ではなく、「共有持分が帰属している共有不動産の共有者」「不動産会社」「投資家」のいずれかに売却することになるでしょう。
| 共有持分の譲渡先 | 主な買取理由 |
|---|---|
| 他の共有者 | 共有持分割合を増やしたい すべての共有持分を買い取って単独名義にしたい |
| 不動産会社 投資家 |
他の共有持分を買い取って不動産を活用したい 転売によって利益を上げたい |
他の共有者や投資家への売却なら「不動産仲介または個人間取引」、その他は「不動産買取」で売却するのが原則です。
不動産仲介を使った売却は買手の多くが一般の人であるため、投資家とマッチングしない限り共有持分の売却は難しくなるのが実情です。一方で他の共有者への売却なら間に不動産仲介を入れることで、売買価格や契約締結面などさまざまなサポートを受けられます。
不動産買取とは、不動産会社が共有持分を直接買い取ってくれるサービスです。不動産買取は「買い取った不動産をリフォーム・転売・賃貸などをして収益を出すビジネスモデル」であり、共有持分やその他訳あり物件を活用するノウハウを持っています。そのため、不動産買取なら共有持分であっても適正な査定と買取を期待できます。
また共有持分を売買で譲渡する場合、譲渡先によって売却相場が変わる傾向があります。譲渡先ごとの相場の目安は次の通りです。
| 共有持分の譲渡先 | 売却相場 | 計算例 ・共有不動産の価値3,000万 ・共有持分1/3 |
|---|---|---|
| 他の共有者 | 共有不動産の市場価格✕共有持分割合 | 3,000万円✕1/3=1,000万円 |
| 業者などの第三者 | 共有不動産の市場価格✕共有持分割合✕1/2~1/3 | 3,000万円✕1/3✕1/2~1/3=333万~500万 |
他の共有者なら買い取った共有持分の分だけ恩恵を受けられる反面、第三者は共有持分を買い取っただけではそのままだと活用できません。他の共有持分を買い取ろうにも、共有物分割請求をしたり揉めてトラブルになったりなどのリスクが想定されます。そのため共有持分は、単純に市場価格に共有持分割合をかけた金額よりも売却相場が低くなる傾向があります。
売買での譲渡のメリット
共有持分を売買で譲渡するメリットは、契約が締結できれば即座に現金化できる点です。贈与や放棄で譲渡すると金銭が得られず、共有不動産の所有権を手放せる以外に直接的な利益がありません。
また、不動産買取を利用した売却なら譲渡先を探さずに即座に手放せるメリットもあります。以下では、クランピーリアルエステートの共有持分買取実績の一部を紹介します。
- 他の共有者と交流がない共有不動産の共有持分を470万円で買取
- ローン残席のある不動産の共有持分を1,500万円で買取
- 駐車場として利用している土地の共有持分を1億円で買取
共有持分の譲渡方法なら、買取業者を利用した売却がとくにおすすめです。
売買での譲渡のデメリット
売買によって共有持分を譲渡するデメリットは、通常の不動産と比較して売却価格相場が低めになることが挙げられます。
共有持分単体の売却よりも、共有不動産をまとめて売却した後に共有持分割合に応じて収益を分配したほうが多くの現金を得られます。しかし前述の通り、共有不動産全体の売却には共有者全員の同意が必要になるため共有者同士で揉めるリスクも想定しなければなりません。他の共有者への売却も、共有者自身に買取に意思がなければ成立しません。
このように、売買による譲渡は譲渡方法・譲渡先によっては自由度が低くなるデメリットがあります。
また、売買による譲渡は売却益に応じて譲渡所得税や住民税などの税金が発生するのもデメリットです。発生した税金に関する確定申告と納税手続きの労力がかかるうえに、申告や納税に問題があると追徴課税が課せられる可能性があります。
贈与での譲渡なら無償かつ相手を選べる
共有持分の贈与とは、自分の共有持分を他者へ無償で譲り渡す方法です。
売買と同じく、自分の共有持分のみの贈与は、共有者が自由に行えます。贈与を行う場合は、贈与契約書の作成の他、贈与先に名義人を変更する登記手続きが必要です。
家族間で共有持分の贈与を行うことで相続対策として活用でき、生前贈与の特例を利用できる場合があります。
ただし、贈与を受けた側(受贈者)は共有持分に応じた利益を得たと解釈されるため、贈与税が課せられるケースがあります。さらに、売買譲渡した場合でも相場と合わない場合は贈与税の課税対象となるケースがあります。
贈与での譲渡のメリット
共有持分を贈与で譲渡するメリットは、放棄する方法と比較して譲渡先を自分で選びやすい点です。放棄は他の共有者の共有持分割合に応じて帰属すると決まっている反面、贈与なら特定の共有者のみへ自分の共有持分のすべて無償譲渡できます。受贈者が共有者なら、受贈者にとっても共有持分を得られる恩恵が大きくなります。
また、贈与で譲渡ならではのメリットは、生前贈与による相続税対策がしやすい点でしょう。たとえば暦年課税なら毎年110万円の非課税枠が利用できるため、評価額が110万円以下になるように共有持分を少しずつ贈与していけば、相続で共有持分を引き継がせるよりも税金を抑えられます。毎年登記費用がかかるものの、相続税や贈与税よりも支出は安くなります。
共有持分の評価額やその他相続予定の財産の金額によっては、贈与の課税方法を「相続時精算課税制度」にするのも手です。法改正により相続時精算課税制度にも毎年110万円の非課税枠が新設されたので、以前よりも制度が使いやすくなりました。
参考:国税庁「No.4103 相続時精算課税の選択」
参考:国税庁「No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」
贈与での譲渡のデメリット
共有持分を贈与で譲渡するデメリットは、共有持分の評価額によっては受贈者に高額の贈与税や不動産取得税が課せられることです。
たとえば暦年課税による贈与で評価額1,000万円分の共有持分を一度に贈与すると、受贈者には231万円の贈与税の納税義務が発生します(特例贈与の場合は177万円)。もし受贈者が贈与税の存在を知らなかったときは、贈与後に「税金がかかるなんて聞いていない」と、トラブルに発展する可能性があります。
前述したように分割して贈与すれば贈与税対策となるものの、毎年の贈与手続きや登記が必要です。
また、贈与は他の共有者に受け取る意思がなければ成立しません。他の共有者が受贈する気がない、他の共有者との関係が悪いなどの要因があると、そもそも贈与そのものができないという事態になります。売買とは異なり、こちら側に金銭が一切はいらない点もデメリットと言えるでしょう。
参考:国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」
放棄での譲渡なら相手を探さずすぐに手放せる
共有持分の放棄による譲渡とは、民法第255条に基づき、自分の共有持分を手放す手続きです。手放した共有持分は、他の共有者へ無償で帰属します。帰属する割合は、原則として共有者の共有持分割合に応じます。たとえば共有持分割合A20%、B40%、C40%でAが20%の共有持分を放棄すると、BとCに10%ずつの帰属です。
(持分の放棄及び共有者の死亡)
第二百五十五条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
e-Gov法令検索 第255条
以下では、贈与と放棄の主な違いを表にまとめました。
| 放棄 | 贈与 | |
|---|---|---|
| 他の共有者の同意 | 他の共有者への意思表示のみ | 贈与者と受贈者の契約合意が必要 |
| 共有持分移転登記の申請 | 贈与者と受贈者による共同申請 | 他の共有者との共同申請 |
| 共有持分の譲渡先 | 他の共有者の共有持分割合に応じて分配 | 指定した贈与先 |
| 課税される可能性がある税金 | 贈与税 | 贈与税 |
| 売却時の取得費の計算 | 取得時期・取得費は引き継がれない | 取得時期・取得費が引き継がれる |
放棄での譲渡のメリット
共有持分を放棄で譲渡する最大のメリットは、他の共有者の意思や譲渡先に関係なく所有権を手放せることです。「他の共有者に意思表示する」「共有持分の放棄について登記する」の2つをクリアすれば、他の共有者へ共有持分が渡ります。
ただし、放棄の登記には他の共有者との共同申請が必要です。
放棄での譲渡のデメリット
共有持分を放棄で譲渡するデメリットは、放棄にまつわるトラブルに発展する可能性がある点です。
たとえば共有持分の登記申請に他の共有者が非協力的だと、共同申請ができず手続きを進められません。どうしても協力を得られないときは、「登記引取請求訴訟」が必要になる可能性があります。
また放棄によって他の共有者へ共有持分が帰属した場合、帰属した分の共有持分に関する贈与税や不動産取得税が他の共有者へ課せられます。他の共有者からすると急に高額の税金の支払い義務が発生することとなり、大きな反発を招くかもしれません。
放棄後の人間関係悪化や共同申請の非協力などのトラブルを回避するためにも、あらかじめ放棄について他の共有者に相談しておくのがよいでしょう。
さらに、放棄を選んだときは自分が所有する共有持分のすべてを手放します。「共有持分の半分だけ放棄したい」「毎年3回に分けて放棄したい」といった希望は通らないので注意が必要です。
分割での譲渡なら各共有者が平等になる
共有持分を譲渡する方法の1つが、分割によるものです。共有不動産の分割とは、複数で共有している状態を解消し、単独所有にするための方法のことです。原則として、各共有者が平等になるよう均等な分割を目指します。
分割を行う場合、共有者間での話し合いにて内容や方法を決めます。話し合いによって決められない場合や、話し合いそのものができない場合は、共有物分割請求訴訟によって分割方法を決定します。
なお、共有者同士での合意があった場合、5年間は分割請求を行わない契約(共有物分割禁止特約)を締結できます。共有物分割禁止特約が有効の間は、共有不動産の分割はできません。
ただし、この契約を締結しても登記しなければ、他の誰かが共有物分割請求を行った場合に対応できません。
具体的な分割方法は、以下の3つです。
- 現物分割
- 換価分割
- 代償分割
それぞれ詳しく解説します。
現物分割のメリット・デメリット
現物分割とは、共有不動産が土地の場合に、共有持分割合に応じて土地を分筆してそれぞれ単独名義にする方法です。
例えば、OさんとPさんの2人で、140㎡の土地をそれぞれ4/10と3/10の割合で共有していたとします。現物分割では、土地を80㎡と60㎡に分けてOさんが80㎡、Pさんが60㎡を受け取ることになります。
現物分割のメリットは、各共有者が単独名義で土地を持てるため、それぞれで活用や譲渡がしやすくなる点です。ただし、土地の分け方によっては、位置関係や形状に差が生まれることがあるため、慎重に土地を分ける必要があるでしょう。
また現物分割は、原則として建物には適用できないデメリットがあります。建物を面積で分割してそれぞれ所有するのは、現実的に困難であるためです。建物付きの土地を分筆する場合は、どこかの土地に建物の所有権を丸々一緒するのが一般的です。たとえば2つに分けるなら、「建物+土地」と「土地のみ」という分け方になります。
換価分割のメリット・デメリット
換価分割とは、共有不動産のすべてを売却して現金化し、得た現金を共有持分割合に応じて分配する方法です。
共有状態にある不意動をOさんが60%、Pさんが40%の割合で保有している場合、その不動産が4,000万円で売却できたならば、0さんに2,400万円、Pさんに1,600万円が分配されます。
換価分割は不動産を換金してから分配するため、不動産の所有権に関するトラブルに発展しにくいメリットがあります。また不動産の全体を売却するため、通常の不動産と同じく市場価格で売れやすく、得られる収益が高額になりやすいのもメリットです。
ただし分配された金額に応じて、共有者それぞれに譲渡所得税が課せられるデメリットがあります。
代償分割のメリット・デメリット
代償分割とは、ある共有者が他の共有者の共有持分をすべて買い取って単独名義とする見返りに、共有持分に応じた金銭を他の共有者へ支払う方法です。
4,000万円の不動産をOさんが60%、Pさんが40%の割合で保有している状況でOさんを所有者とする代償分割を行った場合、OさんはPさんに対して1,600万円を支払うことになります。
代償分割は、その時点での共有者の誰かの単独名義の不動産になるのが特徴です。一方、持分を売却した共有者には譲渡所得税が発生します。特定の1人が単独名義として不動産を所有したいと希望を持っているときは、代償分割を検討してみましょう。
共有持分の譲渡に必要な税金の種類と計算方法
共有不動産の自分の持分を譲渡する場合、以下のような税金が発生する可能性があります。
| 税金の種類 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 不動産取得税 | 不動産を取得した人が支払う税金 | ・土地もしくは家屋を取得した場合|課税標準×3% ・住宅以外の家屋を取得した場合|課税標準×4% ※令和9年3月31日までは土地の課税標準額は価格の2分の1 |
| 登録免許税 | 登記の際に国に支払う税金 | ・土地の所有権移転登記|課税標準×1.5% ・建物の所有権移転登記|課税標準×2% ・相続登記|課税標準×0.4% ・住所変更登記|1件につき1,000円 ・抵当権抹消登記|1件につき1,000円 |
| 譲渡所得税 | 持分が取得時より高く売れて利益が出た場合に支払う税金 | 譲渡所得×税率 ※譲渡所得とは、収入金額から取得費、譲渡費用、特別控除額を差し引いた金額 |
| 贈与税 | 個人から財産の贈与を受けたときに支払う税金 | 年間の贈与された財産総額によって税率が異なる |
| 印紙税 | 売買契約書に貼付する印紙代金 | 売買価格によって異なる |
それぞれ詳しく解説します。
譲渡所得税|譲渡所得の20.315%か39.63%(不動産の保有期間によって異なる)
譲渡所得税とは、不動産を売ったときに利益が生じた場合に課される所得税・住民税・復興特別所得税のことです。共有持分の売却の場合は、給与所得や譲渡所得とは別に計算する分離課税となります。確定申告時に、給与所得と合算して計算しないように注意しましょう。
たとえば共有持分の売却で譲渡所得(売却益)が1,000万円発生したときは、1,000万円分の譲渡所得税等が売主に発生します。譲渡所得税の計算方法は以下の通りです。
譲渡価額とは不動産の売却金額、取得費とはその不動産の購入金額、譲渡費用は売却にかかった諸費用を指します。
次に、取得費に含まれるのは以下の費用です。
- 土地・建物の購入時に納めた登録免許税や不動産取得税、特別土地保有税、印紙税
- 借主を立ち退かせるための立ち退き料
- 土地の埋め立てや土盛り、地ならしのための造成費用
- 土地の取得に支払った測量費用
- 所有権などの確保のための訴訟費用
- 当初から土地の利用が目的と認められる場合の建物の購入代金や取り壊し費用
- 土地や建物の購入に借り入れや資金の利子のうち、土地・建物を実際に使用する日までの期間の利子
- 土地の購入契約を解除して、他の物件を取得した場合の違約金
譲渡所得税の税率は、不動産の保有期間によって異なり、5年を基準に以下のようになります。
| 所得税 | 復興所得税 | 住民税 | 合計税率 | |
|---|---|---|---|---|
| 短期譲渡所得(所有期間が5年以下) | 30% | 0.63% | 9% | 39.63% |
| 長期譲渡所得(所有期間が5年超) | 15% | 0.315% | 5% | 20.315% |
<譲渡所得税等の計算例>
・共有持分の売却価格2,500万円
・譲渡費用300万円
・取得費200万円
・特別控除なし
・長期譲渡所得
譲渡所得=2,500万円-300万円-200万円=2,000万円
譲渡所得税額等=2,000万円✕20.315%=406万3,000円(譲渡所得税300万円、復興特別所得税6万3,000円、住民税100万円)
参考:国税庁「No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)」
贈与税|10%から55%(課税価格に応じて異なる)
贈与税とは、個人から財産を受けたときに支払う税金です。
贈与や放棄によって共有持分の譲渡が実施された場合、持分を受け取った人に課せられる可能性があります。
また、売買によって財産を取得したときでも、時価よりも明らかに低い金額で譲渡された場合は、財産の時価と対価の差額に贈与税がかかることもあります。
贈与税の計算方法は以下の通りです。
その年の1月1日から12月31日までに贈与を受けた財産総額によって税率が異なり、税率は10%から55%となります。なお、1年間で贈与された財産総額が110万円以下の場合は、非課税となります。
<贈与税の計算例>
・贈与額2,000万円(評価額4,000万円、共有持分割合50%)
・暦年課税
・一般贈与
贈与税額=(2,000万円-110万円)✕50%-250万円=695万円
参考:国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」
不動産取得税|土地と住宅は固定資産税評価額の3%、非住宅用の土地建物は4%
不動産取得税とは、土地や建物を取得した人に課せられる税金です。
具体的には、土地や家屋を購入、贈与、新築、改築などによって取得した場合に、その不動産の所在地の都道府県が課すものです。取得時の1回のみ課税され、固定資産税評価額に税率をかけて計算します。共有持分が建物か土地かで税率が変化するので注意しましょう。
税率は以下の通りです。
| 取得する不動産の種類 | 税率 |
|---|---|
| 宅地 | 4% ※令和9年3月31日までの軽減税率の3% |
| 住宅用の建物 | 4% ※令和9年3月31日までの軽減税率の3% |
| 住宅用以外の土地建物 | 4% |
不動産を取得してから4~6か月程度の間に、都道府県から届く納税通知書を使用して納税します。
<不動産取得税の計算例>
・評価額2,000万円(評価額4,000万円、共有持分割合50%)
・建物
・軽減税率3%
不動産取得税=2,000万円✕3%=60万円
参考:総務省「不動産取得税」
登録免許税|不動産評価額の2%
登録免許税とは、不動産などの登記手続きをおこなう際に支払う税金です。持分の買主である受贈者と、売主である贈与者の両方が納付する義務を負いますが、一般的には受贈者が支払うケースがほとんどです。
不動産評価額(課税標準)に税率をかけて計算します。土地の所有権を移転する場合の税率は以下の通りです。
| 移転の内容 | 税率 |
|---|---|
| 売買 | 2% ※令和8年3月31日までに登記する場合は1.5% |
| 相続、法人の合併、共有物の分割 | 0.4% |
| 贈与、交換、収用、競売など | 2% |
また、建物の登記の税率は以下の通りです。
| 内容 | 税率 |
|---|---|
| 所有権の保存 | 0.4% |
| 売買、競売による所有権の移転 | 2% |
| 相続、法人の合併による所有権の移転 | 0.4% |
| 贈与、交換、収用などによる所有権の移転 | 2% |
<登録免許税の計算例>
・評価額2,000万円(評価額4,000万円、共有持分割合50%)
・売買による所有権移転登記
不動産取得税=2,000万円✕2%=40万円
参考:国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」
印紙税|200円から48万円(契約金額によって異なる)
印紙税とは、不動産の売買契約書や贈与契約の作成に必要な税金です。
収入印紙を購入することで、印紙税を支払います。また、印紙税は誰が支払うか明確に決められていません。
不動産の譲渡に関する書類を作成する際の印紙税額は以下の通りです。
不動産の譲渡に関する契約書、地上権や土地の賃借権の設定、譲渡に関する契約書にかかる印紙税額は次のとおりです。
| 契約書に記載された契約金額 | 税額 |
|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 |
| 10万円以下 | 200円 |
| 10万円を超え50万円以下 | 400円 |
| 50万円を超え100万円以下 | 1,000円 |
| 100万円を超え500万円以下 | 2,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下 | 1万円 |
| 1,000万円を超え5,000万円以下 | 2万円 |
| 5,000万円を超え1億円以下 | 6万円 |
| 1億円を超え5億円以下 | 10万円 |
| 5億円を超え10億円以下 | 20万円 |
| 10億円を超え50億円以下 | 40万円 |
| 50億円を超えるもの | 60万円 |
| 契約金額の記載がないもの | 200円 |
ただし、令和9年3月31日までに作成される不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約金額が10万円を超える場合に関しては、印紙税額が以下のように軽減されます。
| 契約書に記載された契約金額 | 税額 |
|---|---|
| 10万円超50万円以下 | 200円 |
| 50万円超100万円以下 | 500円 |
| 100万円超500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 5,000円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 1万円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 3万円 |
| 1億円超5億円以下 | 6万円 |
| 5億円超10億円以下 | 16万円 |
| 10億円超50億円以下 | 32万円 |
| 50億円超 | 48万円 |
※不動産譲渡に関する契約書に記載された契約金額が10万円以下の場合は軽減税率の対象外(税額200円)、契約金額が1万円未満は非課税
※不動産の譲渡に関する契約書のうち、平成26年4月1日から令和9年3月31日まで作成される場合の軽減税率
たとえば売却価格が2,000万円の場合は、通常だと2万円、軽減だと1万円です。
参考:No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで
参考:No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置|国税庁
共有持分の譲渡に必要な費用
共有持分の譲渡では、税金以外にもさまざまな費用が発生します。具体的には、以下の費用が必要です。
- 司法書士への報酬相場|司法書士事務所により異なる
- 仲介手数料|売買金額の3%〜5%(取引金額によって異なる)+消費税
それぞれ詳しく解説します。
司法書士への報酬相場|司法書士事務所により異なる
共有持分の譲渡では、司法書士への報酬が発生します。
不動産の登記を行う場合、司法書士に対応を依頼するのが一般的であり、その際に報酬を支払う必要があります。
報酬の一般的な相場金額は以下の通りです。
| 登記内容 | 相場金額 |
|---|---|
| 所有権移転登記 | 2万円~10万円 |
| 相続登記 | 2万円~10万円 |
| 住所変更登記 | 1万円~2万円 |
| 抵当権抹消登記 | 1万円~3万円 |
ただし、実際の報酬金額は司法書士事務所によって異なるため、Webサイトをチェックしたり、依頼する前に見積もりを出してもらったりして確認しましょう。
仲介手数料|売買金額の3%〜5%(取引金額によって異なる)+消費税
共有持分の譲渡では、仲介手数料が発生するケースがあります。
不動産における仲介手数料とは、住宅の売買や賃貸借の取引が成立した場合に、業者に対して支払う報酬のことです。不動産の売却を不動産業者に依頼して、一般の個人へ売却できた場合、業者に対して手数料を支払います。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限が定められていますが、一般的には上限に近い金額が請求されると考えておきましょう。
仲介手数料の上限金額は以下の通りです。
| 売買取引金額(税抜金額) | 仲介手数料の上限 |
|---|---|
| 400万円を超える金額に対して | 売買金額×3%+消費税 |
| 200万円を超え400万円以下の金額に対して | 売買金額×4%+消費税 |
| 200万円以下の金額に対して | 売買金額×5%+消費税 |
なお、共有持分の買取専門業者を利用する場合、仲介手数料は発生しません。
共有持分を譲渡する時の注意点
共有持分を譲渡する場合、以下のポイントに注意が必要です。
- 事前に譲渡することを他の共有者に伝えておく
- 共有名義の不動産に住宅ローンの残債がないか確認する
- 持分割合を確認しておく
- 譲渡所得が出た場合は確定申告を実施する
- 譲渡する時は持分移転登記を行う
それぞれ詳しく解説します。
事前に譲渡することを他の共有者に伝えておく
自分の持分を譲渡する場合は、事前に他の共有者に伝えておいた方がよいでしょう。伝えずに勝手に売却した場合、他の共有者が赤の他人と共有関係になるため、トラブルとなる恐れがあるためです。
自分の共有持分の売却に共有者の同意は不要ですが、共同申請が必要な場合は他の共有者の協力が不可欠です。また、譲渡方法が贈与や放棄だと受贈者に税金が発生する事実もあります。
無用なトラブルを避けるためにも、譲渡について伝えたうえで売却や贈与などをするようにしましょう。
共有名義の不動産に住宅ローンの残債がないか確認する
共有持分を譲渡する場合は、住宅ローンの残債の有無を確認しましょう。抵当権が抹消されていない不動産は、売却できないからです。住宅ローンの残債がいくらなのかは、融資を受けた金融機関に問い合わせて確認できます。
ローンを完済している場合は、登記簿謄本で抵当権が抹消されているか確認し、抹消されていない場合は法務局で抵当権抹消登記が必要になるため、司法書士への依頼が必要です。
ローンが残っている場合は、金融機関の承認を得て任意売却を行います。売却金でローンを返済し、不足分は継続して返済します。
残債がある場合は、返済が必要になるため、共有者全員で売却するかどうかを慎重に検討しなければなりません。不動産売却を円滑に進めるために重要なため、必ず確認しましょう。
持分割合を確認しておく
共有持分の譲渡では、持分の割合も確認しておきましょう。共有持分割合を把握しておけば、売却時にスムーズに査定や交渉が進められるためです。持分割合は登記簿謄本に記載されており、法務局で確認できます。
譲渡所得が出た場合は確定申告を実施する
共有持分の譲渡によって譲渡所得が発生した場合、確定申告が必要です。共有者の合意の上で、不動産全体を売却した場合でも、すべての共有者が確定申告をしなければなりません。
確定申告は売却した翌年の2月16日から3月15までにおこないます。共有持分の譲渡所得は、給与所得や事業所得とは異なる様式の確定申告書の準備が必要です。通常の確定申告書に加えて、「申告書第三表(分離課税用)」「譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)」などを作成して申告してください。
確定申告を自分だけで進めるのが難しい場合は、税理士に相談するのがおすすめです。
譲渡の際して契約書が必要なものはしっかりと準備する
共有持分の譲渡方法が売却や贈与の場合、そのやり取りについて契約書に残すなど必要なものはしっかりと準備しましょう。もしやり取りについて書面に残していないと、「売却代金が合意した内容と異なる」「分割について合意した後に拒否される」など、合意内との相違でトラブルに発展する可能性が高くなります。
売買契約なら「売買契約書」、贈与なら「贈与契約書」、分割なら「共有物分割協議書(共有物分割合意書)」を残しておいてください。また、書面に残す前の話し合いは、関係者全員が納得するまで詳細まで決めておくことが大切です。
第三者に譲渡するなら専門の買取業者へ!
共有持分を第三者に売却することを検討しているなら、専門の買取業者を利用するのがおすすめです。
そもそも、共有持分を売却することは難しいものです。共有持分のみを購入しても、その後に活用するためには、他の共有者たちの合意が必要になるためです。ニーズが少ないため、一般の不動産業者ではほとんど買い取ってもらえないでしょう。
専門の買取業者であれば、共有持分であっても高額で買い取ってもらえる可能性があります。
また、共有持分では他の共有者とのトラブルが発生するリスクがありますが、買取業者に売却してしまえば、協議をする必要がなく、訴訟を起こされることもありません。また、無償譲渡や持分放棄の後のトラブルも避けられるでしょう。
専門の買取業者を利用する場合は、実績が豊富な業者を選んでください。また、士業と連携している業者であれば、安心して利用できます。
まとめ
共有持分を譲渡する場合、売買や贈与、放棄、分割、分筆といった方法があります。それぞれの譲渡方法には異なるメリット・デメリットが存在するため、あなたの状況に応じたものを選択することが大切です。選択した方法によっては税金や司法書士への報酬、仲介手数料が発生することも理解しておきましょう。
本記事を参考に、共有持分の譲渡方法について検討してみてください。