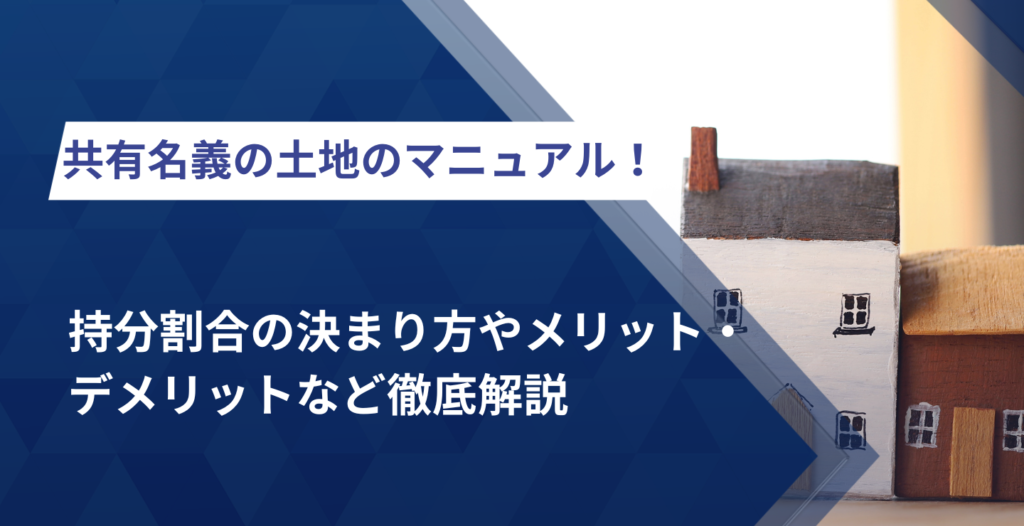相続した土地の売却を徹底解説!売却した場合の代金や税金のシミュレーションも紹介

弊社では、「相続した土地を売却したい」「土地を売却したいが税金が気になる」などのご相談をいただくことがあります。
相続した土地を売却するためには、まず相続登記で土地の名義変更を行い、その後で不動産会社や買取業者に依頼して売却を進める流れが基本となります。相続した土地を売却するまでの具体的な手順は以下のとおりです。
- 遺言書の有無を確認する
- 相続人と相続対象の財産を明確にする
- 遺産分割協議を行う
- 相続登記を行う
- 不動産会社に売却の相談をする
被相続人が遺言書を残していれば、原則としてその内容に従って遺産を分けることになります。遺言書が残されていなければ、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分け方について話し合います。
相続手続きを進めるにあたっては、相続人と相続財産の調査も必要です。被相続人の戸籍をたどって相続人を確定させ、土地以外にどのような財産があるのかもあわせて調査しておきましょう。
ここまでの準備が整ったら、法務局で相続登記の申請をし、被相続人から相続人へ土地の名義を変更します。土地の名義が被相続人のままでは売買契約の締結ができないため、売却前に相続登記を済ませておく必要があります。
相続登記が完了したら、不動産会社で査定をしてもらい、土地の売却手続きを進めます。買主が見つかったら売買契約を締結し、決済と土地の引き渡しをおこなえば売却手続きは完了です。なお、売却で利益が出た場合は、翌年に確定申告をおこない、譲渡所得税を納める必要があります。
このように、相続した土地を売却する際にはいくつかの手順を踏む必要があるため、早めに手続きを進めていくことが大切です。必要に応じて司法書士や税理士などにも相談しながら、効率よく相続と売却を済ませましょう。
目次
相続した土地を売却するためには何をするべき?
相続した土地を売却するために、まずやるべきことを以下の表にまとめました。
| 手続き | 概要 |
|---|---|
| 遺言書の有無を確認 | 被相続人が遺言書を残している場合、原則としてその内容に従って相続手続きを進める |
| 相続人と相続財産の調査 | 戸籍謄本を取得して相続人を確定し、土地や預貯金などの相続財産を調査する |
| 遺産分割協議 | 相続人全員で遺産の分け方を話し合い、合意内容を「遺産分割協議書」にまとめる |
| 相続登記 | 遺産分割協議で決まった内容をもとに、土地の名義を相続人に変更する |
| 不動産会社に査定を依頼 | 複数の不動産会社で査定を受け、依頼する会社を決める |
| 売却手続き | 不動産会社と媒介契約または売買契約を締結する |
相続した土地を売却するためには複数の手続きが必要になるため、事前に全体の流れを把握しておくことが大切です。相続登記や書類の準備に不安がある場合は、司法書士や不動産会社などの専門家に相談することで手続きをスムーズに進められます。
相続した土地を売却するには相続手続きを完了させる必要がある
相続した土地を売却するためには、まず相続手続きを完了させなければなりません。
相続手続きが完了していない状態では、土地の所有者が被相続人のままになっており、法的に売買契約を結ぶことができないためです。
相続手続きを完了させるための手順は、以下が基本となります。
- 遺言書の有無を確認する
- 相続人と相続対象の財産を明確にする
- 遺産分割協議を行う
- 相続登記を行う
遺言書の有無を確認する
相続手続きの最初のステップは、被相続人が遺言書を残しているかどうかを確認することです。
遺言書は、被相続人が生前に「自分の財産を誰にどのように引き継がせるのか」を意思表示するための重要な書類であり、原則としてその内容が最も優先されます。
なお、遺言によって法定相続人以外の人に財産を譲ることも可能となっており、たとえば介護や生前の支援に感謝を示す形で遺贈するケースもあります。
遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。それぞれの違いは以下のとおりです。
| 遺言書の種類 | 概要 | 開封方法 |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 遺言者が全文・日付・署名を自筆で記載する方法 | 家庭裁判所で検認が必要 |
| 公正証書遺言 | 公証役場で公証人が作成する方法 | 家庭裁判所での検認は不要 |
| 秘密証書遺言 | 遺言の内容を秘密にしたまま封印し、公証人のもとで存在のみを証明してもらう方法 | 家庭裁判所で検認が必要 |
もしも遺言書が自宅で見つからなかった場合は、念のため公証役場に問い合わせ、遺言書が残されていないかどうかを確認しましょう。遺言書の有無を確認したら、次のステップに進みます。
相続人と相続対象の財産を明確にする
次に、相続人と相続対象の財産を明確にするため、双方の調査を進めていきます。
まず相続人については、民法で定められた相続の権利を持つ「法定相続人」が誰なのかを明確にします。配偶者は常に法定相続人となり、同時に相続する人は「子ども(直系卑属)」「両親(直系尊属)」「兄弟姉妹」の順で優先されます。
相続人を確定するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、親族関係を正確に確認します。あとから新たな相続人が発覚すると手続きがやり直しになるため、しっかりと調査をおこないましょう。
相続人の確認と並行して、相続の対象となる財産も把握します。土地などの不動産や現金、有価証券、自動車などのプラスの財産のほか、借金や住宅ローン、未払いの税金などマイナスの財産も対象となります。
なお、不動産の有無を確認する際は、固定資産税の納税通知書や登記識別情報通知を探しましょう。見当たらない場合は、市区町村役場で「名寄帳」を請求することで、被相続人がその地域で所有していた不動産を一覧で確認できます。
相続財産の調査が完了したら、すべての財産を一覧でまとめた「財産目録」を作成しておきましょう。
遺産分割協議を行う
遺言書が残されていない場合、相続人全員で遺産分割協議をおこない、「どの財産を」「誰が」「どのように引き継ぐのか」を話し合います。相続人のうち1人でも参加していない状態で行われた協議は無効となるため、全員がそろって話し合うことが大前提です。
遺産分割協議では、現金・預貯金・不動産など、すべての相続財産について分割方法と割合を決定します。土地などの不動産は物理的に分けることが難しいため、以下のいずれかの方法で分割されるのが基本です。
| 分割方法 | 概要 |
|---|---|
| 換価分割 | 土地を売却して得た現金を相続人で分ける方法 |
| 代償分割 | 特定の相続人が土地を取得し、代わりに他の相続人へ代償金を支払う方法 |
| 現物分割 | 土地などの財産をそのままの状態で相続する方法 |
| 共有分割 | 土地を複数の相続人で共有名義にして相続する方法 |
土地は複数人の共有名義で相続することも可能ですが、売却の際に1人でも反対する人がいれば手続きが進められないため、できれば単独名義で相続しましょう。
話し合いの結果まとまった内容は、遺産分割協議書として書面に残し、相続人全員が署名・押印します。
相続登記を行う
相続人が確定し、どの不動産を誰が引き継ぐか決まったら、法務局で相続登記をおこないます。相続登記とは、被相続人の名義から相続人の名義へと不動産の所有権を正式に移す手続きであり、所有権移転登記とも呼ばれます。
相続登記の申請に必要な書類は以下のとおりです。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の除附票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票または戸籍の附票
- 相続人全員の印鑑証明書
- 固定資産税評価証明書
- 不動産の登記事項証明書
- 遺産分割協議書または遺言書
- 登記申請書
- 相続関係説明図
必要書類を揃えたら、窓口・郵送・オンラインのいずれかで相続登記の申請をします。申請をしてから1~2週間程度で相続登記が完了し、法務局から登記完了証が交付されるという流れです。
なお、相続登記は2024年4月1日から義務化されているため、売却をしない場合でも申請する必要があります。相続によって不動産を取得した相続人は、所有権を取得したことを知った日から3年以内、または遺産分割が成立した日から3年以内に登記を申請しなければなりません。
正当な理由なく相続登記を怠った場合は10万円以下の過料を科されるため、必ず期限内に手続きをおこないましょう。
参照:相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)|東京法務局
相続した土地を売却する方法は「仲介」「買取」の2種類
相続した土地を売却する方法は、「仲介」と「買取」の2つがあります。どちらの方法を選ぶかによって、売却までのスピードや売却価格、手続きの負担などが大きく変わります。
| 項目 | 仲介 | 買取 |
|---|---|---|
| メリット | ・市場価格に近い金額で売却できる可能性が高い ・購入希望者が多い場合は高値で売れる場合もある |
・短期間で現金化できる ・内覧や交渉の手間がかからない ・仲介手数料が発生しない ・契約不適合責任が免責される |
| デメリット | ・買主が見つかるまで時間がかかることがある ・内覧対応や条件交渉など、手間が発生しやすい ・成約した際には仲介手数料が発生する |
・買取価格は市場価格より低くなりやすい ・不動産会社によっては買取が不可の場合もある |
仲介
仲介とは、不動産会社に依頼して土地の買主を探してもらう売却方法です。
不動産会社は独自のネットワークや広告媒体を活用し、売主の希望条件に合う買主を見つけるための営業活動をおこないます。市場価格を踏まえた価格設定ができるため、買取よりも高く売却できる傾向にあります。
仲介の主なメリットは、相場に近い価格で売れる点と、売却活動をプロに任せられる点です。買取では不動産会社が利益を前提に価格を決定しますが、仲介では実際に住む個人が買主となることが多く、需要が高いエリアなら相場以上で売れることもあります。
また、不動産会社が売却に必要な書類の準備や買主との交渉、契約のサポートまで一括して対応してくれるため、不動産取引に慣れていない人でも問題ありません。
ただし、仲介は内覧対応や交渉などが必要となるため、買主が見つかるまでに時間がかかる傾向にあります。さらに、売買契約が成立すると仲介手数料が発生する点もデメリットです。
仲介は、売却に時間がかかってもできるだけ高く売りたい人や、市場相場に近い価格での取引を希望する人に向いています。
買取
買取とは、不動産会社に土地を直接買い取ってもらう方法です。
買取業者は、買い取った土地を整地したり不要な建物を解体して再販売できる状態に整えたりしたうえで、他の不動産会社や個人に転売します。再販時の費用や利益を見込むため、買取価格は市場相場よりも低く設定されるのが基本です。
仲介のように一般の買主を探す必要がないため、売却のスピードが非常に早い点が特徴です。双方が査定価格に合意すれば、最短で1週間ほどで売買契約を結び、1か月以内に現金化できる場合もあります。
また、買取業者とは契約不適合責任が免責される契約を結ぶことが多いため、後からトラブルに発展するリスクを抑えられます。
一方で、買取のデメリットは、仲介よりも売却価格が低くなることです。不動産会社は買取後の再販売で利益を得ることを目的としているため、買取価格は市場相場の7〜8割程度が目安となります。また、不動産会社によっては、買取が不可のケースもあります。
買取は、売却価格が安くても素早く現金化したい方や、立地条件の悪い土地を手間なく手放したいという人に向いています。
相続した土地を売却する際に発生する税金の一覧
相続した土地を売却する際に発生する税金は、以下のとおりです。
| 税金 | 課税される場面 | 税率 |
|---|---|---|
| 相続税 | 遺産を相続したとき | 10%~55% |
| 譲渡所得税 | 土地や建物を売却して利益が出たとき | 20.315%または39.63% |
| 登録免許税 | 法務局で登記の申請をするとき | 相続:固定資産税評価額の0.4% 売買:固定資産税評価額の2%(軽減措置の適用で1.5%) |
| 印紙税 | 売買契約書を作成するとき | 本則税率:400円~60万円 軽減税率:200円~48万円 |
相続税
相続税とは、亡くなった人から財産を受け継いだときにかかる税金です。現金や預貯金だけでなく、土地や建物などの不動産も対象となります。
財産の合計額が一定の金額を超えた場合に課税される仕組みであり、すべての人に相続税がかかるわけではありません。相続税がかかるかどうか、かかるとしたらいくらになるのか、具体的な計算手順は以下のとおりです。
- 課税価格を求めて基礎控除を差し引く
- 相続人全員の相続税を計算する
- 各相続人が納付する相続税額を計算する
まずは以下の計算式で、相続財産の「課税価格」を算出しましょう。
まずは遺産総額を計算し、そこから仏壇や墓地などの非課税財産、借金や未払いの税金などマイナスの財産、葬儀費用を差し引きます。
課税価格が算出できたら、「3000万円+600万円×法定相続人の数」で求められる基礎控除を差し引いて課税遺産総額を算出します。基礎控除とは、相続税の計算をする際に用いることのできる非課税枠のことです。
たとえば、遺産総額が5,000万円、法定相続人が2人の場合は以下のように課税遺産総額が計算できます。
課税遺産総額=4,600万円ー(3000万円+600万円×2人)=400万円
上記のケースでは、課税遺産総額は「400万円」となります。このように計算した金額をもとに、それぞれの相続人が受け取る割合に応じて税率をかけ、相続税を計算します。相続税の税率は遺産の取得金額によって異なります。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 1,000万円超から3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超から5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超から1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超から2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超から3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超から6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
参照:相続税の税率|国税庁
たとえば、相続人1人につき200万円の財産を取得する場合、相続税は「200万円×10%=20万円」となります。なお、取得する遺産総額が1,000万円を超える場合、相続税から上記の控除額を差し引くことが可能です。
相続税の申告と納付は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内におこなう必要があります。原則として現金での一括納付が求められるため、相続税がいくらになるのかをあらかじめ計算のうえ、納税資金を用意しておきましょう。
譲渡所得税
譲渡所得税とは、土地を売却して利益が出たときに課される税金のことです。
相続した土地を売った場合も、売却によって得た利益(譲渡所得)があるときは課税の対象になります。内訳は「所得税」「住民税」「復興特別所得税」の3つで、これらをまとめて譲渡所得税と呼びます。
譲渡所得税を計算するためには、まず「譲渡所得」を算出します。譲渡所得の具体的な計算式は以下のとおりです。
取得費とは、土地を購入したときにかかった費用のことで、仲介手数料や登記費用などが含まれます。譲渡費用は、売却のためにかかった費用で、仲介手数料や測量費、契約書の印紙代などがあります。こうした費用を差し引いた残りが利益(譲渡所得)となり、その金額に応じて税金がかかります。
譲渡所得を計算した後は、税率をかけて実際にかかる譲渡所得税を計算します。譲渡所得税では、土地の所有期間が5年以下か、5年を超えるかで税率が変わります。
| 種類 | 所有期間 | 税率 |
|---|---|---|
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 20.315% (所得税15.315%+住民税5%) |
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 39.63% (所得税30.63%+住民税9%) |
相続した土地を売却する場合、被相続人が土地を取得した時点から所有期間を引き継ぐため、長期譲渡所得となるケースが多いです。所有期間が不明な場合は、売買契約書や登記簿謄本で確認してみましょう。
一例として、被相続人が2,000万円で購入し、10年間所有していた土地が6,000万円で売れたケースを想定して譲渡所得税を計算してみます。
譲渡所得税=3,800万円 × 20.315%(税率)=約772万円
上記のケースのように、相続した土地を売って利益が出た場合は、翌年に確定申告をおこない、譲渡所得税を納める必要があります。
申告期間は売却した翌年の2月16日から3月15日までで、住民税はその年の6月以降に反映されます。確定申告を忘れると延滞税や加算税などのペナルティが発生するため、売却完了後は早めに準備をしておきましょう。
登録免許税
登録免許税とは、土地や建物の登記をおこなう際に国へ納める税金です。
登記とは、不動産の権利関係を公的に記録する手続きのことで、登記簿に「誰がその土地を所有しているか」を明確にするためにおこなわれます。具体的には、相続したときや売却したときに登記をおこなう必要があり、登録免許税が発生します。
登録免許税の税率は、登記の理由によって異なります。
| 登記事由 | 税率 |
|---|---|
| 相続 | 固定資産税評価額の0.4% |
| 売買 | 固定資産税評価額の2% (軽減措置の適用で1.5%) |
相続登記の際に課される登録免許税は、土地の固定資産税評価額に対して0.4%がかかります。たとえば、評価額が2,000万円の土地であれば、「2,000万円×0.4%=8万円」の登録免許税がかかります。
また、相続した土地を売却する場合にも、売買による所有権移転登記を行うため、別途登録免許税が発生します。売買登記の税率は2%ですが、令和8年3月31日までに登記をおこなう場合は軽減措置が適用され、1.5%に引き下げられています。
たとえば、同じ2,000万円の土地を売買した場合、税額は通常40万円のところ、軽減措置を利用すれば30万円で済む計算になります。
登録免許税の納付は、現金による一括納付が原則です。金融機関で税額分を納付し、その領収書(登録免許税納付領収書)を登記申請書に添付して法務局へ提出します。
税額は登記の種類と土地の評価額で変わるため、申請をする前に金額を確認し、必要な資金を準備しておくようにしましょう。
印紙税
印紙税は、不動産の売買契約書や領収書など、お金のやり取りに関する文書を作成したときにかかる税金です。
土地を売却する場合は、売主と買主の間で取り交わす売買契約書が課税の対象になります。印紙税の税額は、契約書に書かれている金額に応じて変動します。
| 契約金額 | 本則税額 | 軽減税額 |
|---|---|---|
| 10万円超〜50万円以下 | 400円 | 200円 |
| 50万円超〜100万円以下 | 1,000円 | 500円 |
| 100万円超〜500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円超〜1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
| 1,000万円超〜5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |
| 1億円超〜5億円以下 | 100,000円 | 60,000円 |
| 5億円超〜10億円以下 | 200,000円 | 160,000円 |
| 10億円超〜50億円以下 | 400,000円 | 320,000円 |
| 50億円超 | 600,000円 | 480,000円 |
不動産の売買契約書については軽減措置が設けられており、令和9年3月31日までに作成された売買契約書なら本来の税額よりも安い印紙で済みます。
たとえば、土地の売却価格が3,000万円の場合、本来なら2万円の印紙税がかかりますが、軽減措置が適用されれば1万円となります。
この場合は1万円分の収入印紙を購入し、売買契約書に貼り付けることで印紙税を納付します。収入印紙はコンビニや郵便局、金融機関などで購入が可能です。
相続した土地を5年以内に売却する場合は注意が必要
相続した土地を売却する際は、所有期間によって譲渡所得税の税率が大きく変わります。
前述したとおり、譲渡所得税は土地の売却益に対して課される税金です。土地の所有期間が5年以下であれば「短期譲渡所得」となり、所得税30.63%、住民税9%と、あわせて約40%近い税率が適用されます。
一方で、土地の所有期間が5年を超える「長期譲渡所得」の場合は、所得税15.315%・住民税5%の合計約20%となり、税負担が半分程度に抑えられます。
このように、土地の所有期間が短いほど税金が高くなるため、相続してすぐに売却すると、手元に残る金額が減ってしまう可能性があります。高額な土地を相続した場合ほど税額の差が大きくなるため、売却のタイミングは慎重に検討しましょう。
なお、土地の所有期間は、相続した日から数えるわけではありません。国税庁の公式サイトでは、相続や贈与によって取得した資産の所有期間は、もともとの所有者(被相続人)の取得時期を引き継ぐと定められています。
相続や贈与によって取得したときは、被相続人や贈与者の取得の時期がそのまま取得した相続人や受贈者に引き継がれます。
したがって、被相続人や贈与者が取得した時から、相続や贈与で取得した相続人や受贈者が譲渡した年の1月1日までの所有期間で長期譲渡所得か短期譲渡所得かを判定することになります。
引用元: 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期|国税庁
たとえば、亡くなった親が20年前に購入した土地を相続して2年後に売却した場合、相続人の所有期間は20年前から通算されます。つまり、このケースでは長期譲渡所得として扱われ、低い税率で課税されるということです。
このように、相続した土地を5年以内に売却する場合でも、被相続人の所有期間を含めて計算されるため、必ずしも不利になるわけではありません。
売買契約書や登記簿謄本などで相続した土地の取得時期がいつかを把握し、所有期間を正しく確認したうえで、売却のタイミングを判断することが大切です。
相続した土地を売却で利用できる特例制度の一覧
相続した土地を売却する際には、税率を軽減できる特例制度を利用できる場合があります。主な特例制度は以下のとおりです。
- 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
- 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
- マイホームを売ったときの特例
被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例とは、親などが住んでいた家を相続後に売却する場合に、譲渡所得税を最大3,000万円まで控除できる制度です。
特例の対象となるケースは、被相続人が住んでいた家とその敷地を売却する場合です。ただし、すべての空き家が対象になるわけではなく、いくつかの要件を満たす必要があります。主な要件は以下のとおりです。
- 昭和56年5月31日以前に建てられた家屋であること
- マンションなどの区分所有建物でないこと
- 相続開始の直前に、被相続人以外に住んでいた人がいなかったこと
- 売却代金が1億円以下であること
- 売却先が親族など特別な関係者ではないこと
- 相続後に事業や賃貸などに使っていないこと
- 相続の開始から3年を経過する年の12月31日までに売却が完了していること
建物を取り壊して土地だけを売る場合も特例の対象ですが、解体から売却までの間に他の建物を建てたり貸したりしていないことが条件となります。
上記の要件に当てはまる場合、原則として3,000万円の控除が適用されます。ただし、令和6年1月以降の売却で相続人が3人以上いる場合、控除額は2,000万円までとなります。
【本来の譲渡所得税】
長期譲渡所得:3,000万円×20.315%=約609万円
短期譲渡所得:3,000万円×39.63%=約1188万円
しかし、被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例を利用すれば、譲渡所得から最大3,000万円までを控除できます。
つまり、このケースでは3,000万円の譲渡所得がすべて控除されるため、課税対象額は0円になります。
このように、譲渡所得が3,000万円以下であれば税金が発生せず、3,000万円を超えた部分だけが課税対象となります。条件を満たせば大きな節税効果を得られるため、適用可能かどうかを必ず確認しましょう。
特例を適用するためには、売却した年の翌年に必要書類を添えて所轄の税務署へ確定申告をおこないます。期限内に申告をしないと特例が適用されないため、売却を決めたら早めに準備を進めておくことが大切です。
参照:被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|国税庁
相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
相続財産を譲渡した場合の取得費の特例は、相続時に支払った相続税の一部を「取得費」に加えることができる制度で、譲渡所得税の負担を軽減することができます。
通常、土地を売却したときの譲渡所得は「売却価格-(取得費+譲渡費用)」で計算します。取得費が小さいと譲渡所得が大きくなり、その分だけ税金が高くなります。この特例では、支払った相続税のうち一定の金額を取得費に加算でき、結果的に課税される譲渡所得を減らすことができるという仕組みです。
特例を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 相続または遺贈によって財産を取得していること
- その財産に相続税が課されていること
- 相続開始日の翌日から相続税の申告期限(10か月後)の翌日以後3年以内に、その財産を売却していること
取得費に加算できる相続税額は、次の計算式で求めます。
たとえば相続税として600万円を納め、課税価格が6,000万円、譲渡した土地の相続税評価額が3,000万円だった場合、取得費加算額は「600万円×(3,000万円÷6,000万円)=300万円」となります。つまり、300万円分を取得費に上乗せでき、その分譲渡所得が減るため、最終的な税負担も軽減されます。
相続財産を譲渡した場合の取得費の特例は、相続税申告から一定期間内に相続財産を売却したときに使えるため、納税資金を確保するために売却するケースでとくに有効です。
特例を適用するためには、確定申告時に申請し、相続税の申告書や課税証明書などの必要書類を添えて税務署へ提出します。期限内に申告をしないと適用が受けられないため、売却の時期と申告のスケジュールを確認しながら早めに準備を進めましょう。
マイホームを売ったときの特例
マイホームを売却した場合には、譲渡所得から最大3,000万円まで控除できる「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」が適用できる可能性があります。
こちらの特例を適用するための要件は以下のとおりです。
- 現に自分が住んでいる家、または過去に住んでいた家(住まなくなってから3年以内に売却した場合)であること
- 建物と一緒に売った土地や、建物を取り壊してから1年以内に売却した土地であること
- 災害で滅失した住宅の敷地を、定められた期限内に売却していること
- 売却した年の前年および前々年に、この特例またはマイホームの買換え・譲渡損失の特例を利用していないこと
- 売却した家屋や敷地について、他の特例を適用していないこと
- 親子や夫婦など、特別な関係にある相手に売却していないこと
たとえば、10年前に3,000万円で購入したマイホームを4,500万円で売却し、取得費や諸経費を差し引いた譲渡所得が1,000万円だったとします。特例を適用できれば、譲渡所得を全額控除できるため課税対象は0円になります。
実際に税金がかからないケースも多く、生活の節目でマイホームを売却する際には非常に有利な制度といえます。ただし、投資目的や別荘など趣味・保養用の住宅は「居住用財産」とはみなされないため、こちらの特例は使えません。一時的に住んでいた仮住まいも同様です。
特例を受けるためには、売却した翌年の確定申告で申請する必要があります。必要書類を添えて税務署に提出し、期限内に申告を完了させましょう。
相続した土地を売却した場合のシミュレーション
相続した土地を売却するとき、実際に手元に残る金額は売却価格から各種費用や税金を差し引いた後の金額で決まります。
ここでは、以下の条件をもとに、仲介と買取で手元に残る金額がどれほど変わるのかのシミュレーションをおこないます。
- 土地の相続税評価額:2,000万円
- 土地の市場価格:4,000万円
- 取得費:1,500万円
- 相続税:200万円
- 所有期間:被相続人が取得してから10年以上
- 適用できる特例:相続財産を譲渡した場合の取得費の特例(相続税200万円を取得費に加算)
相続した土地を仲介で売却した場合のシミュレーション
相続した土地を仲介で売却する場合は、市場価格と同じ4,000万円で成約したケースを想定します。譲渡費用は、仲介手数料を含めて200万円だと仮定します。
まずは仲介手数料などの費用、相続税、取得費などを考慮し、どのくらいの譲渡所得が発生するのかを計算してみましょう。
2,100万円 × 税率20.315%=約427万円(譲渡所得税)
ここから税金や諸費用を差し引いて、最終的に手元に残る金額は以下のとおりです。
仲介によって市場価格と同じ価格で成約した場合、税金や仲介手数料などの譲渡費用を差し引いても3,000万円以上の資金が手元に残る計算です。少しでも手元に残るお金を多くしたい場合は、仲介での売却が向いています。
相続した土地を買取で売却した場合のシミュレーション
次に、相続した土地を買取で売却した場合のシミュレーションを見てみましょう。 買取では、仲介のように買い手を探す手間がない代わりに、売却価格が市場価格の7割~8割前後になるのが基本です。
ここでは、市場価格4,000万円の土地を2,800万円で売却したケースを想定します。仲介手数料が発生しないため、譲渡費用は仲介よりも低めの100万円と仮定します。
まずは以下の計算式で譲渡所得税を算出します。
1,000万円×20.315%=約203万円(譲渡所得税)
したがって、最終的に手元に残る金額は以下のとおりです。
買取で売却した場合は仲介よりも約900万円ほど手取りが少なくなりますが、買主を探す手間がなく、最短数週間で現金化できる点が大きなメリットです。スピード感を優先したい場合や、老朽化や立地の悪さなどで需要が低い土地を売りたい場合に、買取が向いています。
相続した土地の売却で実際に起きたトラブル事例
弊社では、相続した土地の売却に関してご相談をいただくことが多くあります。ここでは、実際に弊社へ寄せられたご相談の中から、相続した土地の売却で起きたトラブル事例をピックアップして紹介します。
- 相続人間で意見が対立して売却が進まなかった事例
- 土地を共有名義で相続したことで売却が進まなかった事例
- 遺産分割協議で売却代金の配分をめぐって争いが起きた事例
- 隣地所有者と揉めてしまい売却が進まなかった事例
- 他社の方が査定額が高かったために売主と買取業者でトラブルが起きた事例
相続人間で意見が対立して売却が進まなかった事例
兄弟で相続した土地の売却をめぐり、意見の対立によって長期間話し合いがまとまらなかった事例です。
その結果、固定資産税や維持費の負担が重くなり、土地の管理も行き届かなくなっていた状況でした。当社が第三者として間に入り、双方の意向を整理したうえで共有持分ごとに買取を進め、最終的には全体を一括で引き取りました。
兄弟間の直接交渉を避け、第三者が調整を行ったことで、感情的な対立を深めることなくスムーズに売却を完了できました。
このように、相続人同士で意見が合わない場合は、当事者だけで話し合いを続けるよりも、専門業者や不動産のプロに仲介を依頼することが大切です。中立的な立場から調整してもらうことで、感情的な対立を避けながら円滑な売却につなげられます。
土地を共有名義で相続したことで売却が進まなかった事例
土地を共有名義で相続した結果、1人の共有者が音信不通になり売却が進まなかった事例です。
共有者のうち1人が海外在住で音信不通となっており、手続きが完全に止まってしまっていたのです。
当社では、弁護士と連携して法的手続きを進め、不在者財産管理人を選任することで代理手続きを実施しました。複雑な手続きを経たものの、最終的には土地の売却を無事に完了することができました。
このように、共有名義の不動産は、共有者の1人でも連絡が取れないと売却を進めることができなくなります。音信不通の共有者がいる場合、早めに弁護士や不動産会社などの専門家に相談し、法的な手続きを含めた解決策を検討しましょう。
遺産分割協議で売却代金の配分をめぐって争いが起きた事例
相続した土地の売却代金をどう分けるかをめぐって、意見の対立が起きた事例です。
他の相続人は「介護をしていたから多く受け取りたい」「生前贈与があったから減らすべきだ」など、それぞれの意見を主張しており、話し合いは平行線をたどります。その間にも、固定資産税の負担や管理費が増え続け、土地の維持が難しくなっていました。
当社では、弁護士と連携しながら各相続人の主張を整理し、客観的な資料をもとに公平な配分案を提示しました。最終的には全員が納得のうえで和解が成立し、当社が一括で土地を買取ることで問題を解決しました。
このように、遺産分割協議で感情的な対立が生じると、売却まで長期化する恐れがあります。不動産会社などの専門家を交えて客観的な視点で話し合いを進めることで、トラブルを最小限に抑え、公平でスムーズな解決につなげられます。
隣地所有者と揉めてしまい売却が進まなかった事例
土地の境界をめぐるトラブルによって、売却が一時的に止まってしまった事例です。
当社では、測量士や司法書士と連携し、現地調査をもとに正確な筆界を確認しました。隣地所有者との間で筆界確認書を取り交わし、越境部分を明確化しました。
そのうえで、現在の状態のまま当社が土地を買取する形を提案し、早期に問題を解決しました。
このように、隣地との境界トラブルは、売却を妨げる大きな要因となります。土地の境界線は専門知識がなければ判断が難しいため、専門家に測量を依頼して客観的に状況を整理し、合意形成を図るようにしましょう。
他社の方が査定額が高かったために売主と買取業者でトラブルが起きた事例
他社との査定額の違いが原因で、売主と買取業者の間にトラブルが発生した事例です。
査定内容を確認すると、周辺の取引事例や接道状況などが十分に反映されておらず、相続登記が完了していない点も評価に含まれていない状態でした。そこで当社は、土地の法的リスクや再建築制限、周辺環境などを細かく調査したうえで、根拠に基づいた適正な査定額を提示しました。
査定の内訳を丁寧に説明し、納得いただいたうえで契約が成立しました。最終的に「最初から正確な査定を受けておけば良かった」と安心した様子でした。
査定額の根拠が不明確なまま買取の話し合いを進めてしまうと、誤った判断につながる可能性があります。土地の売却を検討する際は、複数社の査定を比較するだけでなく、評価の根拠をしっかりと確認できる専門業者に依頼することが大切です。
まとめ
相続した土地を売却する際には、相続手続きを完了させなければなりません。
まずは遺言書の有無を確認し、相続人と相続財産を正確に把握しましょう。遺言書がなければ遺産分割協議をおこない、相続登記によって名義を変更します。これらの手続きを終えなければ、土地の売却を進めることはできません。
土地の売却方法には、仲介と買取の2つがあります。仲介は市場価格に近い金額で売れる可能性がある一方、売却までに時間がかかる点がデメリットです。買取は価格がやや下がるものの、現金化までが早く、手間をかけずに売却したい人に向いています。
土地の相続では、相続人同士の意見の相違や登記の遅れなどが原因でトラブルが生じることもあります。スムーズに売却を進めたい場合は、相続登記や不動産売買に詳しい専門業者へ早めに相談しましょう。
よくある質問
相続した土地を売るタイミングはいつがいいですか?
相続した土地を売る最適なタイミングは、相続人の状況によって異なります。
相続税の納税資金を確保したい場合は、相続後すぐにでも売却するのが望ましいです。取得費加算の特例を適用したい場合は、相続税の申告期限(10か月)の翌日以後3年を経過する日までに売却を完了させましょう。なお、維持費や固定資産税などの負担が重い場合は、活用予定がなくても早めの売却を検討することで、金銭的なリスクを軽減できます。
一方で、長期譲渡所得として売却すれば税率が下がるため、所有期間が5年を超えてから売却するのも一つの手段です。
相続した土地に古家が残っている場合はどうすればいいですか?
古家を解体して更地にしてから売却することも可能ですが、解体すると住宅用地の特例が適用されなくなり、固定資産税が最大で6倍に上がることがあります。さらに、解体費用も数十万円から数百万円かかるため、コスト面での負担が大きくなります。
このような場合、建物を残したまま「古家付き土地」として売却する方法もあります。買取業者であれば、建物の状態を踏まえて査定し、解体や処分も含めて一括で対応してもらえるため、手間をかけずに売却を進められます。