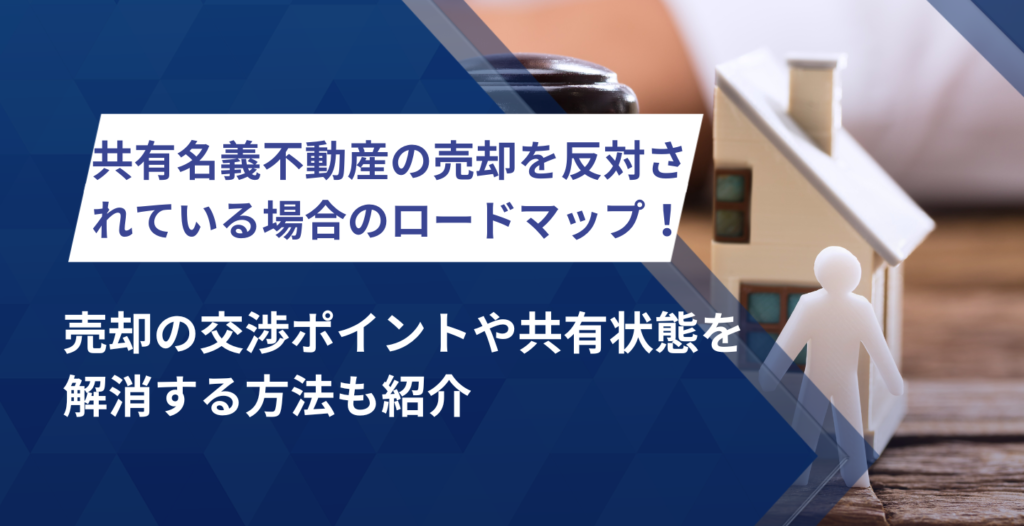共有名義マンション売却の完全解説!トラブルを避けてスムーズに進めるための実務手順を紹介

共有名義のマンションは、複数の共有者で1つのマンションを所有している状態です。売却方法は大きく分けて「不動産全体の売却」と「共有持分のみの売却」の2通りがあります。それぞれにメリット・デメリットがあり、状況に応じた判断が必要です。
| 共有名義マンションの不動産全体の売却 |
メリット|通常物件として売却できるため、買主が見つかりやすく、近隣相場に近い価格で売却できる デメリット|共有者全員の同意を得られなければ、実現できない |
|---|---|
| 共有名義マンションの共有持分の売却 |
【他の共有者への売却】 メリット|売却相場が「市場価格 × 持分割合」と、近隣相場に近い価格で売却できる デメリット|他の共有者に購入の意思や資金がなければ成立しない |
|
【第三者(買取業者)への売却】 メリット|自分の判断だけで手続きを進められ、最短数日〜1週間程度で現金化できる デメリット|売却相場が「市場価格 × 持分割合 × 1/3~1/2」と、他の共有者への売却よりは低くなる |
不動産全体を売却できるのが理想ですが、実務では「共有者が反対して売却が進まない」「条件の折り合いがつかない」といったトラブルが多くみられます。その結果、共有持分のみを売却するケースも珍しくありません。
なお、共有持分は一般の個人が買主になることはほとんどなく、現実的な売却先は「他の共有者」または「第三者(買取業者)」に絞られます。
価格面では他の共有者への売却が有利ですが、「共有者と関係が希薄で、売却交渉が難しい」「手間や時間をかけずに売却したい」といった場合は、買取業者への売却がおすすめです。買取業者への売却であれば、売主と業者の2者間だけで契約が成立するため、短期間での共有持分を現金化できます。
本記事では、共有名義のマンションの売却方法や手順に加え、弊社で対応した共有名義マンションのトラブル事例、売却時にかかる費用・税金などをわかりやすく解説します。
当サイトを運営する「株式会社クランピーリアルエステート」は、共有名義不動産や共有持分を専門に取り扱う不動産買取業者です。
全国の弁護士や司法書士、税理士といった士業と連携しているため、必要に応じて専門家の手を借りながら、共有名義に関する問題解決から買取までをワンストップで対応できます。
「共有者と売却の話し合いが進まない」「自分の持分だけを早く手放したい」という方は、ぜひ弊社の無料相談をご活用ください。
目次
共有名義のマンションを売却するには共有者全員の同意が必要
共有名義のマンションは、複数人で1つのマンションを共有している状態です。兄弟で実家を相続した場合や、夫婦で資金を出し合ってマイホームを購入した場合などによくみられます。
共有名義のマンションを売却する場合には、共有者全員の同意が必要です。これは民法第251条で定められたルールで、共有者のうち1人でも反対すれば、売却手続きを進められません。
たとえば、兄弟で共有している場合は兄と弟の両方が、夫婦で共有している場合は夫と妻の両方が売却に同意する必要があります。共有者の同意を得ずに一方的に売却手続きを進めた場合、取引自体が法的に認められずに売買契約が無効になります。
実務でも、「共有者全員の同意を得る」という部分がネックになり、売却が長期間進まないケースは少なくありません。
共有名義のマンションを売却するためには、まず共有者全員の意向を確認し、売却方針をすり合わせることが重要です。共有者間での協議が整わない場合は、共有名義に詳しい不動産会社や弁護士などの専門家への相談も検討することをおすすめします。
弊社は、全国の弁護士・司法書士・税理士といった士業と連携している不動産買取業者です。必要に応じて弁護士と連携し、共有者の交渉から不動産の買取までワンストップで対応できます。共有名義不動産の売却でお悩みの方は、ぜひ無料相談をご活用ください。
共有持分のみなら自由に売却できる
共有名義のマンションでは、各共有者が「共有持分」と呼ばれる所有権の割合をもっています。共有持分とは、それぞれがどのくらいの割合でマンションを所有しているかを示すものです。
たとえば、兄弟で実家を公平に相続した場合は、兄が1/2、弟が1/2というように共有持分が割り当てられます。
共有持分については各共有者が所有権をもつため、民法第206条に基づき、自由に売却することが可能です。他の共有者全員の同意を得る必要はありません。
つまり、共有者全員の同意が得られずマンション全体を売却できない場合は、自分の共有持分だけを売却するという選択肢もあります。これにより、自分の持分の売却金額を受け取れるうえ、共有関係から抜け出すことが可能です。
弊社でも共有持分のみの買取を行っており、共有名義不動産やトラブルを抱えた複雑なケースにも対応可能です。買取後の活用ノウハウを活かしてコストを抑えられるため、その分査定額にも反映できます。共有持分の売却を検討されている方は、ぜひ無料相談・無料査定をご活用ください。
共有名義のマンションは単独名義よりも売却が難航しやすい
共有名義のマンションの売却は、共有者全員の協議や合意が必要になるため、単独名義のマンションと比較して難航しやすいといえます。
特に以下のような理由から、売却が難航しやすい傾向があります。
- 誰か1人でも反対する人がいると売却が法的に認められないため
- 売却活動中に価格や条件で共有者と揉めてしまうケースも多いため
- マンションの管理組合との手続きがスムーズに進まないケースがある
誰か1人でも反対する人がいると売却が法的に認められないため
冒頭でも触れたとおり、共有名義のマンションは共有者のうち1人でも反対すると、売却が進められません。共有名義不動産の売却は、民法第251条「共有物の変更」に該当し、他の共有者の同意を得なければ、実現できないためです。
(共有物の変更)
第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。
引用元 e-Gov法令検索 民法第251条
法的なルールとして明確に定められているため、実務上もこの点が売却の大きなハードルになります。弊社にも「兄は不動産を残したいが、弟は早く現金化したい」といった共有者間の意見の対立で、売却が進まないという相談が多々寄せられています。
売却活動中に価格や条件で共有者と揉めてしまうケースも多いため
一度は共有者全員が「売却する」という方針で一致しても、具体的な話し合いの段階に入ると意見が食い違い、売却が進まなくなるケースは実務でも多くみられます。特に、売却益の分配や売却時期、価格の設定、費用負担などはトラブルになりやすいポイントです。
以下は、実際に意見が対立しやすい主な項目です。
| 売却益の分配で揉める |
売却益の分配は、持分割合に応じて行うのが一般的です。民法第249条では、各共有者は持分に応じた権利をもつとされており、この考え方は売却益の分配にも反映されると考えられるためです。 ただし、共有者同士の合意があれば、持分割合と異なる分配も可能です。 そのため、税金や維持費などの費用負担、使用状況に差がある場合は、分配の仕方で揉めることがあります。 たとえば「固定資産税や維持管理費を1人で負担してきた共有者が、分配額を多くすることを求める」「いままでマンションに1人で居住していた共有者に対し、他の共有者が分配額を低くすることを求める」といった主張により、売却が難航することがあります。 |
|---|---|
| 売却時期で揉める |
共有名義のマンションに居住している共有者がいる場合、引っ越しや新居探しの準備が必要になるため、売却時期について慎重な調整が求められます。 一方、居住していない共有者は、できるだけ早く売却して現金化したいと考えることが多く、この差が意見の食い違いを生む要因になります。 こうした状況が長引くと、共有者間の関係がぎくしゃくし、感情的な対立に発展して売却が難航するケースも少なくありません。 |
| 売却価格の設定で揉める | 「少し時間がかかってもできるだけ高く売りたい」という共有者と、「多少安くても早く売却したい」という共有者の意見が分かれることで、価格の設定がまとまらず、結果的に売却が難航するケースもあります。 |
| 売却時に発生する諸費用の支払いで揉める |
仲介業者に依頼して売却する場合は、以下のような費用が発生します。 ・仲介手数料 ・印紙税:1,000円~3万円程度 ・抵当権抹消登記費用(抵当権が残っている場合) ・測量費(土地境界が不明な場合) ・解体費用(建物の解体が必要な場合) これらの費用を、誰がどの割合で負担するかについて意見が対立し、売却が進まないケースもみられます。 |
このように、共有名義のマンションは「共有者全員の合意が必要」という法的な前提に加え、売却の段階でもトラブルが起こりやすく、売却が難航しやすいといえます。
マンションの管理組合との手続きがスムーズに進まないケースがある
共有名義に限らず、マンションの場合は管理組合に加入しているのが一般的です。売却する際には、管理組合に対して「所有者ではなくなる」ことを知らせるため、「組合員資格喪失届」や「区分所有者変更届」といった書類を提出する必要があります。
書類の提出や手続きを行わないと、売却後も管理費や修繕積立金の請求が止まらないなど、思わぬトラブルにつながることがあります。
提出書類の内容や手続き方法はマンションごとに異なりますが、共有名義の場合は、組合員資格喪失届や区分所有者変更届などの書類に、共有者全員の署名・押印が必要になるケースもあります。1人でも対応が遅れると、手続き全体が滞ってしまうことがあります。
さらに、管理費や修繕積立金に滞納がある場合は、売却前に清算が必要となるため、支払いが完了するまで手続きが進まず、結果として売却が長引くケースもあります。
共有名義マンションの売却先は「不動産全体」「持分のみ」で変わる
共有名義のマンションの売却には、共有者全員で不動産全体を売却する方法と、自分の共有持分だけを売却する方法の2通りがあります。
どちらのケースでも買主がいれば売却は可能ですが、共有持分に一般の買主がつくことはほぼありません。そのため、売却先の選択肢も以下のように限られます。
- 共有名義マンション全体:住居を探す一般の人にも通常物件として売却可能
- 共有持分のみ:専門の買取業者が主な売却先になる
共有名義マンション全体:住居を探す一般の人にも通常物件として売却可能
共有者全員の合意を得て、共有名義マンション(不動産全体)を売却する場合は、住居を探す一般の買主に対して売却することが可能です。
通常物件と変わらない「単独所有できる不動産」として売り出すため、買主は居住するだけでなく、賃貸として活用したり、将来的に売却したりと自由に不動産を活用できます。そのため、買主が見つかりやすく、市場価格に近い価格での売却が期待できます。
なお、このようなケースでは、不動産仲介業者に依頼して買主を探す「仲介による売却」が一般的です。もちろん、買取業者への売却も可能ですが、不動産全体の売却では幅広い買主にアプローチできるため、仲介を選ぶケースが多くみられます。
共有持分のみ:専門の買取業者が主な売却先になる
共有持分の売却は、各共有者が自分の判断で自由に行うことが可能ですが、実務上、一般の買主が現れるケースはほとんどありません。
その理由は、共有持分が不動産全体ではなく一部の権利にすぎないためです。共有持分を購入しても、買主は不動産全体を自由に活用できません。不動産活用のたびに、他の共有者との協議や合意が必要となるといった制約は、買主にとってマイナス要素でしかないのです。
そのため、現実的な売却先は「他の共有者」「第三者(不動産買取業者)」に限られます。それぞれの特徴は以下のとおりです。
| 他の共有者 |
・売却相場が「市場価格 × 持分割合」と、近隣相場に近い価格で売却できる ・ただし、他の共有者に購入の意思や資金がなければ成立しない |
|---|---|
| 第三者(買取業者) |
・自分の判断だけで手続きを進められ、最短数日〜1週間程度で現金化できる ・売却相場が「市場価格 × 持分割合 × 1/3~1/2」と、他の共有者への売却よりは低くなる |
他の共有者への売却は価格面で有利ですが、交渉や合意が不可欠です。関係性が良く、スムーズに話し合える場合はこちらを優先すると良いでしょう。
一方、共有者との交渉が難しい場合や、できるだけ早く売却したい場合は、買取業者への売却が現実的な選択肢です。価格は下がるものの、業者との手続きだけで売却が完了するため、短期間で共有状態から抜け出せます。
共有持分の売却は、弊社でも対応可能です。実際に「仲介で断られた共有持分を買い取ってほしい」「他の共有者との交渉がうまくいかなかった」というご相談にも数多く対応してきた実績があります。無料相談・無料査定も行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。
共有名義のマンションを売却する流れ
共有名義のマンションを売却する際の流れは、「マンション全体を売却する場合」と「共有持分のみを他の共有者に売却する場合」で異なります。
どちらの方法も不動産仲介業者にサポートをしてもらうのが一般的ですが、依頼のタイミングや交渉の相手が異なるため、あらかじめ全体像を把握しておくことが大切です。
| 共有名義マンション全体を売却する際の流れ | 共有持分を売却する場合の流れ |
|---|---|
|
1. 不動産仲介業者に査定を依頼する 2. 仲介業者と媒介契約を締結する 3. 売却活動・内覧対応をする 4. 売買契約を締結する 5. 決済・所有権移転登記を行う |
1. 共有者に交渉を持ちかける 2. 仲介業者に相談する 3. 価格・条件のすり合わせを行う 4. 売買契約を締結する 5. 決済・所有権移転登記を行う |
共有名義マンション全体を売却する際の流れ
共有名義のマンション全体を売却する際は、共有者全員の合意を得たうえで、通常の不動産売却と同じ手順で進めます。
以下が基本的な流れです。
- 不動産仲介業者に査定を依頼する
- 仲介業者と媒介契約を締結する
- 売却活動・内覧対応をする
- 売買契約を締結する
- 決済・所有権移転登記を行う
なお、買取業者に直接売却することも可能ですが、できるだけ高く売却したい場合は、仲介による売却が選ばれるケースが多くみられます。
1. 不動産仲介業者に査定を依頼する
共有名義のマンションを売却する場合、まずは不動産仲介業者に査定を依頼します。
査定は売却価格の目安を知るためだけでなく、今後の売却戦略を立てるうえでも重要な工程です。複数の仲介業者に査定を依頼し、価格の比較だけでなく、営業担当者の対応力や提案内容もしっかり見極めましょう。
具体的には、以下のようなポイントを確認しておくと安心です。
- 共有名義不動産の取り扱い実績があり、共有者間の調整や書類手続きをスムーズに行えるか
- 近隣エリアの相場や成約事例を踏まえ、現実的な販売価格を提示してくれるか
- 売却スケジュールや進行手順を明確に示し、共有者全員への説明や調整をサポートできるか
- 購入希望者への対応力が高く、交渉力や販売実績があるか
特に「共有名義不動産に慣れている業者かどうか」は、売却スピードやトラブル回避に直結する重要なポイントです。信頼できる仲介業者を見つけることで、売却全体の進行がスムーズになり、価格面でも有利に進められる可能性が高まります。
2. 仲介業者と媒介契約を締結する
査定結果を踏まえ、信頼できる不動産仲介業者を選んだら、媒介契約を締結します。媒介契約とは、仲介業者に正式に売却活動を依頼する契約です。
媒介契約には、以下のように複数の種類があります。
| 契約の種類 | 特徴 | 向いているケース |
|---|---|---|
| 一般媒介契約 | 複数の仲介業者に同時に依頼でき、自分で買主を探すことも可能。業者の販売報告義務はないため、営業活動の積極性に差が出る場合がある。 |
・幅広く買主を探したい場合 ・時間をかけてじっくり売却したい場合 |
| 専任媒介契約 | 1社のみに依頼するが、自分で買主を見つけることもできる。業者には2週間に1回以上の販売状況報告義務があるため、進捗が把握しやすい。 | ・信頼できる業者と二人三脚で売却を進めたい場合 |
| 専属専任媒介契約 | 1社のみに依頼し、自分で買主を探すことはできない。業者には1週間に1回以上の販売状況報告義務があり、より積極的な販売活動が期待できる。 |
・売却を急ぎたい場合 ・仲介業者にすべて任せて進めたい場合 |
一般的には「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」を結ぶケースが多いです。理由は、1社に絞って依頼することで、仲介業者が販売活動に力を入れやすくなるためです。
一方、「一般媒介契約」は複数の業者に依頼できる反面、販売報告義務がなく、営業が消極的になるケースもあるため、あまり選ばれない傾向にあります。
このように媒介契約の種類によって、売却のスピードや営業体制は異なります。契約前に、契約の種類や販売戦略、仲介手数料などをしっかり確認し、納得したうえで進めることが大切です。
また、共有名義のマンションの場合は、共有者全員の署名・押印が必要になるため、事前に全員の同意を取り付けておくと手続きがスムーズに進みます。
3. 売却活動・内覧対応をする
媒介契約を結んだら、仲介業者による売却活動が始まります。販売価格や広告戦略をもとに、不動産ポータルサイトやチラシなどを活用して買主を探します。買主候補が現れた場合は、仲介業者が中心となって内覧を案内し、実際に物件を見てもらう流れになります。
ただし、居住中の共有者がいる場合は、事前に内覧可能な日時を調整しておくことが重要です。スケジュールが合わないと内覧の機会を逃すことになり、売却活動全体に影響する可能性があります。
また、内覧時の第一印象は成約スピードや価格に直結します。事前に室内を整理整頓し、掃除をしておくことで買主に好印象を与えやすくなります。
さらに、一定期間経っても買主が見つからない場合は、販売価格や戦略の見直しを検討することもあります。市場相場と価格がかけ離れていると、問い合わせや内覧数が伸びにくくなります。あらかじめ仲介業者と相談し、価格の見直しタイミングなどの方針を共有者間で決めておくとスムーズです。
4. 売買契約を締結する
買主が見つかり、価格や条件に合意ができたら、売買契約を結びます。売買契約とは、売主と買主の間で「この条件で売る・買う」という約束を正式に交わす手続きです。契約書には売却価格や引き渡し時期、手付金の金額、契約解除の条件などが明記されます。
売買契約における契約書への署名・押印は本来、共有者全員で行う必要があります。ただし、全員の予定を合わせるのが難しい場合は、委任状を作成し、代表者1名が代理で契約を締結することも可能です。
契約締結時には、不動産会社に仲介手数料の半額を支払うのが一般的です。残りの半額は決済・引き渡し時に支払うため、資金の準備も事前に進めておきましょう。
また、契約時には買主から売主へ手付金が支払われます。相場は「売買価格の5〜10%程度」です。手付金には、契約成立の証拠金としての意味に加え、解約時の基準金としての役割もあります。買主が解約する場合は手付金を放棄し、売主が解約する場合は手付金の倍額を返還するのが原則です。
共有名義の場合は、仲介手数料の支払いや手付金の取り扱いについても、共有者全員で事前に取り決めておくことが重要です。
5. 決済・所有権移転登記を行う
売買契約で定めた決済日になると、買主から売却代金が支払われます。支払い方法は「口座振込」が一般的ですが、現金での支払いが行われるケースもあります。
共有名義のマンションの場合、売却代金を共有者それぞれの口座に振り分けたいと希望するケースもあります。その場合は、契約時にあらかじめ買主や仲介業者に伝えておくことが重要です。
代金の着金を確認したら、司法書士が所有権移転登記を行い、正式に物件の名義が買主へと移ります。登記が完了したら買主に鍵を引き渡し、売却手続きは完了です。
なお、売却によって利益が出た場合は、譲渡所得税が課される可能性があります。共有名義のマンション売却に伴い発生する費用や税金については「共有名義マンションの売却にかかる費用・税金」で詳しく解説します。
共有持分を売却する場合の流れ
自分の共有持分を他の共有者に売却したい場合は、以下のような流れで進めます。
- 共有者に交渉を持ちかける
- 仲介業者に相談する
- 価格・条件のすり合わせを行う
- 売買契約を締結する
- 決済・所有権移転登記を行う
共有持分の売却は個人間売買も可能ですが、売却価格の妥当性をめぐるトラブルや、契約書の不備によるリスクが起こりやすいため、おすすめできません。
共有者間の売買であっても、不動産仲介業者に依頼して進めることをおすすめします。価格査定や契約書の作成、所有権移転登記までを一貫してサポートしてもらえるため、安心して取引を進められます。
1. 共有者に交渉を持ちかける
自分の共有持分を売却したい場合は、まず他の共有者に対して売却の意思を伝え、交渉を持ちかけることから始めます。この初期段階では、細かな条件交渉よりも「売却そのものを進められるかどうか」を見極めることが重要です。
交渉の際は、以下のようなポイントを確認しておきましょう。
- 共有者に共有持分を買い取る意思があるか
- 共有者に共有持分を買い取る資金力があるか
- 売却時期や売却価格などを、柔軟に話し合える余地があるか
共有者に買い取る意思や資金力がない場合、共有持分の売却はそもそも実現しません。意思があっても、売却時期や価格などの条件に大きなズレがあると、交渉が長期化したり、最終的に売却できなくなったりするケースもあります。
また、共有者同士の関係性も売却の成否に大きく影響します。関係性が悪いと、話し合いが長引いたり、一度合意した内容が覆ったり、途中で交渉が頓挫したりするケースもあります。こうしたトラブルを避けるためにも、感情的な対立を避け、冷静に話し合うことが重要です。
2. 仲介業者に相談する
共有者との交渉で売却の方向性が定まったら、不動産仲介業者に相談します。共有名義不動産の取引実績がある仲介業者を選ぶと、次のようなサポートが受けられるため、安心して手続きを進められます。
- 共有持分の適正な売却価格の提示
- 売却スケジュールの提案
- 売買契約書の作成
- 売却後の登記手続き・税務面へのアドバイス
また、共有者との条件交渉も、第三者が間に入ることで感情的な対立を避け、スムーズに進めやすくなります。
一方、個人間で売買を進めると、以下のようなトラブルが発生するリスクがあります。
- 期日に入金されなかった、または取り決めた金額と異なる入金があった
- 売買契約書の内容が不十分、または口約束で進めてしまい「言った・言わない」になる
- 登記手続きに不備があり、所有権移転が完了しない
- 税金や登記費用、印紙税などの負担について揉める
- 支払いと引き渡しのタイミングがずれ、トラブルになる
- 親族間などで価格や条件をめぐる感情的なトラブルに発展する
こうしたトラブルを未然に防ぐためにも、専門知識と実務経験をもつ不動産仲介業者に依頼することをおすすめします。
3. 価格・条件のすり合わせを行う
共有者との交渉や仲介業者への相談を経て、実際の売却価格や条件を決めていきます。
共有者間で共有持分を売買する場合の価格は「市場価格 × 持分割合」が目安です。相場とかけ離れた価格で売却すると、税務上「贈与」とみなされ、共有持分を買い取る側の共有者に贈与税(10~55%)が課されるリスクがあります。
たとえば、市場価格2,000万円のマンション持分1/2を500万円で売却した場合、相場との差額500万円が贈与とみなされる可能性があります。この場合、基礎控除110万円を差し引いた390万円に対して贈与税がかかり、共有持分を買い取る側に53万円の税負担が発生するイメージです。
こうしたリスクを避けるためにも、価格設定は非常に重要です。不動産仲介業者にサポートしてもらえば、近隣相場や成約事例を踏まえた現実的な価格を提示してもらえるため、安心して交渉を進められます。
また、価格だけでなく、以下のような条件も合わせて確認しておくと、後のトラブルを防ぎやすくなります。
- 売却時期
- 支払い条件(一括払い、分割払いなど)
- 支払い方法(振込、現金払いなど)
- 入金期日
- 仲介手数料や手付金の扱い
- 契約締結や登記手続きに関する対応方法
- 固定資産税や管理費などの清算
あらかじめ共有者間の認識を揃えておくことで、契約時のトラブルや感情的な対立を防ぎ、売却手続きをスムーズに進められます。
4. 売買契約を締結する
価格や条件のすり合わせが終わったら、不動産仲介業者が売買契約書を作成し、売主と買主の双方が署名・押印して契約を締結します。
契約書には、売却価格、支払い方法、引き渡し時期、契約解除の条件などが明記されます。内容に不明点がある場合は、その場で必ず確認しておきましょう。
共有持分の売買は、売主と買主が親戚同士であるケースも多いですが、「身内だから大丈夫」といった油断は禁物です。後々のトラブルを防ぐためにも、契約内容は口約束ではなく、書面でしっかり残すことが重要です。
契約締結時には、不動産仲介業者に仲介手数料の半額を支払うのが一般的です。残りの半額は決済・引き渡し時に支払います。
また、買主から売主へ手付金を支払うケースもあります。これは契約成立の証拠金や、解約時の担保としての役割をもちますが、共有者間の売買では当事者の合意により省略される場合もあります。
仲介手数料の負担や手付金の有無・金額については、「3. 価格・条件のすり合わせを行う」の段階でしっかり決めておくと、契約当日の手続きがスムーズです。
5. 決済・所有権移転登記を行う
売買契約が成立したら、契約書に定めた決済日に買主から代金を受け取ります。支払い方法は、口座振込または現金が一般的です。
決済と同時に、司法書士が所有権移転登記の手続きを行い、名義が買主へと移ります。登記が完了すれば、売却手続きは終了です。
また、売却で利益が発生した場合は、譲渡所得税の課税対象となります。詳しくは「譲渡所得税・住民税」の項目で解説します。
共有名義のマンションを売却する際にはトラブルが起こりやすいため注意
共有名義のマンション全体を売却するには、共有者全員の同意が必要です。そのため、価格や売却時期などをめぐって意見が食い違い、売却が長期化したり、最悪の場合は頓挫したりするケースも珍しくありません。
共有名義不動産や共有持分の買取を専門に行う弊社にも、「共有者の同意が得られず売却できなかった」という相談が数多く寄せられています。
ここでは、実際に弊社が対応した共有名義マンションの売却で起きたトラブル事例を紹介します。売却を検討している方は、こうしたリスクを把握しておくことで、事前の対策にもつなげられます。
- 相続した兄弟で価格が折り合わず、半年以上売却が進まなかったケース
- 元夫婦の共有名義マンションで内覧拒否のために売却が進まなかった事例
- 持分売却後に新共有者と居住者が対立したケース
弊社「株式会社クランピーリアルエステート」は、共有名義不動産をはじめとする訳あり不動産の問題の解決に力を入れている不動産買取業者です。
共有者同士の意見対立や複雑な権利関係など、一般的な不動産会社では対応が難しい案件にも柔軟に対応可能です。全国の弁護士・司法書士・税理士など、各分野の専門家と連携しているため、法的手続きや税務面の課題を含むケースでも、ワンストップで解決へと導けます。
ご依頼者様の状況や希望に合わせて、最適な買取方法や解決策をご提案いたします。共有名義不動産の売却でお悩みの方は、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
相続した兄弟で価格が折り合わず、半年以上売却が進まなかったケース
相続によって兄弟姉妹がマンションを共有名義で所有するケースは珍しくありません。しかし、いざ売却となると、価格や方針をめぐる意見の食い違いから話し合いが難航し、売却が進まないケースも少なくありません。以下は、実際に売却が半年以上停滞した事例です。
相続をきっかけに兄弟でマンションを共有名義としたものの、売却が長期化した事例です。兄は「できるだけ早く現金化したい」と考えていた一方、弟は「時間をかけてでも高く売りたい」と主張し、売却方針がまとまりませんでした。
販売価格について合意できないまま仲介会社を通じた売却活動を行いましたが、条件が定まらず内覧や交渉が進まず、半年以上にわたり売却が停滞していました。その間、管理費や修繕積立金の負担が続き、一部では滞納も発生するなど、経済的な負担が増していきました。
このように、共有者間で売却方針が一致せず意思決定ができないことに加え、時間の経過とともに費用負担が重くなっていったことから、共有名義のままでは問題が解決しないと感じ、相談に至った事例です。
実際に売却活動に進んでも、価格や売却方針をめぐる意見の対立により、売却が長期化するケースもあります。売却をスムーズに進めるためには、売却開始前に共有者同士でしっかりと方針をすり合わせておくことが重要です。
元夫婦の共有名義マンションで内覧拒否のために売却が進まなかった事例
離婚後、元夫婦が共有名義のままマンションを所有し続けるケースは少なくありません。しかし、どちらか一方が売却に協力しないことで、販売活動そのものが進まなくなることがあります。以下は、共有者の1人が内覧拒否したことにより、売却が停滞した事例です。
元妻がそのまま居住を続けており、元夫が売却を希望しても「知らない人を部屋に入れたくない」と内覧を拒否していました。そのため、仲介会社も鍵を預かることができず、販売活動がまったく進まない状態が続いていました。
時間が経つにつれて、元夫婦間の関係はさらに悪化し、売却条件や今後の方針について話し合うこと自体が難しい状況に。共有名義である以上、どちらか一方の意思だけでは売却を進められず、膠着状態が続いていました。
このように、共有者の一方が居住を理由に売却に協力しないことと離婚後の関係悪化により協議が成り立たなかったことから、共有状態を解消したいと考え、相談に至った事例です。
このように、居住者が内覧を拒否すると、いくら売却活動を始めても実質的に販売が進まないケースがあります。特に離婚後は感情的な対立が生じやすく、第三者が介入しないと問題が長期化することも多いため、早期に対応方針を決めることが重要です。
持分売却後に新共有者と居住者が対立したケース
共有名義不動産では、共有者の1人が持分を第三者に売却することで、新たな共有者が加わるケースがあります。このとき、もともと住んでいる人と新たな共有者との間でトラブルが起こることも少なくありません。以下は、実際に対立が深刻化した事例です。
その後、マンションに居住していた弟に対し、業者側が強引に立ち退きを求めるようになり、関係は急速に悪化しました。日常的な連絡や要求そのものが大きなストレスとなり、安心して生活を続けられない状況に追い込まれていったといいます。
このように、共有者の一部が第三者へ持分を売却したことで、居住の継続や生活環境にまで影響が及ぶトラブルへ発展したことから、「これ以上共有状態を続けるのは難しい」と感じ、相談に至った事例です。
このように、持分を第三者に売却すると、新たな共有者との間でトラブルが生じる可能性があります。
モラルのある業者であれば、残りの共有者との交渉も常識の範囲で進め、円満な解決を目指すケースが多い一方、悪質な業者の場合は強引な立ち退き交渉や圧力的な対応をとるケースもあります。こうした事態を避けるためにも、自分が買取業者に売却する場合は、信頼できる業者を慎重に見極めることが重要です。
共有名義マンションの売却にかかる費用・税金
共有名義のマンションを売却する際には、契約や登記の手続きでいくつかの費用が発生します。費用を理解しておくことで、売却価格から手元に残る金額を正確に把握し、想定外の出費を防ぐことができます。
主な費用・税金は以下のとおりです。
| 印紙税 |
売買契約書に対して課税される 売却金額によって金額が異なる |
|---|---|
| 登録免許税 |
登記申請の際に課税される
抵当権抹消登記:不動産1筆につき1,000円(売主負担が一般的) ※司法書士に依頼する場合は、別途費用が必要 |
| 譲渡所得税・住民税 |
不動産売却で利益が出た際に、売主に課税される 不動産の所有期間が5年超:譲渡所得×20.315% 不動産の所有期間が5年以下:譲渡所得×39.63% |
| 仲介手数料 |
不動産仲介業者に依頼して売却する場合に発生する 仲介手数料=売買価格 × 3% + 6万円 + 消費税 |
なお、買取業者を利用する場合は、売主側の負担が大幅に軽くなり、売買契約書にかかる印紙税のみで済むケースもあります。
まず、抵当権が設定されていなければ、抵当権抹消登記の費用は発生しません。さらに、持分移転登記にかかる費用も、買取業者が負担するのが一般的です。譲渡所得税も、売却で利益が出なければ課税されません。加えて、仲介を介さないため、仲介手数料も不要です。
印紙税
印紙税とは、金銭のやり取りが伴う契約書や領収書などに課される国税で、収入印紙を貼り付けることで納税します。不動産を売却する際には、売買契約書に対して「印紙税」が課されます。
不動産売買契約では契約書を2通作成し、売主と買主がそれぞれ1通ずつ保管するのが一般的です。印紙税は、双方が自分の保有分の契約書に対して負担します。
印紙税は、仲介業者を利用する場合だけでなく、買取業者に直接売却する場合でも発生します。取引形態にかかわらず、売買契約書を作成する限り必要となる費用です
印紙税の金額は、売買価格によって次のように定められています。
| 売買金額 | 軽減税率 | 本則税率 |
|---|---|---|
| 10万円超50万円以下 | 200円 | 400円 |
| 50万円超100万円以下 | 500円 | 1,000円 |
| 100万円超500万円以下 | 1,000円 | 2,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 5,000円 | 1万円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 1万円 | 2万円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 3万円 | 6万円 |
| 1億円超5億円以下 | 6万円 | 10万円 |
| 5億円超10億円以下 | 16万円 | 20万円 |
| 10億円超50億円以下 | 32万円 | 40万円 |
| 50億円超 | 48万円 | 60万円 |
不動産の譲渡に関する契約書で、売買金額が10万円を超える場合は、令和9年(2027年)3月31日まで印紙税の軽減税率が適用されます。
たとえば、共有名義不動産や共有持分の売買価格が2,000万円なら、軽減税率が適用され、1万円の印紙税がかかります。
登録免許税
登録免許税とは、不動産の権利に関する登記申請を行うときに課される国税です。 所有者を変更したり、住宅ローンの抵当権を消したりするときに発生します。現金で納める、もしくは収入印紙での納税も可能です。
登録免許税は、主に以下の2つの登記で発生します。
| 抵当権抹消登記 |
住宅ローンの完済などにより、不動産に設定された抵当権を消す登記です。 税額:不動産1筆(棟)につき1,000円 負担者:売主が負担するのが一般的 |
|---|---|
| 所有権移転登記(持分移転登記) |
不動産の所有権(持分)を移転するための登記です。 土地:固定資産税評価額 × 2%(軽減税率1.5%/令和8年3月31日まで) 建物:固定資産税評価額 × 2%(軽減税率0.3%/令和9年3月31日まで) 負担者:買主が負担するのが一般的 |
抵当権抹消登記は、不動産1筆につき1,000円が課税されます。たとえば、土地1筆・建物1棟の場合、合計で2,000円です。
所有権移転登記に関しては、軽減税率の適用期間であれば、税金を抑えられます。たとえば、2,000万円の土地であれば税額は30万円、3,000万円の住宅であれば9万円となります。
また、登記申請を司法書士に依頼する場合は、税金とは別に以下のような費用が発生します。
- 抵当権抹消登記:1件あたり1万〜2万円程度
- 所有権移転登記:共有者1人分あたり3万〜5万円程度
ただし、所有権移転登記は買主が自分の名義に変更するための登記であるため、買主負担が原則です。マンション全体を第三者に売却する場合や、買取業者に共有持分を売却する場合、売主がこの費用を負担することはほとんどありません。
一方で、マンションの共有持分を他の共有者に売却するケースでは、共有者間の話し合いによって、登記費用を買主と売主で折半するなど、柔軟な対応がとられることもあります。
譲渡所得税
共有名義のマンションを売却して利益(譲渡益)が出た場合は、売主に対して「譲渡所得税」が課されます。課税対象となるのは利益部分だけで、赤字や利益ゼロの場合には課税されません。
譲渡所得税の計算式は以下のとおりです。
課税譲渡所得 = 譲渡所得 × 持分割合 − 特別控除額
譲渡所得 = 売却金額 −(取得費 − 減価償却費)− 譲渡費用
税率は所有期間によって、以下のように変わります。
| 区分 | 所有期間 | 税率(所得税+住民税) |
|---|---|---|
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 20.315%(所得税15.315%+住民税5%) |
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 39.63%(所得税30.63%+住民税9%) |
国税庁|No.3208 長期譲渡所得の税額の計算
国税庁|No.3211 短期譲渡所得の税額の計算
所有期間の判定は「売却した年の1月1日時点」で行われます。たとえば、2020年3月に購入し、2025年7月に売却する場合は、所有期間が「4年9ヵ月」とみなされるため、短期譲渡所得として扱われます。一方、2026年以降に売却すれば長期譲渡所得として扱われ、税率が下がる可能性があります。
また、相続の場合は「被相続人の取得日」を引き継ぐため、相続直後に売却しても、被相続人が10年以上前に購入した物件であれば、長期譲渡所得の税率が適用されます。
なお、譲渡益が出た場合は原則として確定申告が必要です。控除や計算に不安がある場合は、税理士などの専門家に相談すると安心です。
仲介手数料
共有名義のマンションの売却を不動産仲介業者に依頼して進める場合は、仲介手数料が発生します。仲介手数料とは、買主を探したり、契約書を作成したりといった仲介業務に対する報酬です。
法律で上限額が決められており、以下の計算式で算出されます。
たとえば、共有名義のマンション全体を3,000万円で売却した場合、仲介手数料の上限は「 3,000万円 × 3% + 6万円 +消費税= 105.6万円」となります。
なお、買取業者に直接売却する場合は仲介手数料はかかりません。
まとめ
共有名義のマンションを売却するには、共有者全員の同意が必要です。 しかし、実務では共有者間の意見がまとまらず、売却がなかなか進まないケースも多くみられます。
そのような場合は、自分の共有持分だけを売却する方法も検討してみてください。まずは他の共有者への売却を検討することをおすすめしますが、交渉がうまくいかない場合や関係性に不安がある場合は、買取業者への売却という選択肢もあります。
買取業者への売却であれば、売主と業者との2者間で取引が完結するため、短期間で共有持分を現金化することが可能です。
弊社でも共有持分の買取にも対応しており、最短で数日〜1週間程度で現金化が可能です。 万が一、売却後に他の共有者とのトラブルが発生した場合でも、弊社が対応するため、安心して共有持分を手放せます。 共有名義のマンションの売却でお困りの方は、まずはお気軽にご相談ください。
よくある質問
買取業者で共有持分を売却する場合の流れは?
共有持分を買取業者に売却する場合は、仲介による売却よりも手続きがシンプルで、短期間で現金化しやすいのが特徴です。
主な流れは以下のとおりです。
- 査定を依頼する:複数の買取業者に査定を依頼し、売却価格の目安を把握する
- 条件の確認・合意:査定額や支払い時期、登記の進め方などを確認し、合意する
- 売買契約を締結する:買取業者と契約書を交わし、売却価格・支払い方法・決済日などを明記する
- 決済・所有権移転登記:決済日に代金を受け取り、司法書士が登記を実施する
買取業者を決める際は査定額だけでなく、共有持分の買取実績や、利用者の口コミなども確認することが大切です。信頼できる業者であれば売却もスムーズに進み、後悔しにくいでしょう。
共有名義マンションに居住者がいる場合の解決策は?
共有名義のマンションに居住者がいる場合、「すぐに退去できない」「売却に前向きになれない」といった理由から、売却が進まないケースも少なくありません。
こうした場合には、居住者に「リースバック」を提案する方法があります。リースバックとは、自宅を不動産会社や投資家に売却したあと、その買主と賃貸契約を結び、家賃を支払いながら住み続ける仕組みです。
共有名義の場合、居住していない他の共有者は、売却時点で自分の持分に応じた売却益を受け取ることが可能です。居住者はそのまま住み続けられ、他の共有者は現金化できるため、双方にとって折り合いをつけやすい解決策となります。
ただし、所有権は第三者に移るため、居住者は自由にリフォームや転貸をすることが難しくなるなどの制限があります。また、家賃が相場より高くなるケースもあるため、契約内容をしっかり確認したうえで進めることが大切です。
共有名義不動産の売却で「3,000万円の特別控除」は使える?
共有名義不動産の売却でも、一定の条件を満たせば「3,000万円の特別控除」を適用できます。
3,000万円の特別控除とは、自宅(居住用財産)を売却した際に、最大で譲渡所得から3,000万円まで控除できる制度です。この控除が使えると、譲渡所得税の課税額を大きく抑えられます。
共有名義の場合も、各共有者が持分に応じて控除を受けることが可能です。たとえば、2人で50%ずつの共有であれば、それぞれ1,500万円ずつ控除できます。
ただし、以下のような条件を満たす必要があります。
- 売却した不動産が、実際に住んでいた自宅であること
- 住まなくなってから3年目の年末までに売却すること
- 過去にこの特例を利用していないこと
- 譲渡先が親族など特別な関係者でないこと
また、共有者全員が控除を使えるとは限らず、「居住実態があった人」が対象になる点に注意が必要です。たとえば、夫婦共有で実際に住んでいたのが妻だけであれば、妻のみが控除対象となるケースもあります。
さらに、居住していない共有者が持分を売却する場合には、3,000万円の特別控除は原則として使えません。ただし、ケースによっては適用できる可能性もあるため、判断が難しい場合は税理士に相談するのが安心です。
共有名義のマンションを売却したら確定申告は必要?
共有名義のマンションを売却して利益(譲渡益)が出た場合は、原則として確定申告が必要です。共有名義か単独名義かに関係なく、利益が出れば譲渡所得税の課税対象となります。
共有名義の場合は、各共有者が自分の持分に応じてそれぞれ申告を行います。たとえば、兄弟で1/2ずつの持分を所有している場合、それぞれが1,500万円分の譲渡所得を申告するイメージです。
なお、居住者が利用できる3,000万円の特別控除や、損失の繰越控除を活用することで、譲渡所得税が発生しないケースもあります。