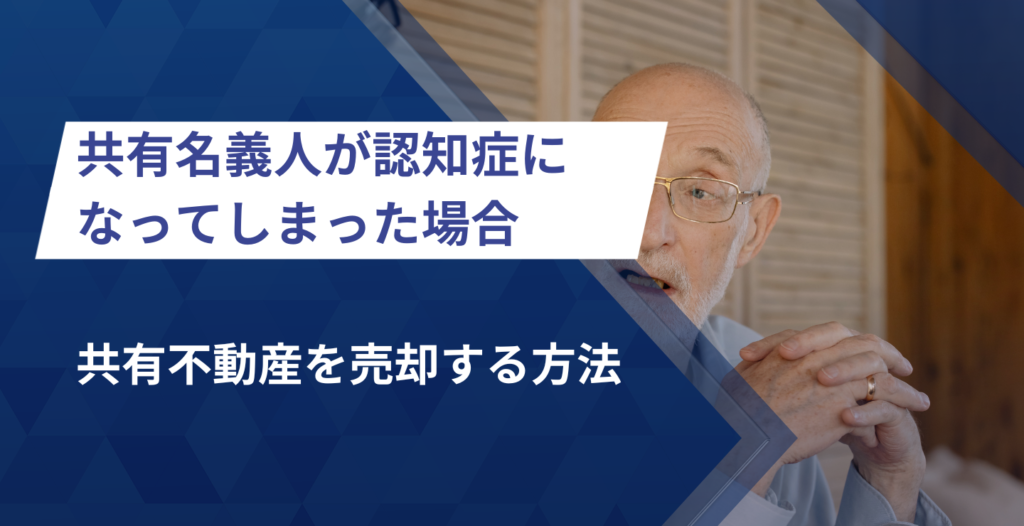共有持分のリスクは?トラブル実例をもとに回避方法を解説

共有名義の不動産は、たとえ自分の持分があっても、勝手に利用・処分することができません。
また、売却や建て替えなどの重要な決定は、原則として他の共有者からの合意が必要になるため、共有不動産を所有しているものの、「他の共有者と意見が合わない」「勝手に売却できず困っている」といった悩みを抱えている方からご相談を受けることもあります。
とはいえ、不動産を活用できないまま共有状態を続けることには、下記のようなさまざまなリスクがあります。
- 不動産全体を売りたいときに他の共有者と揉める
- 不動産を活用・改良したいときに他の共有者と揉める
- 相続などで権利関係が複雑になる
- 突然見知らぬ人と共有関係になる
- 共有物分割請求訴訟を起こされる
- 税金や維持管理費の負担で揉める
- 共有持分だけでは一般の人に売れることがほぼない
そのため、トラブルを回避するためにも、売却などで共有関係を解消するのが最善策といえます。とはいえ、共有持分は、活用しづらく制約も多いことから売却が難しく、不動産全体を売却するにも共有者全員の同意が必要など、一筋縄ではいかないのが現実です。
共有持分の売却は、一般的な不動産ではなく専門の買取業者に依頼しましょう。専門の買取業者であれば、トラブルを抱えた共有持分でも適正な価格でスピーディーな買取相談の対応が可能です。自分の持分を売却する分には他の共有者の同意も必要ありません。
本記事では、共有持分を所有するリスクと起こりうるトラブルおよび、対処方法を丁寧に説明します。安心して相談できる専門の買取業者を選ぶポイントもまとめているので、早めの対処とトラブル回避に役立ててください。
目次
共有持分のリスクとは?
「共有持分」とは、1つの不動産を複数人で所有する「共有名義不動産」において、各々が所有している割合のことです。単独所有の不動産とは異なり、共有名義の不動産では、利用や管理に関する意思決定の際に、他の共有者の同意を得なければなりません。
その際、共有者が複数いると意見の不一致が発生しやすいことから、下記のように多くのリスクを抱えています。
- 不動産全体を売りたいときに他の共有者と揉める
- 不動産を活用・改良したいときに他の共有者と揉める
- 相続などで権利関係が複雑になる
- 突然見知らぬ人と共有関係になる
- 共有物分割請求訴訟を起こされる
- 税金や維持管理費の負担で揉める
- 共有持分だけでは一般の人に売れることがほぼない
共有者同士の関係が良好な場合でも、利害関係でトラブルに発展することがあります。具体的なリスクについて民法の規定も交えながら説明するので、共有持分を相続予定の方、共同で不動産を購入予定の方も自身に当てはめてイメージしてみてください。
不動産全体を売りたいときに他の共有者と揉める
自分の持分を含む共有不動産を丸ごと売却するには、民法251条で定められている通り、共有者全員の同意が必要です。1人でも反対する人がいると不動産全体での売却ができないため、意見がまとまらず揉めるリスクがあります。
(共有物の変更)
第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。
引用元: 民法第二百五十一条|e-Gov法令検索
民法における「変更」とは、以下のような行為を指します。
- 他の共有者の持分を含む不動産の売却および、質権の設定
- 田畑の宅地化といった用途変更や、建物の大規模修繕
- 土地の分筆・合筆、建物の増改築、不動産を長期賃貸借にする など
反対者が多いほど、不動産全体の売却はハードルが高くなります。自分の持分だけなら自由に売却できますが、共有持分は資産価値が低く売却しづらいのが現実です。
実際に弊社にも、「不動産を残したい」という共有者と、「活用が難しいため売却したい」という共有者の間で意見が割れ、協議が難航しているケースのご相談が多く寄せられています。ときには感情的な対立に発展してしまい、不動産の活用どころか一切の話し合いすら進まないということも珍しくありません。
とはいえ同意が得られないからと妥協して所有し続ければ、固定資産税や維持管理費だけがかかり続けるうえ、後述する別のトラブルに巻き込まれるリスクもあります。
そのため、早い段階で共有関係の解消を視野に入れた対策を講じることが重要です。
不動産を活用・改良したいときに他の共有者と揉める
共有不動産の形状や効用を、著しく変更しない範囲で活用・改良することを「管理行為」といいます。管理行為を実行するには、同意した共有者の持分割合が「合計の過半数」にあたる必要があります。
(共有物の管理)
共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。
引用元: 民法第二百五十二条|e-Gov法令検索
民法における「管理行為」とは、以下のような行為を指します。
- 共有不動産の管理者を選任・解任する
- 共有不動産の使用方法を決定・変更する
- 共有不動産に軽微な(形状や効用の著しい変更を伴わない)変更を加える
- 共有不動産に短期賃貸借契約を設定(締結)する
- 短期賃貸借契約における賃料を減額する など
具体例を出すと、共有名義の不動産を賃貸に出したり、リノベーションをしたりする行為は管理に該当するため、持分割合で過半数を超える合意が必要になります。
持分割合で過半数を満たしていなければ、たとえ共有者の人数が多くても管理行為は実行できません。たとえば、1つの不動産を3人で3分の1ずつ分け合っている場合、過半数は【3分の2】なので2人から同意を得る必要があります。
共有者が多いほど異なる考え方や価値観が集まるため、たとえ軽微な活用・改良でも同意が得られず揉めるリスクが高くなります。
たとえば、賃貸物件として活用するために最低限のリフォームを提案しても、過半数の合意が得られなければ工事が進められず、収益化のチャンスを逃すことがあります。
また、過半数の合意を得ていたとしても、反対している共有者が納得していなければ「無断で進められた」と不満を募らせ、関係性が悪化することも少なくありません。
実際に弊社にも、「過半数の同意を得てリノベーションを行ったが、反対していた共有者との関係がこじれてしまい、その後の管理が困難になった」という相談が寄せられています。
管理方針を巡る意見の対立が長期化すると、訴訟に発展するケースもあります。
相続などで権利関係が複雑になる
共有不動産は、所有期間が長くなるほど権利関係が複雑化しやすくなります。これは、年数が経つほどに共有者の誰かが死亡したり生前贈与したりすることで、相続人や譲受人が増加し、所有者の全体像を把握しづらくなるためです。
たとえば、親の代から共有していた不動産を子や孫など複数人で相続した結果、誰がどれだけの持分を持っているのかすら把握できないというケースも珍しくありません。その結果、以下のようなトラブルが発生するケースもあるのです。
- 管理行為や売却に必要な同意を得ようにも、連絡先が不明な相続人がいる
- 身に覚えのない人から突然、管理や売却への同意を求められる
- 遺産分割協議がまとまらず、裁判に発展する
- 管理費や固定資産税の支払いを巡って責任の所在が曖昧になる
だからといって放置してしまうと、問題を抱えたままの不動産に対し税金などの維持管理費を払い続けることになるうえに、さらなる相続が発生して問題が深刻化するリスクもあります。
突然見知らぬ人と共有関係になる
自分の持分のみであれば、他の共有者の同意を得ずに売却できます。自分が売却する際はメリットですが、他の共有者が知らぬ間に持分を売却し、ある日突然赤の他人と共有関係になることもあり得ます。
このとき想定されるリスクとして以下のようなことが挙げられます。
- 購入者(新たな共有者)が、共有している土地などの敷地内に無断で入ってくる
- 購入者が、強引かつ不当に安い金額で持分を売却するように迫ってくる
- 購入者から共有者に対して、相場よりも高い価格で持分買取を強引に迫ってくる
- 購入者が、脅迫のような形で「変更」「管理行為」への同意を求めてくる
- 購入者が、法に触れないギリギリの手段で強引に立ち退かせようとしてくる
- あなたが共有状態にある物件に住んでいる場合、購入者が賃料の支払いを要求してくる など
購入者が悪質だった場合、トラブルが発生するリスクは高いです。また他の共有者の持分が競売にかけられた場合も同様に、第三者との共有状態となります。
競売とは、裁判所を通じて強制的に不動産を売却する手続きのことで、主に債権回収などを目的に行われます。たとえば、他の共有者が借金の返済に行き詰まった場合、その持分が債権者によって差し押さえられ、裁判所によって競売にかけられることがあります。
このケースで想定されるリスクと対処方法は以下の記事に詳しくまとめています。
共有物分割請求訴訟を起こされる
不動産の共有状態を解消するために起こすのが「共有物分割請求訴訟」です。訴訟を起こされた場合は拒否できないため、判決によっては持分を手放さざるを得なくなるリスクがあります。
(共有物の分割請求)
第二百五十六条 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
引用元: 民法第二百五十六条|e-Gov法令検索
訴訟となれば弁護士に相談したり口頭弁論のため裁判所に出廷したりする必要があるため、時間や費用もかかってしまいます。では、実際に訴訟される(共有状態の解消を求められる)のは、どのようなケースが想定されるのでしょうか。
以下に、代表的な例をいくつか挙げてみました。
- あなたは共有状態にある物件(マンション等)に住んでいる
- 他の共有者が自分の持分を売りに出した
- 購入した第三者が、あなたに賃料の支払いを求めてきた
- 話し合ったが折り合いがつかず、余計にこじれてしまった
- 第三者が共有物分割請求訴訟を起こした
- 判決により、あなたは対価を得る代わりに持分を第三者に譲り渡すこととなった
本来は当事者間の話し合いで解決すべきですが、それぞれの思惑もあるためまとまらないことも少なくありません。話し合いがこじれた場合、共有物分割請求訴訟を起こして裁判所に判断を委ねることになります。
仮に和解が成立した場合も遺恨は残るため、その後の共有関係に亀裂が入るでしょう。
税金や維持管理費の負担で揉める
共有持分を所有していると、固定資産税や都市計画税、維持管理費などの支払いを巡り金銭トラブルに発展するリスクがあります。共有不動産の税金は地方税法で「連帯納税」が義務付けられており、持分割合に関わらず共有者全員が全額納税義務を負います。
(連帯納税義務)
第十条の二 共有物、共同使用物、共同事業、共同事業により生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。
引用元: 地方税法第十条の二|e-Gov法令検索
納付書は共有者の「代表者」宛てに届くため、代表者が全額納付したのち他の共有者から回収する流れが基本です。しかし、それぞれの共有者へ直接請求が行くわけではないため、当事者意識が低い共有者がいると全く支払わないケースも珍しくありません。
実際に、共有者が固定資産税を払ってくれないために、弊社の共有持分の買取相談をご利用された方も多数いらっしゃいます。
共有名義不動産における固定資産税は、連帯納税の義務に則り他の共有者が負担することになります。
未納分を立て替えた場合、他の共有者に対して費用の負担分を請求することは可能です。さらに、請求に応じない場合には、裁判所を通じて法的措置を講じることもできます。
しかし、こうした対応には相応の時間・労力・弁護士費用がかかるうえ、共有者間の関係性が著しく悪化するリスクも高まります。そのため、きちんと納税している共有者に大きな負担がかかってしまうのが実情です。
また納税義務は共有者全員にありますが、均等に負担する義務はありません。したがって事前に負担割合を決めておくことが重要である反面、その負担割合で揉めるリスクがあることも知っておきましょう。
なお管理費については、民法で「持分割合に応じて負担する」と規定されています。
(共有物に関する負担)
第二百五十三条 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
引用元: 民法第二百五十三条|e-Gov法令検索
管理の費用とは、維持および改良などにかかる費用、マンションの管理費などが該当します。共有者の中に1人でも支払わない人がいると、税金と同様に他の共有者が立て替えることになります。
未払いの共有者に請求したり裁判を起こしたりなどはできますが、上述の通り労力やコストがかかるうえ、共有者同士の関係が悪化するリスクもあります。
共有持分だけでは一般の人に売れることがほぼない
共有持分だけを持っていても、一般の第三者に売却するのはほぼ不可能です。これは、共有持分の不動産を単独で利用できなかったり、権利関係が複雑になりやすかったりなど、所有するうえでのデメリットが多いことが関係しています。
例えば、賃貸収入を得るつもりで共有持分のマンションを購入したと仮定しましょう。しかし、共有持分だけを所有している状態では、賃貸に出すのに他の共有者の承諾を得る必要があります。
特に、購入した第三者は、他の共有者にとっては赤の他人にあたるため、もともとの共有持分の保有者に比べて承諾を得るハードルは高いです。一方で、マンションの管理・維持費や固定資産税は発生し続けるため、投資目的のつもりが損失だけが発生し続けることになります。
さらに、前述のとおり購入した共有持分を処分するのにも、他の共有者の承諾が要ります。このように、自由な活用・処分ができない共有持分の不動産を、一般の人がリスクを冒して購入することはほぼありません。
そのため、共有持分を売却したい場合は、専門の買取業者に依頼するのが望ましいです。
共有持分のトラブルに発展するリスクが高いケースと対処方法
以下のケースに当てはまる共有持分の所有者は、共有名義の不動産を巡ってトラブルに発展するリスクが高いです。
- 共有者同士で離婚する
- 他の共有者と連絡を取りにくい
- 他の共有者が認知症になる
- 他の共有者が行方不明になっている
- 収益物件の経営で揉める
それぞれ対処方法とあわせて説明します。すでに当てはまっている方はもちろん、将来的に該当しそうな方も以下を参考にトラブルに備えましょう。
不動産を共有する夫婦が離婚する場合
不動産を共有する夫婦が離婚する場合、共有不動産の財産分与でトラブルに発展するケースも少なくありません。これは、本来の共有持分の定義と、財産分与の定義が異なることが関係しています。
財産分与とは、夫婦として築いてきた財産を公平に配分する手続きです。婚姻後に築き上げた財産は、年収に関係なく夫婦で公平に1:1で分けるのが原則です。
一方で共有持分割合は、共有不動産を所有する際に支払った出資額に基づいて決まります。
しかし、婚姻後に共有名義の不動産を所有した場合、財産分与で共有持分割合が考慮されることは少なく、1:1の配分が求められるケースが多いのが実情です。
そのため、仮に持分割合が1:9だったとしても半分ずつ分け合なければならないケースもあります。
・財産分与の規定に従い、持分割合に関わらず不動産を折半する
・折半できない不動産は一方が代償金を支払って買い取り、単独名義とする
・不動産全体を売却し、代金を折半する(または持分割合に応じて分配する)
離婚協議がこじれてから共有不動産の扱いについて話をすると、解決できる問題も解決できなくなるおそれがあります。離婚協議が始まったら、お互いが冷静なうちに話し合いを進めていくことが大切です。
なお不動産の名義が共有状態の場合は、よほど特別な事情がない限り離婚時に解消することをおすすめします。共有名義のままにすると以下のようなリスクが生じるためです。
- 離婚をしても、不動産を所有し続ける限り関わり続けることになる
- 税金や維持管理費の支払いで揉めるおそれがある
- 売却・相続・使用方法などで新たなトラブルを招くおそれがある など
共有名義のままだと離婚後も関係を持たなければならないため、固定資産税などの税金や維持管理費の支払いを巡るトラブルにつながります。一方が死亡した場合に相続が発生したり、不動産全体を売却したいと思ってもスムーズに話がまとまらなかったりなど、新たなトラブルに発展するケースも少なくありません。
また共有名義で住宅ローンを組んでいる場合、離婚をしても当然ですが返済は続きます。一方の支払いが滞るともう一方に負担がかかるなど、こちらもトラブルの元になります。共有名義の住宅ローンについて、離婚時の対処方法や注意点をまとめた以下の記事もぜひ参考にしてください。
他の共有者と連絡を取りにくい
連絡を取りにくい共有者がいると、共有不動産を巡る金銭トラブルなどのリスクが高くなります。共有相手は家族や近親者であるケースがほとんどですが、以下のような事情により意思疎通が困難となることは少なくありません。
- 関係が希薄で所在や連絡先も不明
- 所在はわかるが犬猿の仲
- 過去に不義理をした(された)
- 親の不動産を共有名義で相続していたことを知らない疎遠の兄弟がいる
たとえばあなたが代表で固定資産税を支払っている場合、他の共有者と連絡が取りにくいと請求もしづらく、不動産全体を売却しようにも同意が得られなければ話が進みません。このように連絡が取りにくい共有者がいると税金や維持管理費の支払い、管理行為や売却などすべての場面でトラブルが起こるリスクがあります。
・自分の持分だけを専門の買取業者に売却する
・共有物分割請求訴訟を起こす(所在がわかる場合)
自分の持分のみなら、他の共有者の同意がなくても売却できます。個人相手ではなかなか売れないため、速やかにトラブルを回避するなら専門の買取業者に相談するのが良いでしょう。
また、所在や連絡先はわかるものの連絡しづらいという場合は、共有物分割請求訴訟を起こす方法もあります。ただし、裁判で他の共有者と顔を合わせる可能性があるほか、突然訴訟を起こしたことでさらに関係が悪化するリスクも高まります。
さらに、訴訟を提起する場合は、手続きの複雑さや法的リスクを考慮し、弁護士に依頼するのが基本です。その場合、着手金や報酬などの弁護士費用が発生するため、上記のような精神的負担だけでなく、経済的にも大きな負担がかかることになります。
そのため総合的な負担を考えると、専門の買取業者に共有持分を売却する方法が最も効率よくスムーズに共有状態を解消できる手段といえます。
実際に弊社でも、共有者との連絡が取れなかったり感情的な対立が起きていたりするケースにおいて、数多くの買取実績があります。
ご提案の際は、売主様と他の共有者様それぞれのご事情や利益への配慮を最優先しております。そのため、「共有者と一切やり取りせずに持分だけ手放したい」「連絡が取れずどうしようもない」という状況でも、まずはお気軽にご相談ください。
他の共有者が認知症になる
他の共有者が認知症を発症すると、不動産の売却や管理に関する意思決定ができなくなり、共有関係の維持や解消に支障をきたす可能性があります。
これは、認知症によって判断能力が低下すると、法律行為が制限されるためです。特に意思能力の欠如が認められると、その共有者による同意や契約などの法律行為は無効と判断されてしまいます。
たとえば、不動産全体の売却には共有者全員の同意が必要です。その際、たとえ認知症の共有者が同意しても無効となるうえ、法律行為ができないことから共有関係も解消できないなど非常に厄介な状態に陥ります。
・自分の持分のみを専門の買取業者に売却する
・成年後見人を立てて法律行為の代行を依頼する
「不動産は残らなくてもよいから共有関係を解消したい」というのであれば、自分の持分だけを専門の買取業者に売却すれば解決します。しかし、不動産全体の売却や賃貸活用などの大規模な管理行為では、共有者全員または過半数の同意が必要です。
認知症の共有者が意思表示できない以上、そのままでは手続きを進められません。このような場合には、家庭裁判所に申し立てて成年後見人を選任し、意思能力が失われた共有者に代わって法律行為を行ってもらう必要があります。
成年後見人は、認知症や障害などにより判断能力が著しく低下した人を支援・保護するための制度です。申し立て等の流れについては裁判所のホームページをご覧ください。
他の共有者が行方不明になっている
共有者の中に音信不通や行方不明の人がいた場合、共有者全員または過半数の同意が必要な不動産の処分・管理で大きな障害となるリスクがあります。親や親族から相続を受けたり、他の共有者が第三者に売却したりなど、相続や売却が絡んで面識のない人と共有関係になった場合は特に注意が必要です。
従来のように、裁判所に申し立てて不在者財産管理人を選任してもらう方法があります。しかし、時間がかかるうえに原則弁護士が務める管理人への報酬も必要など、費用対効果は高くありません。
そんな中、2023年に民法が以下のように改正されました。
(共有物の管理者)
第二百五十二条の二 共有物の管理者は、共有物の管理に関する行為をすることができる。ただし、共有者の全員の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。
2 共有物の管理者が共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有物の管理者の請求により、当該共有者以外の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができる。
引用元: 民法第二百五十二条の二|e-Gov法令検索
ポイントは「当該共有者以外の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができる」の部分で、具体的に以下のようなことが可能となります。
裁判所に「所在等不明共有者の持分取得制度」の利用を申し立てる
裁判所に「所在等不明共有者の持分譲渡権限付与制度」の利用を申し立てる
各制度の概要と、それによりどういったことができるのかを以下にまとめています。
| 制度名 | 概要 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 所在等不明共有者の持分取得制度 | 裁判所の判断で、行方不明者の持分を他の(連絡・協議が可能な)共有者に取得させることができる制度。 | 不動産全体の売却や用途の変更などが可能になる | 裁判で決定した行方不明者の持分の価格を供託金として支払う必要がある |
| 所在等不明共有者の持分譲渡権限付与制度 | 裁判所の判断で、行方不明者以外の共有者全員が「第三者に対して、自分たちの持分を全て譲渡すること」を条件に、行方不明者の持分を譲渡する権限を与えることができる制度。が、 | トラブルから開放される | 結果として不動産全体を譲渡することになる |
行方不明とはいえ勝手に売却したり名義変更したりできないため、裁判所に申し立てる手間や費用はかかります。しかし、不在者財産管理人を選任してもらうしか方法がなかった従来と比べると、柔軟な対応が可能になりました。
個人で申し立てることも不可能ではありませんが、行方不明であることを証明する書類など準備の段階から負担が大きいためおすすめしません。また、不動産の売却や譲渡を最終的な目的としている場合は、最初から弁護士や司法書士などの士業とのネットワークを持つ専門の買取業者に相談することをおすすめします。
ちなみに弊社では、1,200を超える士業と連携しているため、行方不明の共有者がいる場合でもスムーズな対応が可能です。
収益物件の経営で揉める
共有不動産が駐車場やマンション、テナントビルなどの収益物件だった場合、管理方法や収益の分配を巡って以下のようなトラブルになるリスクがあります。
- 管理者(共有者の代表者)が収益を独り占めしている
- 他の共有者が税金や維持管理費をきちんと支払ってくれない
- 家賃を受け取らず、共有者が自分の身内をマンションに住まわせている(損失が発生)
- 地価の上昇にともない賃料を上げたいが、他の共有者が協議を拒否する
- 他の共有者が死亡し相続人となった親族が、執拗にあなたの持分の買い取りを迫ってくる
ビジネスモデルにもよりますが、収益をきちんと分配してくれないなど、主に金銭トラブルのリスクが高くなります。
・当事者間で話し合い解決を目指す(相手に不当利益がある場合は返還を求める)
・こじれたときは裁判所に「不当利得返還請求」「不法行為にもとづく損害賠償請求」を提起する
・自分の持分を専門の買取業者に買い取ってもらう
・自分の持分を他の共有者に買い取ってもらう
前述のとおり、裁判所への提起は精神的な負担が大きく、また今後も共有し続ける場合は関係性の悪化も懸念されます。粘り強く交渉を続ければ相手が動いてくれる可能性もありますが、やはり心身への負担は大きなものです。
不動産を手放すことにはなりますが、専門の買取業者に売却すればトラブルから開放され手元には現金が残ります。そのため、一刻も早くスッキリしてリスタートするなら売却がおすすめです。
共有持分のリスクは「共有状態の解消」で回避できる
共有持分のさまざまなリスクを回避するには、共有状態を解消するしかありません。共有状態は以下いずれかの方法で解消できます。
| 解消方法 | 適している状況 |
|---|---|
| 不動産全体を売却し売却金を分配(換価分割) |
・共有者全員と連絡が取れている ・共有者全員が売却に合意している |
| 他の共有者の持分を買い取り単独所有にする(代償分割) |
・資金的に余裕がある ・他の共有者が売却に同意している |
| 土地を分筆して分ける(現物分割) |
・共有不動産が土地 ・各共有者が物理的に分けて使うことを希望している ・隣地との境界が確定している ・分筆後の土地が面積要件をクリアしている |
| 他の共有者に自分の持分を売却する |
・他の共有者と関係が良好 ・資金的余裕があり買い取りを希望している共有者がいる |
| 専門の買取業者に持分を売却する |
・他の共有者と話が合わない ・連絡が取れない共有者がいる ・速やかに共有関係を解消したい |
| 共有物分割請求訴訟を起こす | 話し合いが決裂しており、協議による解決が難しい |
| 自分の持分を放棄する |
・売却益を求めていない ・共有関係から早く抜けたい |
近い将来、相続で共有持分の所有者となる方や共同不動産を購入する方も、トラブル回避につながる知識なのでぜひ役立ててください。それぞれポイントを絞ってわかりやすく説明します。
共有者全員同意の上で不動産全体を売却し売却金を分配する【換価分割】
下記のように共有者との関係性が良い、または共有不動産全体の売却に関して意見が一致している場合は、「換価分割」を提案するとよいでしょう。
- 他の共有者と話し合いができる関係性である
- 不動産全体を売却しても共有者の誰にも支障がない
- 他の共有者も共有状態を解消したいと考えている
換価分割とは、共有者全員の同意を得て不動産全体を売却し、持分割合に応じて売却で得た代金を分配する処分方法です。
共有者の同意を証明するための同意書を作成し、不動産業者に仲介を依頼するのが基本的な流れとなります。
共有持分のみでは資産価値が乏しく売却価格も相場未満になる傾向ですが、不動産全体を売却できれば通常の不動産売却と変わりません。そのため、相場並みの価格で売却しやすくなります。
手元に多くの資金が残り不動産も手放せるため、今後の税金や維持管理費の支払い、また他の共有者とのトラブルのリスクを大幅に軽減できます。ただし、売却で処分することになるため、前述したように1人でも反対する共有者がいると話がまとまりません。
その場合は後述する別の方法を検討しましょう。また売却で得た代金が代表者の口座に入金される場合、分配されないといったトラブルを避けるためにも、連絡は密に取れる状態にしておくことが大切です。
他の共有者から持分を買い取り自分の単独所有にする【代償分割】
下記のような場合は、他の共有者の持分を買い取って自分の単独所有にする「代償分割」を提案してみましょう。
- 他の共有者と話し合いができる関係性である
- 不動産は手放さずに共有状態を解消したい
- 他の共有者が不動産を手放すことに納得している
単独所有になれば、管理が楽になるうえ不動産の使用方法や売却も自分で判断できるため、上述してきた共有持分のリスクはすべて排除できます。ただし代償分割を提案するにあたって、以下の注意点を押さえておきましょう。
- あなたに十分な買取資金があること
- 買い取りを申し出る正当な理由があること
- 相場と同等など適正な評価をつけること
- 支払い・名義変更などは速やかに行うこと
- 誠実に対応する(詐欺など疑いの目を向けられないようにする)こと
正当な理由については、使用実態や生活基盤としての必要性がある場合が挙げられます。たとえば、買い取りを希望する共有者がその不動産に居住し、生活の拠点として使用している場合は、持分取得の合理的な理由として認められやすいです。
また、買い取りを申し出る場合は誠実に対応することが大切です。財産を巡るトラブルは深刻化することがあるため、買い取る理由もきちんと伝えて、できる限り平和的な解決を目指しましょう。
無事に代償分割が成立したら、不動産の名義を「共有名義」から「単独名義」に変更して初めてあなたの単独所有となります。名義変更にかかる費用や流れ、注意点などを以下の記事にまとめているので、代償分割を検討する方はあわせて読んでおいてください。
土地の場合は分筆する【現物分割】
下記のような場合は分筆を提案しましょう。
- 共有している不動産が土地である
- 他の共有者と話し合いができる関係性である
- 誰も土地を手放すことなく共有状態だけを解消したい
分筆とは「一筆(ひとつの土地)」として登記簿に登録されている土地を分割して登記し直すことです。それぞれ単独で所有者を登記できるため、誰も土地を手放すことなく共有状態を解消できます。
ただし分筆することで、ある共有者の土地だけが道路に面していない状態になったり不整形になったりと、極端に使い勝手が悪くなるリスクもあります。そのため、共有者全員が納得した上で行うことが大切です。
また大前提として、分筆前の時点で隣地との境界線が確定していることが条件であり、分筆した土地が最低敷地面積を下回らないことも重要です。
家を建てる際に最低限必要とされている敷地面積のこと。市町村の地区計画区域などによって定められており、全国一律で何平米と決まっているわけではありません。分筆した土地が最低敷地面積を下回っていた場合、家を建てられないなど活用しづらいことから、売却も難しいというデメリットがあります。
分筆すると最低敷地面積を下回ってしまうという場合は、別の方法を検討するのが無難です。
他の共有者に自分の持分を売却する
下記のような場合は、自分の持分を他の共有者に買い取ってもらえないか提案してみましょう。
- 他の共有者と話し合いができる関係性である
- 共有関係を解消できれば不動産を手放してもよい
- 現金が必要
共有持分の売却は難しいと前述しましたが、それはあくまで第三者(個人)に売却する場合です。たとえば、あなたの持分を買い取った他の共有者が持分割合の過半数を取得できれば、不動産の使用方法の決定・変更などの管理行為を自由にできるようになります。
そのため、持分割合を増やすことのメリットを引き合いに出して買い取りを提案すれば、話がまとまりやすくなります。
また売却価格でトラブルにならないためにも、事前に「不動産鑑定」を受けることをおすすめします。不動産鑑定とは、不動産鑑定士という有資格者が基準に沿ってその不動産の適正な評価額を決定する行為で、「不動産査定」とは異なります。
不動産査定は不動産業者(有資格・無資格問わず)が独自基準で評価するため、不動産鑑定に比べて公的性の点で劣ります。
あなたと他の共有者との間で金額に折り合いがつけばどちらでも問題ありませんが、可能であれば公的性の観点からも不動産鑑定をおすすめします。
専門の買取業者に自分の持分を売却する
下記のような場合は、専門の買取業者に売却する方法をおすすめします。
- とにかく速やかに共有状態を解消したい
- できるだけお金を手元に残したい(適正価格で売却したい)
- 他の共有者と関わることなく(こっそり)手放したい
- 他の共有者とのトラブルを抱えた状態だが持分を手放したい
- 他の共有者と連絡が取れず買い取りや売却の提案もできない
ここでのポイントは「専門」の業者かどうかです。賃貸や売買の仲介が中心の不動産業者は共有持分が専門外であることが多いため、断られたり、仮に買い取りが可能でも安い金額を提示されたりするケースも少なくありません。
手続きに不慣れな業者の場合、対応に時間を要することで、売却の意図が他の共有者に伝わってしまうリスクも高まります。
適正価格で売却し、速やかに共有状態を解消するためにも、買取実績が豊富で弁護士や司法書士と連携がスムーズな専門業者を選びましょう。
共有物分割請求訴訟を起こす
下記のような場合は、裁判所に「共有物分割請求訴訟」を申し出るのも選択肢の一つです。
- 他の共有者が協議に応じてくれない
- 話し合いはできるものの折り合いがつかない(こじれてしまった)
裁判所は共有不動産の分割方法として、前述した方法を含む以下3パターンいずれかの判決を出します。
| 分割方法 | 概要 | 注意点 |
|---|---|---|
| 現物分割 | 共有不動産そのものを分割すること | 土地の場合は分筆できるが、建物の場合は物理的・現実的に分割が困難なことも多い(マンションの一室など) |
| 代償分割 | 共有者のうちの1人が他の共有者全員の持分を取得する代わりに、その対価を他の共有者に支払う | 取得する共有者に十分な資金があることが前提 |
| 換価分割 | 共有不動産を競売にかけ、売却代金を共有者全員で分ける方法。現物分割できない(価値が著しく損なわれる)といったケースで出されることが多い | 通常の売却価格よりも低くなる |
共有物分割請求訴訟では、最終的な分割方法は裁判所の判断に委ねられます。そのため、たとえ現物分割や代償分割を希望していても、条件が整わなければ認められず、裁判所が出した判決には必ず従わなければなりません。
もし、裁判所が換価分割を選択した場合、自分で換価分割する場合とは異なり売却方法は選べず、「競売」という形で強制的に売却されます。競売は公開入札形式で行われますが、市場価格の2~3割程度安く落札されるのが実情です。
結果的に不動産全体を売却するのと変わらないため、あらかじめ仲介などで売却していれば、より高値で売却できた可能性があります。このように、共有物分割請求訴訟を起こすと、共有者全員にとって経済的損失が生じる可能性も少なくありません。
そのため、共有物分割請求訴訟はあくまで最終手段として考えておき、なるべく話し合いによる解決を目指すことをおすすめします。
どうしても当事者間の協議でまとまらなかった場合は、下記の流れで共有物分割請求訴訟を行いましょう。
- 共有者に「共有物分割請求訴訟」を起こすことを伝える
- 弁護士に経緯を相談し「共有物分割請求訴訟」の申し立てを依頼する
- 呼出状が送付されたら期日に出廷し、裁判を受ける
- 判決が出たら速やかに従う(判決を待たずに和解も可)
共有物分割請求訴訟を起こされると、他の共有者は拒否できず判決にも従わなければならないため法的に共有状態を解消できます。裁判所からの呼出状が届いたときにトラブルになることがないよう、他の共有者には事前に伝達しておくことをおすすめします。
自分の持分を放棄する
下記のような場合は、所有権を他の共有者に移転して自分の持分を放棄する方法もあります。
- 他の共有者と連絡が取れる/話ができる関係性である
- 不動産を手放したい、現金は残らなくても構わない
- 他の共有者が損害を被らない形で共有状態を解消したい
一部のみの放棄はできないため持分を全て手放すことになりますが、他の共有者の同意は不要です。ただし、放棄した持分を他の共有者の名義で登記し直す際には「協力」が必要になるため、事前に伝えておいたほうがスムーズに進みます。
名義変更に応じてもらえないなどで進展しないときは、他の共有者に自分が放棄した持分の受け取りを求める「登記引取請求訴訟」を起こす手もあります。しかし民事裁判の審理期間(判決が下るまでの期間)は約9カ月という調査結果(※)もあるなど、時間や労力がかかることは覚悟したほうがよいでしょう。
とにかく一刻も早く共有状態を解消したい方は、専門の買取業者に売却するのが最もスムーズです。
※参照:裁判所|第2 審理期間 p.75
共有持分の売却は専門の買取業者に依頼するとリスクを減らせる
共有持分の売却先は、大きく分けて「他の共有者」「専門の買取業者」の2つです。他の共有者に売却する場合、価格交渉で揉めたり、売却相手以外の共有者との関係が悪化したりするリスクもあります。
とくに感情的な対立がある場合は、スムーズに話が進まないことも少なくありません。そのため、トラブルを回避しつつ速やかに共有関係を解消したいのであれば、第三者である専門の買取業者への売却を検討するのがおすすめです。
専門の買取業者に共有持分の売却を依頼すると、次のようなメリットも期待できます。
- 売却後は専門業者に他の共有者の対応をしてもらえる
- 自分の持分のみを早く・適正価格で売却できる
それぞれの内容をみていきましょう。
売却後は専門業者に他の共有者の対応をしてもらえる
専門の買取業者に共有持分を売却すると、買主である買取業者が新たな共有者となるため、売主自身は共有関係から脱出できます。
つまり、共有持分の固定資産税・維持管理費の支払いや、不動産の売却・賃貸に関する共有者全員の話し合いといった、煩雑な対応は今後必要ありません。また、今後発生する可能性のある共有者同士のトラブルとも無縁でいられます。
特に、専門の買取業者は共有持分の活用ノウハウが豊富なため、他の共有者との交渉やトラブルの仲裁、法的手続きの代行が可能です。そのため、すでに他の共有者との関係が悪化していたりトラブルが発生していたりする場合でも、その状態からいち早く解放されることでしょう。
実際に、弊社では以下のようなケースでスムーズな買取を実現しました。
藤沢市本藤沢の土地共有持分2分の1を「1,010万円」で買取
【お取引の概要】
・売主の父が所有していた土地を、母と売主が相続し2分の1ずつ取得
・建物は母が単独所有、土地を母と売主が共有
・長年賃貸に出していたが賃借人が退去
・売主が母に持分売却を打診するも、話し合いに応じてもらえず売却が進まない状態
【物件の詳細】
・母(共有者)と娘(売主)が土地を各2分の1で共有
・建物は母単独所有
・現在空室で利用予定がなく、売主は早期売却を希望
・しかし、共有者である母とは話がまとまらず困っていた
このような状況の中、ご相談からわずか3週間で弊社が買取を実施。今後は、弊社が共有者(母)と協議を行い、共有状態を解消した上で専任媒介契約をお戻しする予定です。
このように、専門の買取業者に依頼すれば、共有持分を所有し続けることで生まれるリスクを大幅に減らせます。その結果、心理的ストレスも低減できるでしょう。
自分の持分のみを早く・適正価格で売却できる
一般的な仲介買取と異なり、専門の買取業者は自社で共有持分を買い取ります。つまり、一般市場で買主を探す必要がないため、スピーディに共有持分を売却できるのが魅力です。実際に弊社でも、最短で48時間以内に共有持分を現金化できます。
また、一般的な不動産会社は、共有持分のノウハウが少ないことが多く、相場より安い買取価格を提示されたり、買取そのものを断られたりするケースも少なくありません。その点、専門の買取業者は共有持分の活用ノウハウがあるため、市場相場を踏まえた適正な買取価格を提示しています。
実際に、弊社では以下のような高額買取に対応した実績もあります。
杉並区井草の共有持分2分の1を「1億5,000万円」で買取
【お取引の概要】
・親が亡くなり、売主は個人と資産法人の両方を相続
・共有者は叔母であり、資産法人には債務があったため売却を希望
・しかし、叔母からは「売却したくない」との返答
・資産法人の解散を視野に入れ、持分を売却する決断に至った
【物件の詳細】
・7筆の土地に建物が3棟建つ複雑な構成
・地上権の仮登記、無償の借地、所有権が混在
・共有者は敷地内の1棟を全所有し、ご家族と居住中
このような複雑な物件でも、ご相談から2週間で現況のまま契約を締結しました。今後は、弊社が共有者と協議を進め、共有状態を解消したうえで1分の1の状態に戻し、専任媒介契約としてお返しする予定です。
また、直接買取にあたるため、高額な仲介手数料もかかりません。このように、専門の買取業者に売却すれば、適正な買取価格かつ仲介手数料なしで共有持分を売却できます。つまり、世間一般的に売れにくいとされる共有持分であっても、利益を最大化できる可能性が高いです。
共有持分の売却は信頼できる買取業者に依頼するべき
共有持分の売却は、買取・活用ノウハウが豊富な専門の買取業者への依頼がおすすめです。
スムーズかつ高値で共有持分を売るためにも、信頼できる買取業者を選びましょう。特に次のようなポイントを押さえることが大切です。
- 買取実績が豊富か
- 買取価格の根拠を明確に説明できるか
- 対応は親切・丁寧か
- 弁護士との連携があるか
- 「宅地建物取引業の免許」を持っているか
前述してきたように、共有持分の買取実績が豊富な事業者であれば、自身の共有持分についてもスムーズな買取が期待できます。事業者の公式HPなどをチェックして、共有持分の買取ノウハウが十分であるかを確認しましょう。SNSや口コミサイトで実際の利用者の声を聞くのも有益です。
また、共有持分の買取実績は、買取価格の根拠を明確に提示できるかという点でも測れます。専門知識のない人にも分かりやすく根拠を提示できる事業者であれば、価格について誤魔化しがないと判断できるでしょう。あわせて、その他の質問や相談事にも真摯に対応してくれるかもチェックしてみてください。
なお、共有持分の売却は前述した訴訟に発展するなどの法的トラブルが発生する可能性があることから、弁護士と連携している事業者の利用がおすすめです。たとえ法律的な問題が発生したとしても、スムーズに対応してもらえる可能性があります。
最後に、不動産の売買を行う事業者には「宅地建物取引業の免許」取得が義務づけられています。免許を持っていても100%の信頼はできませんが、一応は気にしておくと良いでしょう。免許を持っていない場合は違法業者であるため利用しないでください。
これらのポイントに気を付けることで、信頼できる専門の買取業者と契約できる可能性が高まります。
まとめ
共有持分はリスクが多い不動産です。他の共有者との人間関係や利害関係が絡み、問題が複雑化することも珍しくありません。トラブルに巻き込まれたときは共有関係を解消するのがベストですが、他の共有者と連絡が取れない、話がまとまらない、自分の持分だけだと売れないなどハードルが高いのも現実です。
よくある質問
共有持分を専門の買取業者に売却する場合の相場はいくらくらいですか。
市場相場の1/3~1/2程度で買い取られるのが基本です。これは、共有持分は活用が難しく、買取後に共有者同士のトラブルに巻き込まれる可能性があることから、さまざまなリスクを見越して買取価格が低く設定されるためです。
ただし、一般的な不動産会社はさらに安い買取価格をつけることがほとんどであるため、少しでも高値で売りたい場合は、専門の買取業者への売却が望ましいです。
専門の買取業者に共有持分を売却するのに費用はかかりますか。
| 費用の種類 | 概要 | 費用目安 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 登記内容の変更に際して国に支払う税金 | 評価額×2%(税率) |
| 抵当権抹消登記 | 共有持分に抵当権が設定されている場合に必要な手続き | 約2万円 |
| 氏名住所変更登記 | 登記簿に記載されている氏名・住所が現在のものと違う場合に行う変更登記 | 約2万円 |
なお、所有権移転登記には専門知識が必要なため、司法書士に依頼するケースが多いです。この場合は、上記の費用とは別に司法書士への報酬も必要です。
共有持分を売却したら確定申告は必要ですか。
原則として「譲渡所得税」と「復興特別所得税」の納税のために、翌年に確定申告を行う必要があります。「譲渡所得税」とは、不動産の売却利益にかかる所得税と住民税で、「譲渡所得×税率」で計算されます。
一方、「復興特別所得税」とは、東日本大地震からの復興財源として徴収される税金です。所得のある人ならば誰でも、所得税の2.1%相当が課されます。
確定申告が必要なのは譲渡所得税が発生したときのみですが、専門の買取業者に売却するのであれば、基本的に必要と認識しておきましょう。確定申告は毎年2月16日から3月15日の間に行う必要があります。