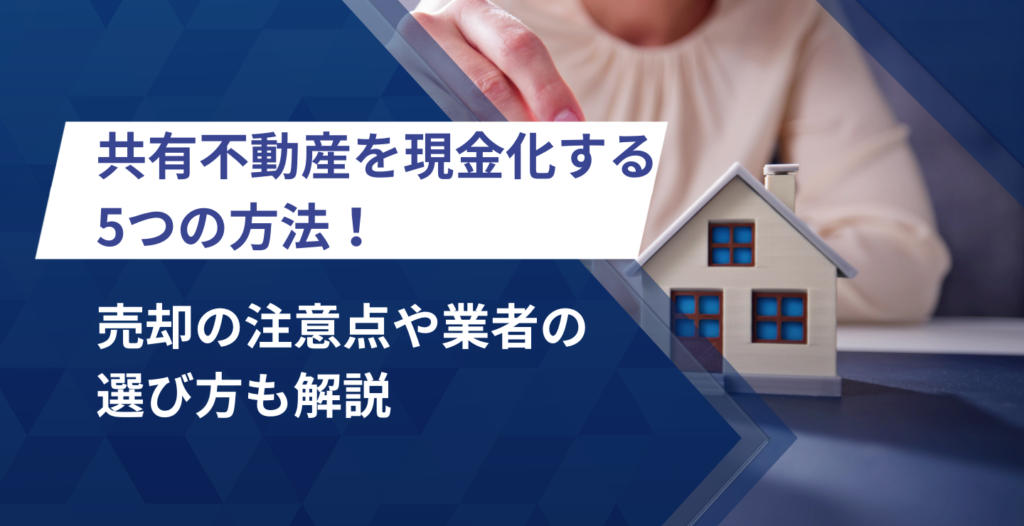共有名義のアパート所有でありがちなトラブル6選|解消法も徹底解説

アパートを兄弟姉妹など複数人で相続した場合、共有名義でアパート経営を行わならないケースもあります。
共有不動産の場合、自由に使用したり売却したりできず、他の共有者と意見が合わず揉めることもあります。
特に、アパート経営の場合、管理会社に支払う委託手数料や修繕、原状回復費用など、居住用の不動産以上に維持管理費用がかかりやすく、収益性を考えなければなりません。
そのため、アパートの収入や維持管理、売却時期などを巡って、次のようなトラブルとなる可能性があります。
| トラブル | 対処法 |
|---|---|
| 管理費用や固定資産税の支払いでトラブルになる | 各共有者の持分割合に応じて、アパート経営にかかる維持管理費用を明確にする。費用を負担しない共有者に対しては、訴訟による請求のほか持分の買取請求が認められる場合もあります。 |
| 共有者が同意しないと売却や賃貸経営ができない | 共有者間で話し合い合意形成を図る。共有不動産の管理行為の賛否を明らかにしない共有者に対しては、裁判所の決定の下共有者以外の持分で決定できる場合もあります。 |
| 共有者の一人がアパートの賃貸収入を独占する | 本来他の共有者が得られる家賃収入を一人が独占している場合、不当利得返還請求することが考えられます(民法第703条)。 |
| 他共有者に賃料の支払いが発生するケースがある | 管理会社や不動産会社に相談して妥当な賃料相場で合意する。金額面で折り合うことが難しい場合、調停や訴訟を申し立てることも考えられます。 |
| 他共有者と連絡が取れなくなる | 長期間連絡がとれない、共有者の所在が不明な場合、裁判所の判断のもと「所在等不明共有者の持分取得制度」や「所在等不明共有者の持分譲渡権限付与制度」の活用が考えられます。 |
| 相続人が増えて子どもや孫がトラブルに巻き込まれる | 共有者が多いほど、共有期間が長期間にわたるほど、相続が発生する可能性が高まるため、できるだけ早く共有関係を解消する |
このようなトラブルに対処するには、話し合いで解決するほか、状況によっては裁判で他の共有者に維持費の負担や不当に得た家賃収入などを請求することが考えられます。
もっとも、そもそも他の共有者と連絡が取れない、あるいは相続が発生し権利関係が複雑になることもあります。
このような状況を防ぐには、できるだけ共有関係にならない対策も必要です。
この点、アパートを相続する前に共有関係を解消する方法として次のものが考えられます。
- 遺産分割で共有状態を解消する
- 相続放棄する
- 遺言書を作成してもらう
遺言書がある場合でも、相続人全員の合意のもと、遺産分割協議でアパートを相続人の一人に単独で相続させることも可能です。
また、すでに共有状態にあるアパートについても、共有関係を解消するために次のような方法が考えられます。
- 自分の共有持分を他共有者に買い取ってもらう
- 他共有者の共有持分を購入して単独名義にする
- 他共有者の合意のもとアパート全体を売却する
- 自分の共有持分を放棄する
- 共有物分割請求訴訟を提起する
- 第三者に自分の持分を売却する
自分の共有持分を他の共有者に買い取ってもらう、あるいは、アパート全体を売却するには他の共有者の合意が必要です。
また、合意が難しく裁判で解決を図るとしても、時間や費用負担が大きいだけでなく、共有者の関係性を悪化させる可能性もあります。
そのため、共有状態を解消するには、共有持分専門の買取業者に買い取ってもらう方法が現実的といえます。共有不動産の取扱いに長けた買取業者であれば、現金化までスピーディーに進められるでしょう。
この記事では、共有名義のアパートについて起こりうるトラブルについて紹介するしたうえで、相続の際に共有状態を避ける対策や共有関係を解消する方法について徹底解説します。
共有名義のアパート所有でありがちなトラブルと対処法
単独で所有する場合と異なり、複数人でアパート経営をするとなると共有者同士で揉めることもあります。
ここでは、共有名義のアパートでありがちなトラブルと対処法について解説します。
- 管理費用や固定資産税の支払いでトラブルになる
- 共有者が同意しないと売却や賃貸経営ができない
- 共有者の一人がアパートの賃貸収入を独占する
- 他共有者に賃料の支払いが発生するケースがある
- 他共有者と連絡が取れなくなる
- 相続人が増えて子どもや孫がトラブルに巻き込まれる
管理費用や固定資産税の支払いでトラブルになる
アパートを維持管理するための管理費用や固定資産税の支払いでトラブルとなる可能性があります。
アパートを所有するうえで必要となる管理費用として次のものが挙げられます。
- 固定資産税・都市計画税
- 共用部の光熱費
- 修繕費用
- 火災保険料・地震保険料
- 不動産会社への管理委託料や広告費 など
これら以外にも入居者が退去する際の原状回復費や借入金が残っている場合であれば毎月のローン返済が必要となります。
共有不動産の維持管理費用については、各共有者はその持分割合に応じて費用を負担することが原則です(民法253条第1項)。
とはいえ、持分割合に納得できない共有者がいたり、アパートの管理方針や処分方法について意見が分かれたりすると、維持管理費用の負担でトラブルとなる可能性があります。
維持管理費用のトラブルに対処するには、まず、アパートの維持管理費かかる費用をしっかりと把握したうえで、各共有者の持分割合に応じた費用を明確にすることが大切です。
そのうえで、維持管理費を肩代わりしている共有者がいる場合、費用を負担しない共有者に対して支払いを請求できますし、請求に応じない場合は、訴訟などの裁判手続きで請求することも可能です。
また、民法では、共有者が維持管理費を1年以上負担しない場合に、他の共有者に持分の買取請求を認めています。
共有者が一年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。
つまり、相当の費用(通常、持分に相当する金額)を支払うことで共有持分を買い取ることにより、費用を負担しない共有者を共有関係から外すことができるわけです。
また、共有持分の買取請求権は、相当の償金を支払うことで効力が生じるため、維持管理費を支払わない共有者は拒否できません。
なお、共有不動産の固定資産税・都市計画税については、代表者に納付書が送付されますが、各共有者は、持分とは関係なく固定資産税全額について納付する義務を負っています(連帯債務:地方税法第10条の2第1項)。
共有者が同意しないと売却や賃貸経営ができない
例えば、アパートを兄弟姉妹で相続した場合など、アパート経営を続けるか、あるいは売却するかで意見が対立し揉める可能性があります。
共有不動産については、アパートを修繕したり、担保に入れてお金を借りたり、あるいは売却する場合、共有持分の割合に応じてできることが決まります。
次の表は、行為の種類に応じて必要な持分割合をまとめたものです。
| 行為の種類 | 具体的内容 | 必要な持分割合 |
|---|---|---|
| 変更行為(民法第251条) | ・売買契約 ・不動産の改築 ・共有物全体への抵当権設定 |
共有者全員の同意が必要 |
| 管理行為(民法第252条) | 原則:賃貸借契約(長期間の賃貸借などは変更行為になる場合あり) | 共有者の過半数の同意が必要 |
| 保存行為(民法第252条) | ・不動産の修繕 ・共有物の不法占有者への明渡請求など |
他の共有者の同意は必要なし |
アパートを売却する行為は共有物に対する「変更行為」にあたるため、共有者全員の同意が必要です。1人でも反対者がいる場合売却できません。
もっとも変更行為のなかでも、例えば、砂利道をアスファルトに舗装するなど、「形状または効用の著しい変更を伴わないもの(軽微変更)」については、持分の過半数で決めることができます。
また、共有物の賃貸は原則として管理行為になり共有持分の過半数の同意が必要ですが、個々の状況によりますが長期の賃貸となると変更行為にあたり共有者全員の同意が必要な場合があります。
このように共有不動産に対して行使できる権利は、持分割合によって決まるため、共有者間で意見が分かれるとトラブルに発展する可能性があるわけです。
これを解決するには、共有者間で話し合い合意形成を図る必要がありますが、なかには話し合いに協力しない共有者がいることもあります。
この点について、2023年(令和5年)4月1日施行の改正民法では、共有物の管理について関心を持たず、共有物の変更に対する賛否が明らかでない共有者がいる場合についての規定が設けられました。
民法改正によって、共有物の賃貸など管理行為の賛否を明らかにしない共有者がいる場合、裁判所の決定を得たうで、その共有者以外の持分の過半数によって決定することができます(民法第252条第2項2号)。
また、共有者間で話し合っても意見がまとまらない場合、共有関係を解消することが考えられますが、これについては後の章で詳しく解説します。
共有者の一人がアパートの賃貸収入を独占する
共有者の一人が賃料収入を独占するなどでトラブルとなる可能性もあります。
通常、アパート経営では、共有者の一人もしくは管理会社の口座に家賃収入が振り込まれます。
経理処理が複雑にならないよう経費なども一括で一つの口座で管理することが通常であり、それ自体は問題ありません。
もっとも、共有のアパートから得られる収入は、原則として持分割合に応じて共有者に分配される必要がありますが、分配されずに揉めるケースがあります。
例えば、アパートから得られる家賃収入が毎月60万円あり、3人で平等に相続した場合、それぞれの共有者は、毎月20万円の家賃収入を得る権利がありますが、その通りに支払われないケースなどです。
このような場合に考えられる解決法として、不当利得として返還請求する方法があります。
共有者の一人が家賃収入を独占することは、他の共有者が本来得られる収益を不当に得ている状態です。このとき、民法第703条に基づく不当利得返還請求ができます。
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
不当利得返還請求にあたっては、毎月の家賃収入の変動や滞納の有無などを考慮して請求額を算出する必要があります。
また、請求する側が本来負担すべき維持管理費を支払っていない場合は、請求する家賃収入と相殺することも可能です。
なお、不当利得返還請求権は、「請求できることを知ってから5年間」または「請求できる時から10年間」で時効となります。
他共有者に賃料の支払いが発生するケースがある
共有するアパートを共有者一人が使用、占有している場合、他の共有者は使えませんが、この場合でも、原則として、他の共有者は建物の明け渡しを請求することができません。
ただし、アパートを使用する共有者は、他の共有者が本来アパートの家賃収入として得られる賃料を支払わなければなりません。
各共有者が請求できる額は、「家賃相場×各共有者の持分割合」で算出できますが、このとき妥当な賃料相場を巡って争いが生じることがあります。
都市部の駅前など好立地に建つアパートであれば、駅周辺の再開発などで賃料相場が変わることもあるでしょう。
このような場合、まず管理会社や不動産会社に相談して、適正な賃料相場を前提に合意を目指すことが必要です。それでも金額面で折り合うことが難しい場合、調停や訴訟を提起することも考えられます。
共有不動産の賃料請求の方法については、下記の記事に詳しく解説していますので参照ください。
他共有者と連絡が取れなくなる
共有不動産では、他の共有者と連絡が取れなくなり、必要な対応ができない可能性もあります。
不動産が共有関係となるきっかけの多くは相続に伴うものであるため、兄弟姉妹やその他の親族が共有者になることが一般的です。
もっとも、普段から関係が疎遠の親族の場合、連絡が取れない、あるいは探し出すまでに時間がかかるケースがあります。
仮に、共有者が見つかっても、普段から交流のない共有者とアパートの管理や処分について話し合うことが困難なケースもあるでしょう。
また、長期間連絡が取れない間に相続が発生し、誰が相続人であるかを把握することが難しくなる可能性もあります。
なお、共有者の所在が不明な場合、「所在等不明共有者の持分取得制度」や「所在等不明共有者の持分譲渡権限付与制度」の活用が考えられます。
裁判所の判断で所在が不明な共有者の持分を他の共有者に取得させることができる制度【所在等不明共有者の持分譲渡権限付与制度】
裁判所の判断で不明共有者以外の共有者全員が、第三者に持分全部を譲渡することを条件に、不明共有者の持分を譲渡できる制度
詳しくは、以下の記事で解説していますのであわせてご覧ください。
相続人が増えて子どもや孫がトラブルに巻き込まれる
共有する不動産を所有する場合、共有者の一人が亡くなり相続が発生すると、権利関係が複雑となりトラブルに巻き込まれる可能性があります。
例えば、3人の兄弟でアパートを相続したのち、そのうちの一人が亡くなり相続が発生すると、その配偶者や子ども(共有者の甥や姪など)が相続人となります。
このとき、新たに共有者の数が増えるだけでなく、関係性が薄い共有者同士だと、賃貸経営の方針やアパートの売却などについての意見が対立しやすくなる点に注意が必要です。
共有者が多く、また共有する期間が長いほど、相続が発生する可能性は高くなるため、できるだけ早期に共有関係を解消することが解決策といえます。
共有名義のアパート相続する前にできる対策
相続後に共有アパートでトラブルにならないために、相続する前に共有関係を生じさせない対策について解説します。
- 遺産分割の際に共有状態を解消する
- 相続放棄する
- まだ存命の場合は遺言書を作成してもらう
遺産分割の際に共有状態を解消する
相続財産の遺産分割協議でアパートの共有状態を解消する方法です。
遺産分割協議とは、相続人同士で遺産の分割方法を話し合うことです。
相続財産は、亡くなった人(被相続人)が遺言書を残していれば、原則として遺言の内容に従って分割し、また、遺言書がなければ相続人全員による遺産分割協議で相続遺産の分割方法を決めます。
もっとも、遺言書がある場合でも、相続人全員の合意があれば、遺言と異なる内容で分割することも可能です。
そのため、遺産分割協議でアパートを共有するのではなく単独名義とすることで、共有不動産に生じうるトラブルを防ぐことができます。
なお、不動産を分割し共有状態を避ける方法として、次のものがあります。
| 分割方法 | 内容 |
|---|---|
| 現物分割 | 不動産をそのまま相続し、相続人間で分割する方法。 |
| 代償分割 | 相続人の一人が不動産を相続し、他の相続分に持分に相当する金銭を支払う方法 |
| 換価分割 | 不動産を売却し、売却収入を相続人間で分割する方法 |
現物分割について、土地であれば分筆し相続人間で分けられるケースもありますが、アパートは分筆できません。
ただし、相続する複数のアパートやその他の不動産がある場合は、相続人それぞれに単独で相続させることも可能です。
また、代償分割は一人がアパートを相続し、他の相続人に持分に応じたお金を支払う方法ですが、代償金を支払うだけの資力が必要です。
換価分割はアパートを売却したお金を相続割合に応じて分割する方法で、もっとも公平に分割できる方法といえます。
ただし、収益性が高いアパートの場合、賃貸経営を継続するか、売却するか慎重な判断が必要です。
なお、遺産分割協議は、すべての相続人が合意する必要があり、通常、のちのちトラブルとならないように、合意した内容について遺産分割協議書を作成し、すべての相続人が署名・捺印します。
相続放棄する
相続放棄することで共有状態を解消することができます。
相続放棄(民法第915条以下)は、プラス財産だけでなく借入金などのマイナス財産も含めて、すべての財産を承継する権利を放棄する手続きです。
他の相続人の同意なく行うことができ、自分のために相続が発生したことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
相続にまつわるトラブルに巻き込まれたくない、あるいはアパートの共有関係を望まない場合など、相続放棄することが考えられます。
なお、相続放棄すると相続人は初めから相続人ではなかったものとされ、代襲相続も生じないため相続放棄した子や孫が相続人となることはありません。
まだ存命の場合は遺言書を作成してもらう
まだ被相続人が亡くなる前であれば、遺言書を作成してもらうことで共有状態を解消できます。
相続人となる兄弟の関係性が悪い場合など、遺言書でアパートを単独で相続する相続人を決め、その他の不動産や預貯金、有価証券などの財産を他の相続人に遺すなどが考えられます。
遺言書にはいくつかの種類がありますが、主に利用されているのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。
財産目録を除く、遺言書の全文、日付を自筆で作成し、署名・押印する遺言書。・公正証書遺言
2人以上の公証人の立ち合いのもと、遺言者が遺言の内容を申述し、その内容を確認のうえ署名・押印して作成する遺言書
自筆証書遺言では、遺言の内容によってはかえって相続人間で争いになる場合や遺言書自体が無効になる可能性もあるため、公正証書遺言がおすすめです。
もっとも、公正証書遺言では、最低5,000円の作成手数料や弁護士や行政書士に依頼する場合は報酬が必要となります。
共有名義のアパートがある場合は共有状態の解消がおすすめ
共有名義のアパートがある場合は、のちのちトラブルを防ぐうえでは共有状態の解消がおすすめです。
ここでは、共有状態を解消する6つの方法を解説します。
- 自分の共有持分を他共有者に買い取ってもらう
- 他共有者の共有持分を購入して単独名義にする
- 他共有者の合意のもとアパート全体を売却する
- 自分の共有持分を放棄する
- 共有物分割請求訴訟を提起する
- 第三者に自分の持分を売却する
自分の共有持分を他共有者に買い取ってもらう
アパートの共有持分を他の共有者に買い取ってもらうことで共有状態を解消し、共有関係から解放されます。
共有持分の売却は、不動産全体を売却する場合と比べて、一般の不動産市場での売却は難しくなります。
これは、共有持分を取得した買主は、自由に不動産を利用・処分できないため需要が少ないためです。
その一方で、アパートについて利害関係のある他の共有者であれば、買い取ってもらえる可能性は高くなります。
特に共有持分を取得することで単独名義となる場合は、売却の話し合いは進めやすいでしょう。
ただし、売主と買主で売却金額で合意するとともに、共有者に買い取れるだけの資力が必要になります。
他共有者の共有持分を購入して単独名義にする
他の共有者の持分をすべて購入することで単独名義にする方法もあります。
単独でアパートを所有できることで、経営方針やアパートの改築、将来の売却まで自由に決定できます。
他の共有者と話し合いができる環境にある場合は進めやすい方法ですが、共有持分すべてを買い取る資金が必要です。
他共有者の合意のもとアパート全体を売却する
他の共有者全員の合意のもとアパートを売却する方法です。売却した収入を持分割合に応じて分配します。
売却収入を持分割合に従って分配できるため、分割方法として最も公平に分けやすい方法と言えるでしょう。
投資用のアパートを売却するタイミングとして、次の時期が考えられます。
- 築20年以内
- 売却価格が投資資金を上回った時
- 賃貸需要や地価動向の下落が予測される時
- 物件の所有期間が5年を超えた時 など
築20年程度までのアパートであれば比較的高く売却しやすい傾向にあります。木造であれば、節税対策における減価償却費の面から見ても売り時と言えます。
また、売却価格がアパートの購入費用や投資資金を上回った時、あるいは、アパート周辺の企業や大学などの撤退によって賃貸需要に下落傾向が予測されるタイミングも売り時の一つです。
税制面から見た場合、所有期間が5年以下の場合、アパートを売却した際の譲渡所得税・住民税の税率が高いため、所有期間が5年を超えた段階で判断することも考えられます。
自分の共有持分を放棄する
相続放棄について紹介しましたが、相続したあとでも共有持分を放棄することができます。
放棄した共有持分は、他の共有者の所有となり次の手続きが必要です。
2,持分放棄の登記をする
他の共有者への意思表示は、その事実を証拠として残すため内容証明郵便を利用して行うとよいでしょう。
また、持分放棄を登記しなければなりませんが、登記手続きには他の共有者の情報(書類)が必要となります。そのため、他の共有者の協力が得られない場合、手続きが進められない場合もあります。
なお、共有持分を放棄しても、その年度分の固定資産税は原則して支払う必要があります。
また、持分を取得する共有者に、贈与税が課税される可能性がある点に注意が必要です。
共有物分割請求訴訟を提起する
他の共有者との話し合いや交渉で合意できない場合、裁判手続き(共有物分割請求訴訟)によって強制的に共有状態を解消させる方法も考えられます。
訴訟で得られた判決には法的拘束力があるため、他の共有者は応じざるを得ません。
もっとも共有物分割請求訴訟を提起するとなると、およそ6カ月~1年程度の期間や裁判費用がかるうえ、他の共有者との関係性が悪くなる可能性があります。
また、共有不動産の分割方法について、裁判所の判断が自分が望む結果とならないこともある点に注意が必要です。
第三者に自分の持分を売却する
他の共有者に買い取ってもらえない場合、あるいは、アパート全体の売却に同意してもらえない場合に、自分の持分を第三者に売却する方法があります。
共有持分のみの売却には、他の共有者の同意は必要ありません。
もっとも、共有持分の売買では、自由に賃貸経営ができず、好きなタイミングで売却できないため、アパート1棟まるごと売却する場合と比べると需要は少なくなります。
そのため一般の個人や法人への売却は難しく、共有持分を専門に取り扱う買取業者などへの売却が有効な選択肢となります。
共有持分専門の買取業者であれば、共有不動産の活用や処分に関して豊富な知識や経験を持ち合わせているため、スムーズに進めることが可能です。
また、買取の場合、買主を探す必要がないため、早く現金化したいときも利用しやすいでしょう。
まとめ
共有のアパートを所有し続けることで次のようなトラブルが生じる可能性があります。
- 維持管理費用の支払いでトラブルになる
- アパートの売却や賃貸経営について他の共有者の同意が得られない
- 一人の共有者がアパートの賃貸収入を独占する
- アパートを使用する共有者が賃料を支払わない
- 他の共有者と連絡が取れなくなる
- 相続が発生し権利関係が複雑になる、トラブルに巻き込まれる
そのため、複数の相続人でアパートを相続する可能性がある場合、亡くなった人(被相続人)に遺言書を作成してもらう、あるいは遺産分割協議でアパートの共有関係を解消するなどの対策も考えるべきです。
とはいえ、すでに共有状態にある場合でも解消する方法はいくつかあります。
- 自分の共有持分を他の共有者に買い取ってもらう
- 他の共有者の共有持分を購入して単独名義にする
- 他の共有者の合意のもとアパート全体を売却する
- 自分の共有持分を放棄する
- 共有物分割請求訴訟を提起する
- 第三者に自分の持分を売却する
これらの方法のなかで、他の共有者の同意が必要なく、また、手続き的な負担が少ない方法は、自分の共有持分のみを第三者に売却することです。
もっとも、共有持分の売却では、購入者は自由にアパートを利用したり売却したりできないため、需要が少なく一般の不動産市場での売却は難しくなります。
そのため、共有持分専門の買取業者への売却がおすすめです。
通常の不動産売却と異なり買主を探す時間が必要なく、売買金額に合意できれば、最短で1週間程度で売却できるケースもあります。
ぜひ参考にしてください。
(参考:アパート経営の固定資産税【計算方法と5つの節税対策】具体的な評価額を表で解説|無料インターネット設備「アイネット」)