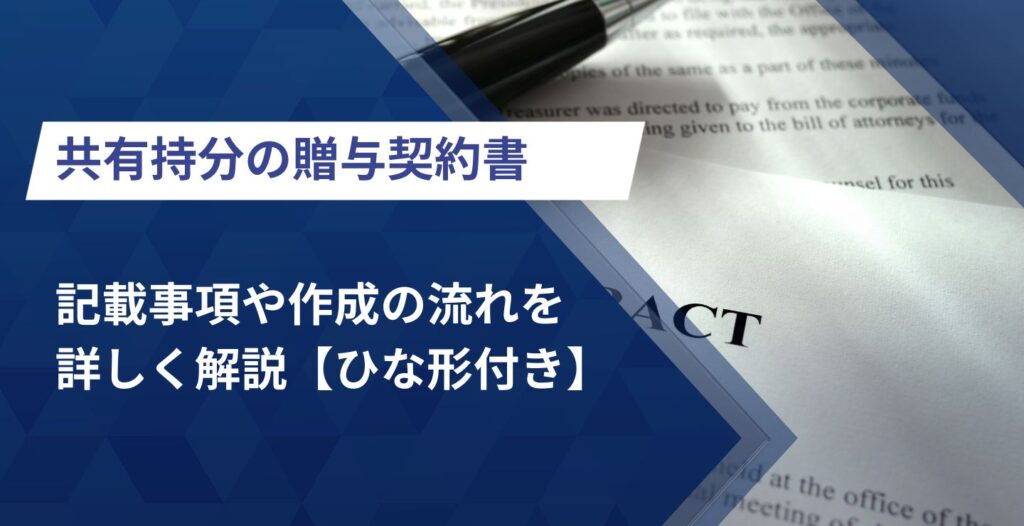共有持分の売却は同意なしで可能!売却方法や共有名義の解消方法を徹底解説

共有不動産を売却する場合、不動産全体を売却するには他の共有者全員の同意が必要です。また、賃貸や改装など、共有不動産の管理体制に大きな変更が加わる行為は、持分割合の過半数以上の同意が必要になります。
しかし、共有持分の売却であれば他の共有者の同意なしで可能です。これは民法第206条で認められた行為であり、自由かつ独断で売却を行えます。
共有持分はあくまで共有名義の不動産全体における所有権の割合に過ぎず、持分を所有したとしても不動産全体を活用できるわけではないため、居住用の物件を探しているような一般の人が買主になることはほぼありません。また、共有持分の売買に関する知識や経験がない場合、不動産会社であっても仲介や買取を断られてしまうこともあります。
そこで、共有持分を売却する場合、弊社のように共有持分を専門とする買取業者に依頼するのが得策です。
当記事では、共有不動産の共有持分を売却する方法や流れ、必要書類などについて解説します。共有持分を所有し続けるリスクについても紹介しますのでぜひ参考にしてください。
なお、クランピーリアルエステートでは、「共有者と連絡がつかない」「売却を拒否している物件」などのトラブル物件も弁護士と連携して買取を行っており、さまざまなノウハウがあります。お客様が他の共有者と直接接触することなくお取引を進めるのも可能であり、売却だけでなく共有不動産に関するご相談だけでも対応いたしますので、お困りの際にはぜひご検討ください。
目次
共有持分だけなら共有者の同意なしでも売却できる
「相続した家の共有状態から抜け出したい」「共有者との関係を断ちたい」などの理由から、共有者からの同意を得ずに共有持分を売却することを考えている人もいるでしょう。
共有持分だけであれば、所有者が単独かつ自由に処分できます。これは民法で定められている権利であり、他の共有者からの同意なしでも共有持分を売却することが可能です。
所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
e-Gov法令検索 民法第206条
弊社には共有名義の不動産に関する相談が多数寄せられますが、なかには「共有者から持分の売却を反対されている」「共有者と連絡が取れずに不動産を活用したくてもできない状態が続いている」といった内容の相談もあります。このような状態でも、共有持分だけであれば自由に売却できるのです。
「共有者とトラブルが起きている」「共有不動産を持て余している」「固定資産税などの支払いだけが続いている」といった場合、共有持分の売却によって共有状態から抜け出すことを検討してみるのもよいでしょう。
家などの共有名義の不動産全体は共有者の同意なしに売却できない
弊社では「共有している家全体は共有者の同意なしで売却できるのか」のようなご相談を受けることもあります。
しかし、家などの共有名義の不動産全体は共有者の同意なしで売却することができません。家全体を売却するためには、他の共有者全員の同意が必要です。
家を共有している場合、共有者それぞれが持分に応じた共有持分を所有しています。共有者の全員には不動産を使用する権利が認められています。
そのため、共有している家を売却するなどの行為をするためには、共有者からの同意が必要になるのです。これは民法によって定められており、共有している不動産に対してどのような行為をするかによって、共有者からの同意がどれほど必要になるのかが変わります。
| 変更行為(民法第251条) | 管理行為 | 保存行為 | |
|---|---|---|---|
| 具体例 |
・不動産全体の売却 ・建物部分の取り壊し ・不動産に抵当権を設定する |
・建物の改装や宅地の整地 ・短期の賃貸契約 |
・建物の修繕 ・不法占拠者への明け渡し請求 ・不動産の状態維持のための行為 |
| 共有者からの同意 | 共有者全員からの同意が必要 | 共有持分の過半数からの同意 | 各共有者が単独で可能 |
| 定められている民法の条文 | 民法第251条 | 民法第252条 | 民法第252条5項 |
共有している家を売却することは民法の「変更行為」に該当します。そのため、誰か1人でも売却に反対する共有者がいる場合、共有名義の家全体を売却することはできません。
なお、共有不動産を第三者に賃貸するなどの「管理行為」は、共有持分の過半数の同意でできます。また、共有不動産を修繕したり、相続登記したりする「保存行為」であれば、各共有者が単独で行えます。
共有持分の売却先は専門の買取業者または他の共有者に絞られやすい
前述の通り、共有持分は共有者からの同意なしで売却することは可能です。ただし、あくまで「自由に売却する権利がある」という話であり、実際に共有持分を売却するには買主を見つけなければなりません。
そして、共有持分の売却先は専門の買取業者または他の共有者に絞られやすいのが実情です。
前提として、共有持分は共有名義不動産における所有権の一部であり、持分を持っていたとしても不動産全体を活用することはできません。「居住用の家を買いたい」のように考えている一般の人からすれば、自由に居住や活用ができない共有持分を積極的に購入することはほぼないのです。
また、共有持分に関するノウハウがない不動産会社では、共有持分を買い取ったとしてもその物件を活用することが難しく、買取を依頼したとしても断られてしまうケースも少なくありません。実際、弊社には「他の不動産会社から断られた共有持分でも買取可能かどうか」という相談を受けることも多々あります。
そのため、共有持分を売却するのであれば、買取業者または他の共有者への売却を考えるのが無難です。
ここからは、専門の買取業者または他の共有者が共有持分の売却先になり得る理由について、それぞれ解説していきます。
専門の買取業者|買い取った共有持分を活用するためのノウハウがあるため
共有持分の売却先としては、専門の買取業者が挙げられます。
共有持分を専門とする買取業者は、共有している不動産全体を単独所有にして、物件を活用して利益を出すことを見越して持分買取を行うのが基本です。そのため、共有持分を買い取った後、基本的に買取業者は他の共有者に対しても持分のみの買取の交渉を進めていきます。
共有していた不動産を単独所有にできれば、不動産全体の売却や賃貸などによって利益を出すことも可能です。そのため、専門の買取業者は共有持分だけを買取にも対応しているのです。
なお、共有持分を専門の買取業者のような第三者に売却する場合、「不動産全体の市場価格×持分割合×1/2〜1/3」程度が相場となります。たとえば、3,000万円の家を共有しており、持分割合が1/2の場合、500万円〜750万円程度が売却価格の目安となります。
○悪質な買取業者が潜んでいるため注意が必要
買取業者の中には、自社の利益を最優先に考えて共有持分の買取を行う業者も潜んでいます。このような業者に持分を売却してしまうと、「相場よりもさらに低い価格で売却してしまう」「他の共有者に対して強引な営業が行われる」などのトラブルに発展してしまうリスクがあります。
そのため、共有持分を買取業者に売却する場合には、信頼できる業者を探すことが大切です。
他の共有者|持分割合が増えることで共有名義不動産の管理や変更がしやすくなるため
共有持分の売却先としては、他の共有者が挙げられます。
前述の通り、共有している不動産において「変更」「管理」の行為をするには、共有者からの同意が必要です。そのため、共有者の独断で共有名義の不動産を売却したり賃貸に出したりすることは原則できません。
しかし、共有持分の売買によって持分割合が増えることで、変更や管理が自由にできるようになるケースもあります。
たとえば、不動産を3人で共有しており、それぞれの持分割合は1/3のケースを想定します。この場合で「大幅なリフォーム」「賃貸に出す」などの管理行為をする場合、持分割合の過半数以上である「2/3」の同意が必要です。そのため、他に誰か1人からの同意を得なければなりません。
この場合で、他の共有者に持分を売却すると、その共有者の持分割合は2/3となり、持分割合の過半数を所有している状態になります。今後は管理行為であればその共有者が自由に行えるため、共有者にとっても持分買取のメリットがあるのです。
当然買主となる共有者からは売買に関する同意を得る必要がありますが、買主以外の共有者からの同意は不要です。そのため、共有者の中に持分売買の交渉ができる人が1人でもいる場合には、この方法で共有持分を売却するのも1つの手です。
共有持分を共有者の同意なしに売却する流れ
ここでは共有持分を売却する流れについて解説します。
- 共有持分の買取相場を把握する
- 査定を依頼する
- 契約を締結する
- 決済・登記を行う
- 確定申告・譲渡所得税の納税を行う
共有持分の買取相場を把握する
共有する不動産の相場を調べてみましょう。
不動産ライブラリやレインズマーケットインフォメーションなどでは、一般の人でも過去の成約事例を調べられます。エリアや立地など、売却予定の不動産情報で検索可能です。
ただし、登録されている情報は不動産仲介での成約事例のため買取価格とは差があります。また、共有持分だけの売却となると、不動産全体を売却する場合と比べて需要が減るため、価格が下がりやすい点を考慮することが必要です。
・レインズマーケットインフォメーション:過去の成約情報をもとにした不動産流通機構が運営するサイト
査定を依頼する
不動産会社に査定を依頼する際は一社だけでなく、複数の会社に依頼しましょう。買取価格や価格を算出した根拠、対応の良さなども含めて比較することが大切です。
当社クランピーリアルエステートでも、共有持分のような訳あり物件の買い取りを積極的に行っており、オンラインから査定の申し込みが可能です。
回答を選択するだけの簡単なフォームかつスムーズなやりとりで、ストレスなく売却までサポートしています。査定は無料なので、業者選びに迷っている方は当社でお申し込みください。
契約を締結する
買取価格や契約条件で合意できれば売買契約の締結です。売買契約書の内容をしっかり確認し、取引条件や特約事項など疑問点があれば契約前に確認しておきましょう。
とくに、契約不適合責任に関する契約書の確認は慎重に行う必要があります。2020年の民法改正により、契約不適合責任に該当する基準について、買主側に告知していた不備でも該当する可能性がある内容に変更されました。
そのため、共有持分であることを知ったうえで購入しても、場合によっては契約不適合責任として契約解除されたり損害賠償を請求されたりする可能性があります。
想定していない形で損害賠償を請求されるケースに備えて、以下の点を盛り込んだ契約書を作成しましょう。
- 買主が知っていた不備については責任を負わない
- 法律で保護されている契約でない限り契約不適合責任を免除する
- 代金の減額や損害賠償など、必要な措置の方法は売主が選択できる
なお、共有持分を専門とする買取業者に売却する場合には、契約不適合責任が免除されて売買契約が締結するのが基本です。弊社クランピーリアルエステートも売主さまが契約不適合責任に問われない形での契約が可能です。
確定申告・譲渡所得税の納税を行う
共有持分を売却したことで利益(譲渡所得)が発生する場合、譲渡所得税がかかります。その場合、売却の翌年2月16日~3月15日(暦によって変わる場合あり)に確定申告が必要です。
譲渡所得税の計算方法はのちほど詳しく解説しますが、共有不動産の売却でも一定の要件を満たせば、「居住用不動産の3,000万円控除」を適用できる可能性があります。
ただし、共有持分のみの売却で譲渡所得が発生することはほとんどないと考えられるため、譲渡所得税の負担は生じないケースが多いでしょう。
共有持分を共有者の同意なしに売却する際に必要な書類
共有持分を共有者の同意なしに売却する際に必要な書類について解説します。
- 登記識別情報(登記済権利証)
- 地積測量図、境界確認書
- 身分証明書、印鑑証明書、住民票、実印
登記識別情報(登記済権利証)
登記識別情報は、不動産の所有者であることを示す書類で、「12桁の英数字のパスワード」で構成されています。不動産売買において最も重要な書類で、下記の情報が記載されています。
- 不動産の所在地
- 不動産番号
- 受付年月日・受付番号
- 登記の目的
- 登記名義人(不動産の権利者)
- 登記識別番号
共有不動産の場合、共有者の持分ごとに登記識別番号が割り振られています。
ただし、登記識別情報は不動産の登記を申請した人へ発行されるものです。不動産を取得した場合に、単独名義であれば所有者に交付されますが、共有名義の場合、全員が共同で登記申請するとは限りません。
代表者の1人が登記申請している場合、申請者にのみ登記識別情報が交付されている場合があるため注意が必要です。
地積測量図・境界確認書
地積測量図は、地積(土地の面積)を測量した図面で、法務局で申請すれば取り寄せられます。
ただし、取得した時期によって地積測量図がない場合や土地の境界が確定されていない測量図もあります。
また、土地を売買するには、原則として確定測量図も必要です。確定測量図は、すべての境界について、隣接地の所有者と合意した内容を基づいて測量・作成された図面です。
一般的に、隣地所有者との合意内容を境界確認書を作成し保管しています。そのため、土地の共有持分を売却する場合、確定測量を実施し地積測量図を作成しなければならない場合もあります。その場合、測量費用やそれにかかる時間が必要です。
身分証明書、印鑑証明書、住民票、実印
運転免許証などの身分証明書や印鑑証明書、住民票、実印が必要です。
共有持分を共有者の同意なしに売却する際に必要な費用
共有持分を共有者の同意なしに売却する場合に必要な費用について解説します。共有者のものが必要な書類もあるため、買取事業者に確認しながら準備しましょう。
- 印紙税:200円〜48万円
- 登記費用
- 仲介手数料:不動産の価格×3%+6万円+消費税
- 譲渡所得税:譲渡所得×税率(39.63%/20.315%)
印紙税:200円〜48万円
印紙税は、売買契約書など課税文書を作成する際に必要となる税金です。売買契約書に、収入印紙を貼付して納付します。
印紙税額は売買金額によって決まります。なお、令和9年3月31日までに作成されたものは、軽減措置が適用されます。下表は軽減後の税率をまとめたものです。
| 契約金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 10万円超え50万円以下 | 200円 |
| 50万円超え100万円以下 | 500円 |
| 100万円超え500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円超え1,000万円以下 | 5,000円 |
| 1,000万円超え5,000万円以下 | 1万円 |
| 5,000万円超え1億円以下 | 3万円 |
| 1億円超え5億円以下 | 6万円 |
| 5億円超え10億円以下 | 16万円 |
| 10億円超え50億円以下 | 32万円 |
| 50億円超え | 48万円 |
| 契約金額の記載がないもの | 200円 |
登録免許税
登録免許税は、不動産を売買したり、抵当権を設定したりなどの所有権移転、抵当権設定登記を申請するときにかかる税金です。
登記をする際は、下記の3つの費用がかかる可能性があります。
- 持分移転登記:不動産の価格×2%
- 司法書士報酬:3~10万円
- 抵当権抹消費用:1,000円
持分移転登記:不動産の価格×2%
持分移転登記とは、共有持分の所有権が他社に移ったことを示す登記のことです。基本的に不動産を所有するには、社会に向けて所有権を証明するために「登記」を行う必要があります。
登記をする際には、「登録免許税」を支払う必要があり、税率は登記の種類や理由によって異なります。売買による持分移転登記の場合、税率は「20/1000」であるため、計算方法は以下のようになります。
登録免許税算定に必要な課税標準価格は、固定資産税台帳に記載されている価格がある場合はその価格です。毎年、市区町村から郵送されてくる固定資産税課税明細書にも記載されています。
司法書士報酬:3~10万円
持分移転登記の手続きを司法書士に代行してもらう場合は、司法書士に支払う報酬が発生します。司法書士報酬は事務所によって異なりますが、3~10万円程度が相場です。複数の共有持分を売却する場合は、件数分の司法書士報酬が必要になる場合もあります。
自分で持分移転登記の手続きを行えば司法書士報酬は発生しませんが、共有持分の売却手続きは非常に難しいため、お金を支払ってでも登記のプロである司法書士に依頼する方が無難です。
抵当権抹消費用:1,000円
抵当権とは、住宅ローンなどを借入して家を購入する場合に金融機関が家を担保に設定し、万が一ローンを返済できなくなった場合は家の差し押さえができる権利のことです。
抵当権が残っている状態で共有持分の売却はできないため、抵当権がある場合は事前に抹消しておく必要があります。抵当権抹消費用は、設定する抵当権を抹消するための費用です。
共有不動産に抵当権が設定されているケースとしては、共有不動産全体に抵当権が設定されている場合と共有持分のみに抵当権が設定されている場合があります。不動産全体に設定された抵当権については、すでにローンが完済されている場合の抵当権抹消登記の申請は共有物の保存行為にあたり、共有者の誰でも申請が可能です。
また、持分のみに設定されている抵当権抹消登記の申請についても、自己の持分については自由に利用、処分できるため抵当権抹消登記はできます。
抵当権抹消にかかる登録免許税は、不動産1個につき1,000円です。たとえばマンションの場合、土地(敷地権)と建物それぞれについて2個必要なため2,000円となります。
ただし、抵当権の抹消も金融機関を相手に複雑な手続きが必要になるため、登記手続きとともに司法書士に依頼するのがおすすめです。司法書士の報酬は依頼先によって変わりますが、抵当権抹消のみであれば1~2万円が相場です。
仲介手数料:不動産の価格×3%+6万円+消費税
不動産会社の仲介を利用して売却する場合は仲介手数料がかかり、取引金額によって計算式は異なります。
- 売買金額200万円以下:売買金額×5%+消費税
- 売買金額200万円超え400万円以下:売買金額×4%+2万円+消費税
- 売買金額400万円超え:売買金額×3%+6万円+消費税
ただし、不動産会社を介さず直接買取業者へ売却する場合は必要ありません。
譲渡所得税:譲渡所得×税率(39.63%/20.315%)
譲渡所得税は、共有持分を売却して譲渡所得(利益)が出た場合にかかる税金です。
譲渡所得税は次の計算式で算出します。
譲渡所得は、不動産の売却収入からその不動産を購入する際にかかった費用(取得費)と売却するためにかかった費用(譲渡費用)を控除して計算します。
取得費には、購入価格のほか、購入時の仲介手数料や登記費用、印紙税などが該当します。建物の場合、購入価格を算出する際に築年数の経過に応じた減価償却分を控除します。譲渡費用は、売却時の仲介手数料や印紙代などです。
次に、譲渡所得税の税率は、短期譲渡所得と長期譲渡所得で異なります。
- 保有期間5年以下(短期譲渡所得):所得税30.63% 住民税9% 合計39.63%
- 保有期間5年超え(長期譲渡所得):所得税15.315% 住民税5% 合計20.315%
ここに、2037年までは2.1%の復興特別所得税が上乗せで徴収されます。
共有持分を共有者の同意なしに売却する際のリスク
共有持分は他の共有者の同意なしで売却できますが、事前に告知をしない場合下記のようなトラブルになってしまうケースもあります。
- 他の共有者との人間関係が悪化する
- 離婚時の売却はトラブルが起きやすい
- 他の共有者が家賃を請求される
実際、弊社に共有持分を売却された売主さまから、「他の共有者から執拗に連絡が来る」というご相談を受けることも多々あります。弊社の場合、買取後は共有者とのやりとりをすべて弊社が行うため、売主さまが共有名義不動産においての連絡などを共有者と行う必要はありません。
しかし、売却先によっては共有者の対応を任せられないケースもあるかもしれません。そのため、共有持分を売却する際には、どのようなリスクがあり、どうすれば回避できるのかを把握しておくことも大切です。
他の共有者との人間関係が悪化する
共有持分のみを売却した場合、他の共有者にとっては見知らぬ第三者と共有関係になります。そもそも共有関係になるきっかけは、夫婦や親子で協力して不動産を購入した場合や相続で兄弟などが取得した場合が多いため、共有者同士が親族であるケースが多いでしょう。
しかし共有持分を売却すると、買取事業者のような第三者と共有関係になるため、他の共有者から非難される可能性があります。共有持分を買い取った事業者から他の共有者へ共有持分の売却を迫るようなことがあれば、さらに関係が悪化するリスクも高いです。
弊社が共有持分を買い取った案件で、売買成立後、他の共有者から売主様に執拗な連絡が届くというご相談がありました。売主様はもともと共有者と疎遠な関係にありましたが、売却をきっかけに関係性が悪化し、「売却されたことが気に入らない」といった感情的な理由で頻繁に連絡を受ける事態に陥りました。
このケースでは、「連絡があっても対応は不要です」とお伝えしたうえで、以後のやり取りはすべて弊社が代行しました。売主様に直接の負担が及ばないよう、速やかに対応しました。
こういったトラブルを避けるためには、事前に他の共有者への買取を提案するか、それが難しい場合は、共有持分の売却について連絡しておくことが大切です。知らない第三者と共有関係になるよりも買い取ったほうがよいと判断する共有者もいる可能性があります。
離婚時の売却はトラブルが起きやすい
共有持分は、原則として不動産を購入する際の出資割合に応じて決まり登記されます。なぜなら、出資割合と異なる割合で持分を登記すると、贈与税がかかる可能性があるためです。
たとえば、夫婦で夫が80%、妻20%の資金を出し合ってマイホームを購入したとします。この場合、それぞれの共有持分は夫4/5。妻1/5です。
ただし、離婚する際には、共有不動産も婚姻期間中に夫婦が共同して築いた財産として財産分与の対象となります。このとき、財産分与は、それぞれの持分割合に関係なく1/2ずつが原則です。
そのため、離婚にともない夫が自分の共有持分(4/5)を売却した場合、本来妻が財産分与として受け取れる1/2を超えているため、妻の取得分は減ることになります。妻は、財産分与でもらえない分を現金などで夫から支払ってもらうのも可能ですが、夫側が支払えない、あるいは支払ってもらえないことでトラブルになる可能性があります。
しかし、共有持分のみの売却は不動産全体で売却するよりも価格が下がるため、配偶者の同意を得ずに共有持分だけを売却する選択をしてもトラブルとなりやすいです。離婚に際しては、婚姻中に購入した自宅は単独名義でも財産分与の対象となるため、他の共有財産を含めて、財産分与が終わるまで共有持分を売却しないのが鉄則といえます。
他の共有者が家賃を請求される
共有名義の家を特定の共有者が占有している場合、それ以外の共有者は居住者に対して自身の持分割合に応じた家賃を請求できます。共有者が親族同士であれば、居住者に対して家賃を請求しないケースも多いですが、共有者に親族以外の第三者が加われば当然の権利として居住者に家賃を請求してくるでしょう。
そうなれば、同意もなく共有持分を売却したことについて居住者から非難されたり、関係が悪化したりする恐れがあります。他の共有者が共有名義の家に住んでいる場合は、家賃を巡るトラブルを避けるためにも事前に同意をとってから売却しましょう。
共有持分の売却以外に共有名義状態を解消するための対策
共有関係を解消したくても、他の共有者から同意してもらえないケースも多くあります。その際は、以下の対処法を試すのがおすすめです。
- 他の共有者に自己持分を売却する
- 他の共有者に共有持分を贈与する
- 共有持分を放棄する
- 共有物分割請求で共有状態を解消する
- 共有持分買取専門業者に売却する
他の共有者に共有持分を贈与する
他の共有者が買い取る資金がない場合、贈与する方法があります。贈与を受ける共有者は、無償で不動産の共有持分を増やせるのが大きなメリットです。
贈与によって持分の過半数を保有できれば、共有不動産の賃貸など管理行為であれば単独で行えます。他の共有者に贈与する流れは次の通りです。
- 贈与する共有者と贈与の内容について協議
- 協議内容で合意できれば「贈与契約書」を締結
- 贈与登記(共有持分の所有権移転登記)を司法書士に依頼
- 贈与税、不動産取得税がかかる場合は、申告・納付手続き
手続きが完了すれば共有関係を解消できますが、贈与税や不動産取得税がかかる可能性があります。
贈与税は、毎年贈与をする人1人につき110万円の控除があるため、贈与した持分の固定資産税評価額が110万円を超える分に対して課税されます。課税額ごとの税率は以下の通りです。
| 基礎控除分抜きの固定資産税評価額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| ~200万円 | 10% | ー |
| 200万円超~300万円 | 15% | 10万円 |
| 300万円超~400万円 | 20% | 25万円 |
| 400万円超~600万円 | 30% | 65万円 |
| 600万円超~1,000万円 | 40% | 125万円 |
| 1,000万円超~1,500万 | 45% | 175万円 |
| 1,500万円超~3,000万 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超~ | 55% | 400万円 |
基礎控除は毎年110万円分受けられるため、110万円を超えない範囲での贈与を毎年少しずつおこなう節税方法もありますが、共有持分のように不動産の贈与の場合はその都度登記が必要になります。
登記には費用がかかるため、基礎控除内の贈与であるかないかに関わらず必ず発生します。贈与する持分が多いと登記費用がかさむだけでなく、すべて贈与が終わるまでに何年もかかるためあまりおすすめできません。
また、持分が増えることで固定資産税等の負担が増える点に注意が必要です。
共有持分を放棄する
共有持分を放棄することで共有関係を解消するのも可能です。
共有持分の放棄は、他の共有者の同意は必要ありません。そして、放棄した持分は「他の共有者に帰属する」(民法255条)、つまり他の共有者が持分に応じて取得することになります。
ただし持分を放棄するには他の共有者への所有権移転登記をしなければなりません。登記手続きは、共有持分を放棄する本人だけでなく、他の共有者全員の協力が必要です。
他の共有者が持分の放棄に同意しない場合、「登記取引請求訴訟」を行う方法もありますが、費用も時間もかかります。可能であれば、他の共有者の同意を得たうえで放棄することが望ましいでしょう。
なお、単独所有の不動産の場合は所有権の放棄ができません。そのため、自分より先に他の共有者が放棄し、自身が最後の一人になった場合は放棄ができなくなります。他に共有者がいる場合にのみできる手続きであるため、早い者勝ちともいわれます。
共有物分割請求で共有状態を解消する
共有物分割請求とは、共有状態の解消を請求することです。民法256条第1項では、共有者はいつでも共有物の分割を請求できる旨を規定しています。共有物を分割する方法としては、次の3つがあります。
| 分割方法 | 概要 |
|---|---|
| 現物分割 | ・相続の際など、財産をそのままの形で分割する方法 ・土地であれば現物分割できる場合もあるが、マンションや一戸建てなど分割対象の建物が一つしかない場合は使えない |
| 代償分割 | 共有者の1人が不動産全体の所有権を取得する代わりに、他の共有者へお金を支払うことで分割する方法 |
| 換価分割 | 不動産を売却した収入を持分割合に応じて分割する方法 |
共有物分割請求は、他の共有者との協議から始まります。共有者間の関係性が良く、持分に見合った対価を支払うなどで合意できれば応じてもらえる可能性もあるでしょう。
当事者間の協議では合意が難しい場合、共有物分割調停を申し立てます。共有物分割調停は、家庭裁判所で調停委員の立ち合いのもと、共有物の分割について話し合う手続きです。第三者である調停委員が立ち合うことで、冷静かつ客観的な話し合いが期待できる可能性が高いです。
共有物分割調停でも話し合いがまとまらない場合は、共有物分割請求訴訟に進みます。共有物分割請求訴訟では、当事者それぞれが主張や証拠を提出し、裁判所の判決によって分割方法が決まります。
しかし、共有物分割請求訴訟までいくと、弁護士費用がかかるうえ、裁判手続きにも時間がかかります。また、希望通りに分割できるとは限らず、競売決定となれば、相場より低い価格で売却せざるを得ないケースも多いです。
共有物分割請求は、他の共有者との関係性を害しやすいため、共有関係を解消するための最終手段として考えておきましょう。
不動産の共有名義状態を続けることで起きるトラブル
ここまで共有持分の売却について紹介しましたが、共有関係を解消せず所有し続けることのリスクもあります。
- 共有者の把握が困難になる
- 共有者間で意見が合わず不動産を自由に活用できない
- 維持費や税金を支払い続ける必要がある
共有者の把握が困難になる
共有関係は単独所有と比べて権利関係が複雑ですが、共有者に相続が発生したり共有持分を売却したりすることで、共有者間の関係性が薄くなるため権利関係がさらに分かりにくくなります。
実際に、弊社が買い取らせていただいた事例には、共有持分の相続が続いたことで、1つの不動産を16人で共有していたケースがあります。売主さまからは「共有者を全員把握できていないが売却できるのか」のようなご相談をいただき、共有者の把握が困難になっていたようです。
このようなリスクを避けるためには、できるだけ早く共有関係を解消するか、共有持分を売却することで共有関係から解放されます。
共有関係を解消するには、不動産を売却して売却金額を分配する方法や共有者の1人が不動産を取得し、その代わりにそれぞれの持分に応じた代償金を支払うなどの方法があります。こういった方法は共有者全員の合意や資金が必要ですが、共有持分の売却なら他の共有者の同意や資金がなくても可能です。
共有者間で意見が合わず不動産を自由に活用できない
共有名義の不動産は共有者全員が自身の持分割合に応じて使用する権利があるため、不動産を第三者に貸し出したり不動産全体を売却したりするには他の共有者の同意を得なければなりません。
前述の通り、建物の改装や短期の賃貸契約などの管理行為は持分割合の過半数、建物の増改築や共有建物全体の売却などの処分・変更行為は共有者全員の同意が必要です。
不動産の活用を巡って他の共有者と意見が対立してしまうと、不動産の賃貸や売却などが困難になってしまうため、不動産が有効活用されずに放置されることになってしまいます。
相続により取得した不動産において、売りたい売主と使用し続けたい共有者の意見が合わなかったことでご相談を承りました。共有者とはそのまま険悪な状態になり相続登記すら進める事ができない状態であり、そこで弊社がご紹介者様からご紹介いただき成約となりました。
維持費や税金を支払い続ける必要がある
不動産を所有し続けるためには、固定資産税をはじめとした「税金」や建物の修理代などの「維持費」がかかります。
固定資産税やその他不動産を維持するための費用は、共有者全員で負担しなければなりません。しかし、前述のように共有者間で意見が合わないことから不動産を十分に活用できなければ、負担だけが続くことになってしまいます。
不仲な兄弟2人で相続した直後に相手方が持分を売却したケースです。新しい共有者と共有名義の不動産について協議を行ったようですが、話が進まなかったとのことです。
長い間空き家状態が続き、固定資産税と維持管理費の支出が続いており、「資産を現金化するため、自身の持分のみ売却したい」というご相談でした。
不動産を所有していても、活用できていないのであれば共有者全員の合意のもと売却するのが望ましいですが、それが難しいなら共有持分のみを売却してしまいましょう。
共有者に共有持分を同意なしに売却された際の対処法
他の共有者が同意なしに買取業者などに売却してしまった場合、どういった対処法が考えられるのでしょうか。
- 共有持分を買い戻す
- 自己持分も売却する
共有持分を買い戻す
不動産を所有し続けたい場合は、他の共有持分を買い戻すのがおすすめです。単独所有になれば共有関係を解消でき、将来的なトラブルを防げます。また、持分の過半数を取得できれば、不動産を活用しやすくなるのも大きなメリットです。
ただし、買い戻す際は相場以上の価格で購入しないように、事前に調べておくとよいでしょう。
自己持分も売却する
不動産を手放しても良いのであれば、共有関係が変わったことをきっかけとして、自分の持分も売却するのがおすすめです。自宅として活用している場合などは難しいかもしれませんが、そうでないなら売却してしまえば知らない第三者と共有関係になることを防げます。
また、自由に活用できない場合も、固定資産税などの負担を続けるより売却して現金化したほうがよい場合もあるでしょう。
まとめ
共有不動産は、その活用や処分は、他の共有者の合意が必要なため、不動産の利用価値が制限されているともいえます。共有関係を解消するには、売却することが考えられますが、不動産全体の売却は、他の共有者全員の同意が必要です。
共有持分だけを売却することは自由にできますが、一般の不動産市場での売却は難しいうえ、慎重に進めないと他の共有者とトラブルになる可能性があります。
ただし、だからといって共有持分を所有し続けることは、維持管理の手間や固定資産税等の負担が続くだけでなく、他の共有者に相続が発生するなど、権利関係がますます複雑になる可能性があります。
そこで共有関係を解消する方法としておすすめなのは、共有持分専門の買取業者を活用することです。買取価格に合意できれば、買主を探す手間がなく、契約関係もスムーズに進めやすいため現金化までの時間も早くなります。
弊社クランピーリアルエステートは、共有持分を専門として買取を行なっています。1,200を超える士業と連携しており、トラブルが起きている状態であっても問題解決に向けて買取を進めさせていただきます。
共有持分の売却を検討している場合には、ぜひご相談ください。