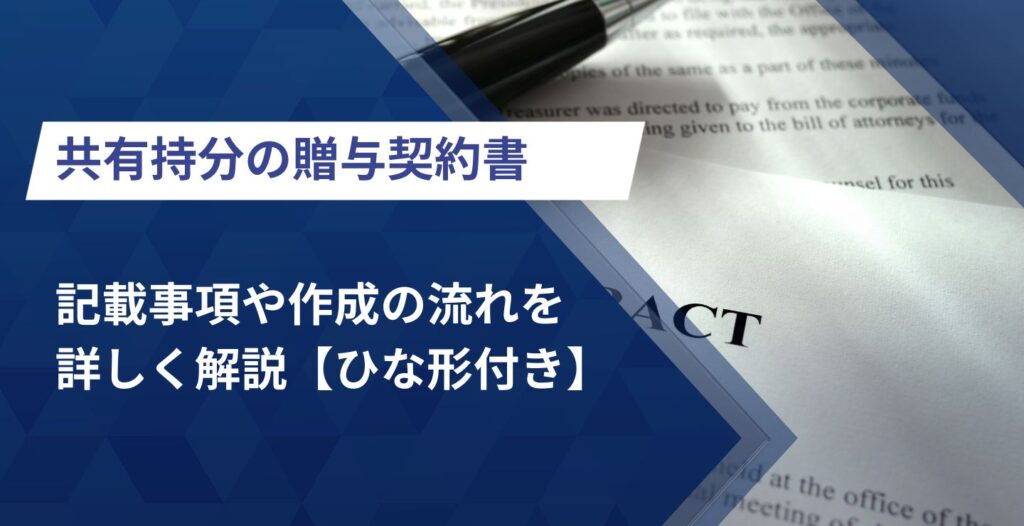共有名義にして後悔した7つの理由!対処法や具体的な相談事例を専門家が解説

複数人で同じ不動産を所有する「共有名義」は、一見すると不動産でも公平に分け合える便利な制度に見えます。しかし、弊社を利用いただいた相談者様のなかには、「共有名義にして後悔している」と心情を吐露する方も大勢おられるのも事実です。
これまでの相談事例から分析するに、共有名義にして後悔するケースは以下の7つが挙げられます。
| 共有名義にして後悔した理由 | 具体的に後悔すること |
|---|---|
| 共有者同士で揉めて人間関係が悪化する | 家族との絶縁、共同経営の破綻、嫌がらせ、知らない第三者とのトラブルなどさまざまな事態が想定される |
| 自分の思い通りに不動産を活用できない | 他の共有者の同意がなければ、不動産の売却や建て替え、リフォームなどを自由にできない |
| 不動産の維持管理費・税金の負担についてトラブルになる | 滞納者の分の肩代わりや滞納者とのトラブルなどのリスクが想定される |
| 共同経営のアパートで家賃収入を独占される | 金銭面での損失や家賃収入を取り戻すための時間・労力がかかる |
| 共有者が建物を占有して自分が使えないうえに追い出せない | 正当事由がなければ占有されても追い出せず、自分が不動産を使えなくなる |
| 共有持分割合の設定を間違えて余計な贈与税が発生する | 取得時の出資割合などとかけ離れた共有持分割合にすると、みなし贈与として判断されて贈与税が発生してしまう |
| 離婚・相続時など権利が複雑になり解決まで長期化する | 財産分与、住宅ローン、相続に伴う共有者の増加などさまざまな権利関係が複雑化し解決が難しくなる |
「自分の意思だけで不動産を活用したい」「共有者同士の争いに巻き込まれたくない」といった方は、後悔する前に共有名義の解消を検討するのがよいでしょう。
共有名義の解消方法には、「共有持分単体の売却や放棄」「共有物分割請求」などがあります。それぞれに向き不向きがあるので、自分に合った方法を選ぶことが大切です。
本記事では、共有名義にして後悔した7つの理由や、弊社への具体的な相談事例を解説します。また、共有名義を解消する方法、共有名義にならないようにする立ち回り方など、専門家目線での対策法も紹介します。
目次
共有名義にして後悔した7つの理由!所有する具体的なデメリットとは
共有名義には、「公平な相続がしやすい」「維持管理費・税金の負担を分散できる」「住宅ローンの融資額を上げやすい」などのメリットがあります。
しかし実務の現場では「共有名義にしたのは失敗だった」と、後悔する声を聞く機会が多いのも事実です。弊社の相談事例のなかで、共有名義にして後悔した理由で代表的なものとして次の7つが挙げられます。
- 共有者同士で揉めて人間関係が悪化する
- 自分の思い通りに不動産を活用できない
- 不動産の維持管理費・税金の負担についてトラブルになる
- 共同経営のアパートで家賃収入を独占される
- 共有者が建物を占有して自分が使えないうえに追い出せない
- 共有持分割合の設定を間違えて余計な贈与税が発生する
- 離婚・相続時など権利が複雑になり解決まで長期化する
共有名義にして後悔した理由を理解しやすくするため、共有名義に関する基本用語をおさらいしておきます。
| 共有名義に関する用語 | 概要 |
|---|---|
| 共有名義 | 同じ不動産について2人以上が所有権を有している状態。所有者全員が正式な名義人として登記されている。「夫婦でお金を出し合って家を購入」「兄弟3人で実家を相続」などの状況で共有名義になる。 |
| 共有者 | 共有名義不動産の所有者。登記簿上の名義人=共有者。 |
| 共有持分 | 共有者が持っている所有権の割合。30%なら、「不動産のうち30%の共有持分を持っていること」を表す。登記情報を見れば確認可能。 |
共有者同士で揉めて人間関係が悪化する
共有名義を後悔する理由としてもっとも多いのが、共有者同士で揉めて人間関係が悪化することです。
共有名義は「同じものを2人以上で一緒に使う」という関係上、権利や人間関係について共有者同士で話し合う機会が多くなります。
そのため、「私は〇〇する権利がある」「あの人のことが嫌い」など、感情的な対立・口論に発展しやすくなります。実際に弊社へご相談いただく方の多くも、「喧嘩して満足な話し合いができない」「相続を機に口喧嘩が絶えない」など、人間関係について悩みを抱えていました。
弊社へ寄せられた相談のなかで、共有者同士の人間関係が悪化した事例は次の通りです。
- 兄弟で相続した土地の活用方法について揉めて、絶縁状態になってしまった
- 共同運営の賃貸アパートの経営について意見が対立し、そこから関係性が悪化して最後は事業そのものが破綻してしまった
- 相続した実家について「残したい妹」と「売却してお金にしたい兄」で口論になり、それまで続いていた家族ぐるみの付き合いがゼロになった
- 共有持分を売って欲しいと打診されて断ると、次の日からしつこい電話や嫌がらせが続くようになった
- いつの間にか共有持分を売却していて、顔も知らない第三者の共有者とのトラブルに発展する
なかでも多いのは、「兄弟喧嘩」です。実家などを相続する際に兄弟で共有名義となるケースは多く、処分方法について揉めているうちに、関係性が悪化してしまうパターンがよく見られます。
お互いに遠慮なく意見を主張できたり、「兄弟だから多少の横暴や雑な対応も許されるだろう」と判断されたりなど、距離が近いからこそ泥沼の争いになってしまうようです。
自分の思い通りに不動産を活用できない
共有名義不動産は、共有者1人だけの意思では思い通りに活用できません。共有名義不動産に対して売却やリフォームなどの行為をおこなうには、一定数以上の共有者の同意が必要だと民法に定められています。
以下では、規定されている行為と必要な同意数をまとめました。
| 民法第251条「変更行為(処分行為)」 | 民法第252条「管理行為」 | |
|---|---|---|
| 行為の具体例 | ・不動産全体の売却 ・建物の建て替え、取り壊し、増改築、新築 ・土地の造成 ・3年超の長期賃貸借契約 ・変更行為に該当する大規模なリフォーム・修繕など |
変更行為に該当しない改装工事 ・土地の分筆 ・共有宅地の整地 ・建物全体の使用方針の決定 ・3年未満の短期賃貸借契約 |
| 必要な同意数 | 共有者全員 | 共有持分の過半数(※) |
参考:e-Gov法令検索「民法第251条」
参考:e-Gov法令検索「民法第252条」
※ 共有者4人のうち、共有持分60%の共有者が軽いリフォームを実施すると言えば、残りの3人が反対してもリフォームを実施できます。
いくら「売却して現金化したい」「大規模リフォームをして雰囲気を一新したい」と目論んでも、他の共有者の同意がなければ実現できません。
たとえば「3,000万円のアパートを3人で1,000万円ずつ出し、共有持分を1/3ずつ持った状態で経営を始めた」という場合、共有者のうち2人が反対すると変更行為も管理行為も認められません。
「1,000万円も出したのに、自分の思い通りに経営できない」と後悔するリスクがあります。また、同意を得るために共有者と交渉しているうちに、言い争いになって人間関係が悪化するケースも考えられます。
「行方不明」「所在がわからない」などの所在不明者がいると、その人からは同意が得られないので、全体の売却などがより難しくなります。対応するには、「所在等不明共有者の持分譲渡の権限付与制度」や「所在者棟不明共有者の持分取得制度」などを裁判所に申し立て、所在不明者の共有持分を売ったり取得したりする許可を得る必要があります。
不動産の維持管理費・税金の負担についてトラブルになる
共有名義不動産の各種支払いについて、法律やルールに基づいて負担割合を決めていても、共有者がお金を支払わないトラブルは後を絶ちません。
共有名義不動産にかかる維持管理費や税金の負担は、共有者全員が負担すべきと民法第253条や地方税法第10条で定められています。
(共有物に関する負担)
第二百五十三条 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
e-Gov法令検索 民法第253条
(連帯納税義務)
第十条 地方団体の徴収金を連帯して納付し、又は納入する義務については、民法第四百三十六条、第四百三十七条及び第四百四十一条から第四百四十五条までの規定を準用する。
e-Gov法令検索 地方税法第10条
負担する割合は、原則として共有持分割合に応じます。ただし上記の法律は義務ではなく、当事者同士の決まりごとのほうが優先されます。つまり、共有者の合意があれば負担割合を自由に設定可能です。
しかし、ここまで法律やルールがあったとしても、支払いを滞納する共有者が出てきてしまうのも事実です。
もし滞納者がいたとしても、一旦は支払先や自治体へ支払わなければなりません。滞納分は、一旦他の共有者で肩代わりする形になるでしょう。
理不尽に思われるかもしれませんが、放置していると相手から損害賠償請求がおこなわれるリスクがあります。固定資産税などを滞納している場合は、地方税法第10条の「連帯納付義務」に基づき、滞納者以外の財産も差し押さえ対象になってしまいます。
さらに、肩代わりしたからといって滞納者がお金を支払うとは限りません。そうなると、代わりに支払い続けるか、協議や求償請求を通じて滞納分を取り戻すかなどの対策が必要です。
どちらにしても長期間の負担を強いられるので、「こんなことなら共有名義にするんじゃなかった」と後悔する原因になります。
共同経営のアパートで家賃収入を独占される
他の共有者と共同でアパートを経営する場合、家賃収入は共有持分割合に応じて分配するのが原則です。月40万円の家賃収入、共有持分割合30%なら、12万円を受け取れる権利があります。
しかし、共有名義アパートだと特定の共有者が家賃収入を独占するリスクがあります。
弊社へ寄せられた相談だと、「代表者がお金を分配してくれない」「知らない間に兄が共有名義の土地の上にアパートを建て、家賃収入を独占していた」などのトラブル事例がありました。
人間関係に容易く亀裂を入れてくるのは、いつの時代もお金関係のトラブルです。仮に問題が解決してもわだかまりが残り、以前の関係性に戻れないケースも不動産実務で多々見てきました。
独占者が「自分が一番アパート経営に携わってるから正当な報酬だ」「他の共有者の管理業務怠慢が悪い」と主張してくる場合は、不当利得返還請求および訴訟などの法的措置での争いも視野に入ります。
当事者同士の話し合い、弁護士への依頼、裁判所での手続きなどが必要になるので、より大きなストレスや労力を強いられます。
金銭トラブルと法的トラブルの両方で畳み掛けられると、共有名義にしたことを後悔する人も多いでしょう。
共有者が建物を占有して自分が使えないうえに追い出せない
弊社へ寄せられる相談のなかに、「ある共有者に建物を乗っ取られてしまい後悔している」というものがあります。
占有行為は一見すると違法に見えますが、占有行為そのものは合法です。建物から出ていくよう要求しても、法的に退去が認められる理由がないと追い出せません。
なぜなら、共有持分を1%でも持っていれば建物の正式な所有者であることは間違いなく、「自分の権利を行使しているだけ」と判断されるからです。民法第249条にも、「共有物の全部について、持分に応じて使用できる」と規定されています。
共有物の使用)
第二百四十九条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
e-Gov法令検索 民法第249条
他にも不動産を使いたい共有者がいるなかで自分勝手に占有する人がいると、人間関係のトラブルが発生するのは間違いないでしょう。将来的に建物を利用したり売却したりしたい人にとっては、占有者は大きな障害になってしまいます。
一応、占有者を追い出せなくても、建物を使っている分だけの家賃の請求が可能です。しかし、家賃を取り戻すための話し合いや訴訟には、膨大な費用・時間・労力がかかります。仮に家賃の支払いが認められても、採算が取れるかは微妙なところです。
占有者への明け渡し請求が認められる「正当事由」と判断されるケースを、以下で紹介します。
- 共有者全員で決定した使用方法と異なった使用をしている
- 「勝手に鍵を変える」「建物を破壊する」などの権利濫用と認められる
- 「物理的なバリケードを作る」「私物を大量に運び込む」など他の共有者の権利を害する行為をしている
なお実際に認められるかは、双方の事情や正当性を見て総合的に判断されます。あからさまな違法行為などがないと占有者に対抗できないと考えると、共有名義にまつわる問題のなかでも厄介な事案だと言えるでしょう。
共有持分割合の設定を間違えて余計な贈与税が発生する
よかれと思った行為が原因で相手に贈与税が発生し、「単独名義で購入すればよかった」と後悔するケースがあります。
余計な贈与税が発生する原因の多くは、「みなし贈与」です。みなし贈与とは、法律上の贈与に該当しなくても、事実上の贈与と判断されることです。
たとえば、夫が全額出して購入したマイホームでも、夫婦で共有持分50%ずつにして登記できます。しかしこの場合だと、「夫が妻に共有持分50%をタダであげた」とみなされる可能性が高いです。本来の共有持分割合との差に応じて、贈与税が課せられるリスクがあります。
もし不動産の購入価格が5,000万円だと、妻にかかるのは「2,500万円-基礎控除110万円=2,390万円分の贈与税810万500円」です。
余計な贈与税を発生させないためにも、出資割合に応じた共有持分割合の設定を推奨します。
離婚・相続時など権利が複雑になり解決まで長期化する
共有名義不動産は、離婚時や相続時のトラブルの原因になりえます。「離婚時」と「相続時」に、共有名義を後悔するケースを紹介します。
離婚時に共有名義を後悔するケース
離婚時に共有名義がもたらす問題の1つが、財産分与の2分の1ルールと共有持分割合のギャップです。
財産分与は、結婚後に築いた財産を原則として夫婦で2分の1ずつにするのがルールです。これは共有名義不動産に関しても同様で、共有持分割合がいくつだろうと半分ずつ分与します。
そのため、「自分のほうがお金を多めに出してマイホームを買ったのに、なぜ2分の1にしなければならないのか」との不満が出ても不思議ではありません。実際にこのギャップが原因で、離婚時や離婚後も争いが続くケースがあります。
離婚後に共有名義を継続する場合も、要注意です。
「顔も見たくない相手と、離婚後も売却や建て替えについて話し合わなきゃならない」「家から出ていってくれない」などのトラブルが想定されます。
さらに注意したいのが、夫婦の連帯債務で住宅ローンを組んでマイホームを購入したケースです。離婚しても連帯債務が消えることはないので、「元配偶者しか家を使っていないのに、自分は住宅ローンの支払いだけ残っている」という事態に陥ります。
弊社がお受けする相談で多いのは、離婚後も共有名義を残して後悔しているケースです。弊社の所感としては、離婚時には共有名義をすぐに解消する方向で動いたほうが、トラブルに巻き込まれずに済むでしょう。
相続時に共有名義を後悔するケース
相続時に共有名義がネックになるのは、相続が続くほど所有権が分散する問題です。
共有持分は、通常の不動産と同じ扱いで相続がおこなわれます。共有持分40%で相続人が子どもの2人だと、2人へ共有持分20%ずつ引き継がれます。
そのまま時間が経ってから子どもが亡くなると、共有持分25%が子どもの相続人へさらに引き継がれます。相続人が配偶者と子ども2人だと、配偶者10%、子どもにそれぞれ5%ずつです。
つまり共有名義のままで相続が進むほど、共有者が立て続けに増加します。子どもや孫、さらにその先の代まで続くと、「誰が共有者かわからない」「共有持分を何%持っているか曖昧」といった事態に陥るかもしれません。
相続で共有者が増えることで後悔する事例を、いくつか紹介します
- 不動産の処分や活用について意見がまとまらず、いつまでも不動産を処分できなくなる
- 面識のない共有者が多くなり、話し合いを取りまとめるのが大変になる
- 維持管理費や税金の負担の分担や支払い管理の労力がかかる
- 所在がわからない共有者が出て、売却や建て替えの手続きが進められない
共有名義で後悔した人からの具体的な相談事例
共有名義不動産・共有持分専門の買取業者である弊社では、共有名義にして後悔している方から数多くの相談をお受けしてきました。
ここからは、弊社「クランピーリアルエステート」へ寄せられた、共有名義を後悔した人の具体的な相談事例を紹介します。
全体売却の話が直前になって白紙に戻った
兄弟2人の共有名義で2つの不動産を相続した相談者様の事例です。
1つは空き家、もう1つは兄の義理の息子が無断で家を建てて住むという、すでにいくつか問題を抱えている状態でした。当初は空き家を全体売却する方向でまとまっていたものの、契約直前になって兄が反対に転じて白紙に戻ってしまったのです。
兄の息子が勝手に家を建てた問題も重なって兄弟仲が悪化してしまい、話し合いすら困難な状況に陥りました。
前述した「全体売却には共有者全員の同意が必要」という、共有名義の典型的なデメリットの影響を直接受けた形です。加えて、無断建築という違法行為にもなりえる相手側の行為に対する、感情的な問題も発生しました。共有名義は、法律的な制約に加えて感情的な摩擦や後悔を生みやすくなってしまいます
なおこちらの事例では、弊社が土地建物および土地のみの共有持分を1,100万で買い取る形で、共有名義を解消しています。買取後は他の共有者様と協議を重ね、土地建物は弊社買取または全体売却、もう一箇所は土地の分筆で対応する予定です。
知らない間に兄が共有名義の土地にアパートを建てて収入を得ていた
兄弟で土地を相続した相談者様の事例です。
相談をお受けした際にはすでに、「兄が勝手に土地上にアパートを建てた」と悩んでおられました。発生した家賃は兄が独占しているにもかかわらず、土地の使用料に当たる地代の支払いは一切ありません。兄とは元々仲が悪く、アパートの賃料・修繕履歴・稼働率等は一切不明な状態です。
「無断で土地上に建物を建てるなんてあり得るのか」と思われるかもしませんが、実は共有者が土地を勝手に活用するパターンはよくあるトラブル事例です。
当然ながら民法上認められない行為ではあるのですが、法的措置には費用、時間、労力がかかります。そのため、実務上は真っ向から争うよりも、とにかく早期解決を目指して動く方のほうが多いのが実情です。
なおこちらの事例では、弊社が共有持分を2,000万円で買い取る形で共有名義を解消しています。複雑な権利関係にあるケースでしたが、ご相談から2週間で現金化させていただきました。
離婚によって元配偶者との共有状態が長らく続いていた
約20年前に離婚した元配偶者との共有名義が続いていた、相談者様の事例です。
離婚後は元配偶者がそのまま居住し、相談者様は不動産の利用や管理に関与できないまま、住宅ローンの連帯債務だけが残る状態でした。相談者様の「使ってもいない家のローンや固定資産税を払い続けるのか」という疑問と心理的な負担は、実務上もよくあるご相談です。
夫婦の共有名義にまつわる問題は、共有持分以外にも住宅ローンや財産分与など多岐にわたります。そのため弊社の相談事例でも、「離婚するなら共有名義は解消したほうがよい」という結論にいたるケースが多いのも事実です。
なおこちらの事例では、弊社で物件および金融状態の確認をおこない、相談者様の共有持分を400万円で買い取る形で共有名義を解消しています。
他の共有者が第三者に共有持分を譲渡した
長年空き家だった実家を兄弟で相続した相談者様の事例です。
実家を相続した直後、不仲だった兄が共有持分を売却し、見知らぬ第三者が共有者になりました。話し合う必要が出たものの協議は難航し、処分の方向がまとまらないまま固定資産税や維持管理費だけが重くのしかかっている状態です。
共有者は、民法第206条に基づき自分の持分を単体で売却することが認められています。しかし他の共有者からすれば、法律的に正しいとしても「なぜ自分がリスクを引き受けなければならないのか」と、簡単に割り切れないものです。新しい共有者が誠実な方だったとしても、精神的な負担は発生します。
さらに深刻なのは、売却先が悪質な人物・会社だった場合です。実務の現場では、早朝・深夜の営業電話、追い出しを目的とした嫌がらせ、脅迫めいた言動・態度などのトラブルも報告されています
なおこちらの事例では、弊社が協議の間に入って交渉し、共有持分を3,500万円で買い取る形で共有名義を解消しています。
連絡が取れない共有者がいて処分や管理ができない
親から土地を相続した相談者様の事例です。
ご相談を受けた時点で共有者の1人が行方不明となっており、相続登記すら進んでいない状態でした。さらに土地には未登記のアパートを建ち、その一室がすでに賃貸中。他の共有者とも不仲で、やり取り自体を苦痛に感じてしまうとのことでした。
共有者のなかに行方不明者がいると、売却や建て替えなどを進めるうえで大きな障害になります。民法の「所在等不明共有者の持分の取得」や「所在等不明共有者持分譲渡」の制度で解決は目指せるものの、こちらも裁判手続きが必要なので時間・労力がかかります。
弊社がお聞きする話のなかでも、相続してから行方不明者がいると気づいた方は少なくありません。「行方不明者がいるなんて聞いていない」と、共有名義にしたことを後悔する方もおられました。
なおこちらの事例では、仲介業者様との協力の下、共有持分を1,390万円で買い取る形で共有名義を解消しています。買取後は、行方不明者の捜索および不在者財産管理人の申し立てを進めていく予定です。
相談事例から見る共有名義を後悔しやすい人の特徴まとめ
これまで弊社に寄せられた相談事例を分析すると、共有名義にしたことを後悔する人には一定の傾向があることが見えてきました。
弊社が考える、不動産を共有名義にして後悔しやすい人の特徴をまとめて紹介します。
- 自分の考えだけで不動産を自由に運用したい
- 固定資産税や贈与税など余計な支払いをするリスクを負いたくない
- 人間関係のトラブルに巻き込まれたくない
- 共有者となりそうな人に自己中心的な性格、お金にルーズな人、すでに不仲の人などがいる
- 数十人近くなど共有者の数が多すぎる
- 単独名義で取得していても問題なかったが、深い理由もなく共有名義にした
共有名義は言い換えれば「複数人で同じものを使う」という、日常生活でもよくある事例が不動産になっただけです。
「なぜあの人ばかりで自分は使えないのか」「ちゃんとお金を払ってくれない」などの不満が発生しやすく、人間同士の衝突を引き起こしやすい仕組みになっています。
上記の特徴に当てはまると感じた方は、共有名義を避けることを検討してみてください。
【所有が決まっている人向け】後悔する前に共有名義を解消する方法
「一度共有名義にしてしまったら、解消するのは難しいのでは」と不安に思うかもしれませんが、共有名義で不動産を所有しても後から解消可能です。早期に共有名義を解消すれば、後悔する前にトラブルを回避できる可能性が上がります。
不動産を所有する人が、共有名義を解消する方法は次の通りです。
| 共有名義の解消方法 | 向いている人 |
|---|---|
| 自分の共有持分を売却する | スムーズな売却と現金化を両立したい人 |
| 共有名義不動産全体を売却する | なるべく多くの売却益を得たい人 |
| 他の共有者の共有持分を買い取って単独名義にする | 不動産を手放さず自分で自由に活用したい人 |
| 共有持分の放棄の手続きをおこなう | とにかく共有名義を解消したい人 |
| 分筆によって土地を単独名義で分割する | 共有者それぞれの単独名義にして争いを避けたい人 |
| 共有物分割請求訴訟を起こす | 話し合いに応じない共有者がいる人や、裁判所の判断を仰ぎたい人 |
自分の共有持分を売却する
「他の共有者が第三者に共有持分を譲渡した」にて少し触れましたが、自分の共有持分単体なら他の共有者の同意を得ずとも売却できると、民法第206条にて認められています。
(所有権の内容)
第二百六条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
e-Gov法令検索 民法第206条
しかし弊社の経験上、共有持分だけを購入したいという個人はほとんど存在しません。
理由は「共有名義にして後悔した理由」や、弊社の相談事例で解説したものと同じです。一般の個人が共有持分を購入しても、共有名義に伴う活用の自由度の制限や共有者とのトラブルリスクをそのまま引き継いでしまうからです。
したがって売却先は、共有持分単体でも活用できる「同じ不動産の他の共有者」または「買取業者」のどちらかになります。
他の共有者へ売却する
同じ不動産の他の共有者なら、共有持分を積極的に買い取ってくれる可能性があります。なぜなら、自分の共有持分が増えるとメリットが大きいからです。他の共有者が共有持分を買い取るメリットは、次の通りです。
- 共有持分割合が過半数になれば、軽微なリフォームや分筆などの管理行為の判断を自分の意思だけで実施できる
- 全員の共有持分を買い取って単独名義にすれば、売却や建て替えを含めて不動産を自由に活用できる
他の共有者へする場合の相場は、「共有名義不動産全体の市場価格✕共有持分割合」です。市場価格3,000万円、共有持分割合1/3なら、1,000万円程度で売却できます。買取業者へ依頼するよりも、高値での売却を期待できるでしょう。
一方で、実際に売却できるかは相手次第になるので注意してください。相手に買い取る意思がない、意思があっても購入資金が準備できないなどのケースだと、売却はできません。
また、売買契約を結ぶ際に想定されるトラブルにも要注意です。実務上、他の共有者は親族などの身内になるケースが多いため、安く買い叩かれたり強引に交渉を進められたりなどの問題が発生しやすくなります。
後々のトラブルを避けるためには、身内相手の売却でも間に不動産仲介業者を挟むことをおすすめします。
買取業者へ売却する
買取業者とは、顧客から不動産を直接買い取るサービスを提供する業者です。買い取った不動産は、独自ノウハウでリフォームや修繕を施した後、賃貸物件として活用したり転売したりして利益を得ます。
買取業者を利用して売却するなら、共有持分を専門に取り扱うところへの依頼がおすすめです。共有持分専門の買取業者へ売却するメリットは、次の通りです。
- 一般的な買取業者や他の共有者から断られた共有持分でも、積極買取を期待できる
- 豊富な専門知識と取引経験を基に、共有持分でも適切に査定してくれる
- 基本的に現況のまま買い取ってくれるので、売却時にリフォーム、修繕、清掃対応をしなくてもよい
- 契約不適合責任免責での取引が多いため、売却後に欠陥やキズなどが発覚しても責任を追わずに済む
- 現金化まで数日~1か月程度と数か月かかる仲介よりもスピーディーに対応してくれる
買取業者ならではの実務経験とサービスが魅力である一方、査定額には上記の対応にかかる諸経費が反映されます。
そのため、売却相場は「共有名義不動産全体の市場価格✕共有持分割合✕1/2~1/3」と、他の共有者への売却よりも安くなる傾向があります。市場価格3,000万円、共有持分割合1/3なら、300~500万円程度です。
共有持分単体の売却について詳しく知りたいときは、以下の関連記事をご覧ください。
共有名義不動産全体を売却する
他の共有者全員から同意を得られそうなら、共有名義不動産全体を売却して共有名義を解消する方法があります。
共有名義不動産全体を売却するメリットは、売却価格の高さです。通常の不動産と、ほぼ同じ価格と需要での売却を期待できます。
なぜなら、全員分を共有持分を売ることになるので、買主から見ると単独名義の不動産を買うのと変わらないからです。不動産仲介業者を利用し、一般の個人へも売却しやすくなります。
また、共有者全員の所有権を手放すので、「残った共有者から文句を言われる」「他の共有者と悪徳業者とで問題が発生する」といったトラブルも回避できます。
共有名義不動産全体の売却については、以下の関連記事をご覧ください。
他の共有者の共有持分を買い取って単独名義にする
他の共有者の共有持分をすべて買い取れば単独名義になるため、共有名義を解消できます。
単独名義にすれば、自由に売却、建て替え、リフォームなどが可能です。共有名義にまつわるトラブルリスクを排除したうえで、不動産の所有を続けられます。
ただし、全員分の共有持分を購入できるだけの資金が必要です。また、他の共有者が共有持分を売ってくれなければ、取引自体が成立しない点にも注意が必要です。
共有持分の放棄の手続きをおこなう
人によっては、「共有持分の売却を断られた」「他の共有者とは不仲でなるべく話したくない」などのケースも存在します。売却が難しいときは、共有持分の放棄の手続きで共有名義を解消するのも1つの手です。
共有持分の放棄の手続きとは、共有持分の所有権を放棄し、他の共有者全員に分配することです。本来、不動産の所有権の放棄は認められていないものの、民法第255条に基づき共有持分の放棄は認められています。
(持分の放棄及び共有者の死亡)
第二百五十五条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
e-Gov法令検索 民法第255条
法律に規定はないものの、実務上、放棄した共有持分は共有持分割合に応じ、贈与扱いで分配されます。共有持分を受け取った共有者は、その分の贈与税が発生します。
共有持分の放棄の手続きには、単独売却と同じく他の共有者の同意が不要です。さらに、第三者と売買契約などの契約を結ぶ必要もなく、意思表示のみで成立します。売却にはない手軽さが、放棄手続きのメリットです。
しかし、受け取る側はいきなり贈与税を課せられるため、放棄後に何かしらの反発が出るリスクがあります。また持分移転登記の際には、共有者全員の共同申請でなければなりません。共有者が登記に協力してくれないなど、新たなトラブルが想定されます。
共有持分の放棄の手続きについては、以下の関連記事をご覧ください。
分筆によって土地を単独名義で分割する
共有名義不動産が土地なら、分筆して単独名義の土地に分割すれば、共有名義の状態を解消できます。
分筆とは、登記情報にある一筆の土地を、2つ以上に区分して登記し直す手続きです。共有名義の場合は、共有持分割合に応じて分けます。たとえば600㎡の土地で共有持分が1/3ずつなら、200㎡の土地を3つ、それぞれの共有者の単独名義として登記します。
分筆で共有名義を解消するメリットは、全員が所有権を手放さずに済む点です。分筆後はそれぞれの共有者は、自分の土地を自由に売却したり活用したりできます。
一方、分筆後の土地が狭すぎたり不整形地だったりすると、むしろ売却や活用が難しくなる点に注意しましょう。また、分筆は管理行為に該当するため、実施するには共有持分割合の過半数の同意が必要です。
分筆の手続きについては、以下の関連記事をご覧ください。
共有物分割請求訴訟を起こす
他の共有者が話し合いに応じてくれない場合は、共有物分割請求にて共有名義の解消を求めましょう。
共有物分割請求とは、民法第256条に基づき、共有者の1人が共有名義の解消を求めるための手続きです。
(共有物の分割請求)
第二百五十六条 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
e-Gov法令検索 民法第256条
共有物分割請求には法的拘束力があるため、他の共有者は応じざるを得ません。そのため、話し合いを求めたいときは非常に有効な手段となります。
また、他の共有者全員への意思表示をするだけで手続きを始められる手軽さも特徴です。なお口頭だけでも成立するものの、手続き開始の証拠が残るよう、内容証明郵便を利用して書面で通知することが実務上多いです。
ただし、共有物分割請求は話し合いの場を設けるだけです。必ずしも、協議がまとまるとは限りません。共有物分割請求の協議でも結論が出ないときは、民法第258条に基づく共有物分割請求訴訟を提起できます。
(裁判による共有物の分割)
第二百五十八条 共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
2 裁判所は、次に掲げる方法により、共有物の分割を命ずることができる。
一 共有物の現物を分割する方法
二 共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法
e-Gov法令検索 民法第258条
共有物分割請求訴訟なら、裁判所での審理を経て、裁判官による客観的な判断を仰げます。裁判所の判決や和解の内容には法的拘束力があるため、決定事項に対して他の共有者もしたがわざるを得ないでしょう。仮にしたがわなかい場合でも、強制執行によって強制的に手続きを進められます。
共有名義の解消について何かしらの結論を得たいときは、共有物分割請求訴訟の提起を推奨します。とはいえ、あくまで裁判手続きであるため、判決や和解になるまでは相応の時間や労力が必要です。また、判決や和解内容が希望通りになるとも限らないので注意してください。
共有物分割請求訴訟では、以下3つの分割方法のうちもっとも適切なものが選定されます。
| 共有物分割請求の種類 | 概要 |
|---|---|
| 現物分割 | 土地を共有持分割合に応じて分筆して共有名義を解消する方法 |
| 換価分割 | 共有名義不動産全体を売却し、得られた売却益を共有持分割合に応じて分配する方法 |
| 代償分割 | 共有者の1人が代償金を支払って他の共有持分すべてを買い取り、単独名義にする方法 |
共有物分割請求訴訟については、以下の記事をご覧ください。
これから共有名義で所有しそうなときに使える予防方法
「これから相続で共有名義になりそう」など、将来的に共有名義不動産を所有しそうになる人もいるのではないでしょうか。しかし、所有する前の段階で対策しておけば、売却や共有物分割請求などをしなくとも共有名義を回避できます。
以下では、これから共有名義で所有しそうなときに使える予防方法を紹介します。
- 不動産を購入するときは複数人でお金を出し合わない
- 相続時に単独名義になるように調整する
- 共有物分割禁止特例にて制限を設ける
不動産を購入するときは複数人でお金を出し合わない
不動産を複数人で購入すると、出資割合に応じて共有持分割合が決まるのが原則です。つまり、複数人で不動産を買わなければ共有名義とせずに済みます。
購入時に共有名義となる要因として代表的なものは、住宅ローンです。夫婦がそれぞれ債務者として契約する「ペアローン」と「連帯債務型住宅ローン」は、購入する住宅が共有名義になります。
| 共有名義になる住宅ローン | 概要 |
|---|---|
| ペアローン | 夫婦それぞれが別々のローンを組んで、1つの不動産を購入するローン |
| 連帯債務型住宅ローン | 住宅ローンを夫婦2人の名義で契約し、2人とも債務者とするローン |
とはいえ、いずれのローンも夫婦の収入を合算して審査を受けられるので、融資額を増やせるメリットがあります。共有名義での住宅ローンにすべきかは、購入価格や経済状況、もとめる不動産の条件などを総合的に見て判断するのがよいでしょう。
それぞれのローンのメリット・デメリットなどは、以下の関連記事で詳しく解説しています。
相続時に単独名義になるように調整する
相続時に複数の相続人がいる場合でも、不動産を単独名義になるように調整できる可能性があります。以下では相続時と相続前に分けて、予防方法を解説します。
【相続時】遺産分割協議で調整する
遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分割方法や分割割合を話し合うことです。遺産分割協議の内容を記載した「遺産分割協議書」は法的拘束力があるため、内容を覆すことは原則としてできません。
遺産分割協議にてうまく立ち回れば、共有名義での相続を回避できます。たとえば、「不動産を相続しない代わりに別の財産を相続する」「自分の単独名義で相続する代わりに他の遺産は諦める」などが、回避案として考えられるでしょう。
ただし、遺産分割協議の決定には相続人全員の合意が必要になるため、交渉によっては希望通りにならない可能性もあります。
【相続時】相続放棄する
相続放棄の手続きを進めれば、相続人としての権利をすべて放棄できます。相続人でなくなれば、そもそも不動産を相続せずに済み、相続争いのすべてから離れることが可能です。
しかし相続放棄をすると、現金、預金、株式、宝飾品など不動産以外の遺産もすべて相続できません。手続き後の撤回もできないので、実施については慎重に検討しましょう。
【相続前】生前贈与であらかじめ取得しておく
被相続人となる人が生きているうちに、不動産を生前贈与してもらう方法があります。生前贈与を受けておけば、相続時にすでに自分の単独名義で所有しているので、所有権が分割されて相続されることがありません。
ただし、所有権移転や贈与税などの問題もあるため、事前に当事者同士や税理士などと相談しておくことを推奨します。
遺言書を利用する
被相続人となる人が生きているうちに、遺言書にて「特定の1人に単独名義で不動産を相続させる」と指定してもらう方法があります。
遺言書の効力は、遺産分割協議や法定相続よりも優先されます。より確実に単独名義の相続としたいときは、被相続人と遺言書について話し合ってみてください。
ただし、遺言書は少しでも不備があると効力を失うため、公正証書で作成するなどの工夫が必要です。遺言書に関しては、以下の関連記事で詳しく解説しています。
共有物分割禁止特約にて制限を設ける
民法第256条に定められた「共有物分割禁止特約(不分割特約)」を利用し、共有物分割請求を一定期間制限するという方法があります。
共有名義を解消する方法ではなく、あくまで一時的に制限する制度です。しかし最長で5年間まで設定できるうえに期間の更新も可能です。
たとえば全体売却や分筆などについて話し合っている最中、突然共有物分割請求を起こされて予定がすべて白紙になるといったリスクを防げます。
なお共有物分割請求特約を第三者に主張するには、特約について登記しなければなりません。
共有名義解消後に後悔しないために確認すべきこと
共有名義で後悔するケースは多いとはいえ、何も考えずに共有名義を解消すると、むしろさらなるトラブルや想定外の費用負担に直面するリスクがあります。
ここでは、共有名義を解消したあとに後悔しないために、事前に確認しておきたいポイントを整理します。
他の共有者と事前に話し合っておく
共有名義を解消したとしても、共有者が親族や知り合いだった場合、人間関係自体は継続します。もし共有名義解消時に不義理な態度や行動をしてしまうと、その後も人間関係のトラブルに巻き込まれるリスクが残ります。
上記のトラブルを防ぐには、共有名義を解消する前に事前に話し合っておくことが大切です。
共有名義単体での売却や放棄などは、他の共有者の同意なく進めることが可能です。しかし、あらかじめ共有者と相談しておくと、他の共有者も心の準備ができます。黙って手放すよりも、軋轢を避けやすくなるでしょう。
売却した場合に備えて確定申告と納税方法を知っておく
不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、確定申告と納税をしなければなりません。税金の計算や申告手続きは、原則として自分で進める必要があります。
確定申告を怠ると、税務署からの追徴課税や延滞税など、余計なペナルティを課されることになります。「税金の計算方法がわからない」「確定申告手続きに自信がない」などの場合は、不動産に強い税理士に確定申告やその他税務について依頼するのもよいでしょう。
確定申告や税金の種類については、以下の記事をご覧ください。
トラブルが想定されるなら早めに弁護士に相談する
共有名義に関するトラブルは、離婚や相続などの権利関係や、共有者同士の感情面の衝突など、当事者同士では解決するのが難しいものも珍しくありません。加えて、時間がかかるほどより問題が複雑化するリスクもあります。
共有名義に関するトラブルが想定されるなら、早めに弁護士に相談したほうが解決はスムーズです。弁護士は単に法律的な判断を下すだけでなく、共有者同士の利害を調整し、裁判や調停に発展する前に収めるための戦略を提案してくれます。
実際に弊社も全国の弁護士様と連携することで、「相続が複雑化している」「共有者が10人以上存在する」といった、難しい問題が存在する共有持分にも問題なく対応できます。
トラブルなく共有名義を解消するなら共有持分専門の買取業者へ相談が得策
トラブルなく共有名義を解消したいなら、共有持分専門の買取業者への相談も1つの手です。専門の買取業者なら共有持分の適切な査定、現況のままでの買取、契約不適合責任免責など、売却前・売却後のトラブルを防ぎやすい取引ができます。
また相談する買取業者によっては、以下のサポートも利用できます。
- 査定依頼前の無料相談
- 他の共有者との協議の仲介
- 相続登記などの登記関係のサポート
依頼する買取業者を選ぶときは、「法律面で強みがあるのか」「共有持分の取引実績はあるのか」などを確認しましょう。
まとめ
共有名義不動産には「複数の共有者」や「法律による制限」があるため、単独名義にはないさまざまなトラブルに巻き込まれるリスクがあります。
共有名義にして後悔しやすいのは、「自分で不動産を活用したい」「人間関係のトラブルに巻き込まれたくない」といったタイプの方です。当てはまるときは、共有持分の売却や共有物分割請求などの方法で、共有名義の解消を検討してみてください。
よくある質問
共有名義にするメリットはある?
共有名義にするメリットは、主に次の通りです。
- 共有名義の住宅ローンなら、審査時に収入を合算できるので融資額が上がりやすい
- 住宅ローン控除や3,000万円の特別控除などを共有者ごとに適用できる
- 維持管理費や税金の支払いを共有持分割合に応じて分配できる
- 相続税評価額を分散できるので相続税対策になる
とはいえ、本当にメリットになりえるかどうかは個々の状況にもよります。
共有名義での所有を続ける際に後悔しない方法は?
「共有名義の解消は考えていないが、所有を続けるうえで後悔しないためにはどうしたらよい」とお悩みの方は、以下の方法をお試しください。
- 共有名義の方針や管理費用の負担についてしっかりと話し合っておくこと
- 契約書や覚書などで共有名義不動産使用のルールを明確化しておくこと